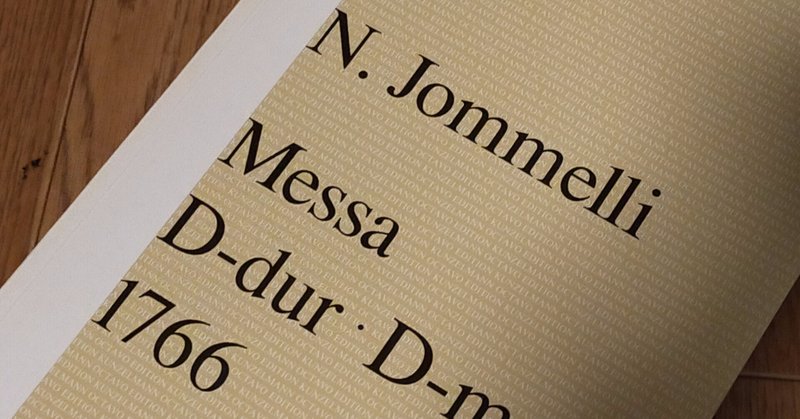
楽譜のお勉強【14】ニコロ・ヨメッリ『ミサ曲 二長調』
ニコロ・ヨメッリ(Niccolò Jommelli, 1714-1774)はイタリアとドイツを中心に活躍したイタリア古典派の作曲家です。オペラの作曲家として名高い作曲家ですが、今日その作品が上演される機会を見つけることは困難です。管弦楽法に優れ、単なる伴奏に終わらない管弦楽パートを作曲し、劇的効果を高めた彼のオペラ作品群にも関心がありますが、彼のオペラのほとんどは今日スコアの入手が大変困難です。今回は彼がドイツのシュトゥットガルトでヴュルテンブルク公爵カール・オイゲンの宮廷楽長として働いていた頃に作曲された宗教音楽『ミサ曲 二長調』(Messa a 4 voci concertata con strumenti obligati, 1766)を読んでみたいと思います。
ヨメッリはローマの聖ペテロ大聖堂で3年間副音楽監督を務めたこともあり、オペラの功績の影に隠れてしまいがちな宗教音楽が実は彼の創作において重要なジャンルです。今日私たちがヨメッリの音楽を何とか耳にする機会があるとすれば、宗教音楽でしょう。変ホ長調の『レクイエム』(Missa pro defunctis, 1756)が特に有名です。レクイエムに関しては『ミサ曲』よりも資料が多く残っているようですが、『ミサ曲』も当時人気を博した曲だったようで、自筆譜は失われてしまっているものの、およそ40の他者による手書きコピー等が残されています。今回読むEdition Kunzelmann社のスコアはヨメッリの音楽の多くを書き残したジュゼッペ・シジスモンド(Giuseppe Sigismondo, 1761-1842)による写譜とシュトゥットガルト・ヴュルテンブルク州立図書館に所蔵されているシュトゥットガルト宮廷劇場に残っていたとされる写譜(スコアとパート譜)を根拠として制作された楽譜です。

編成を見てみましょう。ソプラノ、アルト、テノールおよびバスの独唱と混声四部合唱、オーボエ2本、ホルン2本、ヴァイオリン2部、ヴィオラ、通奏低音(チェロ、ファゴット、コントラバス、オルガンと注意書きがあります)。残された稿によってはトランペットやティンパニのパートが加わっているようですが、トランペットはホルンと同じメロディーを重複して演奏しており、ティンパニは主音と属音を補強するためだけにシンプルに重ねられたものだそうで、出版楽譜では省略されました。古楽の楽譜を今日演奏できる現代の楽譜に直して出版してあるものを読むときは、このような情報がやはり大切です。校訂報告のしっかりした楽譜を用いて勉強したいものです。
次に構成です。キリエ(主よ、憐れみたまえ)、グロリア(天のいと高きところには神に栄光あれ)、シンフォニア、クレド(信条)、サンクトゥス(聖なるかな、「ベネディクトゥス(祝福あれ)」を含む)、アニュス・デイ(神の子羊)となっています。通常のミサ曲はこの構成からシンフォニアを除いたものになります。最初に構成を見たとき、「シンフォニア?ミサ曲に?どういうことだろう?」と思いました。これは写譜の中でも省かれているものも多いらしいのですが、ヨメッリの自筆譜からの直接の写譜であるとされるシジスモンド手稿譜にはシンフォニアが認められるそうで、この版にも収められています(ここで言うシンフォニアとは、古典派以降の交響曲の意味ではなく、それ以前に序曲や間奏曲としてオペラやカンタータの中に用いられる器楽合奏曲のことです)。ミサ曲の中にシンフォニアがある例は極めて稀で、ヨメッリが構成に関するとんでもない実験をしたのかと憶測しましたが、違っていました。教会での礼拝で演奏されるミサ曲には機能があります。キリエやグロリアは礼拝の開催部分で歌われます。その後、言葉の典礼が続きますが、その際に朗読される「グラドゥアーレ」の伴奏としての役割を目論んだのではないかという考察がありました(クレドはグラドゥアーレの後に歌われます)。従ってこの部分は省略して演奏しても良いようです。シンフォニアの音楽は流暢な管弦楽法による活き活きとした音楽です。
長い曲ですので、まず一通りざっと目を通しましたが、とりわけ書法や構成に考察の余地を感じたのは、キリエとクレドでした。この2つの楽章について、簡単に考察してみたいと思います。キリエの冒頭は非常に美しいです。主音であるレの音のみがヴァイオリンによって演奏されますが和音を省略してあるので調は確定していません。続く小節でドミナント(属音)和音に移行しますが、主音のレが第2ヴァイオリンで掛留(サスペンション)されているため、動き始めた旋律のミの音と長2度の音程を作ります。これがとても神秘的で美しく、厚い雲の隙間から光が差し込むような神々しさすら感じます。

この始まりを初めて聴いてヨメッリの『ミサ曲 ニ長調』に期待が高まったのですが、残念ながらこの美しい冒頭の素材はその後著しく力を失ったように思える展開が待っていました。この神々しい序奏の後、素直に「キリエ」と主和音による歌が歌われます。歌詞は「キリエ エレイソン」と続きますが、一回目は「キリエ」までを1小節で歌います。これは長大なミサ曲にはよくある作法です。短い歌詞を繰り返し繰り返し、曲として十分な長さになるまで歌い継ぐのです。この一回目の「キリエ」の後、すぐに冒頭の序奏が全く同じ形で現れます。これは未だ曲(礼拝)は始まっていないというもったいぶった表現としては効果がありそうですが、さすがに間を置かずに印象的なフレーズが繰り返されると印象は弱まります。そして今度は「キリエ エレイソン」と11小節かけてじっくり歌います。管弦楽パートも弦楽器の分散和音を効かせた充実した音楽で、いよいよ音楽が始まる感動があります。そのセクションが終わると、何と3度目の序奏フレーズが、やはり変化なしで現れます。そして冒頭と全く同じように「キリエ」と1小節歌うと、何とすぐに4度目の序奏フレーズが出てくるのです。次にテンポが変わって独唱者たちの歌を聴かせる「クリステ エレイソン」が歌われるのですが、そのセクションが終わると何と5度目の序奏フレーズが演奏されます。もしやと思ってページをめくると最後にあと2回全く同じ序奏フレーズが出てきました。序奏フレーズと書きましたが、実際にはフレーズではなく、和音、テンポ、楽器の使用、強弱、どれをとっても同じように書かれており、完全に同じものが7回、色々な音楽的エピソードを挟む構成になっています。ある種のロンドのような構成で、短期記憶を促進する効果が期待でき、楽曲を印象付ける意図を読み取ることが出来ますが、私の所感ではこの曲においては全然良い効果ではありません。冒頭で聴いた神々しさが、回を増すごとに衰えていき、最後にはこの素材がどうでもよくなっていくような気分を味わいました。記憶を促す良い効果を狙った構成だとは思うのですが、どちらかと言えば作曲家の怠惰のように聞こえてしまうのが残念です。繰り返しを使う時には、繰り返しに向いた素材かどうかの吟味がとても重要に思えます。批判めいた内容になってしまいましたが、ここまで書いて私が今作曲している作品の構成を見直す必要を感じています。人の曲を勉強すると自分の曲への気付きに繋がることも多いのが良いところです。
キリエで感じた期待外れの感覚を補って余りある優れた書法が「クレド」にあります。まず2分音符2つで「クレド」と長2度上行するモチーフが歌われます。調を確定させるための器楽による楽句が挿入され、先ほどの「クレド」から更に長2度上行した音からクレドともう一度歌います。つまり、3度上行するシンプルなモチーフなのですが、これも「キリエ」と同様に繰り返し繰り返し歌われます。最初のセクションだけで6回繰り返されますし、その後もテンポの変更や転調を含んだ独唱セクションを挟みながら全部で11回も同様の「クレド」が歌われます。ただし繰り返しは、完全に同一な形で繰り返されるのではなく、現れるたびに2度ずつ上行して現れるのです。最初はニ長調の主音から始まるので、レーミーファ#です。次にこの3音をクロマティックでなくディアトニックに2度上行させてミーファ#ーソ、その次はクロマティックに上行させてファ#ーソ#ーラという具合です。3度の枠組みは長3度になったり短3度になったりするので、響きの中に長和音と短和音が混ざっていることが分かります。それだけでも先ほどの「キリエ」よりも随分と表情豊かなのですが、更に大事な点は、最初に歌われる2音が必ず長2度であるということです。モチーフの力強さがぼやけることなく、どんどんと上昇して言って歌い手の「クレド(信条)」すなわち信仰心が高まっていく様子が描かれています。転調や長短和音の響き変化を伴う多様性を聴かせながら強力な形式的一貫性を持たせています。単純な上昇は最初のセクションの6回で、その後は多様なソロや合唱の音楽を聴かせながらその場に則した音高で繰り返されることになりますが、とにかく力強い表現が見事だと思いました。






他にも面白い要素はいくつもあって、例えばグロリア楽章における独唱者の曲内での配置はクレド楽章でもおおよそ対応しており、ミサ曲の形式や構成に関する発展に寄与した作曲家だと分かります。クンツェルマン社出版のヨメッリ『ミサ曲 ニ長調』の編集者で音楽学者のヴォルフガング・ホッホシュタイン氏はこのグロリア楽章とクレド楽章の対応構成をモーツァルトの有名な『戴冠ミサ曲』の直接的な先駆作品と評しています。ヨメッリはとにかく今日演奏される機会に恵まれない作曲家ですが、作曲の力は確かなものであるように感じましたし、例えばオペラ作品なんかも現代的な演出で再演されたら面白いかもしれないと思いました。
作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
