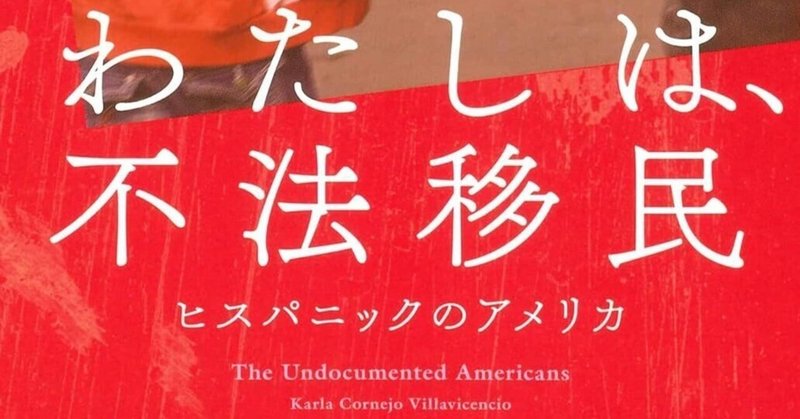
岡嵜郁奈評 カーラ・コルネホ・ヴィラヴィセンシオ『わたしは、不法移民――ヒスパニックのアメリカ』(池田年穂訳、慶應義塾大学出版会)
評者◆岡嵜郁奈
一人の人間が持ち得る声の力と、その可能性――「国境警備局員なんかクソくらえだ」!
わたしは、不法移民――ヒスパニックのアメリカ
カーラ・コルネホ・ヴィラヴィセンシオ著/池田年穂訳
慶應義塾大学出版会
No.3607 ・ 2023年09月16日
■チンガ・ラ・ミーグラ。
『わたしは、不法移民――ヒスパニックのアメリカ』はこの三語で始まる。邦訳は「国境警備局員なんかクソくらえだ」。メキシコから国境を越え入国し、法的滞在資格を持たずアメリカに留まるヒスパニック系の人々についてのノンフィクションである。
著者はカーラ・コルネホ・ヴィラヴィセンシオ。エクアドル生まれ、四歳のときに渡米、ニューヨークで育つ。不法移民として初めてハーバード大学に進学した学生の一人で、最終学年時に自身の経験を匿名のエッセイとしてニュースサイトに寄稿、注目を浴びた。当時はエージェントからの回想録の執筆依頼を断るも、二〇一六年、ドナルド・トランプが大統領に当選した翌日に本書の起稿を決意する。公の場でアメリカへの越境者たちを動物だと言い放った男に対し、著者は二〇一八年、エッセイ“A Theory of Animals"でこう反駁した。「国境の獣たちは晒しものにされた。私たちはもうこれ以上黙ってはいない」。
登場するのは、スタテンアイランドの日雇い労働者、身体・精神疾患を抱えるグラウンド・ゼロの元清掃員、代替医療や民間療法・信仰に走るマイアミの人々、水汚染で鉛中毒に苦しむフリントの親子、強制送還で父親不在となったクリーヴランドの家族など、英語を話せず、肉体労働に従事し、社会の底辺で生きる「不法移民一世」である。
自身も不法移民であった著者は、外側から観察、報道するジャーナリズム的なアプローチを取らず、内側から不法移民のコミュニティ、個々人と密接に関わり、綿密な取材を通して彼らの声を丁寧に聞き取っていく。用いるのはクリエイティブ・ノンフィクションの手法である。ときにフィクションの力を借りて、「見えない」存在である不法移民の姿を描き、これまで黙していた彼らの想いに声を貸す。それだけではない。著者はかつて地上にいた同胞へも思いを馳せる。想像力を使い、死者に声を与えようとする。
本書はまた大学時代に書かれることのなかった著者の不法移民としての回想録でもある。両親との別離によるトラウマ、貧困、摘発への恐怖、将来への不安。彼女は自身のすべてを包み隠さずストレートに語る。語り口は時に烈しい。有色人種への偏見・ヘイトがはびこる社会で育った苦しみや、移民の安価な労働力を食い物にするアメリカという国への怒りをさらけ出すとき、文章はラップのような強烈なビートを帯びる。
著者は不法移民のステレオタイプな見方に嫌気がさしていたという。「移民に関する本をたくさん読んではいたけど(中略)、こうした本の中にわたしの両親はいなかった」。彼女は各地で出会うさまざまな人々に自身の父、母、弟を重ねる。彼らとの「共有されるトラウマ、共有される記憶、共有される痛み」を介して浮き彫りになるのは、不法滞在という状況下で歪になる家族のかたち、そして家族を失った人々の孤独だった。
「はじめに」のなかで、この本は若い移民や移民の子供たちのために書いた、と著者は明記している。「ときに読むのが苦痛な本だ」、万人には好かれないだろう、と。だが本書は出版された年にオバマ元大統領の推薦図書に選ばれ、全米でベストセラーとなる。全米図書賞、全米批評家協会賞のファイナリストにも選出された。二〇二〇年はアメリカでブラック・ライブズ・マターの三語をスローガンに掲げた人種差別撤廃を訴える社会運動が広がった年でもある。
チンガ・ラ・ミーグラ。冒頭の三語は一一〇〇万の不法移民のために著者が上げた声だった。彼女の声によって、これまで存在を無視されてきた不法移民の姿が可視化され、彼らを一人の人間と見なす新しい視点が生まれた。一個人が持ち得る「声」の力。本書はその力の持つ可能性を存分に感じさせてくれる。
それだけではない。著者の率直な語りは、不法移民のルポルタージュと自身の回想録を、現代のアメリカに生きる一人の不法移民の物語にまで昇華させた。未知の人々と知り合い、家族との関係性の変化を経て、一人の女性が成長していく。カーラ・コルネホ・ヴィラヴィセンシオの成長譚である。
〈不法移民であっても人としての尊厳は守られるべきだ〉。物語を通すことで、本書の発する強いメッセージが、よりリアルに読み手に伝わってくる。
「不法移民」という言葉は日本人にとって馴染みがなく、その存在に対して反射的に悪いイメージを抱く人も多い。だがだからこそ、本書を通して彼らの実態、実情を知ることで、読み手は移民/不法移民に対するこれまでの視点を一新することができるのではないだろうか。クルド難民の強制送還や外国籍の子供への在留特別許可の付与など、外国人の不法滞在に関するニュースは少なくない。二〇二一年に名古屋の入管施設でスリランカ女性が死亡した事件は、移民/不法移民に対する視点の一新が、むしろ喫緊のものであることを示している。
とはいえ本書の魅力は何よりも、著者の声と語りによるその物語性にある。「はじめに」から読み手は一人称の語りにぐんぐんと引き込まれていく。最終章、著者は自身とこれまで出会ってきた人々の人生をまっすぐに肯定する。文から伝わるその熱い想いに、読み手の心は震えるだろう。「クソくらえ」で始まったこの物語は、十字架にかけられたイエス・キリストの言葉で終わる。「最も小さい者のひとり」(マタイによる福音書二五・四〇)のために、著者は声を上げたのだ。
(翻訳者/語学講師)
「図書新聞」No.3607・ 2023年9月16日(土)に掲載。http://www.toshoshimbun.com/books_newspaper/index.php
「図書新聞」編集部の許可を得て、投稿します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
