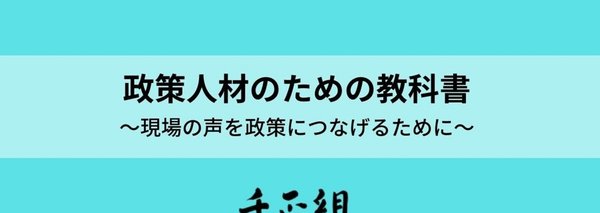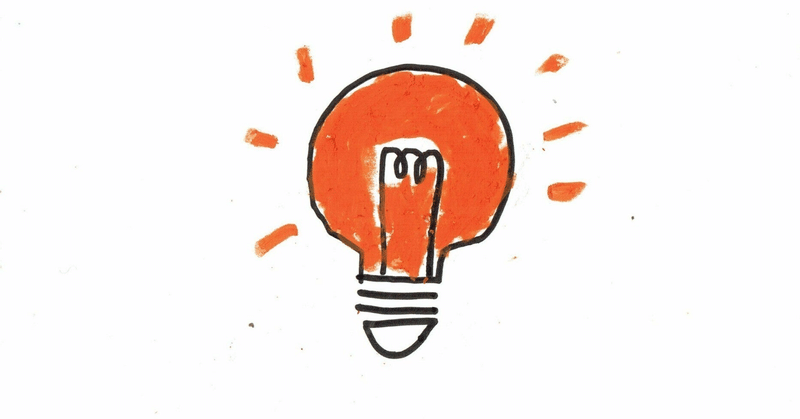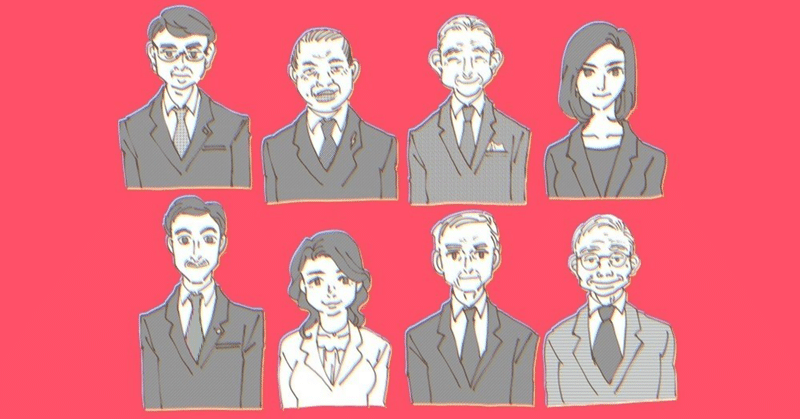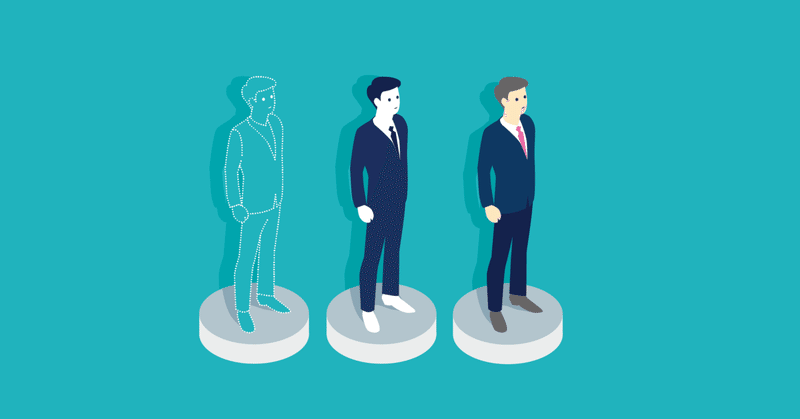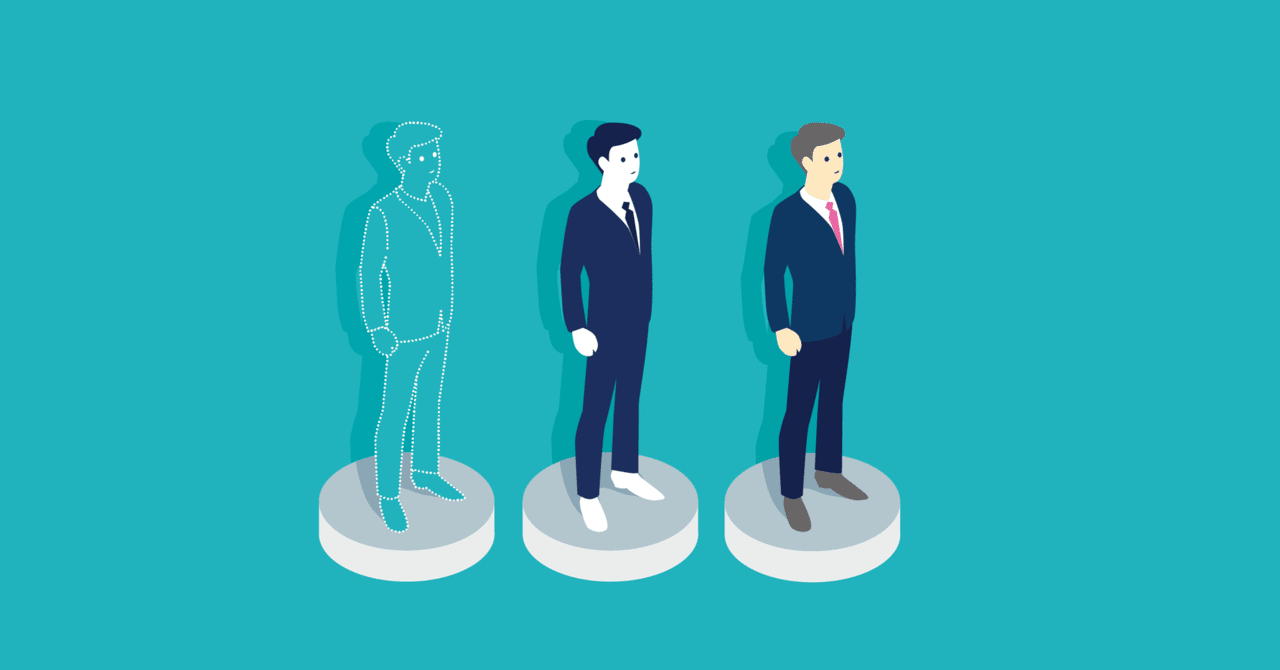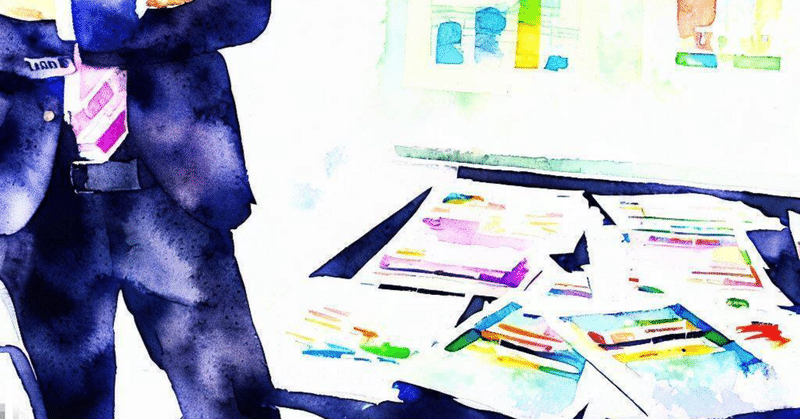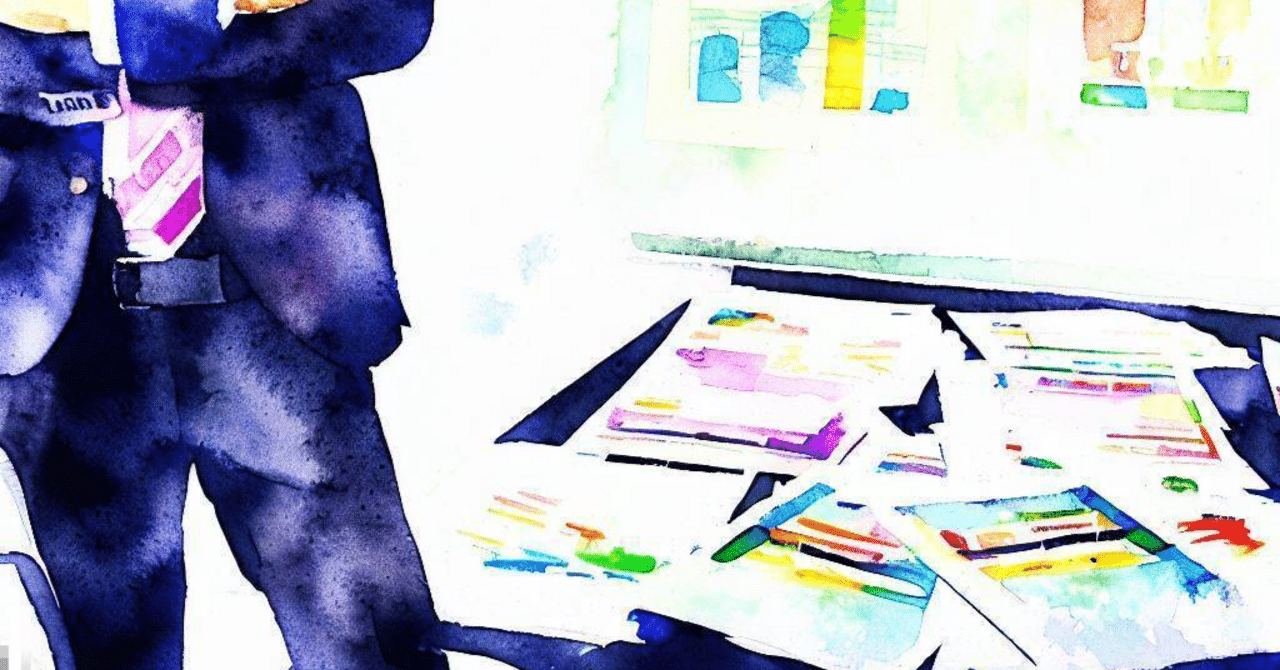株式会社千正組
株式会社千正組。厚労省の医療政策企画官だった千正康裕が2020年1月設立。民間から政策…
最近の記事
- 固定された記事
マガジン
記事
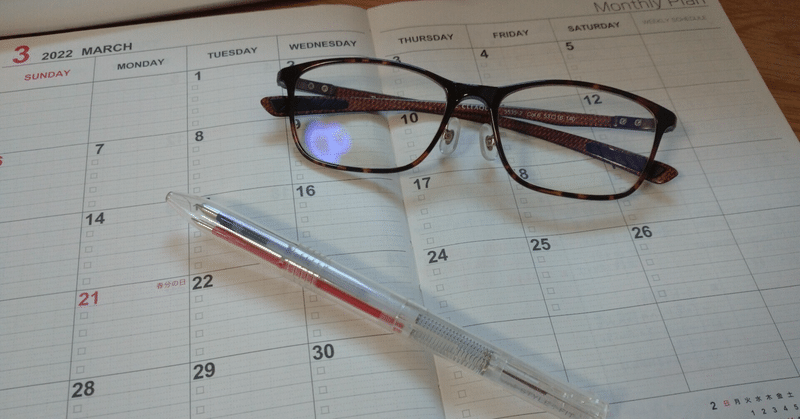
第106回:社会を変えるために「予算」を活用する!政府予算に民間の意見を反映させるために必要なスケジュールとキーパーソンとは
1.「予算」は人の行動を変え、政策の実行性を高めるツール 政府や自治体などが策定する「予算」とは、一言で言えば「金銭という動機付け(インセンティブ)を与えることにより、人々の行動を変化させるツール」です。 とてもいい政策があっても、それを裏付ける予算が無ければ、実際に効力を発揮できないことがほとんどです。 例えば「高齢者施設に、リハビリテーションの専門家を置くことで、高齢者の健康寿命が飛躍的に伸びる」ことが証明され、それを推奨する政策がとられたとします。しかし、その政策
¥1,000〜