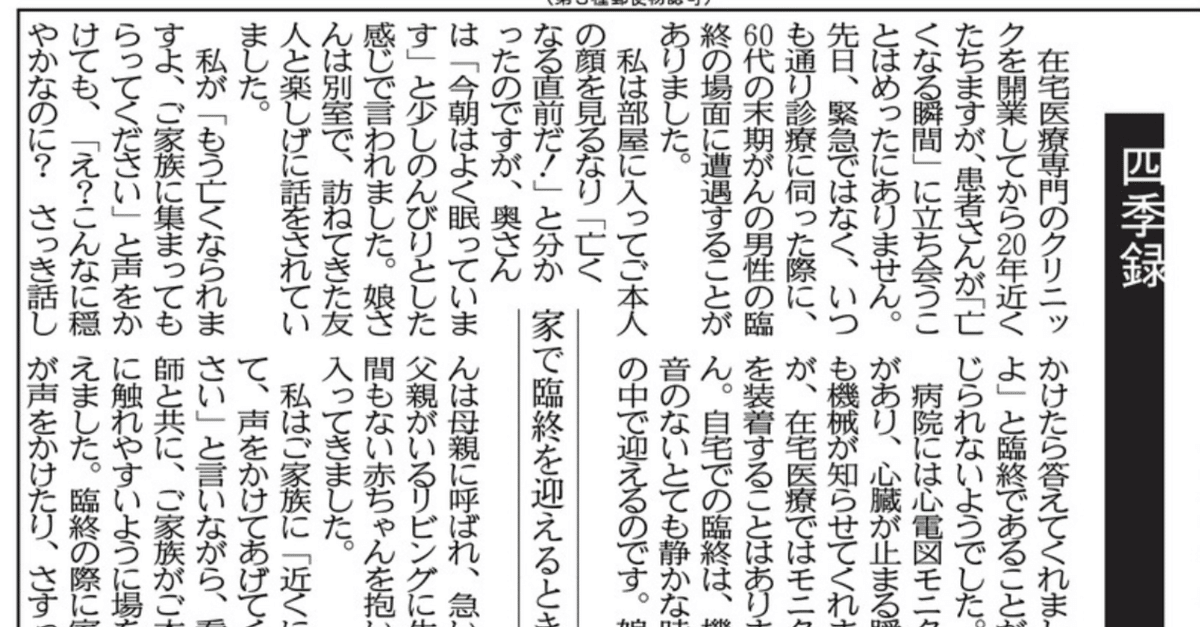
家で臨終を迎えるとき
在宅医療専門のクリニックを開業してから二十年近くたちますが、患者さんが「亡くなる瞬間」に立ち会うことはめったにありません。先日、緊急ではなく、いつも通り診療に伺った際に、60代の末期がんの男性の臨終の場面に遭遇することがありました。
私は部屋に入ってご本人の顔を見るなり、「亡くなる直前だ!」と分かったのですが、ご家族にはわからなかったのでしょう。奥さんは「今朝はよく眠っています」と少しのんびりとした感じで言われました。娘さんは別室で、訪ねてきた友人と楽しげに話をされていました。
私が「もう亡くなられますよ、ご家族に集まってもらってください」と声をかけても、「え?こんなに穏やかなのに? さっき話しかけたら答えてくれましたよ」と臨終であることが信じられないようでした。
病院には心電図モニターがあり、心臓が止まる瞬間も機械が知らせてくれますが、在宅医療ではモニターを装着することはありません。自宅での臨終は、機械音のないとても静かな時間の中で迎えるのです。娘さんは母親に呼ばれ、急いで父親がいるリビングに生後間もない赤ちゃんを抱いて入ってきました。
私はご家族に「近くに来て、声をかけてあげてください」と言いながら、看護師と共に、ご家族がご本人に触れやすいように場を整えました。臨終の際に家族が声をかけたり、さすったりすることは自然に行えそうに思えますが、家族は気が動転していることが多く、ただ茫然と立ちつくしたまま、その瞬間を迎えてしまうこともあるのです。
ご家族は、ご本人の体をさすり、声をかけ続けました。すると、娘さんは抱いていた赤ちゃんを、ご本人の枕元に寝かせたのです。まもなくご本人は、かわいいお孫さんに添い寝をしてもらいながら静かに旅立たれました。
死亡診断書を書いている私に、奥さんはご本人が療養していた部屋いっぱいに飾られていた絵のことや、ご本人がこれまでどのように生きてきたのかということを話し始めました。私はその話を伺い、ご本人は臨終の時がわからないほど穏やかに最期を迎えられたことを伝え、ご家族が十分に介護されたことに労いの言葉をかけました。さらに、お孫さんの添い寝での旅立たちはなんと幸せなことだったろうとお話しすると、ご家族は涙を流しながら笑顔で頷いていました。
このように、ご家族が大切な方の臨終を見極めるのは医療者が考えるほどたやすくはありません。しかし恐れることはありません。在宅には、各々の幸せな臨終の迎え方があることに、私は感動すら覚えるのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
