伊沢拓司著『クイズ思考の解体』を読んで思いだしたこと
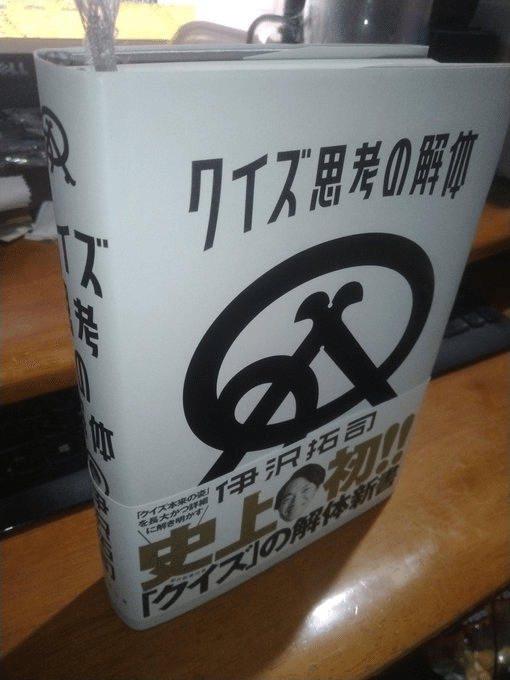
久々にハードカバーの書籍を購入しました。
すごいボリューム。全部はおろかまだ半分も読めていませんが、
少し読んで思いだしたことをつらつらと。
(自分の言うことが正しいというわけではないのでご容赦を)
どこに書かれている、というのは避けますが
「(クイズ大会開催により)趣味のクイズで稼ぐようなことは遠慮されてきた」
という記述があります。
これについて、15年前の私は「稼ぐ」ことにかなり否定的でした。
様々な方面の理由がありますが、その一つとして
「そもそも高い参加費を取るほどイベントが成熟しているのか?」
というのがありました。
当時も「野球観戦や演劇などはもっと値段取っている」などと高い参加費を肯定する論調はありましたが、
当時のクイズ大会にその領域に達するものがあったのか、という点で疑問を持っていました。
当時のこの手のクイズ大会は参加費が数百円、高くても千円でした。
私が主催していた大会も500円だったかな。
当時の相場では順当なはずですが、時間とお金を相当つぎ込んだ大会でかなりの赤字。
それでも、手間暇をとんでもなく掛けていたという自負があります。
で、今ですが、このときとは考え方がほぼ真逆です。
・それなりにお金を出しても良いという意識の人が増えた
・大学や公共施設以外でのイベントも増えた
・クイズ大会が「見られるもの」として成熟してきた
いまはこの認識があるので、2~3千円の参加費も抵抗は感じないですね。
私自身、イベント会場などで3千円のイベントも打ちましたし。
若いときのスタンスは今考えると良かったのか、という疑問もあります。
でもあのときあの状況で、高い参加費を取って納得されたかな? とも思うのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
