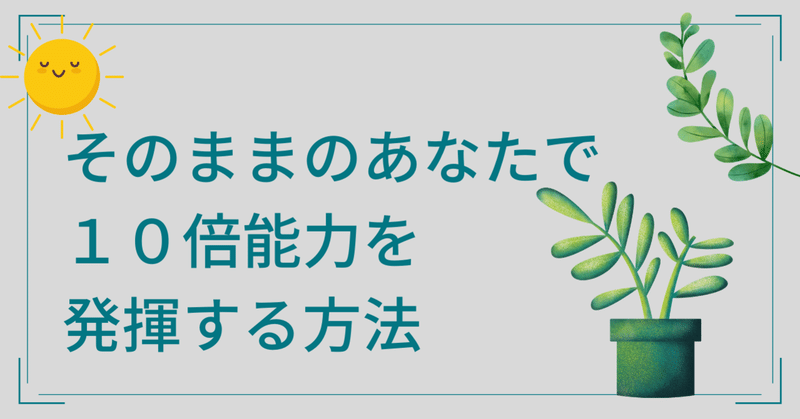
【脳の取説】そのままのあなたで10倍能力を発揮する方法
こんにちは!やる気と元気の出るコーチ♪
桑原奈緒子です。
今日は、タイトルにあるように、
「そのままのあなた」が
10倍能力を発揮するには?というお話です。
(2024/4/8rewrite)
こんなに医学や科学が進んだ現在でも、
私たちは、まだ自分の身体のことを
あまりよくわかってない、
というのはよく聞く話です。
たとえば、脳は、能力の10分の1も
使っていないといいますね。
ホントかな?^_^
「海馬 脳は疲れない」(池谷裕二、糸井重里)
という本には、なんと使っているのは2%!!
と書いてありました。
ちなみに、この本、
人間の脳や身体、ひいては自分自身の可能性に
改めて気づかされる、とてもいい本です。
対談形式で読みやすいですので、ぜひ、
よかったら読んでみてくださいね〜
本題に戻ります。
どうやら、私たちは、
自分の身体を普通に使うだけなら、
脳の能力の10分の1でも十分なんだそうです。
つまり、
私たちはみんな、
自分で思っている以上の能力を
持っているけど、10分の1以下しか
使えていないわけですよね。
それなのに、一方では、
どこかで能力に制限=ストッパーをかける、
ということもしているそうなんです。
なんてもったいない?!
今回お伝えしたいポイントは、
自分の本当の能力を発揮するために、
「能力は、自分の思っている10倍はある」
ことを知って、
それを制限する「ストッパー」を
ちょっと外してみよう!
ということなんです。
🎵自分の能力は多めに見積もろう!
そういえば、最近気がついたのですが、
車のスピードメーターも、
180キロなんて書いてあるの、
ご存知でしたか?
車によっては、メーターだけなら
300キロって書いてある、のもあるそうです。
新幹線と同じスピードが出せるわけ???(°_°)
そんなスピードで走ることは、
(たぶん)ないはずなんですけど、
それくらいの能力はある、ということですよね。
人間もそれと同じ。
本当はまだまだ能力は持っているのです。
私もよくレッスンで生徒さんに、
何でも弾けるとしたら、
どんな曲が弾けるようになりたい?
と聞きます。
子どもだったら
「エリーゼのために」
とか?
「ま、これくらいかな」
という程度の答えが返ってきます。
でも、長い経験からわかるのですが、
その人の限界って、
その人が思っているところにはないのです!
大事なのは
その可能性があることを、
自分自身が知っているかどうか。
自分自身で、自分の能力なんてたいしたことない、
どうせこの辺までよね、と思っていたら、
持っている力の半分も発揮することができません。
いわゆる、宝の持ち腐れ状態💎
🎵そもそも、「ある」と思っていないものは使えない(笑)
ある、と思っていないものは、
そもそも使えないのです!
例に、私の体験談をひとつお話ししますね。
味噌漉しにもなる、泡立て器、
という優れものがあります。ご存知ですか?
泡立て器の部分で味噌をサッとすくって、
そのまま鍋でしばらく動かしていると、
いい具合に味噌が溶けるんです。とっても便利で使いやすいです。
ネットで見て、
コレいいよねーと言ってたら、
娘が、「ママ、コレうちにあるじゃない?」
私「え?ホント?!」

で、探したら、確かにありました。
引き出しの奥に。
いったいいつ買ったんだろ?(・・?)
記憶はまったく無し。でも、
「ある」とわかってからは、
毎日、便利に使わせていただいています。
私の場合、まさに、
宝の持ち腐れ、だったわけ。
娘との会話のおかげで、
「ある」って気がつかなかったら、
一生使っていなかったかもしれませんよねー
なので。
🎵自分の能力を信じるためにやってみたいこと
自分の能力も、まだまだ余力が「ある」、
と思っていることが大事なんだと思っています。
実際そうなんですから。
とはいえ、なかなか「現在の自分」を見ていると、
そうは思えないのもよくわかります。
そういう時は、
過去の自分を見てみましょう。
わかりやすく、
小学生の頃の自分を見てみると。。。
1年生の時に、
知らなかった、
出来なかったこと。
足し算とか、引き算。
字を読む。書くなどなど。。
今は、簡単!
にできてませんか?
こんな感じで、
人間、成長していきます。
もし、
もともと持っている能力は、
自分が思っている10倍以上はある!
と思って生きてきていたら?
もっとすごいことになっていたかも?
だから、
余力、可能性はまだまだある、
と思ってみませんか?
「ある」ものを使わないともったいない。
「ある」と思っていれば、
いつ、どう使おう、という発想もわきますからね(笑)
さて、もう1つのポイント、
ストッパーの働きについては、また次回!こちらからどうぞ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
