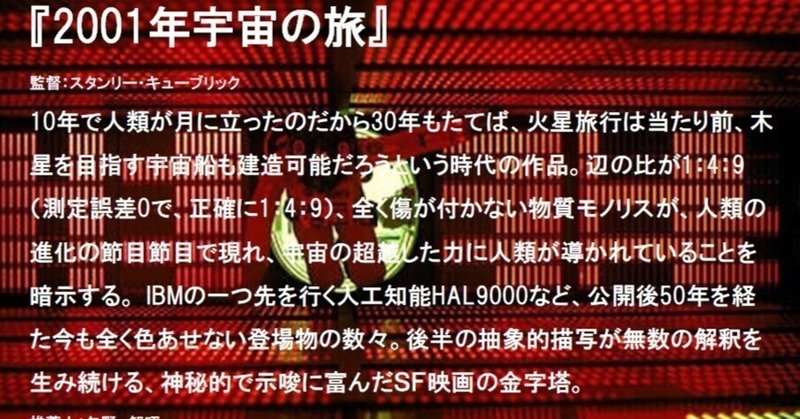
2001年宇宙の旅
#2001年宇宙の旅
10年で人類が月に立ったのだから30年もたてば、火星旅行は当たり前、木星を目指す宇宙船も建造可能だろうという時代の作品。辺の比が1:4:9(測定誤差0で、正確に1:4:9)、全く傷が付かない物質モノリスが、人類の進化の節目節目で現れ、宇宙の超越した力に人類が導かれていることを暗示する。 IBMの一つ先を行く人工知能HAL9000など、公開後50年を経た今も全く色あせない登場物の数々。後半の抽象的描写が無数の解釈を生み続ける、神秘的で示唆に富んだSF映画の金字塔。

はじめに
大阪梅田OS劇場で「シネラマ」上映を観た。
「シネラマ」は、映写機3台の映像を重ねて映すため、超巨大スクリーンに映像を映し出すことができる。

あまりにも有名で、考察が徹底的になされているため、私の解説の出番はないが、鑑賞して自分なりの妄想を膨らませてほしい映画である。
2001年宇宙の旅
映画冒頭、類人猿がモノリスに群がり、一匹の猿が骨を空中高く投げ上げると宇宙船に変身するシーンから始まる。
モノリスが400万年の人類進化の方向を指し示し、次なる跳躍の時を迎えたのだ。
モノリス
モノリスは、どれだけ正確に測定しても縦横高さの比がきっかり1:4:9なのだ。現在は13から16桁の精度で測定可能だが、モノリスは、分子や原子1個の誤差もなく縦横高さが整数比なのだ。

こんな物質が物理空間に存在可能なのだろうか?
まず、不確定性原理にもとづく測定限界が思い浮かぶ。
しかし、この原理は(位置と運動量の積)がプランク定数以下にできないという制限なので、位置だけならいくらでも精密に測定可能なのでクリアできる。
次に、量子効果による測定限界を思い浮かべる。
しかし、縦横高さの比1:4;9の時に、ポテンシャルエネルギーが底になる物質を合成したらどうだろう。
この物質は、自律的にその原子配列を縦横高さの比1:4:9になるように構造を変化させ、安定化するだろう。
傷一つつけられないということからもその頑強さが伺い知れる。
これらは、モノリスが、物理学で最もクールな物質群「トポロジカル物質」であると考えると納得がいく。
クラシック曲「ツァラトゥストラはかく語りき」の調べに乗って、宇宙ステーションがゆっくり回転する様子、宇宙ステーション内の無重力の様子がゆっくりと時間をかけて描かれる。
宇宙ステーション
宇宙ステーションがゆっくりと回転し、スクリーン内の女性がゆっくりと壁伝いに円を描くように歩行して、宇宙ステーション内に遠心力による仮想重力が働いていることを窺わせる。

ただ静かにゆっくりと、かつ荘厳に宇宙ステーションの内部を俯瞰していく映画序盤の「静」が、後半の「動」と見事な対比を見せる。
月面のモノリス
月で調査隊がモノリスを発見する。これにより、モノリスが指し示す惑星、木星探査が実行されることになる。
HAL9000
”IBM”より一歩進んだ”HAL"(I,B,Mのそれぞれ手前の文字はH,A,L)
そのAIは、人間と対等に会話をしていて、宇宙船内の制御一切を担っている。HALと宇宙飛行士たちの緊迫の駆け引きは見応えがある。
映画が公開された1968年は「人工知能」ブームのまっただ中。数学の図形証明問題が、電子計算機を用いて補助線を引くことなく解けたとか、手描き数字が読めた(曖昧さを吸収できた)とか、電子計算機の計算速度があれば人類を超越する人工知能の出現は時間の問題と思われていた。
30年後の宇宙船にHALがいるのは当然だ。
GoogleのLaMDAが、HALに近いと言われていますが、真相はわかりません
木星のモノリス
木星のモノリスとの接触により、人類はさらなる進化を遂げる。
本編はここから怒濤のような終末を迎える。
シネラマの大スクリーンにおける延々とつづくカットの嵐は美しく、見応えがあった。
おわりに
2001年の人類はこの程度宇宙に進出しているはずだった。
2001年宇宙の旅のオマージュとして2010年が作られている。
こちらもそれなりにスケールが大きく面白いが、2001年宇宙の旅のスピンオフ映画の域に留まっている。
本noteは私の備忘録ですが、自由に読んでください サポートは、興味を持ったnote投稿の購読に使用させていただきます
