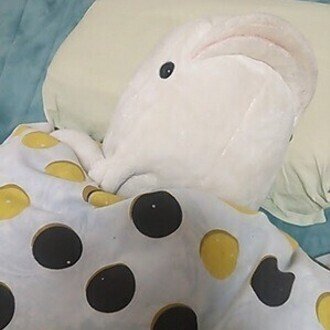2021年11月の記事一覧

元出雲!今でも大社と繋がる「出雲大神宮」微妙な角度で立つ磐座がパワスポ!神仏分離「極楽寺」も忘れずに【京都】紅葉【亀岡】丹波王国
元出雲とし磐座が点在する丹波国一宮。出雲大社は明治まで「杵築大社」と称していたため「出雲神」と言えばここだった(とも)。この神社の有名なのは、本殿裏に微妙な角度で立っている磐座で、この磐座には若い女性が良く来るパワスポ。個人的には奥宮の古代信仰跡がオススメだ。京都・籠神社奥宮・眞名井神社、宮崎・青島神社元宮が好きな人は気に入るはず。 ただ、ここも名称はコロコロ変わっており、古くは出雲神社、千年宮、大八洲国国祖神社(おおやしまのくにのみおやのじんじゃ)という時代もあったそう