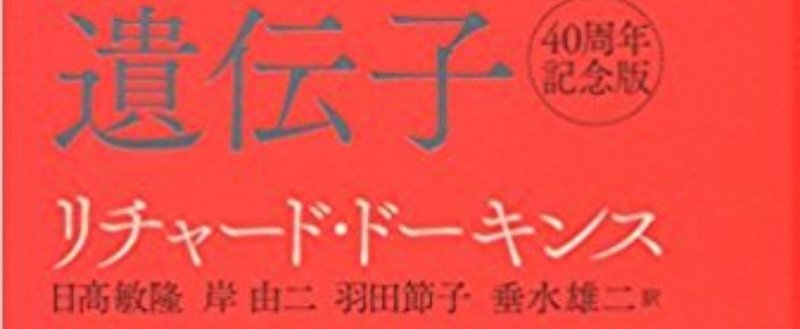
メディアの話、その25。古びない話、古びる話。
「遺伝子」と名のつく翻訳書、3冊を立て続けに手に入れた。
ひとつは、『ゲノムが語る人類全史』(文藝春秋)。もうひとつが『遺伝子』(上下巻 早川書房)。そして『利己的な遺伝子』40周年記念本。
『利己的な遺伝子』については、すでにこの雑文で取り上げた。
リチャード・ドーキンスが記した本書が英国で発行されたのは、1976年。
初版から41年たっているのである。
この本は、日本で4回もかたちを変えて出版され続けている。
日本で最初に本書が翻訳されたときのタイトルは『生物=生存機械論』。
1980年。一般にはほとんど知られることのない存在だった。
次に、いまみんなが知る『利己的な遺伝子』というタイトルに改めて発行されたのが1991年。この本が爆発的にヒットし、トンデモ解説本がいくつも出版され、「利己的な遺伝子」はある種の「流行語」になった。生物学のみならず、心理学、社会学、政治学、経済学など、人間を扱う分野の学問にまで、『利己的な遺伝子』の視座が組み込まれるようになったのも、日本においては、91年の本書の改題版が出てからだ。
2007年。30周年版が発行された。このときは、紀伊国屋書店の紀伊国屋ホールでシンポジウムが開かれ、翻訳者のひとり、日高敏隆さんと、生物学者の長谷川眞理子さん、小説家で『パラサイトイヴ』が大ヒットしたあとの瀬名秀明さんが、登壇した。途中、登壇者のひとりが「そろそろ、ドーキンスの論も、賞味期限かもしれない」と発言して、(え、これって流行り廃りの話、しているわけじゃないよね)と思って、mixiに感想を書いたら、「ご指摘どうもありがとうございます」と別の登壇者から挨拶されてビビったのをいま、思い出した。古き良きmixiよ。炎上より対話を望んだお前はいまいずこに。
そして今回の2017年の40周年版である。
『利己的な遺伝子』は、なぜ40年のあいだ、文庫にもならずにずっと売れ続けているのか。
値段は、今回の2017年版で税別2700円。590ページ。
安くはない。
(いや、実はものすごーく安い。安すぎる。1万円くらいでもいい。という話はまた別にする)
でも、ずっと売れている。
こういう、古びないでずっと売れている本の特徴は、なにかというと、当たり前だけど、「内容が古びない」。この1点につきる。
私がかつて編集した本でいうと、ヤマト運輸の中興の祖、宅急便を発明した小倉昌男さんの『小倉昌男 経営学』は1999年に発行して19年たつが、文庫化もされずに、毎年必ず2回以上版を重ねている。『経営学』も古びない本の典型だろう。
誰もが知る書籍としては、ピーター・ドラッカーは古びない。時代ごとに「ドラッカー、もう古いよね」と書いたりするひとが出てくるのだが、(私が80年代にドラッカーに出会ってから、その手の発言を、経営学の本や評論で何度も見かけた)ドラッカーが廃れることはなかった。
あるいは、部数そのものははるかに絞られているだろうが、マーシャル・マクルーハンの『メディア論』もまったく古びない。むしろ、インターネットが登場して、彼が『メディア論』で語っていた「電気的メディア」や「部族的社会」が体現したのだ、と知り、その預言者ぶりにぞっとしたりする。
古びない本、「いちばん根源的な理」を解明することで、「ひとの未来」を示す。
「ひと」は「未来」を知りたい。「世界の」ではなく、「自分の」だ。
「ひとの未来」。
AIが席巻して、ブロックチェーンがはびこって、人間は清潔で安全な監獄に入れられて、仕事は全部奪われて、そんなとき、いったい何をしていればいいのだろう、という、安っぽくも甘美なデストピアを、マスメディアが大真面目に語ったりする。それがたとえば「ひとの未来」。
ほんとか?
「ひとの未来」って、俯瞰して、これからの人類文明はこっちにいくのだ、という類のものではないのではないか。
それは、「ひと」が抜けた、「文明の未来」みたいなもの、じゃないか。
それぞれのひとが本を開くとき、そのひとはいまいるここから抜け出したいのだ。「いまより面白くなりたい」「いまよりちょっとエッチな気分になりたい」「いまから、素敵な物語に逃げ込みたい」そして「わたしの未来をのぞいてみたい」
この「未来」とは、(俯瞰した「文明の未来」もちょっとはあるかもしれないけど)、まずは「自分の未来」だ。
たとえば、自己啓発本や投資入門本も「未来がうまくいきますように」が描かれている本である。
でも、自己啓発本や投資本に書かれているのは、その時代のその瞬間に微分したら出てきた「角度」を教えてくれるだけ、だったりする。つまり、他の時代になると、その「角度」はもう再現されないから、意味がなくなったりする。
「古びない本」は、時代を微分したりしない。
「古びない本」は、結局ひとつの問いを探っている。
それは「ひととはなにか」。
マクルーハンは、「メディア」という視座から「ひととはなにか」を、
ドラッカーは、「マネジメント」という視座から「ひととはなにか」を、
小倉昌男は、「経営とサービス」という視座から「ひととはなにか」を、
ドーキンスは、「遺伝子単位の進化論」という視座から「ひととはなにか」を考察し、それぞれがそれぞれの視座から「ひととは、こうだ」を示してくれた。
実は古びるのはいつだって、技術である。技術ってのは、常に新しくなる。ゆえに、過去の技術は古くなる、ダサくなる。ゆえに「技術で勝つ」だけのひとは、いずれ「技術に負ける」ことになったりする。
「技術」はとっても大切だけど、「技術」は必ず古くなる。
古くならないのは、そう、人間そのものなのだ。
たぶん、30万年前から大して変わってない。
4000年前くらいの人類は、いま連れてきたらそのまま現代人として育つはずだ。
でも、30万年はいうにおよばず、4000年前の技術は、いまの技術とは比べものにならない。30年前の、4000年前の技術の積み重ねでいまの文明はできあがっている。だから、ほんとは「古びた」というよりは「礎になった」というのが正しいのだろうけど、技術を要素として取り出しちゃうと、やっぱり4000年前の技術は古い。
ひとは、いつでも古くって、いつでも新品だ。個体はいつでも30万年前からの共通の悩みを抱えて成長するはずだ。そんな「かわらぬ心身」をもった、それぞれのひとにとって、「ひととはなにか」を説いたコンテンツは、常に最新の目を見開かれる「新しいコンテンツ」であり続ける。
『利己的な遺伝子』、週末に読もう。
続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
