
いつかどこかで見た映画 その169 『こねこ』(1996年・ロシア)
“Котёнок”
監督・脚本:イワン・ポポフ 脚本:アレクサンドル・マリヤモフ 撮影:ウラジミール・ファステンコ 音楽:マルク・ミンコフ 編集:ワレリーヤ・ベロワ 出演:アンドレイ・クズネツォフ、リョドミラ・アリニナ、アレクセイ・ヴォイチェーク、タチアナ・クラウズ、マーシャ・ポポフ、サーシャ・ポポフ、アレクサンダー・カーギン
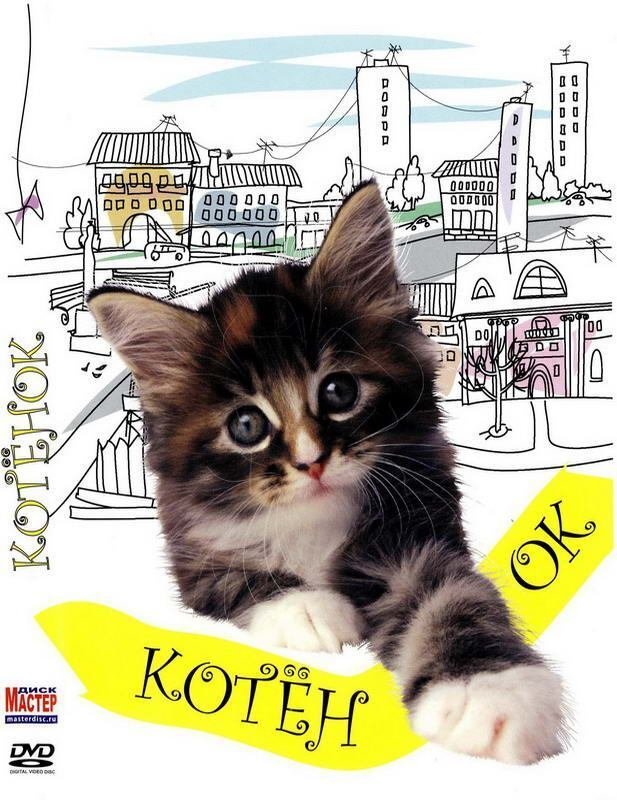
(この文章は、1999年8月に書かれたものです。)
あああ、なんて可愛らしいんだ! ロシア映画『こねこ』を見ているあいだじゅう、それこそ身も世もなくもだえのたうちまわってしまいたくなったじゃないか。実はすでに2回目を見たばかりなんだが、やはり今度もまた画面の猫たちの姿に目をウルウルさせながら心を奪われてしまった。主人公のチビ猫チグラーシャ(とは、ロシア語でトラ猫の愛称らしく、「子トラ」や「トラちゃん」といった意味なんだとか)をはじめ、かれらが小さな「大冒険」は、本当に見るたびに新鮮で、夢中にさせてくれるのだ。
ジョイスの『ユリシーズ』や『フィネガンズ・ウェイク』などの翻訳で知られ、それ以上に(?)稀代の“愛猫家”として有名な英文学者の柳瀬尚紀氏も書いていたが、《猫好きが「可愛い」の一語を発したが最後、これは収拾がつかなくなる。「とにかく可愛くて可愛くて」「そりゃもう可愛いの可愛いの」「ほんとにもう可愛いったら可愛いったら」「ほんとにもうむちゃくちゃ可愛くて」などなど、これがえんえんと続く》ことになる(引用は『猫百話』あとがきより)。でもね、本当にこの映画のチグラーシャは可愛いんだってば! そしてその感情は、よっぽどの猫嫌いを別にして(そもそもそういった人種は、この映画を見ることもないだろうけど)、この『こねこ』を見たすべての観客と分かちあえることを信じる。それほどまでに、ささやかな小品でありながら見る者の心を驚くほど動かす魅力と愛らしさに満ちているのである。
まず、冒頭場面が素敵だ。画面に次々と映しだされる魚や小動物たちと、人々がそのあいだを行きかう雑踏。どうやらここはペットを売買する青空市場[フリーマーケット]のようで、やがて品のよいおばあさん(リュドミーラ:アリニナ)に連れられた姉マーニャ(マーシャ・ポポフ)と弟サーニャ(サーシャ・ポポフ)が登場する。ふたりはなかなか気に入った生き物が見つからない様子。だが、ひとりのおばさんの胸元からちょこんと顔だけだした子猫を見て、いっぺんに気に入ってしまう。

この、おばさんの胸元から眼をまんまるに見開いて周囲の様子をうかがっている子猫の、なんという愛くるしいイメージ! さらに姉弟の家につれてこられ、チグラーシャと名づけられてからは、それこそ世界じゅうの「可愛い」をぜんぶ持ってきたかのような可愛さのオンパレードなのだ。──なにかに驚いたときのピョンと跳びあがるしぐさ。食器棚にもぐり込み、皿やカップを落っことしてもへっちゃらそうなあのまんまるな眼なんて、いたずらっ子なのに愛しくて仕方がない。片づけてあったおもちゃ箱をひっくり返し、散乱したレゴ・ブロックにじゃれつく前肢の動きなどもはや悶絶ものじゃないか。ほかにも、カーテンに爪をたててよじ登り破いたり、フルート奏者のパパの楽器ケースで用を足したりのいたずらのかぎりをつくしながら、夜には何事もなかったかのようにベッドの上で丸くなって眠っているチグラーシャ。一度でも猫を飼ったことがあるものなら、そんな姿のひとつひとつに思わず知らず深くうなずいてしまうに違いない。そして猫好きは、チグラーシャの一挙手一投足(と、猫の場合でもそう言うんだろうか?)を見つめる映画のまなざしに心の底からの“愛”を感じることだろう。

そして何より素晴らしいのが、カメラの目線をチグラーシャと同じ位置にもってきたこと。そうすることで、このやんちゃな子猫が何を見て、何をしようとしているのかが手にとるようにわかる。しかもその目線は、よくありがちな擬人化された猫の視点とかそういったものじゃなく、あくまでこの子猫を見守る映画の、さらには観客であるぼくたちのものだ。こっそりと、息をつめるように、できるだけ腰を低くしながら見つめられた小さなトラ猫の行動[アクション]。ああ、世の中にこれ以上愛らしい映像[イメージ]があるだろうか……
もっとも、ではこの映画が結局は猫好きのため“だけ”のものかと思われたとしたら、あまりにもったいない。これが長編劇映画第1作となる監督・脚本のイワン・ポポフは、子猫チグラーシャの冒険を追うことで現在の混迷するロシア社会の現実──人々の生活や心情こそを浮き彫りにしようとしている。すべての猫好きの琴線をくすぐると同時に、実は相当にアクチュアルで「野心的」な作品なのである。
チグラーシャを飼う幼い姉弟の家は、父親(アレクセイ・ヴォイチューク)が音楽家で母親(タチヤナ・グラウス)が建築家というモスクワでもかなり裕福そうな中流家庭。子供たちはファミコンでゲームをしたり、親たちは客を招いてパーティなどを催したりしている。そんな家庭のなかで前述のとおりのびのび(?)と過ごしていたチグラーシャだが、ひょんなことから真冬の街で迷子になり、それまでの何不自由ない毎日から一挙に過酷な境遇へとおちいってしまう。
そんなチグラーシャを救ってくれたのが、道路の雪かきなどでほそぼそと生計を立てている猫好きの男フェージン(アンドレイ・クズネツォフ)だ。古ぼけたアパートの屋根裏部屋で何匹もの猫に囲まれながら暮らしているフェージンだが、彼を追い出そうとする地上げ屋のやくざなふたり組につきまとわれている。
このフェージンと、消えたチグラーシャの安否を気遣う姉弟やその家族、そしてチグラーシャをはじめ実に個性豊かな猫たちの姿を、映画は外国企業の看板が目立つモスクワ市街や人々の様子を背景にスケッチしていく。どこかくすんだような雪の街並みの映像や、姉弟が手を組み合わせて影絵遊びに興じる場面など、随所にクシシュトフ・キェシロフスキ監督の影響をうかがわせながら、ほろ苦い現実のなかに「詩」を、「美しさ」を、「慰め」を見出そうとするポポフ監督。その繊細な画づくりにしろ、猫の可愛らしさを見事に描きながら決してそれだけに甘えずよりかからない“矜持”にしても、元はグラフィック・デザイナーだという1960年生まれの新人監督の才能は注目に値するといっていいだろう。(註)
まあ、いずれにしろ小さなトラ猫チグラーシャの可愛らしさの前に、あらゆる言説や批評など無力だ。このチビ猫が登場するだけで画面全体が信じられないくらいのキュートネスに包まれてしまうのだから。かつて彫刻家のジェコメッティは、「私の家が火事になったら、ためらうことなくレンブラントの絵より猫を抱いて逃げるだろう」と言ったという。この映画を見たなら、きっとあなたもジャコメッティの言葉を支持することだろう。

(註)イワン・ポポフは、その後3本の監督作を残して2013年に惜しくも他界している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
