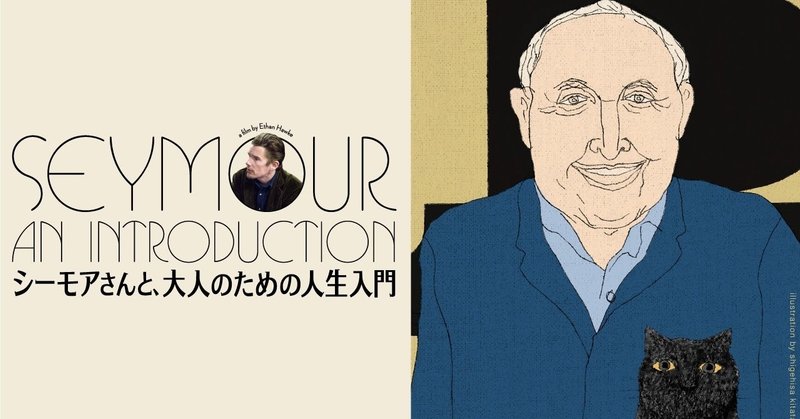
いつかどこかで見た映画 その17 『シーモアさんと、大人のための人生入門』(2014年・アメリカ)
“Seymour: An Introduction ”
監督・出演:イーサン・ホーク 出演:シーモア・バーンスタイン、マイケル・キンメルマン、アンドリュー・ハーヴェイ、ジョセフ・スミス、キンボール・ギャラハー
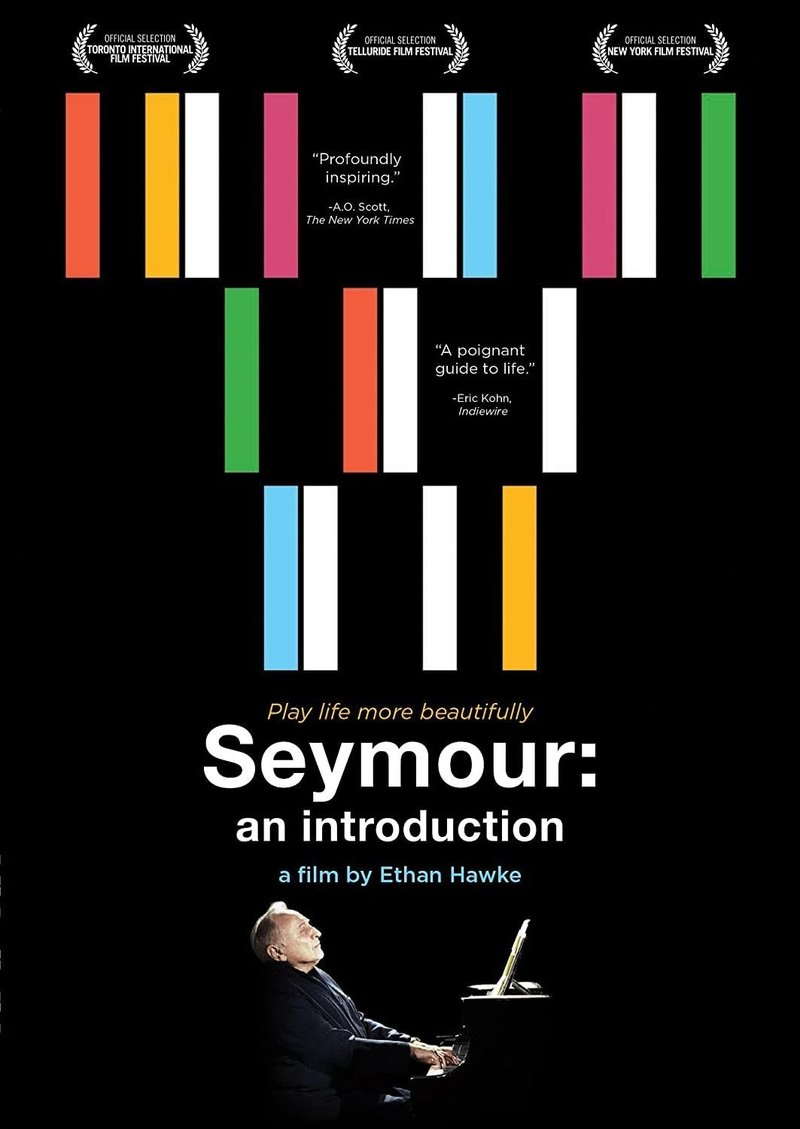
映画を見るにあたって、シーモア・バーンスタインという人物について何の知識もなかったぼくは、多少なりともその人となりを把握しておこうと、インターネットで検索することにした。すると、韓国の聯合ニュースの日本語サイトで、「シーモア・バーンスタイン氏 朝鮮戦争参戦者として来韓へ」の見出しがあるこんな記事を見つけたのだった。
《ドキュメンタリー映画『シーモアさんと、大人のための人生入門』の主人公でピアニストのシーモア・バーンスタイン氏が韓国の国歌報勲処の招きにより朝鮮戦争参戦者として来韓する。(中略)バーンスタイン氏は1951年4月から1年半の間、米軍兵士として朝鮮戦争に参戦した。最前線で100回を超える公演を行い、戦争の恐怖に苦しむ軍人に癒やしと勇気を与えた。いつ戦闘が起こるか分からないため、ピアノそばに小銃が置かれていたという。バーンスタインさんは24日に開かれる朝鮮戦争参戦者を慰労する会と、27日の感謝の夕食会で演奏する予定だ。》(2016年6月20日付けの記事より)
……今年で89歳の老ピアニストが、韓国を訪れて演奏する! ということにも驚かされるが、映画で見るかぎりシーモアさんはとてもそんなご高齢とは思えない。ピアノの個人レッスンはもちろん、大学でも学生たちの指導にあたっているその姿は、明晰かつよどみのない口調やピアノ演奏と同じくとてもおだやかで、何より実に若々しい。というより、もはや「年齢を超越している」といった方が正しい。まあ、この人物なら太平洋を越えての長旅も大丈夫だろう。
が、そのこと以上にこの記事が印象的だったのは、このピアニストの老大家が「戦争参戦者」だったという事実の方なのである。ーーいったい、現役の有名ピアニストで「兵士」として従軍した体験をもつ人物など、シーモア・バーンスタイン氏のほかにいるんだろうか、と。
(……これもネットで得た知識だが、たとえばヴェトナム戦争を体験したダン・タイ・ソンや、コソボ紛争のさなかに青春時代をおくったクロアチア人のマキシム、すでにリストの名演奏家として高名だったケマル・ゲキチたちが、“戦場のピアニスト”とも呼ばれているらしい。が、彼らはあくまで「一市民」として戦禍をかいくぐり、何とか生きのびた人々なのである)。
もちろん、この朝鮮戦争に従軍した体験は、この映画のなかでも重要なトピックとしてシーモアさん自身の口から語られる。当時のことを「日記につけていたが、20年間、開くことはなかった。ページを開くと、一日中、泣き暮らすはめに。死体袋の記憶がよみがえったからだ。」(以下、シーモア・バーンスタイン氏のことばはパンフレットのインタビュー記事より引用)と、それまで柔和な微笑みをうかべていたシーモアさんは、突然、嗚咽をもらしはじめるのである……
おっと、どうやらいささか先走りすぎたようだ。この『シーモアさんと、大人のための人生入門』という映画は、前述の聯合ニュースにもあったけれど「シーモア・バーンスタイン」というピアニストをめぐるドキュメンタリーである。かつては批評家からも絶賛されるコンサート・ピアニストだったが、50歳で演奏活動から引退。それからは音楽教師として後進の指導や、執筆活動、作曲家としての日々をおくっている。そんなシーモアさんと友人の夕食会で出会ったイーサン・ホーク(……そう、リチャード・リンクレイター監督による「ビフォア」シリーズや、『トレーニング・デイ』などの、あの俳優イーサン・ホークである!)がその人物像に魅せられ、いまだ衰えることのないピアノの演奏に感動したことから、イーサン自身が監督を買って出て誕生したのが本作なのである。
映画は、ピアノの個人レッスンや大学で指導するシーモアさん(……しかし、その指導の何という「的確さ」だろう。ぼくはピアノをまったく弾けないが、それでもことば少なくいくつかのアドバイスを受けた生徒たちが、それまでとは別人のような音色をひびかせることに、この映画のなかで何度も驚嘆させられたのだった……)をはじめ、アパートメントでひとり暮らすその慎ましい生活ぶり、さらに教え子だった著述家・ピアニストのマイケル・キンメルマンや、神秘思想家[スピリチュアリスト]のアンドリュー・ハーヴェイ、そしてイーサン・ホークほかとの対話風景をはさみながら、イーサンが主催した35年ぶりの演奏会に臨む姿を追っていく。そこから、シーモアさんの生い立ちや、彼がいかに「音楽」と向き合い、人生を捧げてきたかを、まさに滋味豊かなピアノ演奏とともに語りかけてくるのである。
……シーモアさんは、「自分の演奏に満足感を覚えたのは、50歳になった頃だ。伝えたいことを舞台で表現できるまでに、それだけの時間を要した。50歳になった時、誰にも内緒で、引退コンサートを決めた」と言う。なぜ、自分の演奏が絶頂期に達したときに「引退」を決意したのか? そのことに対して、シーモアさんはコンサートの商業的側面への幻滅と、練習にあけくれる毎日から解放されて作曲や執筆に使える時間がほしかったからだ、と答える。と同時に、「演奏会前の緊張感が苦痛だったし、怖かったから」と打ち明けるのだ。けれど、それを身をもって知ったからこそ後半生を充実した幸せなものにできたのだ、とも。
一方、この映画のなかでイーサン・ホークも「ぼくもまた、ある時分から演じることに疑問をもち、舞台に立つのが怖くなっていた」と言う。それなりに成功してきたし、恵まれた暮らしを送れてもきた。だが、そんなものなどたかが知れている。役者としての自分にいったい何ができるのか、ずっと悩み続けてきた。ーーまさにそんなとき、彼はシーモア・バーンスタイン氏と出会い、そのひとがらにふれることで「救われた」のである。
……ところで、最初の方でぼくはシーモアさんの「従軍体験」についてふれた。それは、この老ピアニストで音楽教師の名前が、ある小説のタイトルを連想させたからでもある。そのタイトルはある人物の名前を冠したものだが、その人物名こそ「シーモア」であり、ピアニストではないものの「神童」で、第二次世界大戦に従軍した体験をもっているのである。
そして映画がはじまって、オープニング・タイトルが映し出された瞬間にぼくは、思わず「あっ」と声をあげてしまった。本作の原題であるその「シーモア:アン・イントロダクション」こそ、ぼくが連想していたJ・D・サリンジャーの小説『シーモア 序章』の英語タイトルそのものだったからだ。
サリンジャーといえば、もちろん『ライ麦畑でつかまえて』などで知られるアメリカの作家。2010年に91歳で亡くなったが、1965年を最後にいっさい作品を発表せず、完全な隠遁生活をおくってきたことでも有名だろう。
そんなサリンジャーに、「グラース・サーガ」と総称されるグラース家の7人兄妹を主人公にした一連の短編・中編がある。いずれも幼少期は秀才ぞろいだが、成長するにしたがって、兄妹それぞれが様々な困難や精神的な危機に直面する姿を描いていくもの。なかでも彼ら兄妹たちに最も影響をあたえ、ほとんど崇拝の対象となるのが長男のシーモアだ。が、彼は従軍中に神経を病み、フロリダで静養中に結婚して間もない妻のかたわらで拳銃自殺してしまう(『バナナフィッシュにうってつけの日』)。「グラース・サーガ」とは、このシーモアの「死」が残された弟や妹たちにどれほど影響を与え、それを彼らがどう乗り越えようとしたかをめぐる物語だといってよいだろう。特に、小説家となった次男のバディが兄シーモアと自分たちについて書くという設定の『シーモア 序章』は、そういう「グラース兄弟史[サーガ]」の決算報告書みたいな小説なのだった。
と書けば、この映画のシーモアさんとサリンジャーの「シーモア」はまるで対照的な存在ではないか、と言われるかもしれない。確かに、どこまでもおだやかに人生と音楽を慈しんできたシーモア・バーンスタイン氏と、謎めいた死によって残された者たちの人生をも狂わせてしまった(かのような)シーモア・グラースとでは、まるで正反対のように見える。
けれども、自らの戦争体験を語る際に今なお嗚咽をもらすシーモアさんとは、おそらくイーサン・ホークにとって“それでも生きのびてくれたシーモア(・グラース)”なのだ。「死」によって永遠の“謎”そのものと化し、それを乗り越えよ告げる「師[メンター]」ではなく、生きること、生きて音楽を奏でることがどれほど価値があるかを教えてくれる「師[メンター]」。だからこそイーサンは、この自作にあえて『シーモア:アン・イントロダクション』というタイトルをつけたのだと、ぼくは思う。
……映画の終盤、35年ぶりに演奏会でピアノを弾くシーモアさん(聴衆のなかに、あのマーク・ラファロもちらりと登場する)。ピアノの背景にある大きな窓からは、人や車が行きかうニューヨークの夜の風景が見えるこのリサイタル場面は、音楽ともどもこよなく美しい。そうして最後につぶやかれるシーモアさんのことばを、ぼくはながく忘れないだろう。
「夢にも思っていなかったーーこの二つの手で青空さえつかめるとは」。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
