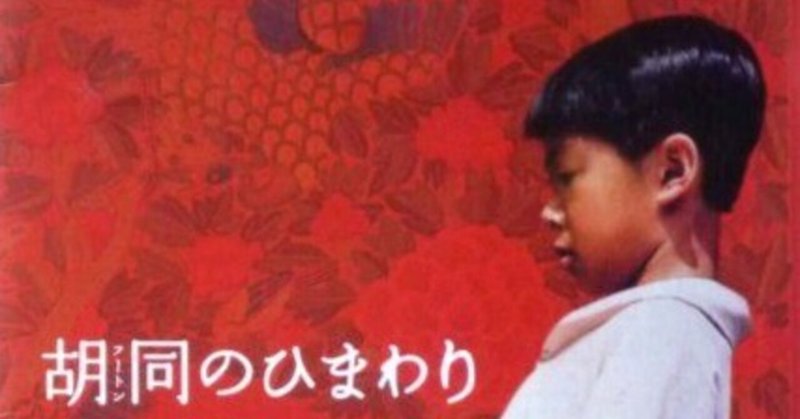
いつかどこかで見た映画 その183 『胡同(フートン)のひまわり』(2005年・中国)
“向日葵(Sunflower)”
監督・脚本:チャン・ヤン 脚本:ツァイ・シャンチュン、フォ・シン 製作:ピーター・ロア 撮影:ジョン・リン 出演:ジョアン・チェン、ソン・ハイイン、ワン・ハイディ、ガオ・グー、チャン・ファン、リュウ・ツー・フォン、チャン・ユエ、リャン・ジン、リー・ビン

(この文章は、2006年6月に書かれたものです。)
とりたてて熱心に中国映画を見続けてきたわかじゃないので、あまり迂闊なことは言えないが、近年で印象に残ったこの国の映画を振りかえるとき、「父と息子」をめぐるものが多いように思う。
最近ではチャン・イーモウ監督の『単騎、千里を走る』が、高倉健と中井貴一の日本人父子の確執と和解を背景としたものだったし、日本でも大ヒットした『山の郵便配達』や、チェン・カイコー監督の『北京バイオリン』も、それぞれ趣は異なるけれど、父と息子のきずなを中心としたドラマだった。
あるいはジャ・ジャンクー監督による『プラットフォーム』にしても、父親の存在が主人公の青年の心理や生きざまに複雑な陰影を与えていたのではなかったか。他にも、1960年代はじめ頃という「牧歌的な時代」へのノスタルジーに満ち満ちた『草ぶきの学校』という映画をはじめ、まだまだ挙げられるかもしれない。
もちろん、「父と息子」というモチーフあるいは“主題[テーマ]”は、なにも中国に限ったものじゃない。ソフォクレスによるあまりにも有名な古代ギリシャ悲劇の代表作『オイディプス王』をはじめ、古今東西、芸術のさまざまなジャンルにおいて描かれ語られてきたものであるだろう。
実際に日本でも小津安二郎監督の『父ありき』など枚挙にいとまがないし、イタリアのタヴィアーニ兄弟監督による『父/パードレ・パドローネ』や、オーストラリアからはスコット・ヒックス監督の『シャイン』、アメリカ映画の『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』等々、いくつものタイトルが思い起こされるはずだ。だからことさら、近年の中国映画だけに顕著なものだとは言いにくい。
(……もっとも、西欧の映画における「父親像」は、往々にして“影が薄い”というのは確かな気がする。むしろそこでは、D・H・ロレンスの自伝的小説『息子と恋人』に見られるように“母親と息子”の関係のほうこそが多く取りあげられてきたのではないか。
対して韓国や中国、あるいは日本においても、映画のなかで「家族」が描かれるときそこには“家父長制”めいたニュアンスが今なお色濃いように思う。家族を良くも悪くも統制し支配する父や、父親的立場をとる「男たち」をめぐる相克の劇[ドラマ]。そこには、東アジアの国々における儒教思想の伝統が否応なしに影響している、と。)
けれどもここ最近の中国映画における「父子もの」には、他の国のものとは一線を画すというか、どこか独特の“陰影[トーン]”があるようにぼくは感じている。単なる世代間のギャップや、封建的な家父長制のなごりにとどまらない、中国の「父と息子」を分かつもの。おそらくそれは“「文化大革命」体験の有無”なのではあるまいか。
1960年代半ばにはじまった文化大革命(文革)は、毛沢東が主導し、「造反有理」のスローガンのもと紅衛兵と呼ばれる少年少女たちが中心となって繰りひろげた政治改革運動だ。が、それは文化破壊と、知識人弾圧の嵐となって中国社会に大きな禍根を残した。そして1976年に毛沢東が死去し、政権を牛耳っていた「四人組」の面々が失脚するまで、文革下の青少年の多くが、僻地の山村や農村などで労働に従事する「下放」を強要されていたという。
その後、鄧小平が主席となって中国経済を立て直す「改革開放政策」を打ち出して以降のめざましい発展は、周知のとおり。その現代中国の“歴史的転回点[ターニングポイント]”こそが、「1976年」なのだった。
……それまでの日常が、突如として国家的規模の“非日常”的な暴力と破壊の場と化すという意味において、文革とは一種の内乱というか「内戦」に比すべきものだったのかもしれない。だからその破壊と暴力を直截に体験した世代と、「1976年」にはまだ幼かったか生まれてもいない世代とでは、日本の「戦中派/戦後派」にも似た“断絶”があったとしてもおかしくないだろう。
文革を身をもって生きた父親と、その後の急激な経済成長とともに育った息子。そこにあるのはエディプス・コンプレックス的な内面の確執とも、家父長制的なるものへの反発とも違う、もはや「別の世界(=価値観)」を生きるものどうしの埋めがたい〈隔たり[ディスタンス]〉に他ならない。そして先に挙げた作品をはじめ、父と子を描く中国映画は、多かれ少なかれこの〈隔たり〉を見つめ、いかに埋めていくか──あるいは“いかに埋まらないか”といった主題において共通している。
そして、チャン・ヤン監督の『胡同(フートン)のひまわり』も、まさにそうした文脈のなかで成立している映画だといえるだろう。この、父と息子の20数年にわたる愛憎劇もまた、文革の犠牲者である父親と、その父を理解できない息子との〈隔たり〉こそがドラマの中心としてあるからだ。
映画は、「1976年」「1987年」「1999年」という字幕とともに、3つの時代をめぐって展開する。その、それぞれの時代背景のなか、胡同[フートン](とは、中庭を囲むように民家が連なる中国の伝統的な集合住宅のこと)に住むある一家の年代記[クロニクル]が描かれていく。
……毛沢東の死去や、「四人組」の失脚で文革路線が終焉し、中国東部を大地震がおそった「1976年」。主人公である9歳の少年シャンヤン(チャン・ファン)と母親(ジョアン・チェン)のもとへ、ながらく不在だった父親(ソン・ハイイン)が突然帰ってくる。画家だった父は、下放での強制労働によって右手をつぶしてしまい、もうまともな絵を描くことができない。しかし、遊び盛りの息子に絵の才能があることを見出し、厳しく指導するようになる。3歳のときに姿を消した父親がいきなり現れ、母や自分の自由を奪ったことに反発するシャンヤン。だが父は、あくまで息子を一人前の画家にしようとする。
……開放路線で人々の暮らしが急速に変わり、民主化の機運が盛りあがりつつあった(結局それは、2年後の「天安門事件」で圧殺されるのだが……)「1987年」。19歳になったシャンヤン(ガオ・グー)は、あいかわらず厳格な父親のもとを逃げだそうと、友人(リー・ビン)と広州行きの計画をたてる。
そんなある冬の日、シャンヤンはスケートが上手い奔放な娘ユー(チャン・ユエ)と出会い、お互いに好意を抱く。そして彼女も広州に行くことになったが、出発の直前、計画を知った父親にシャンヤンは列車から引きずり降ろされてしまう。
しかも父が、妊娠していたユーを病院に連れていき、中絶までさせていたことを知ったシャンヤンは家を飛びだす。が、追ってきた父が足を滑らせて凍った湖の割れ目に落ちたとき、見捨てることはできなかった。
……経済成長によって、中国が高度消費社会の道を突きすすむ「1999年」。32歳のシャンヤン(ワン・ハイディ)は、新進画家として大きな展覧会を目前にひかえている。しかし妻(リャン・ジン)に子供を堕ろさせたことを父に責められるなど、あいかわらず父との関係はぎくしゃくとしたままだ。
だがシャンヤンは、わけあって父と母が離婚(というか、胡同暮らしを嫌い続けていた母が、念願のアパートを手に入れるための“偽装”離婚なのだが)した後、独り身の父が取り壊されていく胡同のたたずまいを毎日スケッチしていること、そしてパーキンソン病に冒されていることを知らない。
以上、いずれの時代にあっても父親は、息子シャンヤンの前で厳格な「脅威」としてあるかのようだ。それは見ているわれわれですら、「何もそこまで……」と思わずにはいられないほどの“頑なさ”としてあるだろう。
けれど、いっぽうでこの映画は、父親が文革で受けた心身の傷を抱えつつそれを決して口外せず、ただ黙々と生きる姿を見つめていく。どうしてもアパートに移りたい妻が、町の有力者にワイロを贈るように頼んでも、彼はどうしても渡すことができない。そして妻のグチや叱責を、だまって受け入れるばかりだ。
さらに、自分を強制労働に追いやったかつての友人(リウ・ツーフォン)にも、相手が後悔していることを承知しつつ謝罪を受け付けず、それでもさりげなく友人を気づかう面をもっている。──そんな、シャンヤンが決して見ようとはしなかった父親の別の一面を、この映画は丁寧に浮き彫りにしていくのである。
それはあたかも、父が息子にとり続けてきた厳しい態度の「理由」を、まるで映画自身が主人公に代わって(!)自問し、理解しようとしているかのようだ。この、理不尽としか映らなかった父親と息子の関係、彼らのあいだにある〈隔たり〉を、映画は、シャンヤンに成り代わって見つめ、父親の秘めた心情をすくい取ろうとする。
だからこそ終盤近く、展覧会で息子の絵を見た父親がだまって握手を求める、さりげない、しかし余韻に満ちた“和解”の瞬間を、ぼくたちも万感の思いで迎え入れることができるのである。
だがその後、シャンヤンの父は家族の前から突然に姿を消す。「これからは自分のしたいように生きる」という言葉を残して、いずこともなく失踪してしまう。……急速な発展で古い町並みは失われ、いつしか「根無し草[デラシネ]」と化した北京という都市の住人たち。そこに、もはやシャオヤンの父親たち(の世代)の“居場所”などありはしない。だから、息子の成功を見届けることで父親は、古い下町とその記憶とともに消えていく。
だがそれを、この映画は決して「悲劇」とは描かない。父親が“不在”となることで、息子のシャンヤンははじめてその存在と真に向かいあう。カセットテープに父が残した「下放から家に戻ったとき、私はお前を何より大事にしようと思った。お前は私より絵の才能がある。だからあんなふうに、お前に厳しくあり続けた……」という言葉[メッセージ]に、実はシャオヤンのほうこそが父親から目をそらし続けてきたことを、彼に気づかせるのだ。
しかもその父が、その後もどこかでシャオヤンたち家族を“見守っている”ことを暗示するラストにいたって、あの頑固で不器用な生き方をしかできなかった父親が、あたかも「天使的存在」として偶像化(!)されるのである(……事実そこでの父親の存在は、まるでクリント・イーストウッド監督・主演の『目撃』で、娘を「守護天使」のように見守り助ける父親[ヒーロー]のようにカッコイイんである!)。
この映画の原題は、中国語・英語ともに“ひまわり”をさす「向日葵(Sunelower)」。主人公の名前シャンヤン(向陽)とは、ひまわりのように「太陽に向かう」という意味だ。シャンヤンの父は、下放から戻ったときにもまずひまわりの種を植えていた。そして映画の最後に映しだされる、ひまわりの花。──そう、シャンヤンが「ひまわり」なら、父親は「太陽」だった。息子がどんなに反発し憎もうとも、父親が彼に与えていたものは、やがて大輪の花を咲かせるための光であり、ぬくもりであり、「愛情」に他ならなかったのだ。
それとともに、本作が監督チャン・ヤンの自伝的作品であることを知るとき(……チャン・ヤンと「シャンヤン」という名前の類似ぶり。しかも主人公は、監督と同じ「1967年生まれ」という設定になっている。さらにチャン・ヤンは、映画史的にはほとんど無名である映画監督を父にもち、胡同で暮らしていたということだ)、この映画のもつ独特の“まなざし”にも合点がいく。これは息子=監督が、治部の父親との関係──その「家族史」をあらためて見つめ直すことで、父親(と、その世代)を理解しようとすること、ふたつの世代の〈隔たり〉を乗り越えようとする試みに他ならなかったのだと。
こうして、チャン・ヤン監督自身の個人的な「父と子の物語」は、この、『胡同(フートン)のひまわり』というたぐいまれな〈ファミリー・ロマンス〉作品として結実した。前述のとおり秀作揃いの中国映画における「父と息子」ものにあってすら、この映画は別格というべき美しいものだと、ぼくは思う。
(追記)
・・・製作のピーター・ロアと監督のチャン・ヤンのコンビは、チャン・ヤンのデビュー作『スパイシー・ラブスープ』の素晴らしさに驚嘆して以来のごひいき。最近その名前を聞かないけれど、もっともっと活躍してほしい “アートとエンターテインメントの均衡” において秀でた才人だと信じている。(2024.1.23記)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
