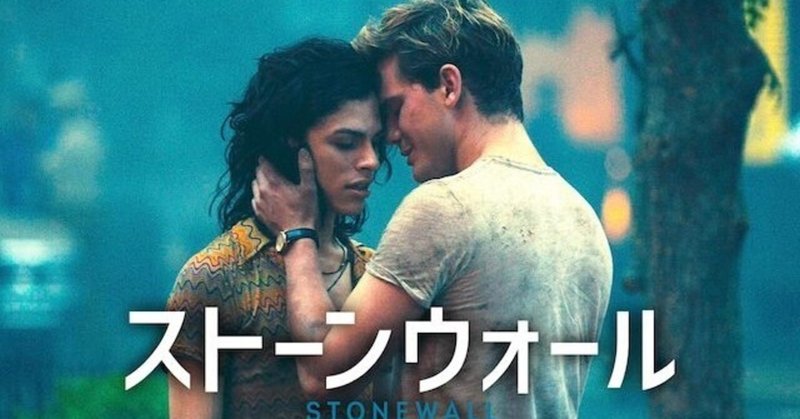
いつかどこかで見た映画 その90 『ストーンウォール』(2015年・アメリカ)
“Stonewall”
製作・監督:ローランド・エメリッヒ 脚本:ジョン・ロビン・ベイツ 出演:ジェレミー・アーヴァイン、ジョニー・ボーシャン、カール・グルスマン、ケイレブ・ランドリー・ジョーンズ、ジョナサン・リース=マイヤーズ、ジョーイ・キング、ロン・パールマン、マット・クレイヴン、デヴィッド・キュービット、アッティクス・ミッチェル、ジョアンヌ・ヴァニコラ、アンドレア・フランクル、マーク・カマチョ
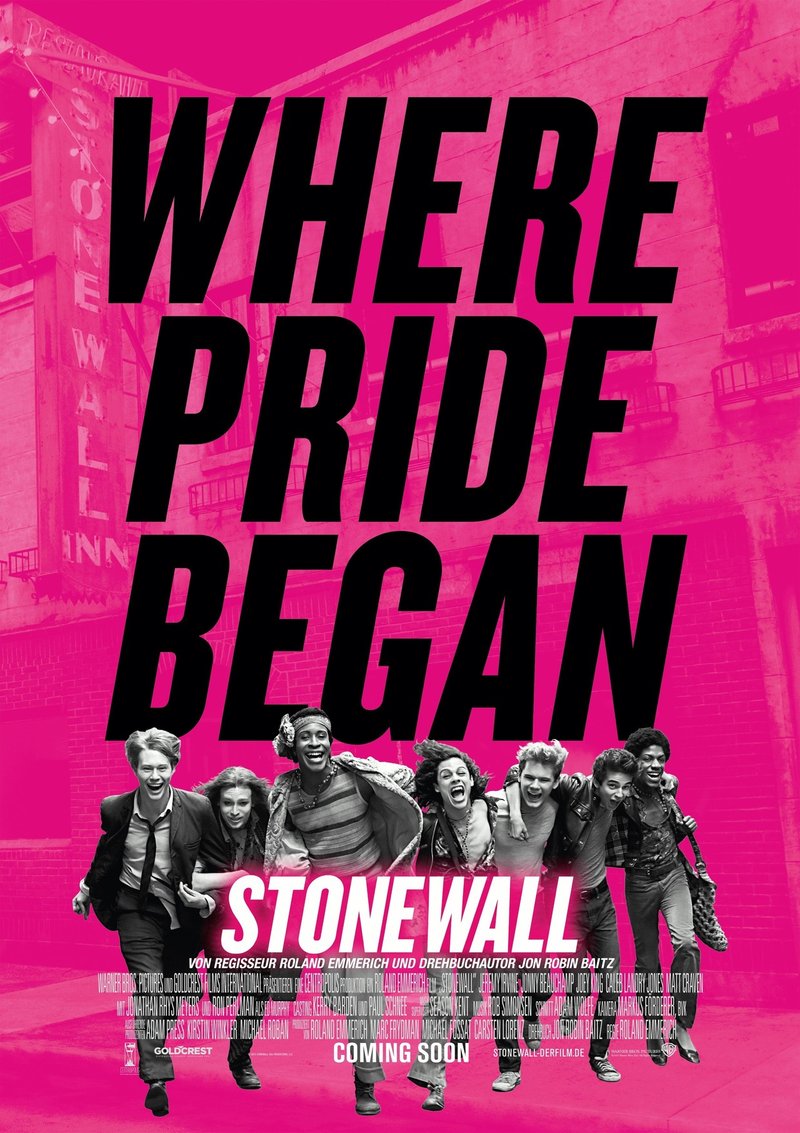
(2016年は)7月に『インデペンデンス・デイ リサージェンス』が公開されたと思ったら、12月の暮れにはもう1本ローランド・エメリッヒ監督作品が公開! おお、こいつは正月前から景気がいいハナシじゃないか。
などと小躍りしている人間がどれほどいるのかは知らないが、少なくともワタクシは喜んでいる。もちろんそれは、ぼくが「エメリッヒ信者」(……ここで「信者」に[バカ]とルビを振ってくださって結構です)であるからだ。であるとともに、何よりこの映画『ストーンウォール』が日本で劇場公開されるかどうか、いささか危惧していたからでもある。
……インターネット全盛の時代では、海外での話題もリアルタイムに知ることができる。だから、『ホワイトハウス・ダウン』と『リサージェンス』のあいだにエメリッヒ監督が撮った『ストーンウォール』が、本国アメリカでどのような評判だったかはおおよそのところ承知していた。だいたいエメリッヒ作品といえば、これまでも「バカ映画」の代名詞みたいな言われようだったが、今回ばかりは程度というか意味あいがちがう。それはもう冷笑や批判という以上に、まさしく憎悪(!)をこめた“酷評の嵐”だったのである。
公開前には作品をボイコットする署名が2万人を超え、ネットにもさまざまな罵詈雑言や本作を揶揄し皮肉るパロディ予告編(……そこには、「『インデペンデンス・デイ』『GODZZILA』『2012』『デイ・アフター・トゥモロー』の監督が贈る新たな“映画的災厄[ディザスター]”」というテロップが流れる)も登場。いざ公開されても(劇場が限定された小規模上映だったらしいが)、さらなる批判[バッシング]と惨憺たる興行成績を残すのみだった。
しかし、どうしてそこまで本作が非難され、嫌われたのか? それはこの映画が、「ストーンウォールの反乱」と呼ばれる歴史的[エポック]な事件を描きながら、その史実を“改ざん”した(と、みなされた)からに他ならない。
1969年のニューヨークで、ゲイやレズビアン、トランスジェンダーなど性的少数者[セクシャル・マイノリティ]たちが警察相手に蜂起した3日間におよぶ暴動。当時は同性愛であるだけで「犯罪者」とされ、電気ショックなど治療の対象扱いを受けていた。家族からも疎まれ見はなされた彼や彼女たちは、グリニッジ・ヴィレッジのクリストファー・ストリート界隈で暮らしはじめ、「ストーンウォール・イン」というゲイ・バーはそんな人々の“憩いの場”でもあったのだ。
そして、ゲイたちのアイドルであり「偶像[アイコン]」でもあったジュディ・ガーランド(……『オズの魔法使い』などで有名な伝説的ミュージカル・スター女優である彼女自身、バイセクシュアルだった)の急逝を悼んで、ゲイたちが「ストーンウォール・イン」に集まっていた6月28日の夜、強制捜査で踏み込んできた警官隊に、日頃から一方的な迫害や暴行に耐え続けてきた彼らの怒りが爆発。ついに街頭で石やビール瓶を投げ、ライター・オイルに火をつけて抵抗を開始したのである。
この映画は、そんなLGBTなどセクシャル・マイノリティたちの人権や尊厳を求める社会運動のきっかけとなった、歴史的な「ストーンウォールの反乱」を再現する。問題はそれを、エメリッヒがひとりの「白人青年」を主人公として描き出したことにあったのだ……
その主人公とは、インディアナ州の田舎町で高校生活をおくるダニー(ジェレミー・アーヴァイン)。彼は、幼なじみで同じアメフトチームの花形選手ジョー(カール・グルスマン)と秘密の“関係”を持っていた。だがその関係はついにクラスメートに知られるところとなり、ジョーの裏切りもあって、彼は町にいられなくなってしまう。追われるように故郷を後にしたダニーは、コロンビア大学の入学資格だけを頼りに、同性愛者たちが集まるニューヨークのクリストファー・ストリートにたどり着く。
ほとんど無一文のまま、身の置きどころもないダニーに声をかけ助けてくれたのが、街で男娼をしているレイ(ジョニー・ボーシャン)だ。やがて、レイや仲間たちとともに、この街の暮らしになじんでいくダニー。一方で、カネのために中年男相手の売春に手を出したり、警官に手ひどい暴行を受けたりと、彼は身をもって同性愛者たちがおかれた“現実”を目の当たりにしていく。
ある日ダニーは、ヤクザ者のエド(ロン・パールマン)が経営し非合法でゲイたちに酒を飲ませるバー「ストーンウォール・イン」で、同性愛者の権利の政治的な獲得をめざす活動家トレバー(ジョナサン・リース・マイヤーズ)と出会う。そして誘われるまま、ダニーは彼といっしょに暮らすことにする。が、その関係は、まもなくトレバーが他の青年と浮気したことで破局。さらに、エドによって無理やり金持ち相手の売春を強要させられそうになるひと幕もかさなって、ダニーのなかで社会に対する“何か”がめざめていくのだった。
そうしてむかえた6月28日の夜、店を強制捜査し迫害しようとする警官隊にダニーたちの怒りが爆発。トレバーの制止も聞かずダニーが投げたレンガ石を合図に、ついに暴動が勃発するのである……。
本作パンフの、映画ライターよしひろまさみち氏による解説によれば、《実際の反乱は、プエルトリコ系トランスジェンダーのシルビア・リベラと、その親友で黒人ドラァグ・クイーンのマーシャ・P・ジョンソンが中心人物だった》のであり、しかも《彼らはその後、LGBT人権活動の中心メンバーとして活躍した歴史的な偉人》なのだという。それをこの映画は、ひとりの「白人青年」を中心人物としたものに改変してしまった。しかもエメリッヒ監督自身が、「この映画は同性愛者のためだけに作ったのではなく、異性愛者に向けての作品でもある。そのために、彼らの同情や共感を得るようなキャラクターが必要だったのだ」みたいな反論(弁明?)をしたことで、さらに炎上。さらなる激烈なバッシングと総スカン状態を引き起こしたのである。
……いやはや、と思わずため息が出てしまう。確かに映画『ストーンウォール』が、「史実」を改ざんしたことはことは間違いない。しかも、よりによって白人を中心人物にしたことで、これが「ホワイトウォッシング」(とは、ここでは「人物や出来事をすべて白人中心に置きかえてしまう欺まん的な史観、あるいは詐術としての作劇術」といった意味)だと批判を受けるのも、至極もっともではある。近年やたらPC(政治的に正しい用語・配慮[ポリティカル・コレクトネス])に神経質なアメリカ映画にあって、ほとんど考えられない“無神経さ”だと認めざるを得ないだろう。
そう、もはや「政治的」にこの映画を擁護することはむずかしい。だが、公開前の予告編の段階で非難していた彼らには、これがローランド・エメリッヒ監督の作品だから“安心”してボロクソにけなしたーーという側面がないと、本当に言えるのか。いくらエメリッヒ自身がゲイであることをカミングアウトしているとはいえ、幼稚でノーテンキなSF大作や大災害[ディザスター]映画の「巨匠」が、何を血迷ったかシリアスでデリケートな配慮を要する題材に手を出したら、案の定いつもながらの“低能[アホ]”な「トンデモ映画」だった……と、はじめからタカをくくって見下してはいなかっただろうか?
なるほど、エメリッヒ監督にとって念願の企画であり私費を投じて製作したにしては、この映画はあまりにも商業的[コマーシャル]というか「娯楽的」でありすぎたかもしれない。けれど、それゆえこれをLGBTをねらった「便乗搾取[エクスプロイテーション]映画」であり、さらには一般観客層[マジョリティ]をも取りこもうとした商売人根性まるだしの作品だとするのには断固として異議をとなえたい。エメリッヒは、「ストーンウォールの反乱」という歴史的な事件の真実ではなく、あくまで事実にもとづく「ドラマ」を撮ろうとした。彼は、ここでも〈共同体〉の理念を謳う映画を創ろうとしたのである。
かつてぼくは、『ホワイトハウス・ダウン』評で次のように書いた。
《どうしてエメリッヒの映画は、「家族愛」にこだわるのか? どうせ、その方が観客の受けがいいからだろといった否定派の揶揄は、この際うっちゃっておこう。そして思うのは、家族というのが〈共同体〉の最小単位であり、エメリッヒはその作品においてほとんど常に〈共同体〉の理念こそを謳うものではなかったか、ということだ。(中略)ときに反目することがあっても、困難に出会ったら全力で戦い、最後にはわかりあえる。なぜなら、そこには〈愛〉があるから。それを地球サイズまで拡大することこそが、エメリッヒ作品における究極のテーマであり“夢”なのである。》
……一見すると大ヒットねらいのブロックバスター映画でありながら、エメリッヒ作品は、一方でほとんど常に〈共同体〉とその理想をめぐるものだった。その映画のなかで彼は、何度も地球を滅亡寸前までもっていく。それは、そのとき人類がひとつになり、新たな〈共同体〉を実現することで危機を乗り越えられるーーと謳いあげるために他ならない。そんな理想主義を、バカバカしいとかオメデタイと嘲笑する向きがあろうとも、その愚直さにはどこか心ゆさぶられるものがあるのも確かだろう。そして、その〈共同体〉の原型を、彼は「家族」に見出すのである。
エメリッヒにとって、本作『ストーンウォール』もまた抑圧され迫害されるマイノリティたちの〈共同体〉をめぐるドラマだった。「ストーンウォールの反乱」こそ、国家や体制に対する〈共同体〉の勝利という彼の理想主義そのものであり、その点における「誠実さ」だけは疑い得ないだろう。が、エメリッヒはそれをここでも「家族」の物語としてしまったことで、ほとんど“歴史修正主義者(!)”扱いされてしまったのだ。その物語にしても、故郷[ホーム]を追われた主人公が新たな〈共同体〉と出会い、そこで人間的成長をとげることでふたたび「家[ホーム]」に戻る。という、何とも実にありきたりなもの。もはや、いかなる弁解や“擁護”も無力かもしれない。
ーーしかし、とあらためて思う。それでもぼくは、ここでのジェレミー・アーヴァインや新人ジョニー・ボーシャンをはじめとする役者たちの、素晴らしいアンサンブルを心から賞賛する。あるいは、電車の車窓から主人公が眺めるニューヨークの街並みなど、その情景描写の繊細さと“郷愁感[ノスタルジア]”を愛する。何よりも、ふたたび故郷に立ち寄ったダニーが道路で父親の車とすれちがう場面などの、見事としか言いようのない演出の確かさに心打たれる。
映画『ストーンウォール』は、確かに「政治的」に間違ったかもしれない。だが、「映画的」には決して間違ってなどいないのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
