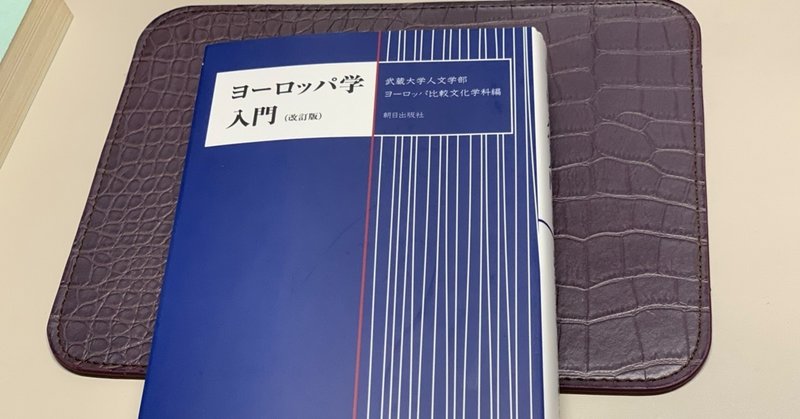
多様性と連帯という〈理念〉:『ヨーロッパ学入門』摘読(5)III&V「EUの歴史と現在」「ヨーロッパ多言語主義の可能性」
『ヨーロッパ学入門』を読み始めて5回目。今回は第3章「EUの歴史と現在」と第5章「ヨーロッパ多言語主義の可能性」を。
この本が改訂版として出たのが2007年であるから、いささか旧聞に属する話ともなる。近年の難民問題やイギリスのEU離脱などには当然触れていない。あくまでも、このnoteは文化の読書会のためのメモなので、そのあたりはご了承願います。
理念としての“ヨーロッパ”
EUとは、ヨーロッパ連合のことである。これは、ヨーロッパの国々が設立した超国家的な国際組織である。ただ、単なる国際機関でもなく、また連邦国家でもない。それぞれの国家の主権を認めたうえで、政治や経済などの一部の権限を委譲するという、歴史上かつてない試みである。現在の構成国は27か国であり、公用語は24言語に及ぶ(第5章では23言語)。
EUにおいて重視されているのは「多様性のなかの統合」である。フォンテーヌは、「欧州人」を「人権への信念、社会的連帯、自由企業体制、経済成長の成果の公正な分配、良好に保たれた環境のもとに生きる権利、文化・言語・宗教における多様性の尊重、伝統と進歩の調和など、先祖から受け継いだ豊かな価値観を大事にしている」と述べている。
「一つのヨーロッパ」への希求
欧州統合の動きが具体的に浮上してきたのは、第一次世界大戦後のことである。オーストリアの貴族であるクーデンホーフ=カレルギーは、汎ヨーロッパを1923年に提唱し、1926年には第1回の汎ヨーロッパ会議をウィーンで開催するところまではいったものの、ヒトラーの台頭によってこの動きは挫折した。
第二次世界大戦の後、独仏間の平和構築、さらに多国家・多民族からなるヨーロッパでは物資の移動や人の移動における大きな障害の克服といった課題が顕在化した。物資の場合は、とりわけ関税である。そのため、関税同盟を念頭に置いた経済協力が議論されていた。それが、フランスのジャン・モネ、そしてロベール・シューマンの提唱や尽力により、ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体として結実する。これが、ヨーロッパ連合の礎石となった。ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体は、ヨーロッパ経済共同体、そしてヨーロッパ原子力共同体への設立へとつながり、1967年にはそれらを統合するヨーロッパ共同体(EC)が誕生することになる。その後、ECそしてEUは次第に拡大し、冷戦終結後は旧東ヨーロッパ諸国も参加するに至る。その過程で、二度の石油危機やニクソン・ショックなどを経て、ヨーロッパ共通通貨制度も1979年に導入されることになる。
共通通貨としてのユーロの強さと脆さ
このヨーロッパ共通通貨制度が、現在の単一通貨ユーロの導入につながっていることは言うまでもない。この単一市場・単一通貨という制度設計が、もともと多様な諸文化を内包するヨーロッパ諸国における、国境を超えた「アイデンティティ」を高めているのは事実だ。
同じ通貨というのは生活の基盤である経済における交換の共通性を担保する。それが、一方でそれぞれの国のアイデンティティにかかわるというのもまたコインの裏面として、看過すべきではないだろう。いわゆるEUでのイニシアティブを有している国と、そうではない国の金融政策に対する温度差や姿勢の違いも、当然ながら顕在化する。対外的には、ドルに対する基軸通貨としての地位をユーロは獲得したわけだが、それゆえにEU内部での不安定性も抱えることになっている。
このあたりは、次に読むブローデルの『日常性の構造』にもかかわってくるのではないか。
“ヨーロッパ”の境界
さて、EUの制度的な側面については、ここでは省略しよう。この文化の読書会での議論の視座に立脚するとき、EUの加盟国の範囲の問題、つまりヨーロッパの境界の問題が、一つの焦点となる。
冷戦終結後の東ヨーロッパ諸国(厳密には、中欧)のEU参加は、単に自由経済圏への参加ということだけでなく、ロシアの東方教会圏ではなく、もともと西方教会の文化圏に属していた国々のヨーロッパへの復帰という側面を有していた。その後、EUはフィンランドやスウェーデンといった北欧諸国、バルト三国など、さらにブルガリアやルーマニアなどの東欧諸国、そして2013年にクロアチアの加盟を承認した。
これ以外にも加盟候補国はいくつかあるが、そのなかでも長期にわたる議論となっているのがトルコである。宗教的な相違や、トルコにおける民族的事情など、さまざまな理由がある。このあたり、まさに〈地中海世界〉の多様性と、それがもたらす文化的・政治的な軋轢があるとみるべきかもしれない。多様性や寛容を謳いつつ、またそれを実現へと進めようとしつつも、乗り越えるべき障壁は決して低くないことを、トルコの加盟問題は浮き彫りにしているように思われる。
移民、そして難民の問題
EUあるいはヨーロッパにとって、今避けられない問題の一つが移民、さらに難民の問題である。この問題に、ここで深く立ち入るだけの準備は私にはない。ただ、これがヨーロッパにとって、EUにとって、その理念を問われる課題であることは明らかである。そしてまた、この問題に対して他人事でいることができてしまう日本に住む私にとって、どう受けとめるべきか。まだ見解を述べることができる段階にない。ただ、考えなくていいわけではないことは確かだ。
そのことだけ、ひとまず書きとめておく。
ヨーロッパにおける言語の多様性(第5章)
ヨーロッパには、インド・ヨーロッパ語族に属する言語だけでなく、ウラル語族、アルタイ語族、セム語族、系統不明なバスク語、混合語であるイディッシュ語などがある。言語は、単なる意思疎通手段ということを超えて、文化として現われる生活それ自体を規定する(生活のなかから生まれてくるとともに)。さまざまな文化的背景を持つ多様な人々が意思疎通する際、共通の言語があることはきわめて便利である。しかし、同時にそれは広い地域で用いられている言語が主流となり、少数派の言語は話者を失って、翻訳されえない多くの文化的な富が活力の基盤を失ってしまう。
そこで、EUは多言語主義を打ち出している。これは、単に多様な言語が存在するというだけのことではない。個人においても、社会においても、複数の言語文化がお互いに影響しあって新たな知と伝達能力を産み出し、これを共有するような状態を意味する。
そのために、義務教育の段階で2つの言語を習得するプログラムのデザインや交流の促進などの言語教育、EUにおける多様な公用語(24言語)の採用などが展開されている。それであっても、多数の話者がいても採用されていない言語はある。さらに、多様性の尊重と統一という、一見すると矛盾した思想を実現しようとするなかで、地域言語や少数言語などの非公用語を文化的財産として位置づけようとする動きもある。ただ、これに関しては、加盟国の批准が得られないなどの停滞もまた存在する。ことほどさように、言語政策というのは、いわゆる国家という政体をかたちづくり、動かしていくうえでシビアな問題なのである。
若干の考察
EUが理念先行、あるいはエリート主義だという批判はよく聞く。たしかに、その側面が多分にあることは事実だろう。その一方で、多様性の尊重とヨーロッパとしての統一性という矛盾した理念をいかにして実現していくのかに膨大なエネルギーを注いでいるのもまた事実である。弁証法(Dialektik)という考え方も、こういった諸対立をいかに止揚(aufheben)して、創造的な解決の可能性を模索するのかという姿勢のなかで捉えられるべきだろう。
長くなった。この辺でひとまず。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
