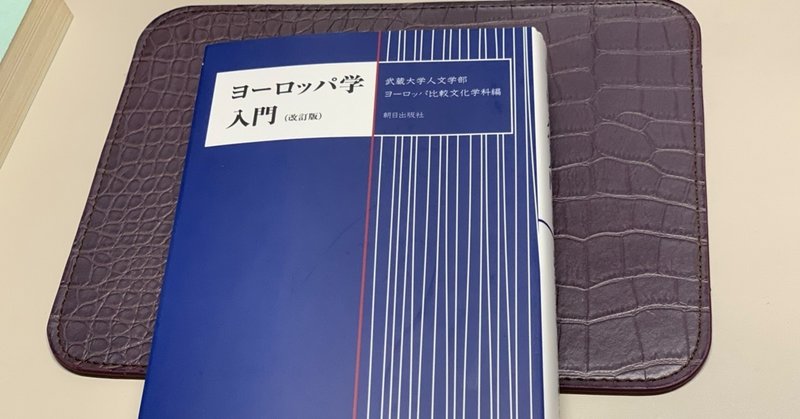
美的批判としての〈前衛〉:『ヨーロッパ学入門』摘読(4)X「近代〈前衛〉の試みと女性芸術家」
『ヨーロッパ学入門』を読み始めて4回目。今回は第10章「近代〈前衛〉の試みと女性芸術家」。
実は、私、言語芸術(文芸)や身体芸術(演劇)にはかなりの関心があるけれども、美術(絵画)にはあまり思い入れがない。建築や庭園などには関心があるのに。でも、この章を読んで、その認識が少し変わりつつあるような気もする。そのあたりも含めて。
中世・近世から近代へ:市民社会における芸術
一般的に「西洋美術」として、私たちがイメージするのはイタリア・ルネサンスにおいて体系化され、ヨーロッパに広まったものである。アルベルティが『絵画論』において述べるように、「描こうとするものを通して見るための開いた窓」から広がる三次元的な空間の奥行きが、絵画として描き出されるという線遠近法(透視図法)が、そこでの基本的な、まさにパースペクティブであった。これは、市民社会が到来するまで変わることがなかった。
というのも、画家をはじめとする芸術家たちのパトロン、つまり発注者は教会や王侯などの貴族階級であったからだ。ところが、市民社会になると、こういったパトロンからの発注ではなく、描き手である画家の自由裁量によって絵が描かれることになる。オリジナリティが求められるようになったわけである。芸術至上主義という考え方も、これに呼応するようなかたちで登場する。
ここで大事なことは、こういった制作者の意思が前面に出てくることによって、芸術が「新しさ」を一つの価値判断基準とするようになった点である。ボードレールは、永遠的な何ものかと並んで、一時的な何ものか、別の言い方をすれば、絶対的な何ものかと特殊的な何ものか、その両方に美が宿ると指摘し、とりわけ後者の重要性を指摘した。ここに、モダニズムという考え方が浮上してくる。
〈いま〉を描く営みとしてのモダニズム
こうして、芸術は定型化された普遍性ではなく、日常に潜むさまざまな瞬間に美を見出すようになる。ここで付け加えておくと、定型化されていない美ということは、今まで〈美〉と無批判に信じられてきたありようについて、そこに潜む問題性を抉り出すことにもつながる。マネの「草上の昼食」における裸婦像は、そういった意識を白日の下にさらしたわけである。また、印象派のモネが試みたのは、世界をどのように描き出すのかという技法や様式の革新だった。モネが挑んだのは、陽の光によってものの色彩が移り変わっていくさまを敏感に写し取ることであった。たとえば、彼の作品のなかでも有名な「睡蓮」においては、遠近法などのそれまでの技法が放棄され、どのように画家の目にその景色が映じたのかを描き出すことに重点が置かれている。このように、モダニズムにおいては画家の視座というものが明確に意識され、それをどのように描き出すかということに焦点が当てられていた。
抽象化と再構成:キュビスムと未来派
20世紀に入り、第一次世界大戦が勃発するまでの14年間はヨーロッパにおける「芸術の英雄時代」とも称される。この時代、伝統的な芸術の枠組を打ち破ろうとする画期的な様式実験が数多く行われた。マティスやピカソ、キルヒナーやカンディンスキーなどの試みがこれにあたる。たとえば、ピカソは対象をさまざまな視点から見た面に分解し、それを組み合わせていくという方法を採った。こうなると、一見してもそれが何を描こうとしているのかわからないという事態が生じる。そこに描かれているのは、目に見える世界とはもっと別の、純粋な感覚や理念、感情であった。こういった急進性が、現代芸術の先駆となっていく。
一方、写真や映画といった新しいメディアを念頭に置いた芸術も台頭してくる。この背景には、急激に進展した工業化や都市化があった。ミラノの詩人・マリネッティが起こした未来派は、躍動感を描きとることに重点を置いた。具体的には、走る自動車や疾駆する馬、サッカーの試合などといった、まさに近代が市民生活にもたらした(馬は、いささか異なるかもしれないが)さまざまなモノやコトが生み出す躍動感である。
このような方向性は、モダニズムが内包していた「それまでの〈美〉に対する批判的視座」を、より濃厚にしたものといえる。それゆえに、社会運動というベクトルとともに、より純粋芸術を志向するベクトルの2つを内包していた。この緊張関係が、これに続く芸術思潮に受け継がれていく。
解体と再創造:ダダとシュルレアリスム
ヨーロッパ全土を戦火の渦に巻き込んだ第一次世界大戦は、一部の芸術家たちに殺戮兵器を生み出した近代、あるいは西洋文明に対する幻滅をもたらした。彼らは、自分という存在を揺さぶるような一見とりとめのない無意味なイメージのなかに、新たな意味と美的経験を見出そうとした。それが、ダダである。ダダイズムは、一見一読一聴して意味のない要素を並べ、混沌を生じさせることで、芸術表現をリセットしようとした。コラージュやモンタージュといった技法は、そのなかで生み出されていった。さらに、デュシャンの「泉」のように、本来、美的価値とは全く無縁の事物を見つけ出して、日常の文脈から切り離して作品とする「レディメイド」というあり方も、ダダから生まれる。ここから「オブジェ」という概念が生まれてくるわけだが、ここには素材の加工から「ものの見え方」の発見やそれを選び取る判断に、作家性のありかを見出すという姿勢がうかがわれる。その点で、芸術はきわめて哲学的思索に近づくことになる。
このダダが1921年ごろに下火になって、ブルトンがシュルレアリスムという方向性を打ち出す。ここで重視されたのが、人間の無意識であった。ここにはフロイトの精神分析、とりわけ自由連想法があった。フロイトの精神分析において、夢は無意識のかたちを変えた現れとして重視される。そこでは、現実にはあり得ない異質なものどうしの出会いが生み出す不思議さ、神秘さ、不安やなつかしさなど「不可思議(驚異)」が美的な経験の真髄として位置づけられている。それを具現化していったのがマックス・エルンストであった。エルンストは、さまざまな技法を駆使して「ありそうであり得ない」光景を描き出そうとした。
シュルレアリスムは、素朴でもいいから自由な空想をはばたかせて描くことを重視した。それゆえに、それまでの主流であったヨーロッパの男性芸術家だけでなく、女性芸術家、そしてアジアや南米などにも広がっていった。
前衛のなかの女性芸術家たち
その一方で、シュルレアリスムが基盤にしていたのは性的欲望をエネルギーの根源とみたフロイトの精神分析であった。そして、それは男性からの視点であった。それを描き出したことで、かえってシュルレアリスムはモダニズムがはらむ物神崇拝を暴き出すことにもなった。
たとえば、ハンナ・ヘーヒは女性向けファッション雑誌から写真を切り抜き、フォトモンタージュという技法で再構成することによって、その混沌から慎重に個々のイメージを取り出して、新しい意味の文脈を構成していった。また、フランスのレオノール・フィニは、自分の個人的な夢のヴィジョンを文学的な想像力をはばたかせて表現した。このほかにも、数多くの女性芸術家たちが、シュルレアリスムの考え方をそれぞれのうちに消化して、自分自身の存在を捉え返すように描き出していった。メキシコのフリーダ・カーロや、写真を用いたフランスのクロード・カーン、そしてメレット・オッペンハイムなどが、ひじょうに優れた表現を提示していった。
彼女たちに共通しているのが、自分という存在を外部から規定している容貌や外見という自己イメージを徹底的に操作することで、現実を超えようとするという姿勢である。この系譜に、シンディ・シャーマンや、ルイーズ・ブルジョワ、キキ・スミス、草間彌生といった現代の表現者たちも連なっている。
【小考】美的批判としての〈前衛〉
この章、私にとってはひじょうに刺激的であった。読む前は、それほど惹かれていたわけではなかっただけに。ここで史的に描き出されているのは、まさに「美的批判としての〈前衛〉とは、いかなる事態をさすのか」であるように思う。私自身、前衛芸術が好きかといわれると、残念ながらそこまで好きともいえない。しかし、好きか嫌いかという話ではないのだ。ついつい、私たちが見ないふりをしてしまっている、何なら気づきさえしていない事態を感性的に伝えるところにこそ、〈前衛〉が私たちの社会にもたらしてくれる「新しい視座」があるわけだから。
その点で、美的批判としての〈前衛〉は、同時に〈批評〉をも要求するといえるだろう。〈批評〉とは、かなりの拡大解釈になるかもしれないが、それを享けとった人がその人が意識的、また無意識的に抱いている価値判断の基準体系としての〈意味〉を自覚的に捉え返しつつ、その作品がその人にもたらす(それが、批評する人以外にとっても同じであるかどうかは別問題である)〈意味〉への影響を咀嚼していくことなのではないか。そして、そのことを人に伝えていくこと、それが〈批評〉であるのではないか。
それゆえに、作品は、つくり手の何がしかの意図を内にはらんだアーティファクトとして自律的に存在しつつ、同時に享受する人からの応答があって初めて成り立つといえるように思う。
こんなことを、この章を読んで考えた。もっといろいろ湧き出てきそうだが、このnoteは本来1,000字までの概要と感想というルールがある。4倍にまで超過してしまったので、これでおしまい(笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
