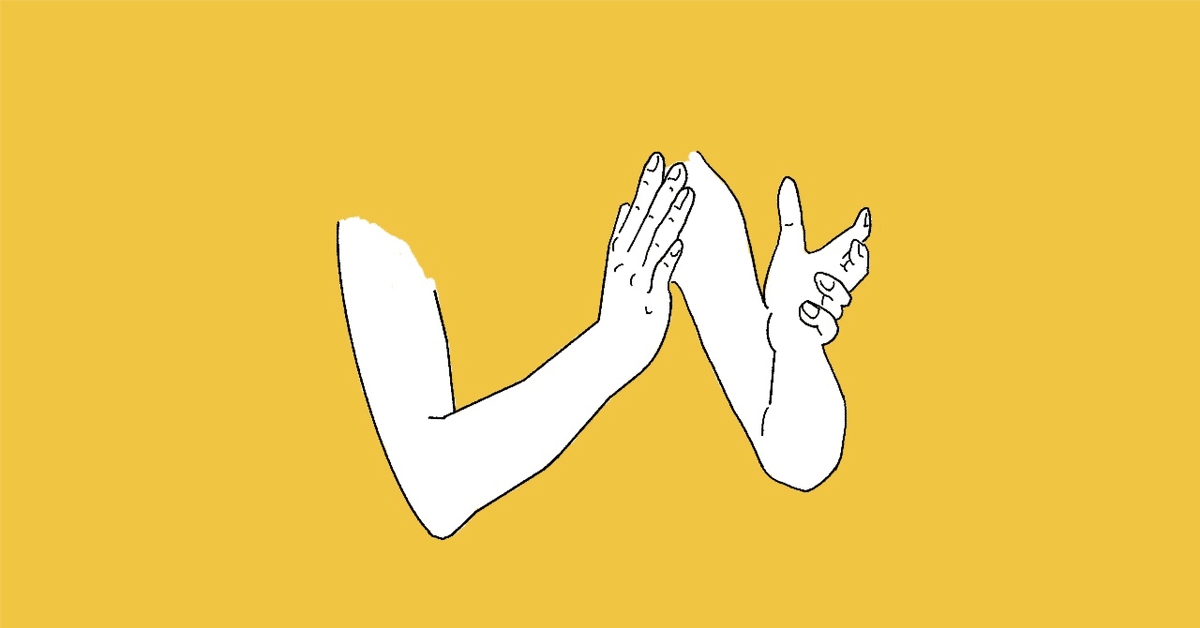
劇場という共同プロジェクト。
僕らがよくよく知っているように、世界は善と悪の二元論ではない。ある視点からは「善い」とされているものが、別の視点からは「悪い」とされるなんて、僕の脳ミソから引き出される拙い例を挙げずとも世の中にはいくらでも転がっている。
そして、そのある種曖昧な善と悪との隙間を埋めるように「場合によっては善」とか「まあ、そのシチュエーションならどちらかといえば悪」といったような都度都度答えを出していくしかないグラデーションの部分が存在していることも僕らはよく知っている。
けれど悲しいことに、日常生活のなかでふいに「これってどうしたらいいの」的場面に出会うと僕たちは往々にして、その瞬間にうろたえるなりパニックになるなりで、反射的に「善だ!悪だ!」の二元論的回答をしてしまいがちなのだ。
それこそが数々の”争わなくてもいいはずの争い”を生んでしまうことを経験的に知っているにもかかわらず、だ。
ところで僕は、舞台に出ることを仕事にしていながら同時に、自分でも舞台を観にいくことが大好きだ。仕事の合間を狙っては気になる作品のために劇場に足を運ぶようにしているし、自分の仕事のせいで見たい舞台を観られない時なんかは「なんのために舞台やってるんだっけ……」という気持ちになったりもする。
だから僕は、劇場という生態系の「中の人」であると同時に観客なのだ。今日はその舞台のあちら側とこちら側を行き来可能な、ある意味、捉え方によっては日和見的な立場から、とある事象について考えてみたいと思う。
観客席での「手拍子」について。
---
・作品に影響を与える力
演劇やダンスなどのパフォーミングアートやコンサートなど、いわゆる劇場空間で行われる生のパフォーマンスは、それぞれの表現形態や観覧文化の違いを見ていくとそれこそ千差万別だ。
僕はいま、ミュージカルや演劇を観にいくときの「手拍子」や「拍手」について考えてみたいと思っているが、これが世界的なロック・ポップアーティストのドーム公演となると話が違ってきたりする。
それに、ミュージカルや演劇であっても、Aという共同体ではOKなことが、Bという共同体では受け入れられないということもある。さまざまなローカルルールが乱立している状況が現在の混乱を招いているように思う。
ただ、どんな会場、どんな作品、どんな団体であっても、共通して言えることがある。
観客からの手拍子や拍手には、演者のパフォーマンスを助ける力もあれば、ある場合においては演者のパフォーマンスを妨げる力もあるということだ。
観客からの手拍子や拍手には間違いなく、「作品に影響を与える力」が宿っている。そこに大きな魅力があると同時に、大きな恐ろしさがあるというこの事実をまず認識するところから全てがはじまるのではないか。
古代ギリシャの悲劇を上演する劇場からインスピレーションを得て、19世期の終わりにリヒャルト・ワーグナーがバイロイト祝祭歌劇場を作り、劇場空間における舞台と客席をプロセニアムによって明確に分化する以前、特に西欧の劇場はいまよりもだいぶ混沌とした場所だった。
社交の場という意味もあるし、平凡な生活から抜け出すための憂さ晴らしの場という意味もあっただろう。だから作品上演中であっても観客席からは、笑ったり囃し立てたりブーイングをしてみたり、あるいはそこで会った人と世間話をしたりなど、さまざまな音が立ち上がっていたろうと推測される。
馬蹄形の劇場。1階の土間。貴族や有力者が買う上階層のボックス席。そのような劇場の建築構造がこの賑やかな観劇スタイルを支持していた。
それがワーグナーによって改革される。1階席には座席が敷き詰められ、間の通路がないため一度着席してしまえば観客が立ち上がることは困難になる。シャンデリアなどの華美な装飾も廃され、舞台上で行われるスペクタクルに集中するように、劇場空間自体が観客に向けて無言の圧力をかける。
近代演劇の流れはこの劇場構造を汲み、また、イプセンに代表される緻密なリアリズムの作劇法が市民権を得ていったことも影響すると思うが、観客は「集中して」「静かに」舞台上の出来事を鑑賞するという新たなお約束が生まれていった。
劇場は混沌とした場所から、「静かな場所」になっていったのだ。
そんな「静かな」空間において、音を立てるという行為は大きな力を持つ。
俳優がセリフをいう。俳優が足音を立てる。俳優が呻き声を上げる。あるいは、劇に伴奏する音楽家がピアノを弾く、ギターをかき鳴らす。音響が雷を鳴らす、銃声が鳴り響く。
こういった、上演者たちによって「意図された音」のすべては、舞台上のドラマをより効果的に客席に伝えるための手段だ。緻密に計算されているし、長い稽古期間を経てこれ以上増やすことも減らすこともできないという地点に落ち着いていることが多い。
ただ、本番ではそういった「意図された音」以外の音が静かな空間に付け加えられる。つまり、観客の咳払い、観客がパンフレットをめくる音、観客の服の衣擦れの音、そして観客の拍手、観客の手拍子だ。さいきんでは不意に鳴る携帯のアラーム、なんかもある。
これらの上演者にとって「意図されない音」たちは、意図されていないから立てるべきではない、というものではない。咳払いや、身動ぎをした際に出る衣擦れの音は生理現象だし、劇を見ながら俳優の名前が気になってパンフレットを確認したくなる気持ちも多くの人に理解されるだろう。
というかそもそも、劇場の客席から音がしてくるという事実は、いまの時代には上演者にとっても当たり前だと認識されている。つまり、アメリカの現代音楽家ジョン・ケージは、オーケストラが放つ音以外にもコンサートホールには音が満ちていることを提示するためにあの有名な無音の音楽「4分33秒」を作曲したのだ。1952年のことだった。
客席から観客が立てる「意図されない音」は、大なり小なり舞台上の演者や上演されている作品自体に影響を与える。この影響がいい方に転ぶか、悪い方に転ぶかは正直言って「ケースバイケース」としか言いようがない。
けれど、最低でも1〜2回劇場に足を運んだことのある人なら自然と理解しているはずだ。
生理現象はとめられない。だけど、だからと言って静かなシーンでド派手に「へっくしょい!!!」とくしゃみをぶっ放す観客はほとんどいない。咳にしたってくしゃみにしたって大概の人達は、大きな音楽が鳴っているときまで我慢するとか、どうしても我慢できないときはハンカチを口元に当ててなるべく音を小さくするとか、そういった気遣いが伴う。
生理現象は仕方ないけれど、するとしたら劇の進行になるべく支障を与えないように配慮をする。こういった心配りは、劇場を愛する観客たちにとってはごくごく自然な振る舞いとして学習されている。愛が溢れている。
パンフレットをめくるにしたって、多くの人たちはこれ見よがしにめくったりはしない。隣の席に座る人に迷惑をかけないようにおずおずとめくる。なぜならばいま座っているこの場所は、自分の部屋ではないと理解しているからだ。
劇場に通う人々が自然に身につけていくこういった気遣いはつまり、「静かな」劇場空間における音の影響を、意識的にも無意識的にも理解しているからこそ生まれてくる心情だと僕は思う。
その上で、拍手や手拍子のことを考えてみるとどうだろう。
そもそも咳などの生理現象と違って、拍手や手拍子は自分の意思で行うものなのだから、同じ土俵で考えるのはおかしい、という見方もあるかもしれない。確かにそうだと思う。
だけど、だからこそその「違い」に、劇場での手拍子の是非を考える上での面白さがある。
なぜ多くの人は生理現象に伴って生じてしまう音については自然に配慮をするのに、自分の意思で行える手拍子や拍手においてはその自然の配慮をときに宙吊りにしてしまうのか。
次の段で、劇場空間で「積極的」に音を出すことについて考えてみる。
---
・ハレオ、大向う、ラデツキー
スペインの民俗芸能のひとつ、フラメンコには「ハレオ」という掛け声の文化がある。
踊り手に対して共演しているアーティストや客席に対して「いいぞ!」とか「素敵!」とか「さあ!行こう!」という意味のスペイン語で声を掛けることが、フラメンコのステージにとっては必要不可欠な構成要素となっている。
当然、のべつまくなし、いつでもかけていいというものではなく、音楽の切れ目のタイミング、踊りのキメのタイミング、あるいは次のフレーズに移り変わる前の踊り手たちが一種様子を伺っているようなタイミングなどで発せられることが多い。
このハレオがいいタイミングで決まると、ステージ上の演者たちの興も乗り、観客との一体感も出て、そのパフォーマンスの空間が劇的に演出されることになる。
もともとフラメンコは民俗芸能であるから、演者と観客の境目は曖昧であった。日常の中に生まれる祝祭的な時間を、このハレオなどを用いてより親密に、晴れやかに過ごしていたのだろう。
一方、フラメンコには構成要素として重要なパルマという「手拍子」のようなものがある。両手を打ち鳴らして音を出すのだが、これは厳密にいえば「楽器」のひとつでもある。
はじめてフラメンコを見るという人がパルマを手拍子と勘違いして客席から手を叩いてしまう、ということがときたま起こるらしいのだが、これは歓迎されない。音楽の流れを理解した人が叩かないと、演奏として成立しなくなるからだ。
日本の伝統芸能のひとつ歌舞伎の世界には、大向うがある。
劇場の最後方席に座る玄人ほどに芝居を観ることに長けた観客が、上演中に舞台に向かって掛ける声のことだ。これも、間合いや言う内容が難しく、演者や舞台上の雰囲気との阿吽の呼吸が必要なため、誰にでも許されたものではない。
なにより、大向うを担当する観客は劇場側から指定されており、その代わりに芝居を観る料金がかからない通行証を持っていることもある。
歌舞伎という芸を盛り上げ、客席と舞台の一体感を生み出すのに必要な要素が大向うだ。客席から発せられる音としてはフラメンコのハレオと同様に、発する側にかなり高度な表現に対する理解が必要とされる。
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によって毎年年明けに開催されるニューイヤーコンサートでは、アンコールで必ず「ラデツキー行進曲」が演奏される。
この楽曲の中では観客が手拍子で音楽に参加されることが慣習的に許されている。こういった例はクラシック音楽の演奏会では非常に稀である。
しかし、この手拍子も全く観客の自由に委ねられていることは近年あまりなく、その音量の大小を、指揮者が(客席側に振り向いて)指示をする場合が多い。
つまり、ウィーン・フィルのニューイヤーコンサートにおいては、「ラデツキー行進曲」の場面だけ限定的に観客の「音楽演奏中の手拍子」が許され、かつ、その演奏のテンポや音量の変化に手拍子も対応することを暗黙のうちに要求されている。
フラメンコのハレオ、歌舞伎の大向う、ラデツキーの手拍子、どれにしてもその上演や演奏のされる空間を盛り上げる効果のある観客の参加行為だ。
しかし、どれにしても適切な場面、タイミング、速度や大きさなどがあり、これは暗黙の了解としてある程度の学習が必要であることが前提とされている。
もちろん、まったくの初心者が初めてその場にいたとして、周りの声や手拍子につられて間の悪いときに声をあげたり手を叩いたりしたとしても、良心的な周りの観客は闇雲に目くじらを立てることはないだろう。
とはいえ、そういった「間の悪い」行為の全てが手放しに許されるわけではないことも認識しておきたい。これは劇空間に於ける排他的な同調圧力というよりは、その表現をその場の大勢と、より楽しく楽しむための最低限のルールとでも認識しておきたい。
---
・「消費型」と「共同プロジェクト型」
少し話は変わるが、社会に参加している私たちは皆、お金を払いモノなりサービスなりを買って生活をしている。
朝、コンビニでコーヒーを買う。昼食に食堂でうどんを食べる。仕事終わりに英会話教室に通う。家に帰って寝る前にサブスクリプションサービスで映画を観る。
コーヒーやうどん、サブスクの映画はモノだし、英会話教室はサービスだ。
この購買行動はざっくりと2つに分類することができる。
「消費型」の購買と、「共同プロジェクト型」の購買だ。
消費型は字のそのまま、お金を払ってモノなりサービスなりを買うところで商取引が完結する。購買者=消費者は金銭を払うことによって、その金額に見合った別の形の価値商品(コーヒー、うどん、映画)を受け取る。
対して「共同プロジェクト型」の購買は、金銭を支払い商品を受け取れば商取引が完結するというシンプルな構造ではない。むしろ「金銭を支払ってからが商取引のスタート」という場合も多い。
たとえばパーソナルトレーニングを例に挙げてみる。これは典型的な「共同プロジェクト型」の購買活動だ。
1時間なり1ヶ月何回なりの設定で顧客はトレーナーに料金を払う。けれど、お金を払ってトレーナーを雇ったところで自分の目的(筋力をつけたい、スタイルをよくしたい)は達成されない。
顧客が買ったトレーナーとの時間で、トレーナーは顧客に目的にあった運動のやり方を教え、実践させる。この時点で顧客側に「トレーナーの指示に従い、最大限に努力する」という協力の必要が発生する。
また、そのトレーニングの時間だけでなく、食事制限などの指示がトレーナーから出される場合がある。あるいは次のトレーニングの約束までに「このストレッチと筋トレを継続してやってきてくださいね」という場合もある。
ここにもまた、顧客自身の継続的努力が要求される。この努力への協力姿勢があるかないかで、パーソナルトレーニングの目標達成の速度と精度は大きく影響を受ける。当然、協力姿勢がある方が目標達成の速度と精度は上がる。
つまりパーソナルトレーニングというのは「私は痩せたい!だからあなたにお金を払う!なのであなただけが努力して私を痩せさせて!」という姿勢では成立しない。お金を払う顧客側の協力姿勢なり努力姿勢が絶対的に必要なのだ。
お金を払ったから払った側がエラい、トレーナー側はどうにかして(お金を払った私は頑張らずとも)私の目標を達成させる義務がある、というような発想は、消費型の購買行為では成立するかもしれないが、共同プロジェクト型の購買行為では成立しない。
パーソナルトレーニングだけでなく、英会話教室やボイストレーニングは共同プロジェクト型の取引だ。あまり意識されない場合が多いが家の建設やリフォームも共同プロジェクト型だし、コンサルタントを雇うということも「共同プロジェクトの相手を雇う」ということだ。
ただ、日本で生活をしているなかで「この購買行動は共同プロジェクト型の購買行動だ」と意識しながらモノ/サービスを買う機会は非常に少ないと思う。多くの場合が「消費型」の思考でされる購買行動だろう。
この「消費型」「共同プロジェクト型」はキッパリと二分できる、二項対立ではないということも指摘しておきたいと思う。大部分が消費型であるが、共同プロジェクト型的な振る舞いも要求されるという場合もある。
例えば会員制のバーやある程度グレードの高いレストランなんかがそれだ。
お金を払えばお酒なり美味しい料理なりは提供されるが、お金さえ払えばすべての欲求が達成されるわけではない。身なり、振る舞い、注文の仕方などなど、その場にふさわしい行動と服装などを”暗に”要求される。
これは、受け取る食べ物や飲み物に関してはある種の消費型購買が成立するが、「その場」に参加するためには「共同プロジェクト型」の行動が要求されるというパターンだ。
その「共同プロジェクト型行動」の煩わしさを嫌う顧客のために、「ドレスコードなし」だったり「明瞭会計」だったりを掲げて「誰でもどうぞ〜」をウリにする店舗もある。これは、「共同プロジェクト型」の雰囲気を借りて「100%消費型」のビジネスとしてリデザインしたものだと考えられる。
いずれにせよ、同じ「モノやサービスを買う」という体験でも、その商品が「消費型」なのか「共同プロジェクト型」なのかで購買者に要求される行動はずいぶんと変わる。
自分の認識に「消費型」の購買行動しかないと、世の中というのはずいぶんと過ごしにくい場所になるのではないかと僕は想像している。
「なぜお金を払っているのに自分の望んだものが与えられないのか」
「なぜお金を払っているのに自分の振る舞いを注意されるのか」
そういった不満を受け取る場面が、あるいは増えてしまうのではないだろうか。
---
・劇場という共同プロジェクト
もう一度、劇場における観客席での「手拍子」について考えてみよう。
「静かな場所」である劇場において、意図的に鳴り響かされる「手拍子」は多大にその劇空間に影響を与える。
それが「良い影響」の場合もあれば「悪い影響」の場合もある。ただこの「良い/悪い」はその劇場の全ての人において100%そうであるということでもない。
ある作品のある場面に発生した手拍子が、とある観客にとっては「悪い」もので、別の観客にとっては「良い」ものであるといった受け取りのばらつきが当然に起こる。当然、ある俳優にとっては「良い」ものであるが、別の俳優にとっては「悪い」ものであるということもあるだろう。
こういった「感じ方が人それぞれである」事柄については、この方針に従っていれば間違いはないなどという絶対的なルールブックは存在しない。それぞれの場面においてケースバイケース的に考えていく必要がある。
(不快に感じる人がいるからと)すべての舞台で手拍子が無くなればいいということではないし、(その方が楽しいからと)すべての舞台を手拍子で盛り上げるべきだということでもない。
その両極端な地点の間にある、無数のグラデーションな点を探りながら、その都度感受性を敏感にして判断するようなことだ。
そんなこといちいち考えるのは面倒くさい、舞台鑑賞とはなんと大変な趣味なのだろう、と感じる観劇初心者の方もいるかもしれない。そう感じて当然だろうなとも思う。
舞台や芝居は、すべての人に開かれているエンタメ/芸術だ。誰が観にきてもいい。しかし、どんな振る舞いも享受される場ではないということもまた事実だ。スポーツにルールがあるように、飛行機の乗客に求められるマナーがあるように。
ただその上でひとつ、考える際に頭の片隅に置いておきたい事柄がある。
手拍子というのは、それをする側は自分の意思でその行動をスタートできるのに対し、周りの観客には(よほどのことがなければ)他の人の手拍子をやめさせる選択肢が与えられてないという不平等性が存在しているということだ。
この不平等性は取り立てて強調する必要もないし、是が非でもこの不平等性を改善せねばならないというものでもない。社会において不平等を生じさせるような事象をすべて排除すればその結果生まれた世界が平和で素晴らしいものになるかといえば決してそうではない。
ただ、手拍子を始める際にはやはりこの「私が立てるこの音を、周りの人は拒むことができないのだ」という事実を僕はいつも意識をしているところがある。山野はそんな面倒なことを考えながら芝居を観ているのかと呆れられるかもしれないが、そうなのだ。僕はそんなことを考えながら芝居を観ている。
そういうことを考えてしまうのは僕自身の特性であり、癖である。だからそれを他のすべての人に強要したいということではない。
ただ時折、客席の一部から立ち上がる「独善的な」手拍子に心を痛めるような場面に出会うことがあるのだ。そして、客席のほかのエリアから立ち上る「居心地の悪さ」を同時に感じることもある。
劇場は開かれた場所だ。誰もが訪れていい場所だし、僕としてよりたくさんの人に訪れて欲しい場所でもある。
ただ、当然劇場は「開かれている」からこそ公共空間としての機能を有しているし、同時に舞台と観客である自分という非常に「閉じられた」関係性が複数存在するという稀有な機能も有している。
舞台と私、というある種プライベートな関係性が同じ時間/同じ場所において複数存在する。そして、そういうプライベートで独立した関係性を持った人々が同じ空間に多数存在することで、互いに「共犯関係」を結ぶ場でもある。
この「共犯関係」のなかでは独善的な振る舞いは成立しない。というか、誰かが独善的な振る舞いをはじめた時点で、この「共犯関係」は一瞬で破綻してしまう。その瞬間、劇場という魔法はあっという間に解けてしまう。
パブリックな場で独善的な欲求を通したいという思考の裏には、「チケットを買った私は、私の好きなようにこの場を楽しむ権利がある」という消費型の購買意識があるのだと思う。
けれど劇場はその性質上、「共同プロジェクト型」の購買によって成立する場だ。
DVDを買って家で鑑賞するのであれば、そのときにどんな見方をしても許されるだろう。だが劇場という場所はあくまでも「開かれた」場所である。開かれた場所においてはやはり、その場によって要求される行動の制限というのが生まれてくる。
そして、劇場という「静かな」場所においては、その静かさをたやすく変容させる「音」の影響力は計り知れない。
基本的には音を立てることを許可されていない観客にとって、例外的に能動的な音を立てられる「手拍子」という行動は特権的な魅力を帯びる。
難しいのは、手拍子に関する明文化されたルールは存在しないということ。観客ひとりひとりの思考と感性、そしてモラルに任されている部分が大きいのだ。
僕は、観客の手拍子は演劇という表現分野において、役者やスタッフとともに劇空間の劇的さを創造していくための重要なピースだと思っている。
しかし、たとえば役者の発する「セリフ」やスタッフの繰り出す「照明」が演劇にとって重要な要素だからといって、常にそれらが舞台上に現象されていれば劇空間の劇的さが最大になるかというと、そうではないのだ。
「セリフ」にも適切なタイミングや適切な音量があり、「照明」にも適切な色彩と適切な光量、そして適切なタイミングがある。
手拍子も、あるいは、それと同じなのだ。
手拍子にも、適切な音量、適切な速度、適切なかたち、そして適切なタイミングがある。
いったい何が「適切」な手拍子なのかは、作品ごとまったく違ってくるし、これはもう観客の経験と感性で察知していく部分が非常に大きい。ちゃんと考えだすとマジで難しい、と思う。
僕としても基本的には「したいと思ったときにする」のが観客の手拍子の正解だと思う。
ただその上でやはりこの要素だけは忘れないようにしたい。劇場は観客と役者・スタッフの「共同プロジェクト」として成り立っているということだ。
この視点をひとつ持っているだけでも、劇場における振る舞いが少しだけ変化すると思う。
そしてその視点を忘れないでいれば、自分が起こす手拍子は自分の気持ちを楽しませるだけのものではなく、劇空間をより劇的に演出する力もあれば劇空間を絶望的に破壊する力もあるという「手拍子の醍醐味」と言ってもいい魅力に、気づく瞬間がくるとも思う。
読んでくださってありがとうございました!サポートいただいたお金は、表現者として僕がパワーアップするためのいろいろに使わせていただきます。パフォーマンスで恩返しができますように。
