
「アフリカのハイエナの子がいるのですが…」 愛犬王の妻・佐與子と”へー坊”の運命的な出会いと、絆のはなし
「アフリカのハイエナの子がいるのですが、見にいらっしゃいませんか?」
世にも珍しい異国の動物、”へー坊”との出会いは、平岩家にかかってきた一本の電話が始まりでした――。
戦前から戦後にかけて、狼をはじめとするイヌ科動物を独学で研究し、雑誌『動物文学』を立ち上げた平岩米吉という人物がいました。
動物行動学の父・ローレンツに先駆けて自宅の庭で犬、狼、ジャッカル、狐、ハイエナと暮らしながら動物を徹底的に観察。「シートン動物記」「バンビ」といった動物文学を初めて日本に紹介し、フィラリアの治療開発に私財と心血を注ぎました。この、知られざる奇人であり偉人を描き切った痛快ノンフィクション、ヤマケイ文庫『愛犬王 平岩米吉』(片野ゆか著)から一部を公開します。

相次ぐ、引っ越し
ある夏の日、午前中の書斎仕事を終えて近所に散歩に出た米吉は、周辺がいつもより騒がしいことに気がついた。隣の家の前を通ると、数人の男たちが簞笥やいくつもの行李を運びだしているところだった。
白日荘のまわりは、ほとんどが畑や竹藪で、引っ越し作業でてんやわんやのこの家の住人は唯一の隣人だった。だがこの家は、空き家になっていることが多かった。新しく入居した人がいても、隣の「動物屋敷」に圧倒されてすぐに転居してしまうのだ。
近所をひとまわりしてきた米吉は、玄関わきの部屋に顔を出した。そこでは、佐與子(※米吉の妻)や由伎子(※米吉の長女)、布士夫(※米吉の長男)などが食卓を囲んでいた。米吉と家族の食事時間はまったく違っていた。昼と夕方の散歩を終えて帰ってくる頃は、家族の食事時間だ。米吉は、そこで二言、三言話してから書斎に戻るのを習慣にしていた。
「隣はまた引っ越しだ。今度は、新記録かもしれないね」
それまでの隣人は入居から1、2か月ほど住んでいた。しかし、今回は2、3週間と今までで一番短かった。
「きっと狐のせいよ、パパ」
米吉は由伎子の言葉に頷いた。
狐は犬科キツネ属に分類される、研究生活にとって重要な観察対象動物のひとつだ。数か月前から飼育しているが、狐には独特の体臭があった。それは犬や狼とはくらべものにならない、強烈な臭いだった。狐専用の小屋は、隣家との境の塀の脇にあった。
どんなに小屋を掃除しても狐の体臭を消すことはできず、それは風とともに隣家の敷地へと流れていく。
現代社会では、近隣に悪臭や騒音などの問題があればすぐに訴えられてしまうだろう。しかし、当時は、こうしたことに苦情を言うという発想はあまりなかったようだ。新しい場所を見つけてさっさと引っ越したほうが、よほど話が早いというのもあったのだろう。
運命的な出会い
こうした生活のなかで、佐與子に大きな変化が訪れた。狼を抱いてから動物への恐怖心が消えたことをきっかけに、動物への愛情をしだいに募らせるようになったのだ。動物にかこまれ、その生態や習性を知るにつれて、それぞれの動物とコミュニケーションもとれるようになり、すっかり動物好きになってしまったのだ。
そんな佐與子によって、白日荘に新しく加わった動物もいた。
「アフリカのハイエナの子がいるのですが、見にいらっしゃいませんか」
上野の動物商から電話がきたのは、昭和十一年の秋だった。犬科研究を始めてから、米吉は東京に何軒かある動物商とつきあい、その事情を知る店主はめずらしい動物が入荷するとかならず米吉に声をかけてきた。
その時、米吉はあいにく体調を崩していて、かわりに佐與子が見に行くことになった。
「まかせるから、もし気に入ったら連れて帰ってもいいよ」
そういったものの、米吉は特に期待していなかった。それは佐與子も同じだった。
見に行った動物をすべて飼えるわけではない。しかし、めずらしい動物がいるのなら参考のために見ておきたい。見るだけでも、研究でなんらかのヒントになることがある。佐與子は、そんな軽い気持ちで出かけていった。
上野に向かう道中で佐與子は、ハイエナについて書かれた本を読んだ時のことを思い出していた。写真を見たかぎりでは、それほど大型ではないようだ。しかし、ライオンの食べ残した動物の骨を嚙み砕いて、食べてしまうほど強い歯を持っているという。
やはりそんな動物と暮らすことなどとても想像できない、と佐與子は思った。
店につくと、さっそく主人が檻のあるところに案内してくれた。そこには生後2か月くらいのシェパードの子犬ほどの大きさの動物が入っていた。薄暗い店のなかではよくわからないので、檻ごと外に運び出してもらった。あらためて日の光の下で見ると、毛がムクムクとしていてぬいぐるみのようだった。
さらに近づいて覘きこむと、犬や狼、狸、狐などとはまったく違う、今まで見たことのない不思議な顔をしていた。大きな耳と大きな真っ黒の眼、上を向いた平らな鼻、ひらいた厚い下顎で、ちょっとおどけたような印象だ。ハイエナの子は興奮や恐怖で暴れたり、声を出したりすることもなかった。ただ眼を見開いて一心にこちらを見つめていた。
この時のことを佐與子はこう回想している。
その様子をみているうちに私は何だか悲しくなり、むねがドキドキしてきました。今から思うと不思議な動物に出会った衝撃と、怖らく母を失って捕えられた幼い姿に心を動かされたのだと思います。
最初に感じたのは、母親と引き離されて捕らえられた小さな生命の存在だった。
きっとここに来るまでに、自分には想像もできない恐ろしく悲しい体験をしたに違いない。そう思うと佐與子の胸の鼓動はおさまらなかった。ハイエナの子は、檻のなかから相変わらず大きな黒い眼でこちらを見ている。ライオンの食べ残しを貪るような獰猛さは微塵も感じられなかった。この子となら、一緒に暮らせるのではないか……。
佐與子は家に電話を入れ、ハイエナを連れ帰ることを報告した。
子どもたちは新しい動物が来るのを心待ちにしていた。そして、それは米吉も同様だった。
地獄の底でお経をあげる!?
白日荘に到着したハイエナは、身動きできない小さな檻からようやく解放された。大きな薄い耳の後ろから背にかけてフサフサとした〝たてがみ〟が続き、胸から尾には縞模様がある。
米吉がさっそく測定をした。肩の高さ38センチ、腰の高さ29センチ、口先から尾根まで67センチ、尾が18センチ、体重七キロと記録した。肩から腰がストンと落ちたような体形が特徴的で毛並みが美しい、ちょっとひょうきんな顔を持つ愛らしい姿だった。名前は、ヘー坊と名づけた。
その晩は犬の移送用の大型の檻に入れた。玄関口に置くのは幼い動物が不安がるだろうと、米吉は自分の寝室へ運びこんだ。その隣の部屋では、佐與子と子どもたちが寝ていた。
家族が寝静まった頃、米吉と佐與子は異様な鳴き声で目を覚ました。
ア、ア、ア、ア……。
咽喉(のど)を締めつけながら、出ない声を無理に出そうとしているような苦しそうな低い声だ。ハイエナの子が、暗闇のなかで鳴いているのだ。
「今のは、ヘー坊ですか」
不気味な声に不安になった佐與子が、米吉に声をかけた。
「うん。少し気味が悪いね。地獄の底でお経でもあげているようだ」
この声には米吉も驚いた。もしアフリカの真夜中の平原で、こんな妖怪じみた声が響き渡ったらさぞ薄気味悪いだろう。屍肉をあさる習性といい、この異様な鳴き声といい、ハイエナが嫌われる理由がわかったような気がした。
しかし、実際に一緒に暮らすうちに、ハイエナはしだいに家族になついてきた。とはいってもハイエナの歯は丈夫なので、遊んでいるつもりでも服などを破かれてしまうことがある。それを防ぐために佐與子や子どもたちは、いつもステッキやほうきを持って、それであやすようにしてハイエナと遊んでいた。
「あのお屋敷の門をうっかり入ると、背中の毛をおっ立てた怪物が飛び出してくるぞ!」
近所の人は、異様な動物の姿を見て驚いた。
「怪物というのは、さすがに大げさだろう」と思った米吉は、実際にハイエナを知る人が何人いるのかと思い、ヘー坊が何の種類の動物だと思うのかを聞いてみた。その答えは、狼や犬、狐、狸、猫、熊、シマウマなど、予想を超えて広範囲に及んだ。なかでも犬や狼という回答がもっとも多かった。
ちなみに当時、ハイエナは和名の「鬣犬(たてがみいぬ)」と呼ばれることもあり、アフリカ産の一種の狼と説明された。また縞ハイエナを「縞狼」と翻訳することもあったという。動物に興味を持ち関連の本を読んでも、正しい情報を得ることはなかなか難しかったのだ。
現在、ハイエナ科は、シマハイエナとブチハイエナ、カッショクハイエナの3種類に分類されている。体形は犬のように見えるが、分類的にはジャコウネコに近いと説明されている。
縞ハイエナの子にとって初めての日本での冬越えにあたり、米吉はかなり気をつかった。寒さが本格的になると、冷え込まないようにいつも寝室に檻を運び入れた。
しかし、夜行性のハイエナは深夜になるほど活発で、夜中にガリガリと藁をひっかいてホコリをたてる。鼻や咽喉が弱い米吉は、くしゃみや咳で眠れなくなってしまった。しかたがないので玄関に出して、風呂敷をかけて冷気の侵入をふせいだり、特に冷える時は火鉢を入れてやったりした。
縞ハイエナは、米吉が想像していたより寒さに順応していた。それでも心配で、雨や雪の日は家の中で運動させた。ヘー坊は、犬や狼のように全速力で駆け回るということはあまりなかった。玄関から廊下にかけての板の間を中心にノソリ、ノソリと歩きまわる。好奇心は旺盛のようで、玄関脇の階段をあがっていってバルコニーの鳩舎を「なんだろう?」という顔で眺めていることもあった。
穏やかな性格だったが、唯一困ったのは食べものへの執着心で、それは成長とともに強くなる一方だった。台所へは絶対に近づけないようにしていたが、それでも我慢できず、食事中に障子を突き破って顔を覗かせることがあった。お手伝いの女性は悲鳴を上げたが、家族は慣れっこで「あら、あら」などといいながらヘー坊を食卓から追い払うのだった。
※ヤマケイ文庫『愛犬王 平岩米吉』の内容を一部抜粋・編集しています。
関連記事はこちらから
「植物の牧野・動物の平岩」と並び称された男の痛快ノンフィクション。好評発売中!
戦前から戦後にかけて、狼をはじめとするイヌ科動物を独学で研究し、雑誌『動物文学』を立ち上げた平岩米吉という人物がいた。自宅に庭で犬、狼、ジャッカル、狐、ハイエナと暮らし、彼らの生態研究に人生をかけた偉大なる奇人の物語。文庫化にあたり、往時の様子を収めた貴重な写真と作家の直筆原稿を収録。第12回小学館ノンフィクション大賞受賞作。文庫解説/村井理子。

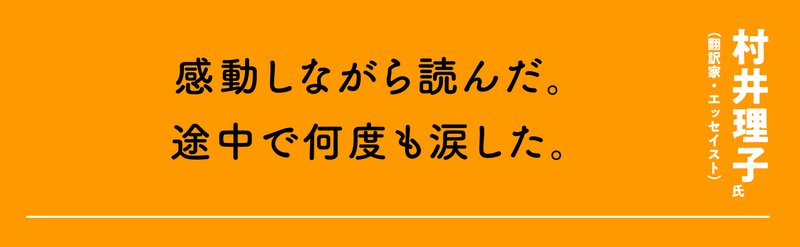


記事を気に入っていただけたら、スキやフォローしていただけるとうれしいです!
