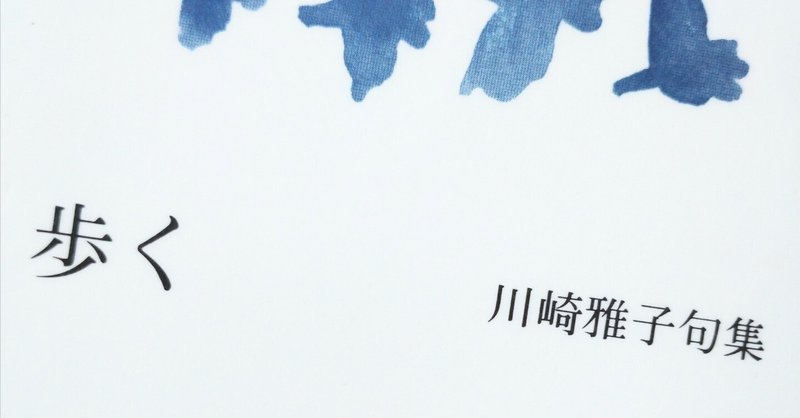
川崎雅子俳句の鑑賞② 〜波状正しき〜
初夏の夜の波状正しき浅瀬かな
「とちの木」句会で、私は主宰・川崎雅子に漢語の使用について注意を何度も受けてきた。
安直に漢語を使ってはならない。よく考えて句に入れるように。
そう伝えられてきている。
この教えは、川崎雅子が「渦」に所属していたときに赤尾兜子から言われてきたことだったそうだ。
たとえば、「場所」という語を入れたのでも釘を刺されたことがあった。多くの人は言われなければあまり意識しないだろうが「場所」は漢語である。対応する和語としては「ところ」がある。
確かに、後者よりも前者のほうがゴテゴテした感じがする。その効果を積極的に狙おうとするのならば別だが、そうでもないのならば後者を使った方が良いように思う。もちろん、音数の問題はあるけれど、何とか融通して後者を使う方がまろやかな響きになるのではないか。
こんなふうに教わってきて、私自身すっかりその考え方が内面化されてしまっているから、人の句で、たとえば「静寂」とか「透明」などといった、和語との交換が難なくできそうな漢語の入っているものを見ると、すこし居心地悪い感じがするほどだ。
ただ、だからといって、漢語を避けるべきだというのが俳句の金科玉条の一つだというふうに思っているわけではない。
そもそも季語にも「薫風」「秋霖」「除夜」「彼岸」など多くの漢語がある。二十四節気など時候を表す語は漢語が多数を占めるわけだし、代替の和語が存在しない季語が結構ある。そう考えれば、漢語に潔癖になって俳句を詠むことは難しいだろう。
実際、そんなふうに教えるわが師だって、上掲句のようなものを詠んでいるではないか。「初夏」は置いておくとして、「波状」という漢語がある。この句は、雅子が「渦」の時代に詠まれているのだが、兜子はどのようにこの句を見たのだろう。
と言って、勘違いしないでもらいたいのだが、私は師の矛盾を批判したいというのではない。そもそも私はこの句が好きである。師の句だという贔屓目抜きにして「波状」という漢語は気にならない。漢語であっても優美な靭やかさがあって、景の美しさを妨げていない。
また、この句の眼目は「正しき」という措辞にあると思う。この「正し」は「正誤」や「正義」などのそれではなく、「端正」の「正」、あるいは「整」や「清」に通じる語感を帯びるものとして受け止めるべきか。
いずれにしても一般的な「正し」のニュアンスとは少し異なるものが表されていると思う。けれども、私たち俳人はこんな「正し」の語感を容易に受け入れることができてしまう。それは、ほかでもなく、飯田蛇笏の〈芋の露連山影を正しうす〉の存在による。
そういえば、この蛇笏の句も、「連山」という漢語に「正し」が伴われている。
言うまでもなく、この句は「連山」という漢語でなければならない。漢語だからこそ厳粛かつ麗しい格調が発揮され、甲斐の山景の荘重な佇まいや懐の深さが見えて来る。
それに、「正し」と響き合うのも漢語「連山」だからこそと言えるのではないだろうか。この「正」の語感が「端正」のそれであるならば、やはり漢語の持つきりりとした雰囲気と調和する。和語を用いるならば、「うるはし」とか「やさし」としたくなる。そうなると、実に陳腐な形容に堕ちてしまう。
雅子の上掲句も同じことが言えるだろう。「波状」という漢語だから「正し」が生きるのだ。
雅子がこの句を詠んだとき、蛇笏の「連山」と「正し」が頭をよぎっただろうか。分からないけれど、その可能性は大いにあるのではないか。いや、「正しき」という措辞が思い付いた瞬間に、蛇笏を連想しないはずは無いと思う。
今度うかがってみよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
