
2. ジオパーク用語のあいまいさ
ジオパークのガイドラインや、Guy Martiniの動画を含めた、ユネスコ世界ジオパーク(UGGp)の幹部の説明は、かなり難しい文章で綴られています。しかも、詳しく見ていくと、論理の飛躍(説明の省略ともいえる)や、定義が曖昧な用語の使用が垣間見えます。以下は、ジオパークとは何か?についてUGGpやJGC、JGNなどジオパークの主要団体が記述した文章でありますが、用語がバラバラになっていることが分かります。
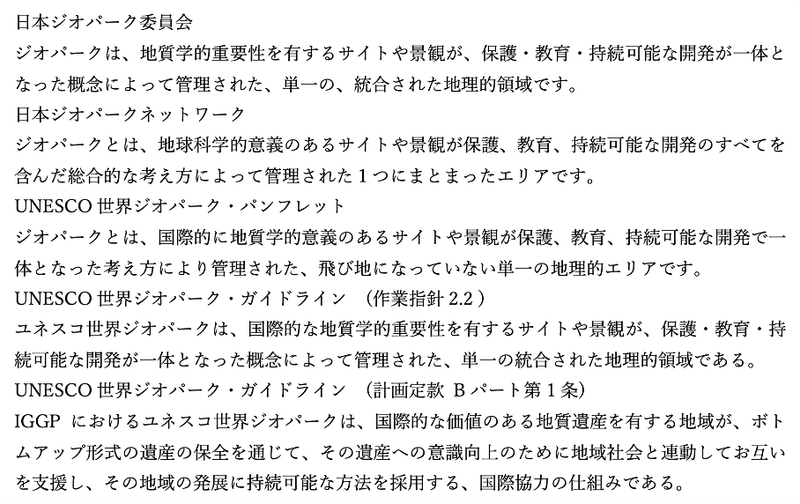
ユネスコ世界ジオパークのガイドラインに記述された「地質物品の販売に特化した部分の記述」は、以下の通りです。

ここでは、短い文章の中で、以下の3つの用語の定義が曖昧なまま使用されています。しかも、その適用範囲はそれぞれ大きく異なっていますが、それらの関係性の説明が全くなされていません。

上記の①と②は、かなり限定されたものですが、③は非常に広範囲で、地球上のすべての岩石・鉱物・化石等を含む可能性があります。この用語の記述に基づいて、すべての岩石・鉱物・化石等の販売を禁止することを主張する人々も存在するようです。
また、「地質物品の販売に特化した部分の記述」では、以下のように、文章ごとに次第に、禁止する範囲を広げつつ、より強い表現に変わっていっています。

Guy Martiniの動画においては、地質遺産の保護と地質物品販売の関係について、以下のように述べられています。

以上の記述には、地質物品の販売を抑制する強い意志が働いているが、① どのように関係しているのか?② どのように矛盾しているのか?③ 保護を手段として使用するとはどのようなことか? などの説明は一切なされていない。
「ガイドライン:作業指針3. ユネスコ世界ジオパークの基準」には、以下の記述があります。

このうち「単一の、統合された地理的領域でなければならない」理由は、全く示されていませんし、ジオパークの会合その他で、説明されたことはほとんどありません。これは、地質遺産を守るために、このような領域である必要があるようです。例えば、2015年に世界遺産に認定された「明治日本の産業革命遺産 製鉄、製鋼、造船、石炭産業」では、宮城県から鹿児島県までばらばらに点在する10箇所の産業遺産を総合して世界遺産となっていますが、このように点在してする地域において、地質遺産を統一的に説明し、保護することが困難であることが考え方の根本にあるようですが、そのような説明は一切ありません。ガイドラインのそこかしこには、このように、背景を含めた詳しい説明のない用語や文章がちりばめられています。
ジオパークの根幹とも言える「国際的に価値のある地質遺産」の定義についても、曖昧さが存在します。個々の地域のジオパークでは、「ユネスコ世界ジオパークに認定された地域のすべての地質遺産は、国際的に価値があるに違いない。」とか、「世界中の人々が地質遺産の美しい風景に感動するから、国際的価値があるのだ。」といった理解が散見されます。ユネスコ世界ジオパークでは、その分野が専門の研究者によって査読(論文の審査のこと)され国際的によく知られた研究雑誌に掲載された論文によって正当化された価値を各地域のジオパークが説明した文章の作成が求められます。その文章を、ユネスコ世界ジオパークから依頼された国際地質科学連合(International Union of the Geological Sciences: IUGS)が審査し認めることで、国際的価値として認定されます。ただし、途上国など、国際的論文を書くための研究レベルが存在しない国などに対しては、英訳した国内の研究論文や報告などで代用することが認められています。ガイドラインで示された「国際的に価値のある地質遺産」の定義は、非常に曖昧だったため、先にのべたような誤解が生じていましたが、2023年6月に、国際地質科学連合(IUGS)が「ユネスコ世界ジオパークにおける地質遺産の国際的重要性を評価するガイドライン」を公表しました。英文で22ページに渡る解説で、地質遺産の国際的価値の定義とその評価方法がしめされています。要約は以下の通りです。

これにより、地質遺産の国際的価値の定義の評価方法はより明確になりましたが、この長大な文章でも、まだまだ曖昧さは残っています。このような曖昧さの存在は、ジオパークのガイドラインや解説などに限った話ではない。法律でも、多くの解釈がなされ、裁判で争点となることが多いのは、周知の事実である。宗教の教義も、「人を殺す勿れ」(旧訳聖書 十戒)のように、厳しく戒めても、旧約聖書に基づいて暮らしているはずのイスラエルの人々でも、周辺諸国と争い、殺戮をくり返しています。決まりごとの文章や言葉の解釈はいかようにでもなるのが、世の習いです。そうは言っても、実際に活動している各地域のジオパークでは、曖昧さがあると、活動に支障が生じます。ですから、しっかりとした基準が欲しくなるのは当然です。しかし、ガイドラインなどジオパークの基本となる文章は、頻繁に変更することはできません。ジオパークが成立して長い年月が経過し、非常に多様なジオパークが集うようになると、地質遺産やジオサイトは、質や量においても多様になり、ガイドラインの解釈やジオパーク認定審査の視点は、次第に変化していきます。ジオパークでは、時間経過とともに変化する考え方や、世界各地にことなる習慣や文化をもつ地域がジオパークとしてネットワークに参加することで生じる変化に対応する方法として、「曖昧さ」を活用しているのではないか?と創造しています。この曖昧さは、「融通が利く」という別の側面(肯定的側面)も持っているからです。この柔軟性が、世界各地にネットワークを持ち、ユニークな世界観を構成するジオパークの運営に重要な役割を果たしているのだと思います。そうは言っても、ジオパークの中核にいる人々は、その変化をキャッチアップしていくことが可能ですが、各地域のジオパークでは、キャッチアップのアンテナを常に張り巡らせる訳にはいかないので、なかなかジオパークの変化についていくことは簡単ではありません。地質物品の販売問題でも、同じことが言えると思います。
このような状況の中で、地域のジオパークが出来ることは、JGCやJGN, UGGpとの不断の対話だと思います。分からないことや、疑問に思うことがあったら、ジオパークの中枢に居る人々に、次々と疑問や質問を投げかけることです。全国大会や研修会などは、そうしたチャンスであると思います。そうした不断の努力があれば、審査において、審査員と各ジオパークの担当者は、意見を戦わせるのではなく、意見交換や意見のすり合わせをすることが可能になるのではないかと思います。そもそもジオパークの審査は警察の捜査や裁判所の審理とは違います。審査という名前が良くないのでしょう。審査ではなく、心差地を取り除くダイアログ(対話)みたいに考える方が良いのかもしれません。より良いジオパークとなるための言葉のキャッチボールを可能にするために、ジオパークの決まりごとに曖昧さがあると、とりあえず前向きに考えることにしましょう。

