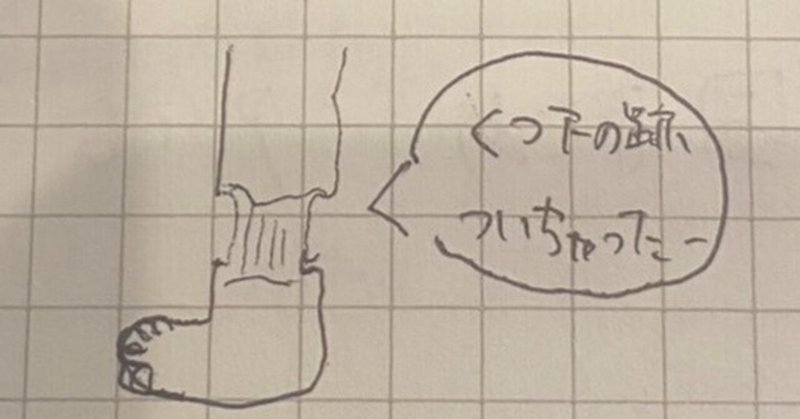
浮腫を起こす原因薬剤一覧
降圧薬
Ca拮抗薬
→細動脈への血管拡張作用が強いが、細静脈に対する作用は弱いため、細動脈の血管内圧上昇による浮腫を来たしやすいです。(ニフェジピン等のN型に起こりやすい、シルニジピン等のL型を含む薬剤は細静脈にも作用するため浮腫が起こりにくい)
ACE阻害薬
→キニナーゼが作用点であり、主作用のアンギオテンシン変換酵素の阻害以外にもブラジキニンの分解阻害も起こるため、炎症作用の1つである血管透過性の亢進により浮腫を来たしやすいです。(炎症作用として空咳も起こりやすい)
β遮断薬
→自律神経の交感神経の遮断薬であり、心臓に作用して血圧や脈拍低下に貢献するが、循環血液量の低下による浮腫のリスクもあります。
・NSAIDs
COX-2阻害作用によるPG産生抑制を起こします。PGは腎血管拡張作用があり、主に輸入細動脈(糸球体手前の血管)に作用します。PG産生抑制により輸入細動脈からは虚血となり、腎機能低下による浮腫を起こします。
・糖尿病治療薬
主にチアゾリジンについては腎臓遠位尿細管のPPAR-γに結合してNa吸収を促進して浮腫の原因となります。(急激な水分貯留により心不全のリスクも大きい)
チアゾリジンは有名ですが、メトホルミン・DPP4阻害薬・インスリン製剤なども浮腫を起こすことがあるみたいです。
・中枢神経薬
炭酸リチウム
→尿細管への細胞毒性・間質性腎炎・糸球体障害によるネフローゼ症候群等、腎臓への負担による血液濾過量の低下や低アルブミン血症など原因は広いです。
カルバマゼピン
→薬疹として、アレルギー性での血管透過性亢進による浮腫が考えられます。SJSなどが代表的ですね。
*その他三環系抗うつ薬、ベンゾジアゼピン系薬等はNa貯留作用を持っているみたいですね。
・漢方
甘草はグリチルリチンを主成分に持ちます。グリチルリチンは生体ホルモンのアルドステロンと同様の作用を持ち、尿細管のNaと水の再吸収作用によって浮腫・高血圧を生じます。(Kの再吸収作用もある為、低カリウム血症も起こり得ます)
漢方薬の70%は甘草を含むので要注意です。
・ホルモン製剤
ステロイド製剤やエストロゲン、ゴナドトロピン、テストステロン等の性ホルモン製剤はNa貯留作用を持つため、浮腫を起こしやすいです。
まとめ
結構、薬剤性浮腫を起こす機序は様々ですね。
主に、
(腎臓)
・腎機能低下による血液濾過量低下
・腎臓からのNa貯留
・糸球体破壊によるネフローゼ症候群(低アルブミン血症)
(心臓)
・心機能低下による血液循環低下
(血管)
・血管内圧亢進
・血管透過性亢進
以上の分類で大体考えられそうですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
