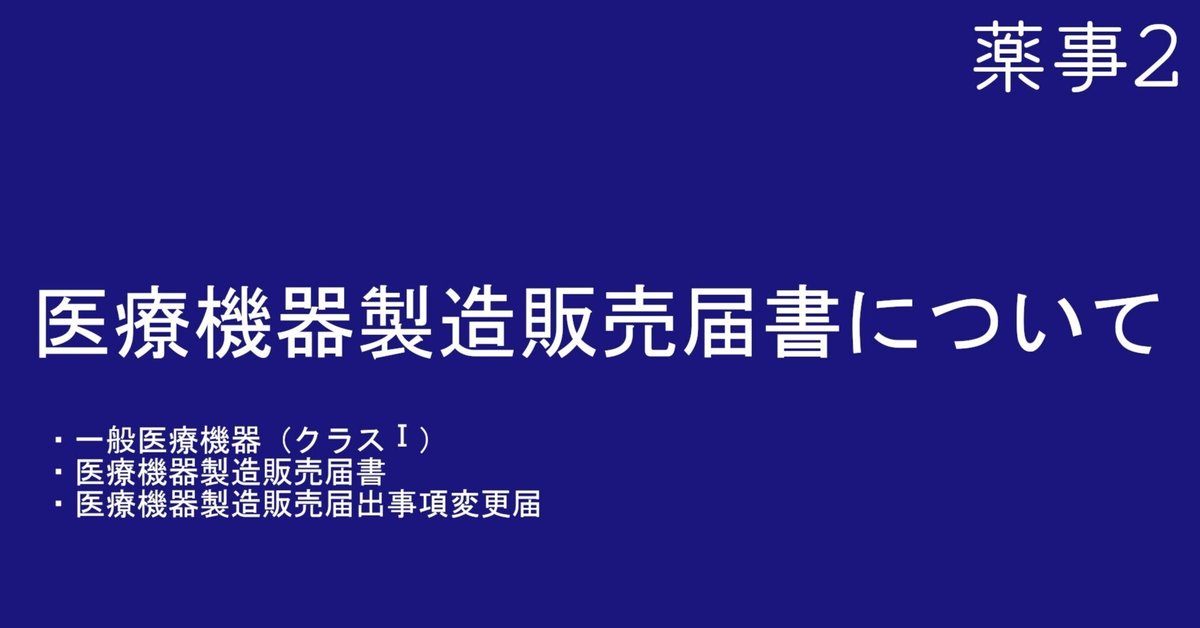
医療機器製造販売届書について
概要
「高度管理医療機器」又は「管理医療機器」を製造販売するためには、品目ごとに厚生労働大臣の「医療機器製造販売承認」を受けなければなりませんが、認証基準が定められている場合については、厚生労働大臣の登録を受けた登録認証機関の「医療機器製造販売認証」を受けなければなりません。
「一般医療機器」には「医療機器製造販売承認」や「医療機器製造販売認証」は不要ですが、あらかじめ「医療機器製造販売届書」を提出する必要があります。
注意
・医療機器を日本市場に出荷するためには医療機器製造販売業許可が必要で、製造販売業許可が無ければ、製品ごとの製造販売届書を提出することはできません。
許可の種類(製造販売できる医療機器の種類)
第一種医療機器製造販売業許可(高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器)
第二種医療機器製造販売業許可(管理医療機器、一般医療機器)
第三種医療機器製造販売業許可(一般医療機器)
・「一般医療機器」の一般的名称の定義の範囲内のものであっても、既存の医療機器と構造、使用方法、効果、性能等が明らかに異なるもの(新医療機器)に関しては、製造販売承認申請が必要です。
<<日本で始めて、世界的にも類似品は見当たらない場合は要注意>>
【様式】第63の21 医療機器製造販売届書
【提出部数】3部(正副控え)FD申請ならCD-Rも、返信用レターパック
【届書提出先】[pmda受付業務について]
【手数料等】不要
【受付作業期間】数日程度(提出部数、混雑状況による)
【法律等】
〇法23条の2の12(製造販売の届出)
・平成26年11月21日薬食機参発1121第41号「医療機器の製造販売届出に際し留意すべき事項について」
[pmdaチェックリスト]
通知研究
[pmda各種関連通知]にて主な厚生労働省通知が参照できます。
<<太文字>>にて参照事項等を追記してみました
薬食機参発1121第41号
平成26年11月21日
医療機器の製造販売届出に際し留意すべき事項について
医療機器の製造販売届出の取扱いについては、「医療機器の製造販売届出に際し留意すべき事項について」(平成17年3月31日付け薬食機発第0331002号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知。以下「旧届出通知」という。)においてお示ししてきたところです。
今般、平成25年11月27日に公布された薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145 号。以下「法」という。)は、薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第268号)により平成26年11月25日から施行されることに伴い、法第23条の2の13第1項の規定に基づく医療機器の製造販売届出の取扱い等については下記によることとしましたので、御了知の上、貴管下関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その適正な運用に努められますようお願いします。
本通知の適用(平成26年11月25日)に伴い、旧届出通知は廃止します。
なお、本通知の写しを、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、一般社団法人日本医療機器産業連合会会長、米国医療機器・IVD 工業会会長、及び欧州ビジネス協会医療機器委員会委員長及び薬事法登録認証機関協議会代表幹事宛てに送付することとしています。
<<法改正により、届出事項や製造業の取扱いが変わり、平成26年11月25日からはこの通知により取扱う>>
記
第1 医療機器製造販売届書各欄の記載事項について
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)様式63の21(1)による医療機器製造販売届書の各欄の記載事項は、次によることとする。
1 製造販売業の許可の種類
届出を行う者の製造販売業許可の種類を記載すること。
2 製造販売業の許可番号及び年月日
届出を行う者の製造販売業許可番号及びその年月日を記載すること。
<<許可年月日とは、許可有効期間の始期>>
3 類別欄
類別は、「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(平成26年政令第269号)による改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」(昭和36年政令第11号)別表第1に従って記載すること。なお、各類別への該当性については、「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」(平成16年7月20日付け薬食発0720022号医薬食品局長通知。以下「クラス分類通知」という。)の別添を参考にして判断すること。
また、一品目が複数の類別にまたがる場合は、名称欄に記載する一般的名称から判断した類別を記載すること。
<<類別は名称欄の一般的名称に紐づく類別を記載する。[pmda医療機器等基準関連情報]参照>>
4 名称欄
(1)一般的名称は、クラス分類通知の別添に記載される一般的名称の定義に基づき記載すること。一般的名称の定義への適合は、クラス分類通知の別紙1に示すクラス分類ルール等を踏まえて判断すること。
一品目中に複数の一般的名称が含まれる場合であって、品目全体を総称した一般的名称がない場合は、主たる使用目的又は性能から判断した一般的名称を記載すること。
(2)販売名は、当該医療機器の性能等に誤解を与え保健衛生上の危害を発生するおそれがないものであり、かつ、医療機器としての品位を保つものであること。
また、他の用途を想定させるような名称は認められないこと。
なお、一物一名称が原則であるが、妥当な理由により一物多名称のものを申請する場合は、その説明資料を届出書に添付すること。ただし、この場合、販売名ごとに製造販売届出を行う必要があること。
<<クラス分類通知の一般的名称定義は[pmda医療機器等基準関連情報]参照>>
<<アルファベット、数字のみの販売名は不可>>
<<一物多名称の妥当な理由の例「販売先により販売名を使い分ける」>>
5 使用目的又は効果欄
当該品目の使用目的又は効果について、当該品目に係るクラス分類通知の一般的名称の定義の範囲内で記載すること。
<<クラス分類通知の一般的名称定義は[pmda医療機器等基準関連情報]参照>>
6 形状、構造及び原理欄
当該医療機器の外観形状、構造、原理、各構成部品又はユニット、電気的定格、各部の機能等、どのような品目であるのか分かりやすく記載すること。
「使用目的又は効果」に影響を与えることがない付帯的な機能を有する場合は、その内容を説明すること。また、形状が粉状又は液状の医療機器については形状としてその区別を記載すること。
他の製造販売届出を行った医療機器との組合せである医療機器については、その医療機器の該当する一般的名称の定義から逸脱しない使用目的等である場合に限り、原則、省略することができるものとする。その場合、当該欄には該当する構成医療機器の名称を記載する。なお、当該構成医療機器に関する製造販売届出番号等の記載事項は、「製造方法」欄に記載すること。
<<H21/03/31薬食機発第0331002号・組合せ医療機器に係る製造販売承認申請、製造販売認証申請及び製造販売届出に係る取扱いについて>>
7 原材料欄
形状、構造及び原理欄において記載した内容との対応関係が明確となるように原材料等を正確に記載し、その規格を明らかにすること。血液・体液・粘膜等に接触(直接・間接を問わない。)せず、かつ、性能に大きく影響しない部品又は材料については、簡潔な記載で差し支えないこと。特に記載を要する原材料がない品目においては空欄にする。
<<R02/01/06薬生機審発0106第1号・医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方についての改正について>>
<<H30/06/12薬生機審発0612第4号・歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について>>
8 性能及び安全性に関する規格欄
品質、安全性及び有効性の観点から、本品の要求事項として求められる設計仕様のうち、「形状、構造及び原理」欄に該当しない事項を記載する。これらの内容は、主に設計段階の検証により得られた製造販売時における当該品目の品質、安全性及び有効性を保証した内容であり、品質、安全性(物理的・化学的・生物学的安全性を含む。)及び有効性(性能、機能)の観点から求められる規格等を設定すること。その他、JIS規格、国際基準等、参照できる規格・基準がある場合はその規格・基準を記載すること。
<<[pmda各種関連通知][電気的安全性関係][電磁両立性関係]参照>>
9 使用方法欄
使用方法については順を追って、必要に応じ図解する等により、分かりやすく記載すること。未滅菌製品で使用に際して必ず滅菌した上で使用すべき製品にあっては、その旨及び滅菌方法、滅菌条件(薬剤、ガス等を含む。)を記載すること。
他の医療機器と組み合わせて使用する場合であって、有効性及び安全性の確保のために特定の条件を満たす機器と併用しなければならない場合は、組み合わせて使用する機器の条件を記載した上で、当該機器を含めた使用方法を説明すること。
なお、再滅菌を行って繰り返し使用することを前提とする医療機器にあっては、その旨と再滅菌の方法を記載すること。
10 保管方法及び有効期間欄
特定の保管方法によらなければその品質を確保することが困難であるか、又は経時的に品質の低下をきたし有効期間を定める必要がある製品について記載すること。なお、有効期間が3年を超えるものについては有効期間については記載を要しないものであること。
保管方法については、冷暗所等一定の条件の下に保管しなければ、変質、劣化等が起こり得る製品については、その保管方法、条件を記載すること。
<<[pmda各種関連通知][安定性関係]参照>>
11 製造方法欄
ア 各製造工程に係る登録製造所が単一でない場合等、各工程の関係について誤認が生じないよう、各登録製造所の関係について分かりやすく記載すること。工程ごとの記載や工程フロー図等は原則として記載しなくてよいこと。
イ 工程の製造加工条件によって製品の使用目的、性能等が影響を受ける品目にあっては、登録製造所以外の施設が行う工程であっても、その製造加工条件の記載を行うこと。若しくは「原材料」欄に加工の目的、加工後の仕様を記載すること。
ウ 滅菌医療機器にあっては、滅菌方法、引用する滅菌バリデーション基準を記載すること。本体と構成部品で滅菌が異なる場合は、それぞれの滅菌方法を明確にすること。「製造販売する品目の製造所」欄に記載する滅菌方法が放射線又はその他である場合は、「製造方法」欄に滅菌方法を具体的に記載すること。
エ 当該医療機器の構成部品を単品として流通させることがあるとして製造販売届出書を提出する場合の当該構成部品に関しては、当該構成部品の製造工程について上記ア~ウの事項を記載する必要があること。
オ 構成部品単体で医療機器として製造販売届出を行っているものを組み込む場合、当該構成医療機器の製造販売業者の氏名、製造販売届出番号、販売名、並びに構成品の名称を記載すること。
<<[pmda各種関連通知][滅菌関係]参照>>
<<H30/02/28薬生機審発0228第10号・滅菌医療機器の製造販売承認(認証)申請における滅菌に関する取扱いについて>>
<<R04/10/17薬生監麻発1017第1号・滅菌バリデーション基準の制定について>>
<<H21/03/31薬食機発第0331002号・組合せ医療機器に係る製造販売承認申請、製造販売認証申請及び製造販売届出に係る取扱いについて>>
12 製造販売する品目の製造所欄
製造販売する品目に関して、登録を受けた製造所ごとに、製造所の名称、製造業登録番号、製造工程を記載すること(別紙参照)。
製造工程に関しては、施行規則第114条の8の各号に基づき、「主たる組立て」(第3号イ等)、「滅菌」(第3号ロ)、「保管」(第2号ロ等)の別を、該当する製造所ごとに記載すること。
また、滅菌については、放射線、EOG(エチレンオキサイドガス)、湿熱、その他の別を製造所ごとに記載すること。
<<医療機器の定められた工程(主たる組立て・滅菌・国内最終製品の保管)を行う製造所には製造業登録が必要です。>>
<<H26/10/03薬食機参発第1003第1号・医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の取扱いについて>>
<<H26/10/20薬食機参発第1020第4号・医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について>>
13 備考欄
(1)製造販売業者自らが当該品目に係る製造販売届出番号を定め、その製造販売届出番号を記載すること。
当該製造販売届出番号については、製造販売業許可番号の後に製造販売届出順に000001番から連番で付番するなど16桁の品目固有の番号となるように付番すること。なお、6桁で番号が不足する場合などにおいては、数字の代わりにアルファベットを使用しても差し支えない。
(2)特定保守管理医療機器に該当する場合はその旨記載すること。
(3)単回使用の場合はその旨記載すること。
(4)新規原材料を含有する場合はその旨を記載すること。
(5)複数の一般的名称が含まれる場合は、「名称」欄に記載しなかった一般的名称を記載すること。ただし、品目全体を総称した一般的名称を「名称」欄に記載した場合を除く。
(6)当該品目が他の医療機器の一部として他の品目の製造工程において使用される場合は、「製造専用として使用されうる医療機器」と記載すること。
(7)当該品目の外観が把握できるような写真を添付すること。
(8)当該品目が該当する一般医療機器の定義に該当することについて説明した資料を添付すること。なお、この説明には、必要に応じ、「使用目的又は効果」「使用方法」等について言及すること。
(9)その他、関連通知に基づき備考欄に指定された事項を記載すること。
第2 その他
1 添付文書案の添付について
製造販売届出には、施行規則第114 条の47第3項の規定に基づき当該製品の添付文書案を添付する必要があること。
<<[pmda添付文書関連通知等]、他社添付文書参照は[pmda医療機器 情報検索]>>
2 新医療機器である一般医療機器の取扱いについて
一般医療機器の一般的名称の定義については、クラス分類通知に示されるとおりであるが、その定義の範囲内のものであっても、新医療機器に該当するものに関しては、製造販売承認申請が必要であること。なお、当該新医療機器の承認時において使用成績評価の対象とされた品目については、当該調査期間の終了後、承認整理を行うとともに、製造販売届出を行うこと。
<<H26/11/20薬食発第1120第5号・医療機器の製造販売承認申請について>>
3 メス、ピンセット等の品目の考え方について
メス、ピンセット、縫合針等(いわゆる鋼製小物)のように、その使用者の使いやすさの向上を目的に使用者の求めに応じて形状に変化を付けることが前提のものについては、その材質に変更がない限りにおいて、当該品目が対象とする使用部位が変更にならない範囲において、1品目として取り扱って差し支えないこと。ただし、この場合、当該品目が対象とする使用部位を特定しておく必要があること。なお、製造販売承認における一部変更及び軽微変更の考え方については、別に定めのない限り、同様の考え方であることに留意すること。
<<H26/11/20薬食機参発第1120第1号・医療機器の製造販売承認申請書の作成に際し留意すべき事項について 別紙2>>
<<H20/10/23薬食機発第1023001号・医療機器の一部変更に伴う手続について>>
4 届出事項の変更について
製造販売届出事項に変更があった場合、その届け出なければならない変更の範囲については、製造販売承認における、承認事項の一部変更の範囲及び軽微変更届での範囲に準じた取扱いとする。
<<施行規則様式第40医療機器製造販売届出事項変更届 FD申請E94>>
<<H20/10/23薬食機発第1023001号・医療機器の一部変更に伴う手続について>>
5 届出を行った品目の廃止について
製造販売届出を行った品目について製造販売を廃止した際は、医療機器製造販売届出事項変更届(施行規則様式第40)の変更事項に当該品目の製造販売を廃止した旨を記載した上で、廃止後30日以内に独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出すること。
<<施行規則様式第40医療機器製造販売届出事項変更届 FD申請E94>>
6 一般医療機器における基本要件基準への適合について
(1)製造販売届出される医療機器については、基本要件基準(法第41条第3項に基づき厚生労働大臣が定める医療機器の基準をいう。)に適合している必要があること。
なお、当該品目の届出を行った製造販売業者は、「医療機器の製造販売承認申請書添付資料概要作成の手引きについて」(平成17年2月16日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知)を参考に、当該品目に係る技術文書の概要(Summary Technical Documentation)を作成し、製造販売業者の主たる事業所及び当該品目の製造所において保管することが望ましいこと。
(2)一般医療機器に関しても、品目によっては、別途通知により基本要件基準への適合への判断基準を示す場合があることに留意すること。
<<基本要件基準に適合しない医療機器は、販売目的の製造・輸入・貯蔵・陳列が禁止されている。 法65条>>
<<承認申請や認証申請の際には基本要件基準への適合性について、項目ごとに適合性を説明する必要がある。H27/01/20薬食機参発0120第9号・医療機器の製造販売承認申請書添付資料の作成に際し留意すべき事項について>>
別紙
製造販売する品目の製造所欄の記載例
(例1)製造工程ごとに製造所が異なる場合
製造所の名称 登録番号 製造工程
△△△工場 ・・・ 主たる組立て
□□□工場 ・・・ 滅菌(EOG)
☆☆☆工場 ・・・ 保管
(例2)一つの製造所で複数の製造工程を有する場合
製造所の名称 登録番号 製造工程
○○○工場 ・・・ 主たる組立て、保管
□□□工場 ・・・ 滅菌(放射線)
(例3)主たる組立ての登録製造所が2か所ある場合
製造所の名称 登録番号 製造工程
△△△工場 ・・・ 主たる組立て
▲▲▲工場 ・・・ 主たる組立て
□□□工場 ・・・ 滅菌(EOG)
☆☆☆工場 ・・・ 保管
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
