
【高校生物】細胞③「細胞同士はどのように関わり合っているのか?」
~プロローグ~
文化祭の準備を思い出そう。ある目的を持って、複数の人が働く場合、お互いに連絡をとり合うことが大切になってくる。
同様に、多細胞生物をかたちづくる細胞達は、適切に生命現象を進行させるため、お互いに連絡をとり合う必要がある。また、時には、隣の細胞としっかり手を繋ぐこと(細胞接着)が必要なこともある。
「私たち二人の手を結び合わせてください。」シェイクスピア『ロミオとジューリエット』より ロミオの言葉
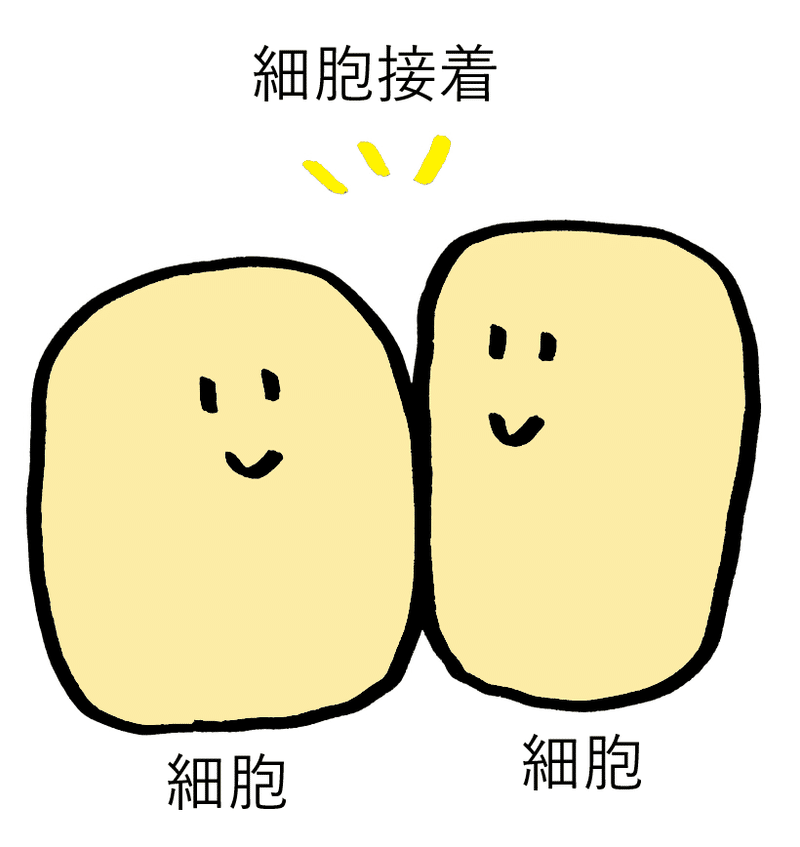
★テストに出やすいワード
①密着結合
②カドヘリン
③デスモソーム
④ギャップ結合
⑤ステロイドホルモン
要点:細胞は、密着結合、接着結合、デスモソームによって他の細胞と結合する(細胞接着)。
●細胞と細胞の接着、あるいは、細胞と細胞の外にある構造との接着を細胞接着という(下図はいろいろな細胞接着のイメージ。この後1つ1つ詳しく見ていく)。

● 動物の上皮組織などでは次のような細胞接着が見られる。詳しくは問われない。まずはキーワードだけチェックすればよい。
(1) 密着結合
● 密着結合:クローディンというタンパク質によって細胞間隙がふさがれ密着して結合。細胞間隙をふさぎ、水分子すら通さない。
キーワード「密閉、細胞間隙をふさぐ」
雑談:皮膚から体液が漏れないのは密着結合のおかげである。なお、クローディンは京都大学の月田承一郎によって発見された。
雑談:クローディンの遺伝子が欠失しているマウスは、皮膚の細胞間に密着結合が形成されないため、皮膚から水が急速に蒸発し、死んでしまう。
下図は密着結合のイメージ。

(2) 固定結合
固定結合には以下の3つがある。
① 接着結合
● 接着結合:カドヘリンというタンパク質とアクチンフィラメントが結合。
*カドヘリンが働くためにはCa2+が必要。
キーワード「カドヘリン、アクチンフィラメント」
雑談:接着結合は、密着結合とデスモソームの中間にあることから、中間結合とよばれることもある。接着結合は、ある細胞のアクチンフィラメントと、隣接する細胞のアクチンフィラメントを間接的に連結している。それによって、細胞達は、協調した動きを取れるようになる。接着結合は大学ではアドヘレンスジャンクションと呼ぶことが多い。
語呂「かたいセッチャアク(カドヘリン、アクチンフィラメント、接着結合)」
下図は接着結合のイメージ。

カドヘリンが働くためにはCa2+が必要である。
雑談:下図は接着結合のカドヘリンの周辺を少し詳しく描いたイメージ。実際はカテニンには複数の種類がある。

② デスモソーム
● デスモソーム:カドヘリンと中間径フィラメントが関わる。ボタン状の構造である。
キーワード「ボタン状、カドヘリン、中間径フィラメント」
語呂「甲冑です(カドヘリン、中間径フィラメント、デスモソーム)」
雑談:デスモソームは細胞間接着装置である。デスモソームは上皮の機械的強度を増強させている。細胞膜の下に様々なアダプタータンパク質(デスモプラキン、プラコグロビンなど)の混合物から成る構造体があり、その表面に中間径フィラメントが付着している(デスモプラキンというタンパク質が中間径フィラメントの側面に結合する)。デスモソームに付着する中間径フィラメントは細胞の種類によって変わる。

③ ヘミデスモソーム
● ヘミデスモソーム:細胞と細胞外基質(細胞外マトリックス)との結合に関わる。ヘミデスモソームはあまり問われない。インテグリンというタンパク質が使われている(結合するintegrateという語に由来)。インテグリンと、(ケラチンなどの)中間径フィラメントが結合している。
*細胞外基質とは、細胞の外側にある構造的なものの総称。有名な細胞外基質にコラーゲンというタンパク質がある。コラーゲンは動物の全タンパク質中で最も多く、非常に重要なタンパク質である。
雑談:コラーゲンを食べても、そのままコラーゲンがお肌に運ばれるということはない。消化によって分解される。コラーゲンたっぷりのお鍋を食べた時にお肌が潤うのは、単に水滴が付着したか、汗をかいたためである可能性が高い。
雑談:大航海時代の頃、多くの船の上で、ある恐ろしい病気が船員を襲っていた。口や鼻から出血し、多くの船員が死んでいった。これは壊血病(かいけつびょう)と呼ばれ、コラーゲン合成が不完全であることが原因となる。毛細血管の壁にはコラーゲンが多く含まれている。ビタミンCが不足することによって、もろいコラーゲンが生じ、出血が起きやすくなると考えられている(ビタミンCはコラーゲンの形成に関わる)。海軍医リンドは、柑橘類が壊血病の治療に有効なことを発見した。有名な探検家であるクック船長は、船員たちに柑橘類(ビタミンCを含む)を食べさせたという。
雑談:コラーゲンは動物の細胞外マトリックスの主要成分であり、引っ張り強度を与える。漫画『ワンピース』のルフィは、特別なコラーゲンを持っている可能性がある(冗談です)。
雑談:上皮細胞を基底膜に接着させているのはヘミデスモソームである。上皮細胞の基底側には、基底膜というシートがある。基底膜はあらゆる上皮に不可欠の支持基盤であり、上皮の土台である。基底膜は細胞外マトリックスの特殊化した形態の一つである。基底膜にはコラーゲンやラミニン(糖タンパク質の一種)が存在する。ヘミデスモソームにおいて、インテグリンは、細胞外でラミニンと結合し、ラミニンがコラーゲンと結合している。インテグリンは、細胞内では、(プレクチンなどの細胞内アダプタータンパクを介して)中間径フィラメント(ケラチンなど)と結合している。
下図はイメージ。


雑談:上図のヘミデスモソームでは、インテグリンは、細胞内の「中間径フィラメント」と細胞外マトリックス中のタンパク質に(様々なタンパク質を介して)結合しているが、多くのインテグリンは、細胞内の「アクチンフィラメント」と細胞外マトリックス中のタンパク質に(様々なタンパク質を介して)結合している。いずれにしろ、インテグリンは、細胞と細胞外マトリックスの結合に重要な役割を果たしている。
雑談:組織内を動き回るマクロファージのような細胞は、インテグリンの状態を上手く変えながら移動を行っていると考えられている(インテグリンには、結合をすぐにつくれる活性化状態と、結合をつくりにくい不活性化状態がある[2つの状態で、インテグリンの立体構造が異なる]。これらの状態の切り替えが様々な機構で調節されていると考えられている。活性化状態になると、インテグリンの両末端にある細胞内外のリガンド結合部位が露出する)。

● 一般に、カドヘリンは同種のもの同士で結合する。これにより同種の細胞が集合することができ、組織を形成できると考えられている(上皮細胞と神経細胞をごちゃまぜにしても、同種の細胞同士集合できることが実験で確かめられた。これを細胞選別という)。
なお、カドヘリンはタンパク質なので、トリプシンなどのタンパク質分解酵素で分解される→細胞は接着できなくなる(文化祭の打ち上げで、はじめは座席がランダムでも、時間が経つと、同じ趣味をもつグループに分かれていることがある。そのような現象は細胞選別に似ている。冗談です)。
雑談:カドヘリンはcalcium-dependent adhesion moleculeが語源(カルシウム依存的な接着分子。語尾が「in」になっているのはタンパク質であることを表している)。多くの種類がある。竹市雅俊が発見・命名した。
雑談:カドヘリン同士の結合力は非常に強い。
● カドヘリンが働くためにはカルシウムイオンが必要である(非常によくテストに出る)。

雑談:カルシウムイオンが存在しないと、カドヘリンの分子の形態が変化し(別の細胞のカドヘリンと相互作用できるような方向に向かなくなって)、接着が起こらなくなると考えられている。

(3) ギャップ結合
● ギャップ結合:円筒状の膜貫通タンパク質による結合。低分子物質やイオンが移動でき、細胞間の情報伝達に関与している。
キーワード「物質の移動」
雑談:コネクソンというタンパク質がトンネルのような構造をつくっている。様々な物質がこのトンネルを通る。ギャップ結合は、心筋の細胞など、他の細胞と迅速に情報をやりとりしたい時などに重要になる(ただし、現在では、ギャップ結合は、動物の同種細胞間に広く分布することがわかっている)。ギャップ結合のはたらきは植物細胞の原形質連絡に似ている。

講義動画【細胞骨格と細胞接着】
要点:白血球はサイトカインで情報を伝え合うことがある。
● 白血球はインターロイキンというサイトカイン(細胞が産生するほかの細胞に働きかけるタンパク質の総称)により情報伝達を行う。
*インターロイキン:白血球間の相互作用に働く物質の総称。インター「相互」ロイコサイト「白血球」から作った造語。
*サイトカイ「ニ」ンは植物ホルモンであり、サイトカインとは別の用語なので注意。
要点:MHCタンパク質は細胞膜上に存在し、拒絶反応の原因になる。
(1)トル様受容体(TLR)
● 微生物感染を感知する一群のタンパク質をトル様受容体(TLR)という。トル様受容体は、マクロファージ、樹状細胞などの細胞に存在する。トル様受容体にはいくつか種類が存在し(ヒトやマウスでは10種類のTLR遺伝子が発現している)、それぞれ、細菌由来の細胞壁の成分・細菌由来の鞭毛の成分・ウイルス由来の二本鎖RNAなど、病原体には存在するが自身では合成できない物質(病原体が侵入してきた証拠となる)を認識している(どのようにトル様受容体が病原体の成分と結合しているのかについては、完全には解明されていない)。
トル様受容体で病原体の成分を認識した細胞は、サイトカインを分泌する。このサイトカインによって、炎症反応などの反応が誘導されたり、抗原提示細胞の抗原提示能力が促進されたりすることが知られている(したがって、TLRは獲得免疫にも重要な役割を果たしていると言える)。
雑談:トル様受容体は細胞の表面だけでなく、細胞の内部にも存在する。細胞内部に存在するトル様受容体は、エンドソーム(エンドサイトーシスにより形成された膜小胞)上に存在しており、ウイルス由来のRNAなどを認識する。

雑談:Tollレセプター遺伝子は、もともと、ショウジョウバエの胚発生において、背腹軸パターンを正しく決定するために働く遺伝子として同定された。後になって、Tollレセプターは、ショウジョウバエの成虫では、免疫にかかわる機能を持つことがわかった。その後、ショウジョウバエのTollと類似の分子であるTLR(Toll-like receptor)が、植物や昆虫の成虫、さらに哺乳類を含む脊椎動物における感染防御に重要な役割を果たしていることが明らかになった。この受容体の起源は非常に古く、進化の歴史の中で長い時間保存され続けてきた考えられている。
(2)BCR・TCR
● B細胞はB細胞表面にあるB 細胞受容体(BCR)で抗原を直接認識する。
*B細胞が抗体産生細胞に分化すると、B細胞受容体は分泌されるようになる。分泌されるようになったB細胞受容体を抗体(免疫グロブリン)という。
● T細胞は抗原提示によって提示された抗原をT細胞受容体(TCR)で認識する(T細胞は提示された抗原しか認識できない)。

(3)MHCタンパク質
● 脊椎動物の細胞表面には主要組織適合抗原複合体(MHC)という遺伝子からつくられる、MHCタンパク質とよばれるタンパク質(MHC、MHC分子などとも呼ばれる)が発現している。
補足:「MHC」が遺伝子を指しているのか、タンパク質を指しているのかを区別するために、MHCが発現してできたタンパク質を「MHC分子、MHCタンパク質」と呼ぶことが多いが、単に「MHC」と呼ぶこともある(たとえば『スタンダード免疫学』丸善、『免疫学コア講義改訂4版』南山堂、『岩波生物学辞典第5版』岩波書店など)。免疫の単元は、すぐに教科書の内容が大きく変わるので、高校生は必ず最新の教科書と資料集の用語の使われ方をチェックし、大学入試では教科書と資料集の解釈にあわせること。細かい用語がたくさん登場して、高校生は大変だろうが、ここで学んでいることの本質は、『脊椎動物は、自己と他者を区別するための、精巧なシステムを獲得した』ということである。
雑談:無顎類を除くすべての脊椎生物がMHCを持つことが明らかになっているが、その進化上の起源についてはよくわかっていない。
● MHCタンパク質は個体によって異なる。
● T細胞の表面にあるT細胞受容体(TCR)が、MHCタンパク質及びその上に乗った成分を認識・識別している(TCRは、MHC-抗原ペプチド複合体を認識する)。
● 臓器移植で拒絶反応が起こるのはMHCの違いによる。
● MHCには2つの分子種、すなわちクラスⅠとクラスⅡが存在する。
● MHCクラスⅡは、主に樹状細胞、マクロファージなどの抗原提示細胞が発現している。『MHCクラスⅡ分子+食作用によって取り込まれ断片化された抗原断片』を、ヘルパーT細胞はTCRで認識する。
● MHCクラスⅠは生体のほぼすべての組織に強く発現していて(樹状細胞などにも発現している)、細胞内のタンパク質の断片を提示している。細胞内のウイルス断片(細胞に感染したウイルスは細胞内で増殖する)や癌特有のタンパク質なども細胞膜表面に提示する(この提示ははキラーT細胞に対するメッセージである。たとえば「自分の中にウイルスがいる。はやく自分を壊してくれ」とキラーT細胞に伝えているのである。だから、大学入試ではそう書いてはいけないが、ある意味『ほぼすべての体細胞は抗原提示細胞なのである』。大学入試的には抗原提示細胞はマクロファージや樹状細胞のみを指す)。
雑談:ある種のがん細胞やウイルス感染細胞は、宿主のMHCクラスⅠの発現量を減らすことによってキラーT細胞からの攻撃を回避しようとする。しかし、MHCクラスⅠをもたない細胞は、NK細胞が殺傷する。


雑談:MHCクラスⅠとペプチド断片が結合する過程
①細胞内のタンパク質(侵入してきたウイルス由来のものも含む)は、プロテアソームという酵素で分解される。
②その後、その産物の一部が小胞体に運び込まれる。
③小胞体内でMHCクラスⅠに結合し、ゴルジ体を経て細胞表面に提示される。
雑談:MHCクラスⅡとペプチド断片が結合する過程
①樹状細胞などの抗原提示細胞は、細胞外にある抗原をエンドサイトーシスで取り込む。
②エンドソーム(エンドサイトーシスで生じた小胞)はリソソームと結合し、タンパク質分解酵素により抗原は適度に分解される。
③MHCクラスⅡは、小胞体からゴルジ体を経て抗原断片のある小胞(②)まで運ばれ(ゴルジ体から生じた小胞の膜に埋め込まれて運ばれる)、その中で抗原断片と結合し、細胞膜表面に提示される。
*ただし、上記①②のような「MHCクラスⅠは細胞内の抗原、MHCクラスⅡは細胞外の抗原と結合する」という選択性は、厳密ではないことが明らかになっている。詳細は大学で学んでほしい。
● ヒトのMHCはHLA(ヒト白血球型抗原)とよばれ、兄弟間では25%の確率で一致する(母から相同染色体2本のうち1本をもらい、父からも2本のうち1本をもらう。したがって兄弟で一致する確率は1/2×1/2=1/4)が、他人と一致することはほとんどない。
雑談:ヒトのMHC遺伝子は、個人間での白血球の抗原性の違いから発見された遺伝子であるために、ヒト白血球抗原遺伝子( human leukocyte antigen 遺伝子)、あるいはHLA遺伝子と呼ばれる。異なるHLA遺伝子の産物は、異なる溝の形を持っているので、そこに結合できるペプチドの形も異なる。

(HLAをコードする遺伝子は同じ第6染色体に6対存在しており、それぞれの遺伝子は膨大な種類が知られている。この6対の遺伝子が他人と一致する可能性は非常に少ない。ただし、染色体ごと同一の遺伝子のセットをもらう兄弟姉妹では一致しやすい。)

雑談:実際は、ヒトでは、MHCクラスⅠ分子としてHLA-A、B、Cが、MHCクラスⅡ分子としてHLA-DR、DP、DQが、第六染色体上のHLA遺伝子領域にコードされている。それぞれの遺伝子座について、多数の遺伝子多型が存在する。これらの型が他人と全て一致することはまれであるが、親子間では50%の対立遺伝子が一致し、兄弟姉妹間では25%の確率で完全に一致する。

雑談:HLAには、クラスⅠ分子としてHLA-A、B、Cがあり、クラスⅡ分子としてHLA-DR、DQ、DPがある。それらの遺伝子は第6染色体にある。ただし、第6染色体のHLA-A、B、C領域にはHLAクラスⅠの「α鎖」の遺伝子のみが存在し、それらの産物は、15番染色体に存在する遺伝子の産物である「β2ミクログロブリン(HLAのこの部分には遺伝的な多型性がないので高校では記載されないことが多い)」と結合して働く。HLA-DR、DQ、DP領域にはα鎖とβ鎖の遺伝子座が存在し、α鎖とβ鎖遺伝子の産物同士が結合して、DR、DQ、DP分子を形成して働く。
*HLAの対立遺伝子の数(遺伝子解析の研究が進むに伴って数は増加していく)
クラスⅠ A:650種類程度
クラスⅠ B:1000種類程度
クラスⅠ C:350種類程度
クラスⅡ DR:α鎖3種類+β鎖650種類程度
クラスⅡ DQ:α鎖30種類程度+β鎖100種類程度
クラスⅡ DP:α鎖30種類程度+β鎖150種類程度
雑談:MHCは細胞表面に(細胞1個当たり)10万個のオーダーで存在するとされる。
*たとえば、ヒトの場合、そこに6種類(父由来の遺伝子から3種+母由来の遺伝子から3種)のクラスⅠ分子が存在することになる(なお、クラスⅡ分子に関しては、α鎖とβ鎖の組み合わせにより、6種類以上が生じることが知られている)。
雑談:異なるMHC遺伝子の産物は、異なる溝の形を持っているので、そこに結合できるペプチドの形も異なる。したがって、個体が所有するMHCの種類によって、T細胞に提示可能なペプチドが異なることになる(実際は、ある1個のMHCには、結合力の強いペプチドから弱いペプチドまで含めると、数千~数万種類のペプチドが結合し得ると考えられている)。MHCの遺伝子が複数存在し、複数の種類のMHCを持つという事は、免疫応答で対応できる抗原の種類を増やすことにつながっていると考えられる。
雑談:MHCの高度な多型性は、個体だけではなく、集団にも利益をもたらしている可能性がある。仮に、すべてのヒトのMHCが同一であるとすると、そのMHCに結合するペプチドの種類も比較的均一なものになるだろう。その場合、ある病原体がまん延した時、ほとんどのヒトがその病原体に対して同じような免疫応答を起こすと考えられる。その病原体由来のペプチドがMHCと結合しにくい場合は、十分な免疫応答が起きず、ヒト集団が絶滅する可能性がある。一方、(MHCに多型が存在し)個人のMHCが異なれば、一部の個体は、その病原体に対して強い免疫応答を起こすことができるかもしれない。結果、絶滅は避けられることになる。
雑談:タスマニア島にはタスマニアデビルという有袋類の動物がいる。この動物は、食料などをめぐって、同種内でかみ合う。この時、がん細胞が他個体に移ってしまうことが知られている(すなわち、驚くべきことに、がん細胞が「伝染」してしまう)。ふつうはこのようなことは起こらない。多くの場合、ある細胞が別の個体に移ると、MHCの型が違うため、その細胞は免疫系によって排除される。しかし、タスマニアデビルは、離島という閉鎖的な環境で繁殖してきたので、遺伝的な多様性が低く、個体間でMHCの型に違いがほとんどないのである。それで、ある個体のがん細胞が、別の個体に簡単に移ってしまうのである。
講義動画【MHC】
講義動画【獲得免疫】
講義動画【MHCクラスⅠ・Ⅱ、HLA】
発展:クローン選択説
①異なる特異性をもつ多数のリンパ球が生み出される(それぞれのリンパ球は固有の特異性のある受容体を1種類ずつもっている)。
②自己反応性をもつ(自己抗原を強く認識する)未熟リンパ球は除去される(免疫寛容)。
③成熟したリンパ球の受容体が(非自己)抗原と結合すると、リンパ球は活性化し、増殖する。
⓸抗原が排除される。
⑤免疫応答が終了し、一部のリンパ球は記憶細胞となり生き残る。
上記のような現象が起きているとする説をクローン選択説という。
講義動画【クローン選択説】
要点:ペプチドホルモンは細胞膜を通過できない。ステロイドホルモンは細胞膜を通過できる。
● ペプチドホルモンは細胞膜を通過できない。ペプチドホルモンは細胞膜上の受容体と結合する。その情報はセカンドメッセンジャーとして働くcAMP(サイクリックエーエムピーと読む。環状AMP)などが伝えていく。
● 高校で習うほとんどのホルモンはペプチドホルモン。
ペプチドホルモンの例:インスリン、グルカゴン
● ステロイドホルモンは細胞膜を通過できる。一般的に、ステロイドホルモンは細胞内で受容体と結合する。
ステロイドホルモンの例:コルチコイドや精巣・卵巣から分泌されるホルモン
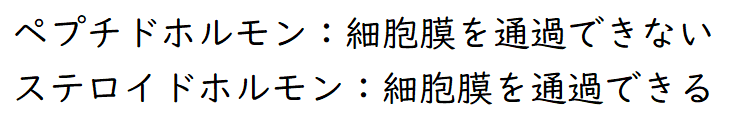
*ステロイドホルモンは脂溶性であり、細胞膜を通過できる。ステロイドホルモンの受容体は細胞質や核内に存在する。ステロイドホルモンは受容体と結合して核に作用する(遺伝子発現の変化が誘導される)。ペプチドホルモンは水溶性であり、細胞膜を通過できない。ペプチドホルモンは標的細胞の細胞膜にある受容体と結合する。ペプチドホルモンと受容体が結合すると、一連の反応が進行し、cAMP(短命なセカンドメッセンジャー)の合成が促される。cAMPは細胞内にある酵素を活性化し、様々な反応が誘導される(酵素の活性化・特定の分子の取り込み・遺伝子発現の変化・細胞骨格の再配置など、様々な反応を活性化させる)。

雑談:一般に、ステロイドホルモン受容体(性ホルモンや副腎皮質ホルモン[糖質コルチコイド、鉱質コルチコイド]の受容体)は、ホルモン結合領域とDNA結合領域をもつ。ステロイドホルモン受容体にホルモンが結合すると、この受容体はDNAの特定の領域に結合し、遺伝子の転写を制御する。
雑談:例外的に、細胞膜上の受容体に結合するステロイドホルモンもある。ステロイドホルモンであるプロゲステロンは、両生類では卵細胞膜に局在する膜受容体に結合し、細胞内情報伝達系を介して卵成熟を誘起する。
<Q.ペプチドって何?ステロイドって何?…ペプチドはアミノ酸の鎖のこと。タンパク質がふつう脂質二重層を通過できないことを思い出そう。ペプチドホルモンは細胞膜を通過しない。ステロイド(ステロイド骨格という、炭素がつながった特定の構造を持つ。脂質の一種と考えてよい)は、リン脂質でできた細胞膜を通過できる。ちなみに、チロキシンはステロイドではない(チロキシンはチロシンというアミノ酸の誘導体で、ヨウ素を含み、細胞膜を通過できる)が、受容体は細胞内にある。なお、アドレナリン(第二級アミン)の受容体は細胞表面にある。>
雑談:「脂質」の一種であるステロイドは、リン「脂質」でできた細胞膜を横断できる。
「似たものは似たものと最も容易に交じり合う」ローマのことわざ
雑談:以下はステロイドの基本骨格。覚えなくてよい。3個の六員環と、1個の五員環は、A、B、C、およびD環と呼ばれる。

講義動画【ペプチドホルモン・ステロイドホルモン】
発展:セカンドメッセンジャー
● ホルモンや神経伝達物質などの細胞外情報物質が細胞膜に存在する受容体と結合することによって細胞内で新たに生成される別種の細胞内情報物質をセカンドメッセンジャーという。
● cAMP(サイクリックAMP、環状AMP)がセカンドメッセンジャーとして有名である。

雑談:セカンドメッセンジャーに対して、細胞外情報物質として働くホルモンや神経伝達物質をファーストメッセンジャーという。
雑談:受容体などのタンパク質に特異的に結合する(一般に低分子の)物質を、総称してリガンドと言う。
雑談:cAMPの他にも様々なセカンドメッセンジャーが発見されている。カルシウムイオンなども重要なセカンドメッセンジャーである。
雑談:cAMPは環状ヌクレオチドの一種である。以下のような構造をしている。

雑談:サザランド(アメリカの薬理学者、生理学者、生化学者。グリコーゲン代謝を研究し、cAMPを発見した。1971ノーベル賞受賞)は、アドレナリンが細胞膜を通過せずに、何らかの仕組みでグリコーゲン分解を引き起こすことを明らかにした。それがきっかけとなって、セカンドメッセンジャーの研究が開始された。
サザランドは、アドレナリンが細胞膜にある受容体に結合すると、細胞内のcAMPの濃度が上昇することを発見した。cAMPがセカンドメッセンジャーとして働いていたのである。
アデニル酸シクラーゼ(adenylyl cyclase)という酵素がATPをcAMPに変換する(アデニル酸シクラーゼの働きによって、細胞内のcAMP濃度は数秒の内に20倍に増加する)。アデニル酸シクラーゼは活性化されたGタンパク質によって活性化される。Gタンパク質は、アドレナリンと結合したGタンパク質共役型受容体によって活性化される(Gタンパク質やGタンパク質共役型受容体の詳細は「細胞④」の資料にある)。
cAMPは、タンパク質キナーゼA(環状AMP依存性タンパク質リン酸化酵素)という酵素を活性化する。タンパク質キナーゼAは、別のタンパク質をリン酸化する。その結果、様々な反応が進み(タンパク質キナーゼAはホスホリラーゼキナーゼを活性化させる。ホスホリラーゼキナーゼはグリコーゲンホスホリラーゼを活性化させる)、最終的にグリコーゲンが分解される(グリコーゲンホスホリラーゼはリン酸を使ってグリコーゲンからグルコース1-リン酸の形でグルコースを放出させる)。

なお、この反応は長くは続かない。ホスホジエステラーゼという酵素がcAMPをAMPに変換するからである(したがって、再び細胞内のcAMP濃度を上昇させるためには、もう一度アドレナリンがやってこなくてはならない)。ONになったっきりOFFにならないシステムは、生体内ではまず役に立たない。OFF状態に変える反応も重要である。

まだわかっていないこと
● シェイクスピアの『ハムレット』には次のような台詞がある。「生きるか、死ぬか、それが問題だ。」発生過程で、細胞はどのようなシグナルを送り合っているのだろうか。たとえば、指は、指の間の細胞がアポトーシスを起こして形成される。どのように細胞は自身が生き残るべきか、アポトーシスを起こすべきかを判断するのか、完全には明らかになっていない。
● MHCの進化的な起源は何か。そして、どのような選択圧が働いたのか。MHCクラスⅠ、クラスⅡ分子は、軟骨魚類以上の種に存在ししている。有額脊椎動物における適応免疫のシステムは、進化上、突如として現れたように見え、「免疫学的ビッグバン」などと呼ばれたこともあった。
● 発生の過程において、細胞が大きく移動し、選別され、配置を変えることがある。その時、どのように細胞間接着が制御されているのか。たとえば、神経管になる細胞集団はNカドヘリンを発現する。実験的に表皮の細胞にNカドヘリンを強制発現させたり、予定神経細胞でNカドヘリンの合成を阻害すると、皮膚と神経系の境界が正しく形成されなくなる(Kintner et al. 1992)。
● 多くの種で、交配相手の選択は、MHCの影響を受けると考えられている。個体は、MHCの異なる交配相手を選ぶ傾向がある。この性選択の原理についてはよくわかっていない。
