
【高校生物基礎】第11講「何が全身の細胞に酸素を運ぶのか?」
~プロローグ~
運送屋は、依頼された荷物をしっかり持たなくてはならない(荷物と結合しやすい方が運送屋が望ましい)。かつ、届け先で、必ず荷物を手放さなければならない(荷物を手放しやすい運送屋が望ましい)。「荷物と結合しやすく」、「荷物を手放しやすい」運送屋が望ましいことになる。酸素を運搬するヘモグロビンも、「酸素と結合しやすい」という性質と、「酸素を解離しやすい」という性質の、両方をもつ方が望ましい。これは一見矛盾しているように思える。どうすればいいのだろう?
実は、ヘモグロビンは、「肺のような(酸素が多く二酸化炭素が少ない)環境で酸素と結合しやすく、活発に呼吸を行っている組織のような(酸素が少なく二酸化炭素が多い)環境で酸素を解離しやすい」という性質を持っている。この性質により、酸素を肺から組織へ効率よく運ぶことができるのである。
「有機体とはじつは目的そのものが物の形をとったものである。」ヘーゲル『精神現象学』より
★テストに出やすいワード
①酸素解離曲線
②ヘモグロビン
③血ぺい
④フィブリン
⑤血清
要点:赤血球に含まれるヘモグロビンというタンパク質は、酸素を運搬する。
(1)ヘモグロビン
● 肺では多くのヘモグロビン(Hbと省略することがある)が酸素と結合し、酸素ヘモグロビン(HbO2と省略することがある)になる。HbO2は、組織で酸素を解離し、酸素は細胞に供給される。下図はイメージ。
(実際は、肺においても100%のHbが酸素と結合するわけではない。また、組織においても全ヘモグロビンが酸素を解離するわけではない。)
(実際は、ヘモグロビンは、4分子の酸素と結合することができる。)

● ヘモグロビンは、ヘム(鉄を含む色素)とグロビン(タンパク質)からなる。

雑談:一酸化炭素(CO)は無色無臭の気体で、石炭、ガス、木などの炭素を含んだ物質が燃焼する時に出る副産物である。COはO2と同じようにヘモグロビンのへムに結合するが、COはO2より200倍以上も強く結合する。一酸化炭素が0.1%あるだけでヘモグロビン分子の半分がCOと結合し、血液の酸素運搬能力が50%低下する。血液中のCO濃度が上昇すると、一酸化炭素中毒が引き起こされる(唇が鮮紅色となる。これはCOが結合したヘモグロビンの色である)。急いで治療しなければ、死に至る。酸素を投与することにより、ヘモグロビンからの一酸化炭素の分離を促進し、一酸化炭素中毒から救うことが可能である。
発展:ヘモグロビン
ヘモグロビンは、グロビンと呼ばれるタンパク質部分と、ヘムと呼ばれる鉄を含む色素部分からなる。それぞれのグロビンにヘムが1つずつ結合している。ヘムの鉄原子が酸素結合部位である(ヘムの中心には1個の鉄イオン[Fe2+]があって、1個の酸素分子と結合したり解離したりすることができる)。グロビンにはα鎖とβ鎖がある。ヘモグロビンは、α鎖とβ鎖を1対ずつ含む(この4本のポリペプチドの配置がヘモグロビンの四次構造である)。下図はイメージ。

雑談:ヘモグロビンのヘムにあるFe(鉄)に酸素が結合すると考えられている。

(2)酸素解離曲線
● ヘモグロビンと酸素との結合のようすを表したグラフを酸素解離曲線(さんそかいりきょくせん)という。
● 酸素解離曲線はS字型になる。
● その環境に酸素が多いほど、全ヘモグロビン中の酸素ヘモグロビンの割合は増えていく。また、二酸化炭素が多いほどヘモグロビンは酸素を解離しやすくなる。
よって、下のグラフではAよりBのほうが二酸化炭素の量が多い条件で実験したということがわかる(AよりBの方が酸素ヘモグロビンの割合が小さくなっているから)。

● 上の酸素解離曲線において、『酸素濃度100、二酸化炭素濃度がAの条件』では、ヘモグロビン100個中95個が酸素と結合することがわかる。
同様に、『酸素濃度30、二酸化炭素濃度がBの条件』では、ヘモグロビン100個中25個が酸素と結合することがわかる。
*様々な酸素濃度条件・二酸化炭素濃度条件の下でデータをとり、作製したグラフが酸素解離曲線である。
例題:肺胞中のHbO2(酸素ヘモグロビン)の割合を97%、組織中のHbO2の割合を26%として、以下の問い①②に答えよ。
①肺胞で酸素を結合していたHb(ヘモグロビン)のうち、組織で酸素を解離したHbの割合は何%か。最も近い整数で答えよ。
②全Hbのうち、組織で酸素を解離したHbの割合は何%か。整数で答えよ。
答え:
(下に貼ってある講義動画【酸素解離曲線】も参照せよ。)
①「肺で酸素と結合したHbのうち」、何%が酸素を解離したか聞かれているので、分母は97にする。Hbが全部で100個あったとすると、酸素を解離したHbは97-26=71個。肺で酸素と結合していた97個のヘモグロビンのうち、71個が酸素を解離した。その割合を求める。
(97-26)/97=71/97=約0.73
よって73%
②「全Hbのうち」、とあるので、分母を100にする。
(97―26)/100=0.71
よって71%
(全Hb=Hb100個のうち、71個が酸素を解離した。)
● 温度が高い(代謝が活発)ほど、
二酸化炭素が多い(呼吸が活発)ほど、
酸性である(代謝が活発な組織ほど、CO2が多く産生され、pHは低下する)ほど、
酸素解離曲線のグラフは右に(下に)ずれる(=ヘモグロビンはそこで酸素を解離しやすくなる)。つまり、酸素が必要な組織で、HbO2が酸素を解離しやすいようになっている。
*AよりBのほうが高温、高CO2、酸性条件。

● 母体のヘモグロビンから酸素をもらう(奪う)必要がある胎児のヘモグロビンや、酸素の薄い高地にいるリャマなどの動物のヘモグロビンは、酸素と親和性が高く、酸素解離曲線は(成体や平地に住む動物のヘモグロビンに比べて)左に(上に)ずれる。
問題:リャマなどの高地に住む動物のヘモグロビンや、胎児のヘモグロビンの酸素解離曲線は、左と右、どちらにシフトしているか。
答え:左
講義動画【酸素解離曲線】
発展:ミオグロビン
ミオグロビンと言うヘモグロビンに似たヘムタンパクは、骨格筋や心筋などに高濃度に存在する(そのためこれらの組織は特徴的な赤色をしている)。ミオグロビンは酸素の保持に役立っている。ミオグロビンはヘモグロビンより酸素との親和性が高い。下図はミオグロビンとヘモグロビンの酸素解離曲線のイメージ。

発展:胎児のヘモグロビン
胎児は胎盤を通じて母体の血液から酸素を得る。下図はイメージ。

上図のように、胎児の血管と母体の血管は、直接つながっているわけではない(もし母体と胎児の血液が混ざるとすると、たとえばA型の母とB型の娘の血液が混ざってしまうことになる。そんなことは起こらない)。
母体の動脈の末端から母体の動脈血が吹き出され、血液のプールに入る。その母体血から酸素などが胎児の毛細血管に取り込まれる。その後、酸素は胎児の静脈を通って胎児の体に運搬される。母体の静脈は、再び酸素を補給するため母体の肺へ向かう。
胎児ヘモグロビンの酸素解離曲線は母体ヘモグロビンのそれより上(左)にずれているので、同じ環境では、母体ヘモグロビンより胎児ヘモグロビンのほうが多くの酸素を結合する。このような胎児ヘモグロビンの性質により、母体酸素ヘモグロビンが解離した酸素の一部を胎児ヘモグロビンが回収することが可能になっている。

雑談:高地でトレーニングを行うと、血中にBPG(ビスホスホグリセリン酸)という物質が増えることが知られている。この物質は、ヘモグロビンと結合し、ヘモグロビンの酸素との親和性を下げる(BPGは酸素輸送の調節因子として働いている)。BPG濃度が高いと、ヘモグロビンは、組織でよりたくさん酸素を解離する(すなわち、たくさんの酸素が組織に供給される)と考えられている。このような状態の人が低地に戻ると、運動に伴う息苦しさを感じにくくなると考えられている。また、低酸素状態では、エリスロポエチンという、赤血球の産生を促す物質(糖タンパク質)の分泌が高まる(エリスロポエチンは主に腎臓でつくられ、分泌される。エリスロポエチンはヘモグロビンの合成も促進する)。高地トレーニングを行うことによって、エリスロポエチンの分泌量を増加させ、赤血球数を増やすことが可能である(エリスロポエチンの投与により、赤血球数が増加し、有酸素運動で有利となることができる。これは、ドーピングとして問題になっている)。
要点:血小板という血球は、血液凝固反応に関わる。
● 血液は酸素(ヘモグロビンに結合)や栄養分(血しょうに含まれる)を運ぶので、血液の流出は命にかかわる。
● 血管が傷つくと傷口に血小板(けっしょうばん)が集まって傷口をふさぐとともに、血小板から血液凝固に関わる因子が血しょう中に放出される。すると、血液凝固因子(けつえきぎょうこいんし)などの働きによって、フィブリノーゲンから繊維状のフィブリンが形成される。
● フィブリンが血球を絡め取り、血ぺい(血餅)が形成される。血ぺいによって傷口がふさがれるので出血が止まる

*以下は血ぺいのイメージ。

● 血液凝固を防ぐには、①棒でフィブリンを絡め取る、②ヘパリンやヒルジンによるトロンビンの機能の阻害、③クエン酸ナトリウムによるCa2+の除去などの方法がある。
雑談:ヘパリンは、血管内での血栓形成の阻止に使われている。ヘパリンは肝臓にもともと存在する血液凝固阻止物質として得られるが、医薬品として工業生産されている。ヒルジンは、医用ヒルの唾液腺中に含まれているポリペプチド。ヒルは、吸血と同時に、抗凝血作用を持つヒルジンを分泌する。ヒルジンの作用により、吸血後十数時間ゆっくりと出血が持続する。
● 血液凝固反応とは逆に、固まった血液が溶ける反応を線溶(せんよう)という。
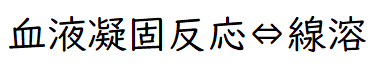
● 血ぺいは血液を静かに放置することでも観察することが出来る。血液を放置すると、血ぺいと、液体成分の血清(けっせい。うす黄色の液体。血清の中には抗体が含まれることから、血清療法に使われる)とに分離する。
*フィブリン(血球をからめとって血ぺいを生じさせるタンパク質)はフィブリノーゲンという物質からつくられる。つまり、血清は、血しょうからフィブリノーゲンを除いた物にほぼ等しい。
*血液凝固反応の詳細:損傷した組織から放出されるトロンボプラスチン(反応開始の引き金である)という血液凝固因子と、血小板から放出される血小板因子(けっしょうばんいんし)が、複雑な反応を経て、プロトロンビンをトロンビン(酵素の一種)にする。トロンビンはフィブリノーゲンをフィブリンに変える(ここまでの反応にはCa2+が必要である)。フィブリンは血球をからめとり、血ぺいにする。
*なお、実際は、血液凝固反応はもっと複雑な反応であり、他にも多数の凝固因子が関わる。多くのステップで、Ca2+が必要になる。

*高校では、血小板に由来する因子を「血液凝固因子(凝固因子)」と呼ぶことも多い。テストでは学校の教材の解釈に合わせること(ただ、生理学では、ふつう血液凝固因子と言ったら、第Ⅰ因子~第XⅢ因子などの因子を指す。血小板固有の因子[血小板膜リン脂質と血小板中のα顆粒に含まれる特有のタンパク質]は、ふつう、血小板因子と呼ばれる)。
雑談:以下に血液凝固因子を記すが、高校生は覚えなくてよい(発見順にローマ数字が振られている)。
第Ⅰ因子:フィブリノーゲン
第Ⅱ因子:プロトロンビン
第Ⅲ因子:組織トロンボプラスチン
第Ⅳ因子:Ca2+
第Ⅴ因子:不安定因子
第Ⅵ因子は欠番(現在用いられていない)。
第Ⅶ因子:安定因子
第Ⅷ因子:抗血友病因子
第Ⅸ因子:クリスマス因子
第Ⅹ因子:Stuart因子
第Ⅺ因子:血しょうトロンボプラスチン前駆物質
第Ⅻ因子:ハーゲマン因子
第XⅢ因子:フィブリン安定化因子
講義動画【血液凝固】
雑談:トロンビンは巨大なフィブリノーゲンを加水分解して、フィブリンモノマーをつくる。フィブリンモノマーは重合して、鎖状のフィブリンポリマーを作る。フィブリンはフィブリンモノマーとフィブリンポリマーの総称である。血栓はthrombusと言う。トロンビン等の語源である。
雑談:Ca2+は、血液凝固の反応のほぼすべての過程で必要である。
雑談:フィブリノーゲンの語尾「-gen」は、「源」という意味。つまりフィブリノーゲンはフィブリンの源という意味。 グリコーゲンがグルコースの源であるのとネーミング規則は同じ。
雑談:タンパク質の語尾は「インin」になっていることが多い。繊維(ファイバーfiber)状のタンパク質であるフィブリン(fibrin)もその例。
雑談:血小板因子は、当初、第1因子~第9因子まで提唱されたが、その後、多くのものが整理され、第3因子(血小板膜リン脂質)と第4因子(血小板特有のタンパク質)だけがその名を残している。
雑談:損傷した組織から放出されるトロンボプラスチンは、分子量約45000の糖タンパク質である。
雑談:プラスミンという糖タンパク質が、フィブリンを溶かし、血栓を溶解する現象を線溶という。この線溶の勢いと、血液凝固を進めようとする勢いが、常に拮抗している。優勢な方に現象が進む。
雑談:どうして血液凝固因子が放出された後、関係ない様々な場所で血液凝固が起こらないのだろうか。いくつか理由はあるが、最もシンプルな理由は、血液に流れて因子が薄まるからである。
雑談:実際は、血液凝固反応のルートには、損傷した組織からトロンボプラスチンが放出されて始まる反応ルートと、破れた血管のコラーゲン等がきっかけになって始まる反応ルートがある。高校生は知らなくてよい。
実験動画【血球と血しょうの分離・血液凝固反応の阻止】
*豚の血液を使った実験です(血液が苦手な人は見ないでください。おすすめに出ないように限定公開にしてあります)。
発展:CO2の輸送
CO2の輸送については、めったに問われない。CO2の大部分は炭酸水素イオン(HCO3-)の形で運ばれるとだけ知っておけばよい。以下、少し詳しく記す。ヘモグロビンはHbと略す。

①CO2は拡散によって赤血球内に入る。
*非常に少量のCO2は血液に溶解した状態で運ばれる。
②赤血球内に入ったCO2の一部はHb(ヘモグロビン)と結合する(覚えなくてよいが、できた物をカルバミノ化合物と言う)。
③CO2は水と反応して炭酸(H2CO3)を形成する。血しょう中でのこの反応はゆっくりだが、赤血球内では炭酸脱水酵素(たんさんだっすいこうそ)が触媒し、この反応の反応速度を5000倍に高めている(上図の※で働く酵素が炭酸脱水酵素。酵素の名前が紛らわしいが、この酵素はH2CO3⇄CO2+H2Oの反応を触媒する)。
(図には示していないし、気にしなくてよいが、血しょう中のCO2も、血管内皮細胞表面にある炭酸脱水酵素によってH2CO3になる。)
④赤血球内で形成された炭酸(H2CO3)は、次の瞬間には水素イオン(H+)と炭酸水素イオン(HCO3-)に分離する。
⑤ヘモグロビンには強力な酸塩基緩衝作用があり、大部分のH+はヘモグロビンと結合する。
⑥HCO3-は赤血球膜上の輸送体(Cl-ーHCO3-交換輸送体)を介して血しょうに出る(赤血球に残るものもある)。
⑦⑥と同時に、Cl‐が赤血球内に入る(これによりイオンバランスが保たれていると考えられている)。
*肺では、HCO3-は赤血球内(や血管内皮細胞表面)でCO2に戻り、拡散する。(肺では上図の逆向きに反応が進む)
Q&A
Q.酸素解離曲線って何?…ヘモグロビンの性質を表す曲線(周囲に酸素が多いとたくさん酸素と結合する性質や、二酸化炭素が多いと酸素と結合しにくくなる性質がわかる)。
Q.二酸化炭素の濃度が高いと酸素ヘモグロビンの割合が減るのはなぜ?…原理は少し難しい。ヘモグロビンの立体構造が変わり、酸素との親和性が下がる(ボーア効果という。pHの低下により、ヘモグロビンのアミノ基などにH+が結合し、ヘモグロビンの構造変化が起こる。それによってヘム鉄と酸素との間の結合強度が変わると考えられている)。余談だが、ボーア効果を報告したクリスチャン・ボーアは、ニールス・ボーア(理論物理学者。量子力学の誕生において指導的役割を果たした。量子力学の確率解釈をめぐるアインシュタインとの論争は有名)の父である。
Q.なんでヘモグロビンの酸素解離曲線はS字なの?…ヘモグロビンは、4つのサブユニットから成る。1つのサブユニットに酸素が結合すると、その情報が他のサブユニットに伝わる。すると、酸素との親和性が上昇する。したがって、酸素との結合は、さらなる酸素との結合を促進する。S字はこの性質を反映している。
Hb「酸素なんていらないよ」
↓ 酸素と結合する
Hb「酸素・・もっと欲しいかも」
↓ 酸素と結合する
Hb「酸素欲しい!酸素大好き!酸素をよこせ!」
みたいに、だんだん酸素が好きになっていくイメージ(冗談です)。
*上の説明は非常に雑である。
ヘモグロビンの酸素結合反応において、4個のヘム鉄のうち最初の1個に酸素が結合すると、残りのヘム鉄の酸素親和性が増大することは、昔から知られていた。この現象をヘム間相互作用という(ヘム間相互作用:はじめの酸素との結合が、後に続く酸素との結合を増強する作用)。
現在、この仕組みについて、いくつかのモデルが提唱されているが、完全には解明されていない(特に、酸素が1~3個結合した中間体のみを単離することは困難であるため、それらの中間体の性質は研究しにくい。ただ、一般には、ヘモグロビンは、酸素と結合すればするほど、酸素との親和性を上昇させていくと考えられている)。
ヘム間相互作用の詳しい機構は明らかではないが、酸素の結合に伴う、ヘモグロビンの高次構造の変化によることは間違いないであろうと考えられている。この相互作用によって、「肺のような高酸素分圧下で酸素と結合しやすい。また、組織のような低酸素分圧下で酸素を放出しやすい」という性質を実現している(酸素運搬体として非常に都合が良い)。
雑談:デンマークの生理学者クリスチャン・ボーアはヘモグロビンの酸素解離曲線がS字状になることに気が付いた(その理由を説明する様々な説が出された)。その後、ヘモグロビンのサブユニットが協同的に相互作用し、最初のHbO2の生成がさらなるHbと酸素との結合を容易にするらしいことが分かった。
Q.酸素解離曲線の学習で出てくる「組織」って何?…正確には、同種の細胞の集まりを組織というが、まあ、「体の色々な部位」という意味でも使う。
