
聖書とナニナニ
畏友より質問をもらった。テーマは「聖書と性」。たとえば、あからさまに女性蔑視と見える聖書の記述がいくつかある。以下は有名なところだ。事実、歴史的に何度も槍玉に挙げられてきた。
男は、怒ったり争ったりしないで、どんな場所でも、きよい手をあげて祈ってほしい。また、女はつつましい身なりをし、適度に慎み深く身を飾るべきであって、髪を編んだり、金や真珠をつけたり、高価な着物を着たりしてはいけない。むしろ、良いわざをもって飾りとすることが、信仰を言いあらわしている女に似つかわしい。
女は静かにしていて、万事につけ従順に教を学ぶがよい。女が教えたり、男の上に立ったりすることを、わたしは許さない。むしろ、静かにしているべきである。なぜなら、アダムがさきに造られ、それからエバが造られたからである。
またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされて、あやまちを犯した。しかし、女が慎み深く、信仰と愛と清さとを持ち続けるなら、子を産むことによって救われるであろう。
(Ⅰテモテ2章 抜粋)
すべての男のかしらはキリストであり、女のかしらは男であり、キリストのかしらは神である。祈をしたり預言をしたりする時、かしらに物をかぶる男は、そのかしらをはずかしめる者である。
祈をしたり預言をしたりする時、かしらにおおいをかけない女は、そのかしらをはずかしめる者である。それは、髪をそったのとまったく同じだからである。もし女がおおいをかけないなら、髪を切ってしまうがよい。髪を切ったりそったりするのが、女にとって恥ずべきことであるなら、おおいをかけるべきである。
男は、神のかたちであり栄光であるから、かしらに物をかぶるべきではない。女は、また男の光栄である。なぜなら、男が女から出たのではなく、女が男から出たのだからである。また、男は女のために造られたのではなく、女が男のために造られたのである。
(Ⅰコリント11章 抜粋)
なかなか刺激的だ。現代なら、パッと読んで憤死する人もいそうだ。では、これらの記述をどう考えれば良いのか。参考になるのは、Pトリブル著『フェミニスト視点による聖書読解入門』(新教出版社、2002年)だろう。
本書におけるトリブルの議論を要約しておく。まずトリブルは、読者に「聖書が父権制の産物である」と認め、徹底的に批判することを求める。その上で、テクスト自体から「父権制」を相対化、解体して、新たな解釈の地平へと招く。
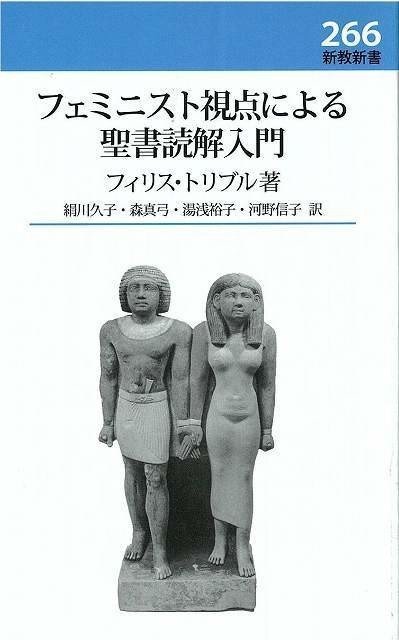
トリブルは、この目標にそって、モーセの姉ミリヤム、エリヤと対決した女王イゼベル、イエスの母マリアと無数のマリア(ミリアムのアラム語読み)へと読者の注意を促す。
また伝統的な「創世記」読解にも異を唱えて、男女の創造の前に「土の人」という無性別の被造物を見出している。
たしかに「彼女ら」に注目することで、男性中心で進んでいく聖書物語が相対化され逆転される。テクストの含むところ、その意味世界は「女」の登場により拡大され、浮き彫りになる。
トリブルは自身の聖書解釈について異端的かもしれないが、それでも構わないと振り切って、これらを語る。その潔さが彼女の確信と真剣さを物語っている。ぼくとしては「土の人」解釈は、アクセルを踏み切っている感じがするので、高く評価したい。おもしろい。
もちろんトリブルへの批判もある。大別すると三つ。一つは、当然ながら、現代的な価値規範に当てはめた「古典」解釈の是非である。
また一つは、弱者としての「女性」を言いながら「同性愛者」についてトリブルが言及しないこと。「弱者」として名乗り出ながら、他の弱者を抑圧している、という批判。
さらにもう一つ。文法解釈など一般的な文献学的な手続きからいって、トリブルの解釈に問題がある、という批判。要するに、彼女の文法理解への疑義申し立てだ。テクスト自身に語らしめていない、トリブルの思想にテクストが呑み込まれてしまっている、という批判。
では、トリブルの意欲的著作、またそれへの批判的検討によって明らかになったことは何か。
それが「思想とテクスト」なる根源的問題だ。ある実践とテクストを反復しながら「社会運動」へと展開するときに、誰もが直面せざるを得ない問題である。
「思想とテクスト」の二者択一を求めるのは愚かだ。とはいえ、大きな問題だと思う。たとえば、ある被害者の証言(テクスト)を元に、二度とそのような悲劇を繰り返さないために、証言は事実となり、社会的認知を求めて(実践)、やがて法制化される(思想の具現化)。社会思想に基づく、多くの差別解消/権利獲得の運動は、この過程を経るだろう。
しかし、その繰り返される「語り」によって、しばしば記憶と記録が一体化することはないのだろうか。運動拡大のために、誠実で緻密な作業を捨て、含意しないものまでも呑み込んで、目的がすり替わることはないのか。「弱者」であり続けることが目的ではないハズである。
無論、ことばを紡いて思想を編むとき、折り重なる記憶は、ある種のデザインを纏う。その善悪は問題にしていない。そういうものである。
だから、トリブル流の聖書解釈に対するぼくの評価は肯定的だ。思想を立ち上げ、顕名で語るなら、そのくらい力強いほうがよい。文法的厳密さは当然だ。しかし、思想は、その文脈の全体から離陸するような、たとえば一つの島が浮き上がるような飛沫とうねりを起こしてこそであろう。
トリブルは実名で語り、研究者として語っている。それゆえ「思想とテクスト」の関係は、自他ともにかなりの程度まで峻別可能である。言わば、テクストの検証による再現可能性がある。従ってトリブルは正当な意味でフェミニストである。
裏返せば、この手続きの責任を放棄する者は、思想ともテクストとも関係がない。それは、悪魔的に自己目的化したモンスターである。和風にいえば、ただの生霊か怨霊の類であって、必要なものはデータに基づく誠実な対話と建設的議論ではなく、お祓いである。だから、学問的、社会的に取り扱うに足りない。医療と福祉ケアの対象である。
ではトリブルが言及しなかった「同性愛者」について、どんな事例があるのだろうか。J.C. ブラウン著『ルネサンス修道女物語―聖と性のミクロストリア』(ミネルヴァ書房、1988年)という本がある。

本書は、あのメディチ家「雑録」に挟まれていた裁判記録から再現された、宗教改革時代のイタリアを生きた修道女ベネデッタ・カルリーニの物語。「歴史」から発掘された「聖書と性」の事例として、世界各国で史学者らによって翻訳され、話題を呼んだ。
預言と幻視、レズビアン疑惑、中世キリスト教世界における同性愛の実例として、彼女の名は文明の限り、記憶されるだろう。
そのほか、最近年の「聖書と性」に関する言論状況を確認するなら、雑誌『福音と世界』の2015年6月号「教会と性」、2017年7月号「クィア神学とは何か」などが参考になるだろう。
とくに前者「教会と性」特集冒頭の勝村弘也「雅歌研究史から見えてくるもの」は、明晰かつクリアに聖書解釈と性について土台を据えてくれる。また後者「クィア神学」特集の佐々木裕子「クィアな知の営み――周縁から規範を徹底的に問い直す――」は、神学の持つクィア性の射程を見せてくれる論考である。
「聖書と性」をめぐる先にある「思想とテクスト」の問い。その落しどころは、どこにあるのだろう。

個人的な見立てと意見を述べておく。
1960年代以降のフェミニズムの隆盛は、聖書解釈にも連動して「フェミニズム神学」へと結実した。しかし、現在、それへの批判として米国では「ウーマニスト神学」が出ている。人間を男で考える者たちを批判したフェミニズムに対し、女を白人女性で考えたフェミニズムを批判したのが、黒人女性らによるウーマニスト神学だ。
このウーマニスト神学については、ぼくも研究指導の中で聞いた程度で詳しくは知らない。参考書としては、Nyasha Junior著『An Introduction to Womanist Biblical Interpretation』(John Knox Press、2015年)がある。思想的源流としては、黒人作家アリス・ウォーカーの『カラー・パープル』などがあるだろう。
この時代の変遷から明らかなように、フェミニスト神学もウーマニスト神学も、「身体性」の神学である。従って、次に来たのが「クィア神学」であることもまた当然の帰結であろう。
では、クィア神学は他の神学と何が違うのか。上掲の佐々木論考によれば、それは「ジェンダー」の問題系をより広く問うことで、ジェンダーに限定されず、そこに拘泥しない可能性を持つ点である。

別件ながら指摘しておくと、自身の固有性≒身体性の神学という意味では、これらの領域に「障害者の神学」も想定され得るし、事実、研究と実践の蓄積もある。
ぼくとしては、これらは「解放の神学」という一語において括れるのではないか、と思ってしまう。無論、そのような思考法こそが差別抑圧に無自覚かつ暴力的な...とお叱りを受けそうである。
しかし、「聖書と性」の問題から遠い者として思ってしまう。ぼくは異性愛の非モテ中年男性だ。それゆえ、マジョリティである。正直にいって「聖書と性」については、それほど関心がない。だから厳密な議論はできない。ただ、勝村先生や佐々木先生のような、当該分野の専門家の発信を真摯に拝読する気はあるつもりだ。
ぼくは「性(genderとsex)」を「身体を解釈する関係性」だと考えている。究極的に「性とはその瞬間ごとに生成し変化するグラデーション」だと理解している。自己申告に基づく「性」という名のアイデンティティ=人格の表象は、尊重されてよい。
単なる物理的身体として「性別」、男女に区分し得ないものは、「その他」として対応するしかない。被造物全体を見渡せば、生殖のための性はかなり多様である。たとえばゾウリムシには十数の性別があると言われるし、その他生物にも雌雄同体、性転換、工夫を凝らした生殖器など、かなりの多様性がある。
すなわち問題は、人類における「性別」の意味するところに「人格」が含まれていることだ。こうなると近代社会は大きな問題を抱えてしまう。
自己申告の性別と、その可変性に、どこまで社会インフラが対応すべきなのか。否、そもそも性と混在して語られる「個人」や「人格」は、そこまで確かなものか。
大胆にいおう。「性」の相対化は、究極的に「人格」や「歴史」を相対化するものである。ここまで来ると答えは単純。いわゆる仏教の「縁と空」が極北だ。行くなら、あの彼方まで行ったほうが、みな幸せになるのではないか。聖書なんか読まずに、きちんとした寺で坊さんから学んだほうが良い。ぼくは本気でそう思う。
だから個人的には「聖書と性」の話は、あまり広がりのある話にならない。結局、「固有の私の性別」問題は、近代社会における「個なる人格」という病の副作用のように思えてしまう。
さて、ここまで「聖書と性」の問題から、二つの根源的な問いが現れた。一方は「思想とテクスト」の問題、他方は「個なる人格」の問題である。ぼくは、この両者の交差点が「解放の神学」にあると考えている。
「解放の神学」は、本来この語彙そのものを学問的に論じるべき内容であるが、そこは各自で検索して頂きたい。日本語でも英語でも読み物は見つかるだろう。
すべてを割愛していえば、ぼくは「日本の国体」に関する「解放の神学」を考えている。きっと、ぼくのキリスト教信仰の歴史的意味は、これに尽きる。このために召し出されたのだろうと勘違いしたくなるほどには、このテーマについて考えている。
では「「日本の国体」解放の神学」とは何か。それは、「日本」と名指された国の「体」から起き上がり湧き出すもの、日本語の身体によるキリスト教思想である。
この轍は、トリブルと似た道を取ることになる。きっと、思想がテクストを呑みこんでしまう。そして、個なる人格は虚妄として雪のように溶け、地肌が露わになってしまうだろう。
固有性から普遍性を語ること、その語りはときに騙りになってしまう危うさがある。しかし、それでも公共性と呼ぶに足る地平、了解可能な水平線がどこかにあるのではないか。そう思っている。
もはや新たな中間共同体を形成していくのは無理な気がする。しかし、大きな物語もなしに人生の悲劇と辛苦を認めるのも難しい。ましてや神仏も超越もないのに有限性を自覚して諦念を得よ、というのも厳しいのだろう。
個の時間を超えながら、なお個と共にある時間を回復すること。記憶と期待の狭間で、主体や人格には足り得ぬ、歴史になり得ないぼくらの新大乗キリスト教への道筋が、いま狐火のように青く揺らめいている。その照り返しが、ぼくの胸中に未見の故郷へのノスタルジーにも似た憧れを灯している。
以上、「聖書と性」をめぐって思うところを書き殴った。なお本題は「聖書と何々〜」と語ること自体であったが、前置きが長くなったので、ここでスマホを置く。

最後に参考文献を置いておく。伊藤明生の論文『「子を産むことによって救われる」とは : テモテヘの手紙第一2章15節の釈義をめぐって』である。検索の上、熟読されたい。
※全文無料ですが研究継続のためご支援下さい。
ここから先は
¥ 500
無料公開分は、お気持ちで投げ銭してくださいませ。研究用資料の購入費として頂戴します。非正規雇用で二つ仕事をしながら研究なので大変助かります。よろしくお願いいたします。
