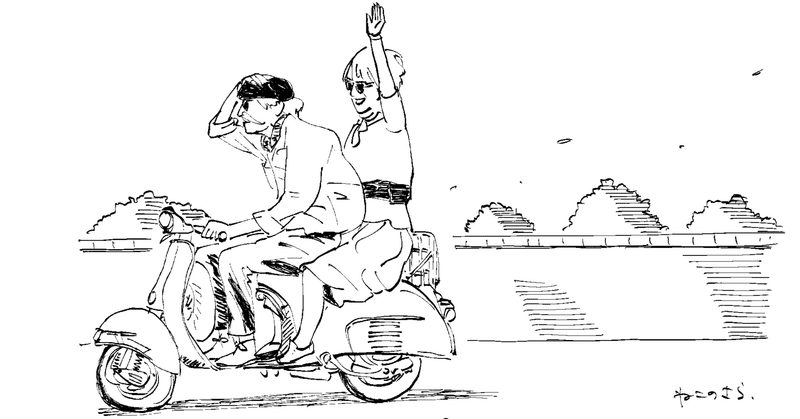
年齢による違いが消えていく
おはようございます 渡辺です。今日もとても良い天気ですね。
今週は、「消齢化社会」- 博報堂生活総合研究所 を紹介します。
この本のサブタイトルは、「年齢による違いが消えていく!生き方、社会、ビジネスの未来予測」です。ちなみに、博報堂生活総合研究所(生活総研)は、「生活者発想」を具現化するために1981年に設立されたシンクタンクです。40年に渉って調査を続けてきているからこそ、経年での変化が目に見えるわけですね。
さよなら、デモグラ。
この本の「はじめに」は、タイトルとして、「~ さよなら、デモグラ。~」となっています。ご存じの方も多いかと思いますが、デモグラとは、正確には、「デモグラフィック属性」のことで、性別、年齢、居住地域など人口統計学的な属性のことで、多くの場合においてマーケティングのターゲットを明確にするための指標として使われています。
そして、この本のタイトル「消齢化社会」ですが、生活者の意識や好み、価値観において、年齢による違いが小さくなっていることを発見し、その現象を「消齢化」と命名し、調査・研究を行っているということです。
本にも書いてありますが、身近な感覚としても、「元気で若々しいご老人が多い気がする」とか「最近の若者は大人びている気がする」というのは、ズレていないモノだと思います。
例えば、どういうデータがあるのか?ということですが、下のグラフの「将来に備えるよりも現在をエンジョイするタイプ」という問いに対し、20代がゆるやかに下降する一方で、60代がぐんぐん上昇していき、1992年の調査時には、最大値と最小値の差が24.2ptだったの対し、2022年では、差は、わずか7.6ptに縮まっていることが分かります。

当然、年を経ることにより、年代差が大きくなっている項目もあるのですが、1992年と2022年の30年変化で見た場合、全366項目中、年代による違いが大きくなっている項目は7項目に対し、年代による違いが小さくなっている項目は70項目ということで、これらのことからも、年代間の違いが縮小傾向にあることが分かりますね。
という訳で、今週は「消齢化社会」について掘り下げていこうと思います。
それでは、11月最終週ですね。本日もよろしくお願いいたします!
消齢化の傾向の例
おはようございます 渡辺です。雲一つない青空が広がっています。
さて、「消齢化社会」2日目です。昨日は、「将来に備えるよりも現在をエンジョイするタイプ」という設問がありましたが、他にどのような項目で消齢化の傾向がみられるか紹介したいと思います。
消齢化クイズ
次の5つの項目は、「生活定点」で実際に調査している質問項目です。年齢の違いが小さくなってきているのは、どの項目でしょう?
A.ハンバーグが好き
B.超能力を信じる
C.夫婦はどんなことがあっても離婚しない方がよいと思う
D.木の床(フローリング)が好きだ
E.世界にひとつしかない自分の服や小物などを作りたいと思う
如何でしょうか?実は、すべて年齢における違いが小さくなっている項目となります。詳細は、こちらのデータ
を参照してみるといいかと思いますが、ざっくりで紹介します。
【03 食】ハンバーグが好き
こういう項目があるのに驚きましたが、他にもチャーハン、パスタ、丼もの、刺身から野菜の煮物といったものから、調理済食品(レトルト、冷凍食品、惣菜など)をよく使う といったような設問もあります。で、ハンバーグですが、全体的に右肩上がりの傾向ですが、2002年には2割程度だった60代が2022年に約5割まで上昇することで、年代差が縮まっています。
【21 心理・身体特性】超能力を信じる
これも中々、面白い設問ですが、先ほどと逆傾向で2002年には過半数だった20代30代が2割近くまで減少することで差は5.7ptまで縮まっています。背景の一つに、90年代のミステリーサークルや人面犬、ノストラダムスの大予言などのブームがあるかもしれません。
【10 家族】夫婦はどんなことがあっても離婚しない方がよいと思う
結婚観、家族観みたいなものは、結構変化した項目かもしれないですね。依然60代は他の年代に比べ高い傾向ではありますが、2002年には5割程度だった60代が2022年に2割をきるまで減少することで、年代差は7.7ptと縮まっています。
いかがでしたでしょうか?なかなか興味深い内容だとおもいますので、興味を持っていただいた方は、ぜひ上のリンクから詳細やほかのコンテンツなども見てみてください。
本日合宿で終日大久保会議室にいますが、何かありましたらslackなどでご連絡ください!それでは、本日もよろしくお願いいたします!
消齢化3つのパターン
おはようございます 渡辺です。
さて、「消齢化社会」3日目です。今日は、消齢化3つのパターンと共に消齢化の背景について触れていきます。
パターン1:上昇収束型
各年代で、増加しながら、年代間の違いが縮小傾向にあるパターンになります。参考としての設問としては、以下のものが挙げられています。
・携帯電話やスマホは私の生活になくてはならないものだ
・調理済み食品をよく使う方だ
これで、興味深かったのは、作家の山根一眞さんがかつて唱えた「人生ゴムバンド」という考え方です。簡単に言えば、寿命が70年だった時代の70歳と寿命が100年時代の100歳は、年齢の感覚的にだいたい同じであるという考え方です。つまり、同じ60歳でも感覚的にも昔より若いですね。他にも、コンビニやファストフード、宅配といった生活インフラの充実などにより、出来ることが増えたというのが背景にあるとなっています。
パターン2:下降収束型
各年代の回答が減少しながら近づいていくというパターンになります。
・子供は親の老後の経済的な面倒を見る方が良いと思う
・家庭生活よりも仕事を第一に考える方だ
・習慣やしきたりに従うのは当然だと思う
これは、戦前世代の退出により、常識や慣習、価値観の面で保守的・伝統的な考え方から離れ、違いが小さくなっていることが挙げられています。それと共に、社会全体での「すべき」が減り、それらにとらわれずに暮らす人が増えたということになります。
パターン3:中央収束型
文字通り、各年代が真ん中に集まる形で近づいているパターンになります。
・ものやサービスの購入についてこだわる方だ
・流行やトレンド情報に関心がある
・お酒をのむ
生活者の嗜好の違いや特徴が、年代による差がなくなってきているということです。お酒の例でいえば、年代関係なく、飲む人は飲むし、飲まない人は飲まないというかんじですね。「年相応」や「適齢期」というよりは、一人一人の好きなように、生き方の選択肢が広がってきているということになります。
いかがでしたでしょうか?それでは、本日もよろしくお願いいたします!
消齢化社会の死語を考えてみる
おはようございます 渡辺です。引き続き良い天気が続いて嬉しいですが、寒くなりましたね。
さて、「消齢化社会」4日目です。本日は、コラム「消齢化社会の死語を考えてみる」から紹介します。死語として捉えなくても、ダイバーシティの観点からもあんまり使ったりしない方がよさそうな言葉になってくると思います。
1.年齢を、未熟なこと/成熟していることのたとえに使う
すでに、「青二才」「若造」みたいな言葉は、もはやあんまり聞かなくなってきましたね。既にノスタルジックな響きさえも感じます。一方で、「年寄り」「年増」は未だ多少聞く気もします。僕は、なんとなく最近は「先輩」とかいうようにしたりしてます。そういえば、「耳年増」なんて言葉もありますが、この言葉こそ既に死語ですかね。
また、この本では「老害」もなくなっていく言葉として挙げられていますが、僕はむしろ残るのではないかと思います。このような消齢化社会において、古い考えを引きずって、押し付けようとする先輩達は一定数残る気がして、その人たちを表現するとしては消えないかもしれません。
2.年齢とライフステージを結びつける言葉
「お年頃」「婚期」「適齢期」などですね。かつて「女性はクリスマスケーキ」なんていう言葉もありましたが、今調べてみましたら「平均初婚年齢」が24歳台なのは昭和50年(1975年)で僕が生まれた年までなんですね。こういうのこそ、ほっといてくれてという感じで消えていくかと思います。
3.年齢で思考や行動、趣味嗜好を限定する言葉
「若づくり」「もう、〇歳」「いい年して」などでしょうか、比較的若い人よりも、年上の人に対し、批判的に使われる言葉が多い気がしますが、これからその年代に突入していく(もしくは、すでにそちら側)僕にとっては、無くなってくれるとありがたいです。上に同じくほっといてくれてという感じで消えていけばいいなぁと思います。
それでは、11月最終日もよろしくお願いします!
「消齢化社会」とダイバーシティ
おはようございます 渡辺です。今日から12月。12月に入った途端すごく寒いですね。(天気のせい?)
さて、「消齢化社会」5日目です。引き続き、ダイバーシティの観点から考えてみようと思います。
昔は、ビールのCMの女性というと、男性に向けて「お疲れさま」とエールを送る感じが多かった気がしますが、今年、25歳になった広瀬すずがプレモルのCMに起用されて話題になりましたが、今や女性がメインのCMも多いですね。これは、消齢化と共に消性化?男性でも女性でもビールを飲む人がいれば、飲む人もいないという中で、かつては男性をメインターゲットとおきフォーカスを当ててきたところから、光の当て方が変わって来た感もありますね。(実際には、もっと複雑なマーケット戦略がもちろんありそうですが)
そういう意味ですと、ゲームも年代や性別に関係なくなってきましたね。僕が小学生の頃は、ファミコンは男子で、女子でも男兄弟がいるこがちょっとやったことがある位でしたし、子供のやるものという感じでした。今や、特にswichなんかは正に老若男女に愛されているゲーム機になってるなと思います。
また、お酒の話になりますが、以前「日本酒好きクリエーター呑み会」というのに誘われて、参加したことがあったのですが、7割位は女性の参加者でした。そこで、「普段はどんな日本酒呑んでるんですか?」「アテは何が好きですか?」なんて話をしてたんですが、「職場では、日本酒が好きと言われると若干引かれるか、やたら飲まされるか、なのでニュートラルにこういう話が出来て嬉しい」といっていたのを思い出しました。そこらへん弊社は、割とニュートラルな感じもしますが、世の中ではマダマダ生きづらい会社もありそうですね。
という訳で、今週は消齢化ということについて考えてきましたが、性別や年齢によるステレオタイプな違いを決めつけるのでなく、ひとりひとりの価値観の多様性ということを柔軟に受け入れる必要性があるということを認識しました。何かの参考になれば幸いです。
それでは、師走突入ですね。今月もよろしくお願いいたします!
(2023.11.27-12.01)
サポート頂きました分は、他の方へのサポートに使わせて頂きたいと思います。サポートの輪が拡がっていくとよいですね。
