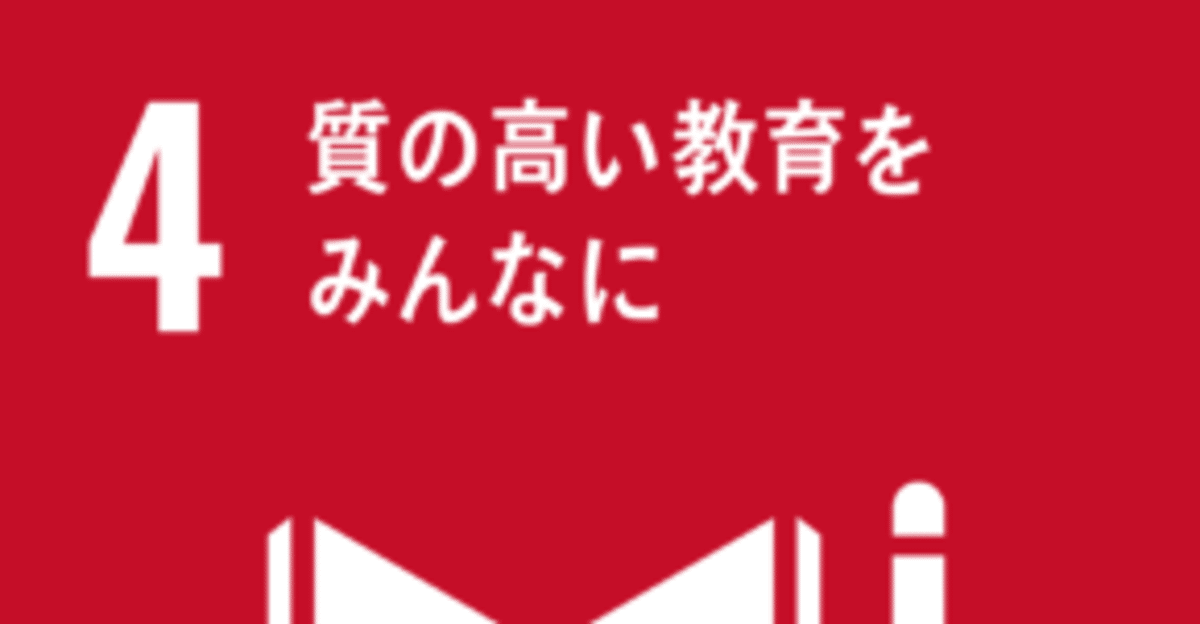
スマホは人類の救世主なのか?
毎日新聞のこの記事をまずはご覧頂きたい。
簡単に言えば学習効果を高めるためには読む、書く、聞くといういわゆる面倒な作業が必要で、簡単・楽に学べるというのは罠であるとのことだ。
人類が手にした最高のポケット知能スマートフォンだが実は人類を退行させているようだ。もちろん、昔から人類が発展すると必ずその反論があったものだ。記憶に新しいのはTVである。しかし、今更TVを悪者扱いする者はいない。毎日新聞の憎らしいところが同日の朝刊で台湾の天才大臣オードリータン氏も特集している。
オードリー氏は言わずと知れたこのコロナ状況下で世界がマスク不足に喘ぐ中、マスクを検索できるアプリを開発し国民全員に行き届かせたというまさにデジタルで世界を救える数少ない人間。オードリー氏の偉業の数々はこちらから
この時代を作る人間がスマホに対して否定的な発言をしている。普通に買えるのか、彼が独自で開発したのかわからないが、スマホと同じ機能を持つガラケーを愛用しているらしい。指でスワイプして使うスマホは知らず知らずのうちに自分を無駄な時間へと誘うのを警戒してのことらしい。デジタル分野を開拓する人間がここまでスマホというデバイスに否定的だと我々一般人にコントロールするのは不可能に思える。読者の多くも知らないうちに同じことを幾度も検索したり、面白い動画を意味なく見続けたりという経験はしたことがあるだろう。私ももちろん経験しており、人生最大の悩みとも言える。
しかし、学校現場ではスマホではないがタブレット端末の導入を積極的に進めている。タブレットは画面は大きくなったが実質的にはスマホと変わらない。
このような警笛が鳴らされる中、最近注目されているのはハイブリッド方式である。つまり、ざっくりした内容はタブレットで楽しく学び、そこから最も学習効果の高い紙とペンへと移行していくという流れである。
興味のないことを教科書、ドリルで学ぶのは本当に苦痛だし、モチベーションが上がらないのだから学習効果も上がらないのは当然である。だからこそ、スマホが持つ利点、触るだけで楽しい、学習が動的になるを生かし、興味関心が生まれたところで今度は紙とペンで予習、復習を繰り返し学習を定着させていく。
このように科学的根拠に裏付けられた学習態勢はすでに確立されている。あとはそれを指導する側の問題だ。
タブレット端末の導入率は高校でだいぶ改善はされたものの48%と約半数のようだ。そして、デジタルデバイスの使用を校内では強く禁止している例が目立つ。中学生ぐらいであればまだ判断がつきにくいが流石に高校生になったら自分の人生に自分で責任は持ってもらいたいものだ。つまり、ICTの危険性を理解し、自己判断で上手く付き合うスキルの獲得である。禁止ばかりを主張し、その理由を伝えない日本型教育の弊害とも言える。
私の知る生徒に自身の受験勉強の妨げになるとスマホもタブレットも全て売り払った者がいた。学校からの連絡は友達から聞く(本校では学校連絡に関して学内SNSを使っている)という徹底ぶりだ。まさに自分で考え、行動する力である。誰が何を言おうともこの世界からスマホを無くすことはできない。それであれば、科学的根拠を基本としたICTと紙の両立の必要性(技術が発展すればいずれは全てICTで賄えるのかもしれないが)を学校は伝えていくべきで、それが教育というものではないだろうか?
世界を旅するTraveler。でも、一番好きなのは日本、でも住みたいのはアメリカ・ユタ州。世界は広い、というよりも丸いを伝えたいと思っている。スナップシューターで物書き、そうありたい。趣味は早起き、仕事、読書。現在、学校教員・(NGO)DREAM STEPs顧問の2足の草鞋。
