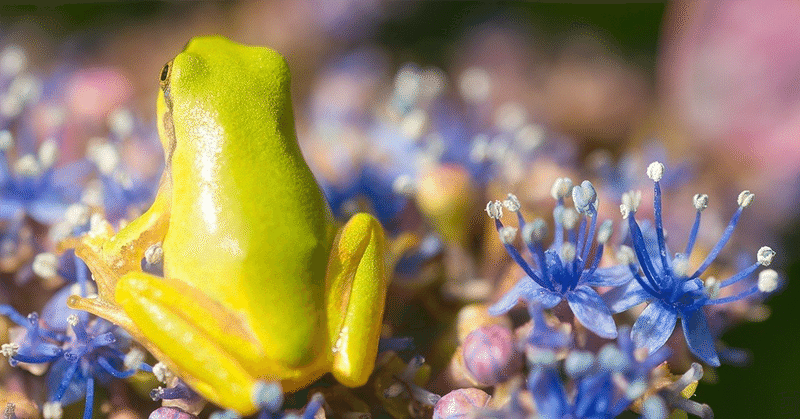
くだらなくて素晴らしい-しゃべれども しゃべれども-
3月の赤城亭以来、3ヶ月ぶりに落語に行った。
関西ではテレビ出演も多い桂雀々と、「笑点」や「タイガー&ドラゴン」でもおなじみの春風亭昇太の二人会ということで、今まで聴いた中では、もっともメジャーな噺家の高座と言える。
落語を趣味に持ち始めたのは、つい去年のことなので、東京に暮らす都合から、普段耳にするのは江戸落語が中心。
もともと出身が関西なので、聴きなれているのは上方落語のはずなのに、近頃はすっかり江戸前に馴染んで、上方を聴くのは随分久しぶりの気がした。
しかも、今回は桂雀々だ。
故桂枝雀の弟子である。
桂枝雀は、ツルツル頭の丸顔をして、汗をいっぱいかきながら、目を顔と同じくらいまんまるにしたり、漫画みたいにオーバーアクションしたり、観客を全身全霊で惹きこんでしまう噺家で、私にとっては、子どものころ、落語家と言ったら真っ先に浮かぶ人だった。
あるとき、彼は自殺によってこの世を去ってしまうのだが、あの愉快な笑顔の裏側に、天才の苦悩とも言うものがあったかと思うと、切ないような、寂しいような、愛おしいような気持ちになる。
先週末、ようやく「しゃべれども しゃべれども」を鑑賞したのだが、登場人物の一人である関西人の少年が枝雀の落語のDVDを観て、「なんや、これ!これも落語なんか!」と感嘆するシーンがある。
確かに、枝雀の落語は、一度観たら忘れられない印象的かつ独特なスタイルだ。
落語も色々聴き始めると、その人、その人の個性があって面白く、同じ演目をやっても、それぞれ違うことが分かってくる。
じっくり噺を聴かせる人、勢いとテンポで引っ張る人、渋みと深みで魅せる人。
枝雀の落語というのは、噺がどうこうというより雰囲気自体が面白い。
何をしゃべっているかはそれほど重要でなくて、その存在感が笑いを誘う。
大体、英語落語なんてものも、やっていたくらいだから。
弟子の雀々は、テレビで観かけたことは何度もあったものの、落語を聴くのは初めてだったが、気持ちいいほど枝雀を思い起こさせた。
この人、少々滑舌がよくなくて、噺の細かいところは聞きとれなかったりさえするのだが、けれど、キャラクターの演じ分けがものすごくうまい。
トリの「遺言」には恐れ入った。
次々登場する、ひたすらアホなキャラクターを、ひとつひとつ、一生懸命、丁寧に演じる。
そのどれもが活き活きとして、とにかく純粋に面白い。
声を上げて笑う。
おかしくて、おかしくて笑う。
もうなんというか、久々に、心底すかーっとした。
最近少し、頭の中でぐるぐるしていた事柄についても、「なーんだ」という気分になった。
人生、シリアスになったら負けやなあ、というか。
全部アホらしくて、全部お笑いみたいなもんやん、みたいな。
落語の世界の素晴らしいところは、果てしなき、このくだらなさだ。
あまりにくだらないこと、くだらない人物、くだらない機微が、研ぎ澄まされた芸によって表現される。
このくだらなさと真摯さの、絶妙のバランス。
「しゃべれども しゃべれども」はいい映画だった。
国分太一演じる主人公は、いまいちぱっとしない二ツ目の噺家だが、あるとき、頼まれて生徒3人の落語教室を開くことになる。
生徒は、美人だけどいつも仏頂面で愛想のない女、明るく元気だが転校先の東京で友だちが作れない関西弁の男の子、うまくしゃべれず解説が不得手な強面の元プロ野球選手と、個性的な面々。
主人公も含めて、彼らは皆、コミュニケーションに不器用で、うまく気持ちを伝えるのが苦手だ。
自分らしさを認められなくて、欠点ばかり気にしてしまう。
人間のかたちは色々だから、最初から型になどはまるはずないのに、がんじがらめの「理想」から、はみだした部分や欠けた部分を無理矢理に隠したり、歪めようとしてしまう。
怖がったり、怒ったり、うつむいたり、逃げたりする。
しゃべれども、しゃべれども、伝わらないもどかしさは、言葉が埋めるものじゃない。
何かを伝えるのに必要なのは、もっと、別の何かだろう。
くだらないこと。
でも、素晴らしいこと。
ちょっとした素直さ、ちょっとした勇気、ちょっとした笑顔、ちょっとしたきっかけ。
誰かを好きになったり、自分を好きになったり。
何をしゃべっているかはそれほど重要でなくて、その存在感が笑いを誘う。
そういうものの大切さを、なんだかようやく、思い出せた気がする。
しゃべれども しゃべれども(2007年・日)
監督:平山秀幸
出演:国分太一、香里奈、森永悠希他
■2008/6/1投稿の記事
昔のブログの記事を少しずつお引越ししてきます
サポートをいただけるご厚意に感謝します!
