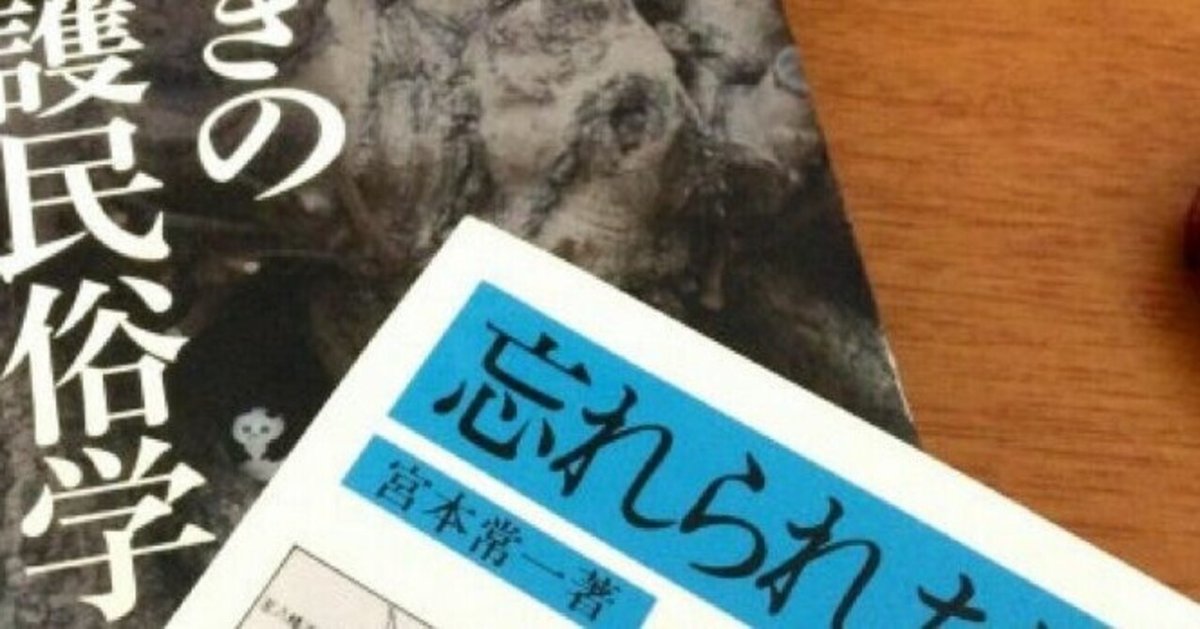
驚きの介護人類学(書評)
老人ホームで出会った「忘れられた日本人」
<一言紹介>
①民俗学者的な手法によって、いかに介護現場におけるコミュニケーションが豊かになるかの発見のレポート(思い出の記しを代表とする)
②それに対する民俗学者としての感動とそれを軸にした問題提起。
介護現場は民俗学的知見の宝庫。
ありそうでなかった、社会構造を支える価値観を揺るがすくらいの力がある切り口。平易で読みやすい文体も見事。正直”神本”ただし…(!)
<印象的な引用><こんな文章>
“そう考えた時に「人を騙す狐」の物語世界を生きる老夫婦と、「殺せ」とやってくる子供たちの存在を感じるまさ子さんや、死者の声が聞こえる美智子さんとの間には決定的な違いなどあるのだろうかと思えてくる。一方は、昔話の語り部であり、民俗学の対象となり、一方は認知症の高齢者であり、治療の対象になると分ける根拠も曖昧になって来ないだろうか?”(p140)
“民俗学では、老人と子供も神に近い存在として説明される。つまり、生まれて間もない子供と死を間近に控えた老人は、世俗にまみれた此の世の両端に生きる存在であり、したがって両者ともあの世に近い(…)神に近い存在である老人と子供であるからこそ、世俗的な説明など必要とせずに、語られる物語世界をそのまま受け入れることができるのである。”(同)
<書いたのはどんな人?>
六車/由実さん
介護職員、社会福祉士であり、日本の民俗学者。
1970年、静岡県生まれ。大阪大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。
民俗学専攻。
地方大学で准教授のポストを経たのち、”訳あって”大学の職を辞し、介護の分野に転身。
静岡県東部地区の特別養護老人ホーム内デイサービスに介護職員として勤務時本書「驚きの介護民俗学」が書かれた。
現在は沼津にて、小規模デイサービス施設「すまいるホーム」の管理者。
本書で課題であった時間面の融通が、理解のある経営者に支えられて解消され、最大限介護民俗学の本領が発揮されたのが次作『介護民俗学へようこそ「すまいるホーム」の物語』(’15)
ちなみに
2003年サントリー学芸賞受賞の『神、人を喰う―人身御供の民俗学』(新曜社)は未読だが、人身御供の民間伝承の本、大変面白そう。
当時の選評では大阪大学の哲学科の教授鷲田清一氏が六車氏を新進気鋭の民俗学者として紹介している。
<この本の対象と目的、骨組み>この本は誰に向けて≒どんな目的で書いたか?
本書はあるテーマにおける民俗儀礼のまとめ本(『神、人を喰う―人身御供の民俗学』のような)でもないし、
あるローカルな土地における風俗の学問的考察でもない。(老人ホームが沼津にあるようなので、若干その要素はなくはない)
この本の魅力のひとつは確かに聞き書きによって得られるカラフルな民俗学的事例ではあるが、本書の狙いは学問的な整理というより社会に対するある問題提起にある。少なくともそう言う体裁をとっている。
そういう受け取り方でいいと思うし、自然に読めばそうなると思う。
本書が看護師のためのウェブマガジン「かんかん!」に連載された文章の書籍化であることからもうかがえるだろう。
ただ、そう考えると「読み」に関して注意しなければならない点が一つ出てくるように思われる。どういうことか?
一言で言うと
利用者に寄り添ったユートピア的な空間における特別な「お仕事物語」と受け取られてしまえば、それで消費されて終わってしまうということだ。
以下補助線を引いていきたい。
読み飛ばしていただいて構わない。
<自分の読み>
タイトルにある”介護民俗学”が、著者の造語であり、提案である。
“「介護民俗学」などという分野があったわけではないし、ましてやそんな言葉だってなかった。民俗学にとって、介護の現場は関心の外だったのである”(p5)
そして
本書の魅力的な点は”民俗学と介護の出会い”それ自体であり
それが著者の身体を通した「驚き」によって行われているということ。
つまり「価値の転換」の”瑞々しさ”である。
一方
「介護民俗学」という議論は
もし論理的に考えれば以下の三点に集約されると思う。
①まずそもそも「介護民俗学」とは何か?>その本質
②次に、「介護民俗学」は有効か?>それはどのようにか?
③現実的にそれは可能かどうか?という話
つまり
介護側から読めば「介護民俗学」は要するに、
介護現場で通常コミュニケーションの難しいと思われる特老や認知症のデイサービスのような場所においての利用者とのコミュニケーションの量と質の改善の提言で
その手法に民俗学の手法を応用できるのではないかということだ。
で、この本の注意点は、この本に対するむしろ好意的な評価の仕方にある。
「介護民俗学」は上記の実践的な切り口ではあくまでアイデア=問題提起に留まっており、特殊な技能と環境を必要とする、やはりレアケースであるのは確かである。
だから
もちろん著者の”介護に対する真摯な態度”は一個人として大変素晴らしい方だと思うし、
次作「すまいるホーム」の”和気藹々とした雰囲気の心地よさ”や
”介助者と介助を受ける人も、お互いを人間として尊重している様子”に感動するのは、全く悪いことではない。
しかし、それは介護民俗学のあくまで果実の部分であり
介護”サービス”という業態の論理に対し、情緒的な話を無警戒に持ち込んでしまうことで、もっともであるが、つまらない批判を呼び込んでしまう可能性がある。
例えば
ネットに散見される
“こんな1時間も2時間も話を聞くだけの時間を取ることは、昨今の介護業界では無理に等しい”とか
”やたらと話を聞きに来る介護職員よりも、効率よく的確に介護を行う介護職員のほうに介護してもらいたい”とか言った批判である。
つまり新しい価値観や社会観を提示する大きな本であるがゆえに
既存の価値観に還元されてしまえば、瑕疵だらけの単なる理想論やお仕事物語
と取られてしまう。
本書の意義を最大限に引き出すには(つまり感動するにはと言い換えても良いが)
既存の価値観の延長で評価(還元)することに慎重であったほうがいいと思う。
例えば
介護職員がたくさんお話聞こう…!となることが、この本のゴールならば良いが
それだけではないはずだ。
著者自身が指摘するように、介護の現場文化が変わらなければ
コミュニケーションのための十分なゆとりを確保することは難しい。
ましてや民俗学専攻の学生を介護現場に誘導することはさらに困難だろう。
補足の結論のようなもの
これは決して
限られたユートピアにおける、利用者に寄り添った「お仕事物語」ではなく
民俗学的な感動が介護現場で得られるという大きな可能性の発見であり
そのコミュニケーションの源流は柳田邦夫であり、レヴィ=ストロースである。
生れる・病む・死ぬことは人間の根本存在にそもそも含まれていて
弱いメンバーとの共生は人間が社会的動物である限り避けられない。
しかし、優れたコミュニケーションをする余地がある。
それが文化の価値である。
構造主義の考え方をこの文脈で超訳すればこういうことになる。
古代の、あるいは現代でも文明の浸透していない(未開)民俗の
古老や長老の扱いに学ぶ点は多いかもしれない。
太古の狩猟採集生活を営む「ハッザ」の人々の社会には「うつ病」が無縁であることが最新の研究結果でわかっている。
狩猟に参加できない長寿の女性でも分け前がもらえるが、その女性はそれを当然のこととして受け止めている。その尊厳には揺るぎないものがある。なぜか?
“そこで、改めて介護現場での聞き書きにおける関係性をターミナルケアと関連づけて考えてみると、こう言えるだろう。介護の現場での聞き書きは、心身機能が低下し常に死を身近に感じている利用者にとって、一時的にではあるが、弱っていく自分を忘れられて職員との関係が逆転する、そんな関係の場なのであると。それは、同じように利用者の話を聞く臨床心理士によるカウンセリングとも、社会福祉士による相談援助とも異なる関係性である(…)。(p168 語りの森へ)”
社会的な課題にはいろんなアプローチがある。技術革新、経済援助などなど。
そして根本的な課題を考えるときに結局”教育でしょ”論法がある。
それは言い換えれば
「知識と技術の工夫によって”次の世代が”問題を比較的容易に解決する」という考えだ。
大人の変化は難しいという前提から、それはだいたい子供へ向かう。
しかし大人が大人に再生産し続ける介護現場こそ、現代の暗黒大陸なのではないか?
そして介護の主体は誰なのか?大人である自分を含んだ現在の社会だ。
そして介護する相手は?間違いなく未来の自分の姿である。
簡単に言えばこれは貴方が介護が必要な立場になった時
どういう構えで扱われたいか?という話でもある。
AIの方がよほど人間らしい…となってしまったら
ある意味楽になるのかもしれないし、そういう議論もあるけれども。
<介護民俗学の要約>
という補助線を引いた上で、介護民俗学の理論的な部分と呼ぶべき項が
第4章「語りの森へ」にまとまっているので、この章を中心に
簡単に要約して書評のまとめとしたい。
この章は、現行の介護現場の価値観と、それによっている「回想法」への批判を民俗学的調査における価値観を軸に展開している。
具体的には以下の二点について
①そもそも”高齢者は評価される対象なのか?(p148)”
②”テーマから外れてはいけない?(p145)”
「講座日本の民俗学11 民俗学案内」から民俗学者の言葉を引用しながら
著者の考えを述べている。
“一方的に贈与を受け続ける調査者とは、乞食に他ならない。情報の贈与者は被贈与者に対して無報酬の贈与を行い続けているのであり、被贈与者は常に社会的劣位に置かれ続ける存在となるのである「講座日本の民俗学11 民俗学案内」新谷尚紀(p154)”
“「(…)しかし、予定していた質問が計画通りに進むことはまずない。それは話者の答えが、話者自身の関心によっておのずからひとつの流れを作りつつ展開されるからである。私は、話者の語りの流れをさえぎることは、極力避けている。こちらの計画的な質問に対する答え以外の部分で、こちらが気づかなかった重要な問題が語られることが多いからである。「講座日本の民俗学11 民俗学案内」野本常一(p98)”
これらの引用に著者の思想は集約されている言っても過言ではないだろう。
さて個別に見ていきたい。
①高齢者は評価される対象なのか?について
正直これは社会に広く存在する根深い問題である。
つまり“客観的な評価を点数で示せ”ということの必要性と限界という文脈だ。
主語を変えれば子供の教育にも通じるし、
卑近な例で言えば鍼灸整骨院の医療保険問題にも通じる。
また回想法はリバビリテーションの一つの手法として位置付けられている。
つまりその思想は”自立生活(IL)”や”ノーマライゼーション”の基本理念に準拠している。だから、これはその手法の理念からの反省という文脈でもある。
ここでは風呂敷を広げすぎないために、本文に戻るが
著者は介護における、助ける側と助けられる側という非対称的な関係で成り立つ行為を批判して、民俗学的な関係性を持ち込む意義があるとしている。
“だから、聞き書きの場では、アカデミックな知識はあっても、実際の経験やそれに基づく民俗的知識を持っていない調査者と、それらを豊富に身につけていて、それについての記憶を語ってくれる高齢の話者(かつて民俗学者の多くが話者のことを古老と読んでいたことも関係するか)との関係は、話者が調査者に対して圧倒的な優位にあるといるだろう。(…)調査者は、まさに話者に教えを受ける。それが聞き書きなのである。”
と締めくくり、そうした聞き書きの成果を続く章で述べている。
②”テーマから外れてはいけない?(p145)”について
さて、これが多分多くの読者の引っかかるポイントではないかと読んでいて思った。
一見どちらでも良い瑣末なことかもしれない。となれば、
余裕を持ってる人がカネを払って受ければいいオプションサービスなのではないか?
しかし注意深く考えると、非常に大きな問題をはらんでいる。
著者は以下のようなエピソードを通じて疑問を呈している
“ある施設の職員から「回想法」を行うといつもいつの間にか話がテーマから逸れていってしまうのですが、どうすればいいでしょうか?という質問が出された。
”それに対して私は自分の経験から「テーマから外れたところで興味深い話が聞けることもあるので良いのではないか」と発言した。ところが間髪入れずに「それはダメです。テーマから逸れたら、なるべく話をテーマに沿うように戻しましょう」と講師から指導が入った。(p146)”
著者は以下のように述べている。
“たしかに、同世代や共通体験を持つ人々が集まって話をすることは共感しやすく(…)しかし、テーマの枠外に逸脱するのを否とされることによるストレスは大きいだろうし、またさらに言えば、メンバー同士の深い関係性が築かれていなければ、本当のところ互いに胸襟を開いて話をすることはないだろう”
それには著者の野本常一氏の言葉の引用が示すとおり、
民俗学的コミュニケーションの作法が念頭にあるだろう。
その上で
“こうした問題は一対一で行う個人回想法によって解決されるように思われるしかし、現場では個人回想法を導入することに消極的だし、たとえ導入したとしても慎重に行うことが求められ、個人的な事情をあまり深追いしてはいけないとされている。”
“その理由を講師は深追いすることで、対象者が動揺したり不穏になったりする危険性が高いからだと説明し、そのあたりは精神科医やカウンセラーなどの専門家に任せれば良いと言い切った(…)身近に接している介護士に対してだからこそ利用者が話せること、話したいことがもあるだろうと私は思うのだが”
著者の言いたいことに自分は非常に共感する。が同時に著者側にここでもう一歩踏ん張って欲しいと思う。
なぜなら、講師にも一見、一理あるからだ。
つまりこれは介護士の専門家化を明らかに示唆しており、
言い換えれば、全国の教師にカウンセラーになれと言っているようなものである。
「理想とかけ離れちゃってるじゃないですか」と素朴に批判しているようにも見える。
前にも触れたが、ネットにはそういう批判が散見された。
介護業界の闇については改めて勉強しておきたいが、
図式的に考えれば、
介護士のフットワークの軽さは、その教育期間の身近さからきている可能性がある。
増え続ける高齢者に対し
微妙なコミュニケーションの技法を持った介護士を一人一人用意することは果たして可能なのだろうか?
(逆に、個人のコミュ力に全て依存していいのか?)
絶望的に見えなくもない。
で、その問題の渦こそ、大きな社会構造を変革すべきモチーフがあると自分は思うし、これをどう捌くか、著者の今後の仕事に目が離せないところである。
著者は終章でこう述べている。
“上野(千鶴子)は、「ケアワーカーの賃金はなぜやすいのか」という問いのもと、低賃金の背景には、介護報酬を低く抑える政府と、労働者の賃金をあげようとしない事業者の存在があるが、それを許しているのは、つまるところ、ケアワークの社会的評価をその程度に低くみているという国民の意識があることを指摘している。「自分は受けたいが、やりたくない労働」というのがケアワークの実態から浮かび上がってくる本音であると上野は辛辣に批判する(p224)”
このことは問題のすべてを説明しているとは言えないが、本質は突いているだろうと思う。
著者は続ける。
“それでもあえて、「介護民俗学」の可能性を訴えたい。(…)民族調査で鍛えられてきた彼ら(学生)が介護現場でやれることは多い”
“しかし、学生たちを介護現場に誘導するには、職場環境があまりに過酷であるという現実はある。やりがいと充実感はあるが、それに対する賃金と社会的評価があまりに低い。”
“それによって、介護施設の職員の離職率は高く、現場は常に人手不足である。すると、高い理想を持って、働いている介護職員たちも、日々「食事・排泄・入浴」という三大介護に手一杯になり、疲弊してくる。これが現状である(p224)”
著者はそれに対し
⑴「介護民俗学」を掲げて高齢者介護施設での活動をして、人々の理解を得る
⑵介護現場が社会へもっと広かれていく必要がある
と述べていてる。
⑴は当然実現できるとして
⑵は正直かなり根深い問題かもしれない。
ここでは深く追求しないが、日本は過剰に保護をする社会だからだ。
“聞いた内容を残さない、傾聴ボランティアは広く受け入れられているが、個人情報保護や、家族からのクレーム、さらに感染症予防等への配慮から、施設は利用者を過剰なまでに保護しているため、彼らが研究者の調査やマスコミからの取材を受けることについては消極的だからである(p225)”
だが、これはもしかすると驚くほど簡単に解決する可能性もある。
つまり、介護される人自身が
”要介護状態になる前に、介護されるための物理的・精神的準備をしておく”
のだ。
“それは、家族の意向に傾きがちな現在の介護施設の状況を、本来の利用者本位に引き戻すことになる”
それなら、事前に個人情報に対する意思を表明することもできるし、
また、
“在宅介護にしろ、施設介護にしろ、ケアマネージャーにより介護サービスのアセスメントが行われるが(…)家族構成や、既往歴やADLに関するものであり、その人となりを知るための生活歴や人生歴などの情報は極端に少ない”
“しかし、介護準備という文脈では、むしろ高齢者本人が、自分が介護される状態になるのに向けた準備として、自分の歩んできた人生を文章にまとめておくことを勧めたい”
それは著者自身が述べるように、いま流行りの自分史日記の延長にあり
非常に簡単に取り組めることであり、自然な行為でありながら、
工夫ひとつで介護現場におけるコミュニケーションの可能性を著しく広げるだろう。まさに慧眼である。
著者の聞き書きのケースの引用も考えたが、長くなりすぎるので端折ることにした。
それはぜひ本を手にとって読んでもらいたいと思う。
特に「幻覚と昔話」(p130)で死者の声が聞こえる渡辺美智子さんの語る身体の喪失の物語(右手を失った)は圧巻でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
