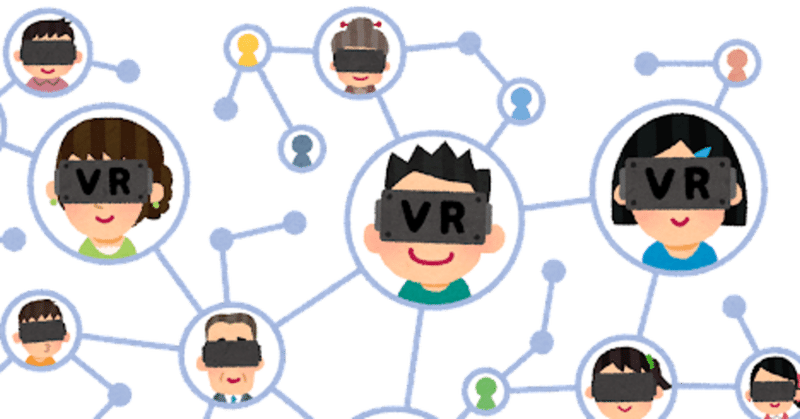
「生活用品オール付喪神(つくもがみ)化計画」と「世界カスタマイズフィルター」 #XR創作大賞
ふとしたことで XR創作大賞 という、XR(VR=Virtual RealityやAR=Augmented Reality:拡張現実、といった技術の総称)の未来像の提案が募集されていることを知りました。
●作品の完成度は問わず、XRのミライが見えるもの
・ラフ、ネームやプロットレベルのものでも、XRのミライが把握できればOK
・「辛い現実から逃れるXR」はお腹いっぱいなので対象外
僕自身、20年近くゲームエンジニアとして働いてきた中で、VRやAR案件に携わったことも何度かあります。個人的にもとても興味がある分野です。そんな身としては応募要項にあった上記のコンセプトはとても興味深く、同意できるものです。
そこで、XRのミライに繋がる一助にでもなればと思い、2つほど案を考えてみました。それらを以下に記します。
案1:生活用品オール付喪神(つくもがみ)化計画
【コンセプト】
「長く使っていたモノには付喪神(つくもがみ)が宿る」という日本古来からの逸話があります。これをXRにより「逆説的に」現代に具現化します。
「モノを大事に使っていたから付喪神が宿る」ではなく、「モノの情報からXRで具現化させた付喪神キャラの親近感や愛おしさが故に、モノを大事にする」と視点を転換するのです。
これにより、モノを大切にする教育効果を生み出し、ゴミの削減や有限資源の節約、ひいては資源循環型の永続的社会の構築へ寄与することを目指します。
【具現化】
●XRデバイスとしては、現実世界を見通す必要があることから、パススルー機能を持ったVRデバイスやAR機能を持ったゴーグル/スマホを想定。
●電化製品などIoT技術によるデバイスを仕込めるものからは、そこから使用履歴などの情報を取得。
●ペンやハサミなどの道具については、外観の画像解析により経年劣化や欠け/変形を読み取り、使用状況を類推。あるいは薄型ICタグを貼るなどして位置や移動情報を取得。
上記のようにして得た「モノにまつわる情報」を元に、「そのモノの付喪神」をキャラクターとしてXRデバイス上に具現化。この付喪神達は自分で呟いたり、ある程度のインタラクションは可能。
※1999年発売のゲーム『シーマン』のような、シンプルだが「独立した個」を感じさせるAIを備えているイメージ。
例)
・あちこちに置き忘れられるペンから具現化した妖精的なキャラが
「ちょっと、もー。アタシをいつも見つけやすいようにしといてよね」
とボヤく。
・オーブントースターレンジから具現化したおばあちゃんキャラが、いつも同じ操作ばかりの稼働履歴を見て「最近、同じような料理ばかりだけど、栄養バランス大丈夫かい?」と優しく気を遣ってくれる。
案2:世界カスタマイズフィルター
【コンセプト】
世界の感じ方は人それぞれです。同じ色、形、音、などを見たり触ったり聴いたりしても、それが心地良いかそうでないかは人それぞれの感覚や、同じ人でも気分などによって異なります。逆に言えば、僕ら人間は自らの五感を通じて得た情報から「自分がその時に感じている世界」のイメージを個々の脳内に構築しているわけです。つまり、僕らの脳こそが最も高性能かつ身近なVRデバイスであるとも言えます。
そう考えれば、現実世界とは決して固定で動かしがたいものではありません。僕らがより心地よく、より活動しやすいように「カスタマイズ」や「チューニング」が可能です。XR技術はそれを現実のものにしてくれます。
【具現化】
●XRデバイスとしては、現実世界を見通す必要や没入感を要することから、パススルー機能を持ったVRデバイスを想定。
※AR機能を持ったゴーグル/スマホでも一部実現は可能。
●目が疲れている時は、まぶしい光や街の装飾が煩わしい。iPhoneにモノクロ表示モードがあるように、視界全体をモノクロ調にすれば目に優しい。
●どうしても人前で緊張してしまうのであれば、顔認識で検出した顔をジャガイモにでも変換してしまおう。人前でも本来の実力が発揮できます。
●見たい/聞きたいものがあっても、世に溢れるモノや音が多すぎるこの社会ではなかなか見つけにくい。そこで、世界から自分に届くものを「調整」する。
・普段はXRデバイス付属ヘッドフォンのノイズキャンセラーにより静かな世界。しかし、自分の好きな話題を示すワード、お気に入りのジャンルの音楽、そういったものをヘッドフォンが感知した場合だけ自分の耳に聞こえる。
・視野の方では、普段は目に優しいモノクロの世界。しかし、事前に登録した興味あるもの/見つけたいモノや人だけがカラーで見える。
※もちろん、聴覚/視覚を連動させればより「自分の興味向けにフィルタリングやチューニングを施した世界」で活動できる。
【おわりに】
即興で考えてみたアイデアではありますが、これで応募してみます。
発表当日、受賞作のアイデアはどんなものが集まっているのでしょうか?
楽しみに待ちたいと思います(^^)
好き勝手なことを気ままに書いてるだけですが、頂いたサポートは何かしら世に対するアウトプットに変えて、「恩送り」の精神で社会に還流させて頂こうと思っています。
