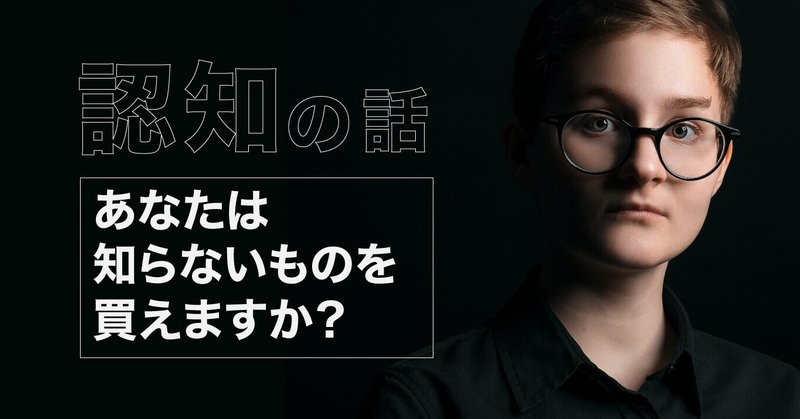
"私たちは見たことがあるものを無意識に買ってしまう"マーケティングにおける認知の正体と全体像
あなたは知らない商品を買えますか?
「買わない」という方が大半だと思います。
なぜなら知らないことは「恐怖」だからです。
一度も見たことや聞いたことがないものを買うのはあまりないのではないでしょうか。
これはBtoB、BtoC関係なく、
知っているということはすなわち信頼であるということがいえるからです。
名前を知っているだけで
商品がどのようにできているのか知らなくても、
セールスマンの本当の性格がわからなくても、
なぜか信頼してしまっているのです。
このようにマーケティングにおいて認知は非常に重要な要素であり、ビジネスにマーケティングの活用を検討されているのであれば認知の全体像を知っていて損はないはずです。
最後の方に具体的なハウツーを載せていますので、具体策だけ知りたい方は目次から飛んでください。
認知が重要な理由
そもそもなぜマーケティングを考える上で認知が外せない要素になっているのでしょうか。多くのマーケターの教科書であるとされている名著『売れるもマーケ 当たるもマーケ―マーケティング22の法則』の中でアル・ライズとジャック・トラウトは以下のように述べています。
マーケティングの世界に存在するのは、ただ、酷悪や見込み客の心の中にある知覚だけである。知覚こそ現実であり、その他のものは全て幻である。
引用:売れるもマーケ 当たるもマーケ―マーケティング22の法則
言い換えると、マーケティングとは顧客の頭の中の戦いであり、顧客の頭の中という陣地を支配したブランドが有利に戦うことができるということができます。(ここではマーケティングの定義という観点には踏み込まず考え方の一つでとして紹介いたします)
つまり、マーケティングという顧客の頭の中の戦いにおいて、頭の中の陣地の第一段階である認知は非常に重要であるといえます。(認知の段階については後述)
認知がないものは買われない
日頃買い物をするときのことを思い出すとわかりやすいと思うのですが、まずは知っているブランドが第一選択肢に入り、その後値段や機能などを検討したのち購入に至る流れがあります。まずは知られているか、目に入るかがそもそもの勝負で顧客になり得る人の頭の中に入ることのできない商品やサービスは多くの場合購買の機会すらありません。
商品やサービスを好きになってもらう、リピートしてもらうことに重点を置く施策も重要ですが、売り上げを伸ばすことのできる余白としてそもそもの認知度をあげる必要性がある場合は非常に多いと考えています。
USJをV字回復させたことで有名な森岡氏も著書の中で以下のように述べています。
認知率の伸びに対してビジネスはあるレベルまでは直線的な関係で伸長していきます。
引用:確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力
特に中小企業やスモールビジネスなどはまず知ってもらう認知を獲得していくだけで単純な売上の増加が見込めることが多いと思われます。(実際の施策フローでは認知拡大施策の前に商品・サービスの質の向上や広告流入先の改善などを行う場合が多いです。)
認知と購買までのハードル
ここで注意しなければならないのは認知はあくまでの購買までのプロセスや手段の1つであり、認知を取ることは目的ではないということです。
購買には商品カテゴリーごとのハードルがあります。ハードルの高さは一般的には金額に比例し、高額な商品であるほど強い認知(商品への理解)を必要とし、安価な商品であるほど弱い認知で事足りる場合が多くなります。
家や車など高額な商品は事前の調査や打ち合わせなど増える傾向にある一方で、ランチや洗剤などの消費財は目に入ったなどの一瞬の認知で購買までのハードルを乗り越えることができます。
厳密には異なるのですが、『ブランディングの科学』バイロン・シャープ氏のフィジカルアベイラビリティーの話が近いかと思います。そこではここで短い時間での認知ではなく、物理的に購買可能であるか、また購買可能であるとした際の接触の質について触れられています。
認知には順番がある
息抜きも兼ねて質問です。
「ランチで使うお店を思いつく限り教えてください」
いくつ思いつきましたか?おそらく3つ程度、多くても7つほどではないでしょうか?人は物やサービスを思い返す際、脳内での順位づけが自動的に行われます。とにかく大切なことは思い出してもらえるブランドの1つに入り込んでいることです。
ここで思い出してもらえるブランドの1つ、最低1/7に入っていないと購入される可能性はほぼゼロになります。正確にはたまたま通りがかって見たとか目的のものを購入できなかったから仕方なくなど購入してもらえる可能性はありますが、運による要素が大きくなります。
認知の1位になる重要性
さらには1/7に入るだけでは充分ではありません。認知の1位になれるかどうかは売上に大きく影響してきます。
「日本で1番大きい山を教えてください」こう聞かれたらもちろん富士山であると答えるはずです。では、「日本で2番目に大きい山を教えてください」という質問に答えられますか?正解は北岳です。
実際の調査の数値では富士山の認知率は北岳の認知率と比べ4倍以上の数値を出していました。実際の購買場面でも最初に思いついた候補がよほど不都合が出ない限り、2番目や3番目の候補に負けることはないのではないでしょうか。
「認知の1位になることが大切そうなのはわかったけど、実際大手が認知の上位を占めてるしそんなの無理じゃないのか?」こんな疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思いますので、次の項ではその対処法についてお話します。
認知にはジャンルがある -1位になる方法-
1位になれなかった場合は違うジャンルの1位を目指すことで新たな立ち位置の獲得を狙うことができます。
PCというジャンルで1位を取れなかったのであれば、より高機能なPCを製造し勝負しにいくのではなくノートPCなどジャンルを切り分けそこでの1位を狙っていくべきということになります。
ポイントは顧客の頭の中のイメージで実際のシェアなどは関係ないことです。つまり、見込み客その人にとっての1位であれば良いということです。
ランチでよく使う行きつけの中華料理屋さんがあったとして、そこのお店は売上シェアNo.1もしくは食べログ評価No.1のお店でしょうか?
おそらくそのどちらでもないはずです。ただオーナーの人柄や接触回数の多さ、立地条件などでその人独自のNo.1になっているから利用されているのです。つまり、見込み客独自の基準においてNo.1かどうかが重要なのです。
また1位になることに固執するあまり無意味な差別化を繰り返しそもそも需要がないところで戦わないようにすることも大切です。また詳細は別の記事を予定していますが、売上の計算を行う際に用いる数式は掛け算が基本であり、売上が最大になる掛け合わせを見つけることが重要です。簡単に説明すると買ってくれるお客さん
狙うべきジャンルはどこ??
認知の1位になる必要性と、1位のなり方がわかったところで具体的な部分に入っていきます。実際に以上のことを実務で使用しようとした場合問題になるのが「どのジャンルを狙えばいいの?」ということになります。わかっていてもわかりにくい...ここが企画者の腕の見せ所です。
ここで基本になる考え方がCEP(Category Entry Point)になります。現実の購買行動に即した場合、「ビールはいくつ思いつく?」「ランチはいくつ思いつく?」などの質問により商品・サービスは想起されません。
「なんかスッキリしたいな」「お腹すいたなぁ」「とりあえずスーパーにいってみよう」などより曖昧な無意識に近い領域で選択の判断は進んでいます。この実際の購買行動の動線になりうる共通の想起(CEP)を認識させられるよう意識すべきです。
CEPを検討する上で重要なポイントは以下の3点です。
1.購買に近いこと
2.No.1になれること(顧客の頭の中独自のNo.1)
3.認知の質と量を確保できること
ここまでBtoCジャンルでのお話でしたが、BtoBにおいても中小企業などにおいては同じCEPの考え方は通用すると考えております。スモールビジネスの初期などに多い紹介や口コミなどはまさに小さい範囲でかつ購買に近いCEPで1位を取れている証拠です。
業界全体と比較してどんなに小さな会社であっても個人としてのつながりや、直接の説明の機会を得ることは広告などよりも強い独自の認知を獲得することができるからです。会食やゴルフで仕事が決まるのは話す相手が決済者であり(購買に近い)、独自のNo.1になり、対面で充分な話す時間を確保(認知の質と量)できるからです。
WEB広告、特にFacebook・Instagram広告では細かいターゲティングも可能であることから上記条件を満たすクリエイティブの作成もしやすい傾向にあります。このあたりはブランディングとも大きく関係してくるので別記事で紹介させていただけたらと思います。
まとめ
マーケティングにおいて認知は重要な要素の一つです。それはマーケティングには顧客の頭の中の認知の取り合いという側面があるからです。そして意味のある認知を取るためにはジャンルごとの1位になる必要があると考えています。CEPを基準に選定し条件を満たすジャンルを選定することは認知を売り上げに活かすためにより有効になります。
長々と書いて参りましたが、拙い文章のため読みにくい箇所や説明が足りずわかりにくい箇所などあったかもしれません。ただその中でももし誰かのお役に少しでも立つことができたり、何かのきっかけになっていただけたのであればこれ以上に嬉しいことはありません。また色々なご意見あるかもしれませんが、よりお役に立てるようアップデートしていくことが一番だと考えておりますので、ご感想やご意見などございましたらお教えください。
ご質問や不明点なども以下の連絡先までDMお待ちしております。
私でお役に立てることがございましたら、無料相談も実施しておりますのでお申し込みの方は以下サイトのフォームよりご連絡ください!
WHAT 山本
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
