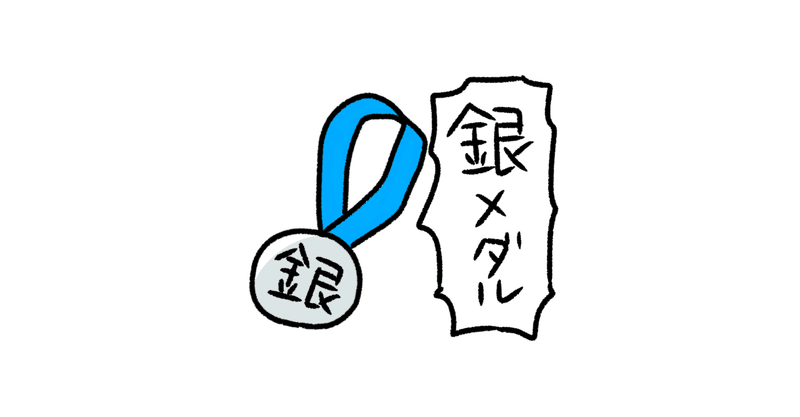
柔道団体戦を見ながら、ふたつのナショナリズムについて考えた。
サッカーやラグビーのワールドカップでも、五輪でも、心のなかのナショナリズムについて、ふたつの感情を呼び起こします。それをあぶり出します。
日本のチームや日本人を応援する気持ちは、これは自然に心のなかに、沸き上がってきます。
ここまでは特に目くじらを立てることはないと思います。
しかし、この先に、ふたつの異なる反応が起きます。対戦する相手、外国チーム、外国人選手への態度です。
スポーツ、競技は相手がないとできません。スポーツを成立させる大切な仲間です。相手を尊敬し尊重しつつ戦うことが、スポーツには求められます。闘争心を燃やしつつ、相手を尊重する。難しいことですが、絶対に必要なことです。
僕が柔道やラグビーが好きなのは、相手の身体に直接的に攻撃をしかける競技であるからこそ、相手を尊重することを常に心の中に置いておくように、自分の心を鍛えるように、競技文化が成り立っているからです。ルールもそれを常に選手にもとめるようにできています。
競技者がそのようにあろうと努力し競い合っているのですから、応援する側も、「日本人の柔道は素晴らしい。外国人のは柔道ではなく力まかせのJUDOだ」などと外国人の柔道をけなし、敵がい心を燃やすのはやめて欲しいなあと常々思います。そもそもそんなのは分かっていない人のこねあげた嘘っぱちです。柔道が国際化し、多様化しても、この中で柔道の本質は受け継がれ、進化しているのです。例えば、背負い投げの理想的な美しい技を、重量級で体現し、背負い投げ復権のトレンドを作ってくれたのは、ポルトガルのフォンセカ、ウクライナのハンモら外国選手たちです。
ラグビーワールドカップでも、グループリーグ最終スコットランド戦、ラグビー人気が、急激に盛り上がったのはよかったのですが、報道もスコットランド首脳の発言を敵がい心を煽るように取り上げ、スタジアムに集まった観客の雰囲気も、それまでの試合とは異なり「ラグビーを楽しむ。相手サポーターとも和気あいあいと交流する」というアイルランド戦のときの雰囲気から一変し、サッカーの偏狭で敵対的なフーリガン的サポーター的な「ニッポンニッポン」と騒ぎたい人の比率が増えて、なんとなく、いや、はっきりといやな雰囲気でした。(2試合とも、会場で観戦しています。アイルランド戦が静岡という遠方までわざわさいくラグビーファンが多かったのに対し、スコットランド戦が横浜国際で、普通の人たちが多かったのかもしれませんが。)
私は後半スコットランドを応援しながら(だって、本当に素晴らしいプレーと気迫を、見せていたから)、スコットランドがんばれと拍手声援を送りながら観戦していました。日本は引き分けでも勝ち上がりは、決まっていたのだし。
今回の五輪柔道、大野将平の態度はすごく立派でした。個人戦優勝の後も、自らは畳の上では喜びを爆発されることもなく、インタビューでの発言も完璧でした。社会や、取り巻く環境、応援してくれる人だけでなく五輪に反対の人までも視野に入れた言葉の選び方。
大野の立派さは。さらに、昨日の団体戦で破れた後、フランスの柔道の強さ素晴らしさへの尊敬をのべた言葉にも表れました。大野は、自分の理想とする柔道は語りますが、外国人の柔道を批判しません。むしろ、それが持つ強さへの尊敬を言葉にしたのです。
一般の人にも柔道関係者にも、外国人選手の、勝った瞬間、礼よりも先に喜びを爆発させることを批判する人がいます。勝った直後、感情を抑制する大野が武道家として素晴らしいのは確か。しかし、勝って喜びを爆発されるのも、それはお国柄。大野を誉めてもよいけれど、それと比較して外国選手の振る舞いを批判する心は、偏狭で美しくないなあと私は思います。
外国人選手も、喜びを爆発させたあと、それでもちゃんと礼をして、相手を讃える。どこの選手もちゃんとする。それなのに目くじらを立てて、「日本人は素晴らしい、外国の柔道家は」というのは偏狭な考え方だと思います。(ヤフコメの、ネトウヨは、必ずそういうコメントをしますね。むしろお前が恥ずかしい。)
サッカーが世界中に広まる中で、同じルールに基づいていても、その文化個性は、地域、国ごとに多様です。
先週、久しぶりに家に帰ってきたサッカー観戦が好きな五男と一緒に、コパ・アメリカの、決勝戦と、EUROの準決勝決勝を、一気に見る、私の解説付きで見るということをしたのですが、どれも歴史に残る名勝負でしたが、「南米のサッカーと欧州のサッカーは、ビックリするほど違う」という印象を、五男も私も、改めて感じました。
ひとつひとつの球際に深くタックルにいくアルゼンチンやチリの文化。それを避けるために接触されたら大袈裟に転がるブラジルの文化。深いタックルでしか止まらないブラジル人の個人技。アルゼンチン人の気迫。それが当たり前なものとして高め合いながら100年以上の歴史を重ねているわけですから、それを欧州の価値観、ましてや歴史の浅い日本の価値観で批判しても仕方ない。
イタリアの、スペインの、イングランドのサッカーの中には、各国ごとの「理想の伝統的サッカー観」が埋め込まれていて、表面はみな欧州共通の最新式の戦術を採用しても、身体に染み付いた国ごとのサッカー文化が、追い詰められると丸出しになる面白さ。
柔道も世界中に拡がる中で、技術戦術という競技内容についても、礼法振る舞いについても、その国ごとの個性をもって定着している。
嘉納治五郎先生が、その、多様な拡がりを見たとしたら「礼法がなっとらん」とか「あんな技は、柔道じゃない」と怒ったかなあ。いや、「ここまで柔道が世界中の人に愛されるようになったか」「その技、面白いなあ。新しい名前をつけようか」なんて、あの世で喜んでいると思うんだよなあ。
男女混合団体戦は、世界各国で、柔道が愛され、日本を凌ぐほど、盛んに行われていることを見ることができて、勝った負けた以上の喜びがありました。
スポーツの国際大会が、自然な愛国心を刺激するのは、別に悪いことではないと思います。しかしそれが、すぐに偏狭で、過剰なナショナリズムに変わり、他国選手の行動や言動のあら探し、批判、敵がい心、「ニッポンだけ素晴らしい」「ニッポンだけ、勝てばいい」に結びつく心の動きは、「とても恥ずかしいことだ」と、メディアもスポーツ関係者も、常に意識して発信すべきだと思います。
私がTBSはじめ民法地上波テレビの、日本人競技者ばかり取り上げる放送内容、今、現に行われている最高の競技、試合を取り上げないことを、「最低」と批判し続けるのは、こうした民放地上波放送が「恥ずべきほうの偏狭なナショナリズム」に、阿(おもね)り、それを煽る原因になっていると思うからです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
