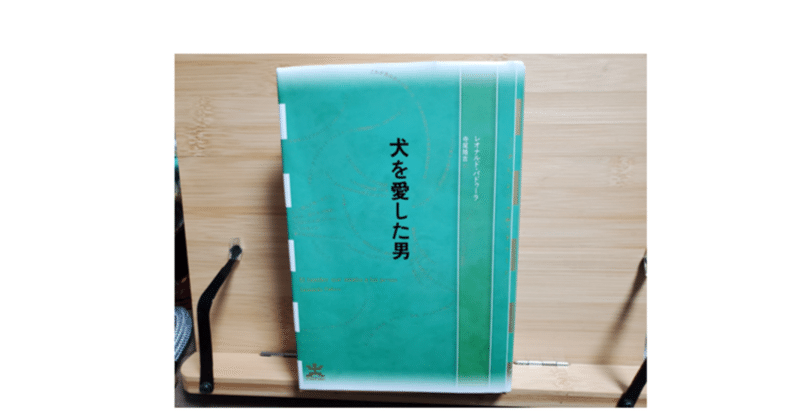
『犬を愛した男』 レオナルド パドゥーラ(著)寺尾 隆吉 (訳) キューバの現代文学です。トロツキー暗殺を軸に、20世紀全体の時間を、ソ連、スペインからメキシコ、キューバにまたがる空間的スケールで描く。本としても600頁を超える、物理的にも分厚い超重量級の大作でした。
Amazon内容紹介
世界革命を夢見るレフ・ダヴィドヴィチ(トロツキー)の亡命、暗殺者ジャック・モルナルに成り代わるスペイン人民戦線の闘士ラモン・メルカデール、そして舞台はメキシコへと至る。イデオロギーの欺瞞とユートピア革命が打ち砕かれる歴史=物語を力強い筆致で描く、現代キューバ文学の金字塔。
ここから僕の感想
読書師匠しむちょんが最近読んで、紹介してくれたので読みました。中南米の政治的暴力(暗殺など)をめぐる小説を、ここ最近、続けて読んでいたのですが、これはキューバの作家なのでキューバ革命とかそのあたりの話かと思ったら、さにあらず。
トロツキー=ロシア革命の指導者の1人だが、スターリンとの路線闘争に敗れ、まずはソ連内ウズベキスタンに幽閉され、その後国外に追放され、トルコ⇒フランス⇒ノルウェーと逃亡しつつ抵抗を続け、最終的にメキシコに亡命しているところを、スターリンが差し向けた暗殺者に殺される。小説のひとつの軸はこのトロツキーの逃亡生活。
もうひとつの軸は、そのトロツキーの暗殺者。数奇な運命で、スペイン内戦の共和政府側、ソ連の支援を受けて戦っているうち、ソ連から共和軍支援のためのスペインに派遣されているソ連の工作員にスカウトされて、暗殺者としてのトレーニングを受けて、トロツキー暗殺へと向かっていく。(スペイン時代の名前はラモン・メルカデール。その後いくつも名前を持ち、暗殺時はジャック・モルナルとなっている。)
トロツキーの逃亡抵抗生活と、暗殺者がスペイン内戦の若き闘士から暗殺者になっていく過程。
さらにもうひとつの軸が、その「トロツキーと暗殺者の物語」を、キューバの小説家が書いていくプロセス。正確には、冷戦時代には共産党のための文学しか書くことを許されなかったために、小説家としては挫折した男イバン。
この「トロツキー」の章、暗殺者「ラモンメルカドール」の章、キューバの「イバン」の章が繰り返し交錯しながら小説は進む。
時代的にも、トロツキーのロシア革命前夜の1910年代の回顧から、1930年代、トロツキーの亡命生活と、暗殺者のスペイン内戦が重なる時期、そこから第二次大戦を経て、戦後の冷戦から冷戦の終結後のキューバ社会の混乱と変化という、現在に至る「20世紀まるごと」を、三者の視点から立体的に描き出していく。
直接は登場しないのだが、トロツキーの逃亡生活は、端的に言ってスターリンとの闘争であり、スターリンが、革命時代の同僚ライバルたち、指導部も軍人将軍たちも文化人も、まるごと、難癖をつけては粛清していくプロセスが、トロツキーの逃亡生活の中で詳細に描かれていく。トロツキーの家族、子供たちも、その犠牲になっていく。
暗殺者を、スペイン内戦の闘士からスカウトし、スパイとして育て、暗殺計画の「駒」として送り込んでいくのも、スターリンの意志のもとに動く組織の上司たちである。その上司とて、少しでも失敗したり、政治的風を読み損ねれば、いつ自分もスターリンに粛清される側に回るか分からない。
スターリンの常軌を逸した権力欲と猜疑心と残虐さが、小説全体を覆う。全体主義の恐怖、暗黒面が一人の人格に凝縮したような存在である、スターリンという人。
もちろんトロツキーとて、革命直後、反対派などを残虐に多数処刑した人物であり、単純に「スターリン悪、ならばトロツキーは悲劇の正義の主人公」かというと、そんな単純な描かれ方はしていない。が、生活の細部を、家族や友人との交流が描かれていくので、読み進むうちに人間的共感は次第に形成されていく。これに対して、スターリンは小説中には登場せず、ライバルやその家族まで残酷に殺していくその「やったこと」だけが描かれていくので、どうしてこのような怪物を誰も制御できなかったのか、その恐ろしさが際だつのである。
スペイン王政に、そしてフランコ、ファシズムに対抗しようとしたスペイン内戦での共和政府側も、さまざまに内部分裂して内ゲバ状態になっていく過程も描かれる。「共産党・スターリン」の指導従う側と、それに対するアナーキスト、サンディカリスト、トロツキーに近い側。主人公ラモンは、たまたまさまざま成り行きで共産党・スターリン側について、思いもかけぬ運命に巻き込まれていくわけだが。
このスペイン内戦では共和軍側をソ連は支援していたのに、突如、スターリンはナチスと独ソ不可侵条約を結ぶ。ファシズム側と手を結ぶのである。また、フランスやイギリスがスペインを見捨てるところとか、第二次大戦に向かっていく欧州情勢を、スペインの視点から見るとこういうことだったのかというのも、小説ならではの体験である。主人公の視点から、歴史を体験する。
この五月にNHKの番組で「スターリンとプーチン 映像の世紀 バタフライエフェクト」というのがあった。
KGBの謀略、政敵の暗殺、目的のためなら何でもして自分の政権を維持しようとする。戦争をするのも、隣国を蹂躙するのも勝てるなら躊躇は無い。その中で、自国民も、隣国の国民も、抑圧され、密告の恐怖におびえる。スターリンのやったこと、手口とプーチンのやり口を重ねて見せるドキュメンタリーだった。
この小説でのスターリンのめちゃくちゃぶりを読んでいるとき、「ソ連(~ロシア)というのはもう100年以上、こういうことをやり続けていたわけだから、それは、プーチンも、普通に、いくらでも残虐なことも卑怯なことも、それはやるよなあ。権力闘争っていうのはそういうもんだと、からだに染みついちゃっているんだろうなあ」と、どうしても思ってしまった。ちなみにスターリンはグルジア人で、トロツキーはスターリンのことをグルジアの田舎者として見下していて、いつでも潰せるとタカをくくっていたために、ひどいめにあうのである。
このことを書いているのが、西側の作家ではなく、作家としてのキャリアをキューバの、それも共産政権の文学への抑圧がきつい時期に作家としてのキャリアをスタートした人物が書いていく。小説内の小説家になり損ねたイバンも、実際の作者パドゥーラもそうである。
共産党の、圧政の圧力が小説家にかかる。小説を書くこと、真実を知り、語ること自体に「恐怖」がのしかかってくる。
政治的暴力の恐怖が、殺される側、殺す側、それを書き残そうとする者、全体を包み込む。その間で不思議な因果が巡る。
ここでは深く書かなかったけれど。それぞれの家族の物語としても、複雑で悲劇的な物語が紡がれる。政治的暴力は、一人の個人だけでなく、家族まるこどを、さまざまな形で引きずり回し、すりつぶしてしまうのでした。
かなり気合を入れないと、読むの大変かと思いますが、それでも挑戦する価値はある。読んでよかった。感動するとかいうことではなく、歴史の重さ。政治的暴力の恐怖、それに人生まるごと、家族まるごとが巻き込まれるということ。それを小説を読むことで体験すること自体に意味がある。そういう小説でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
