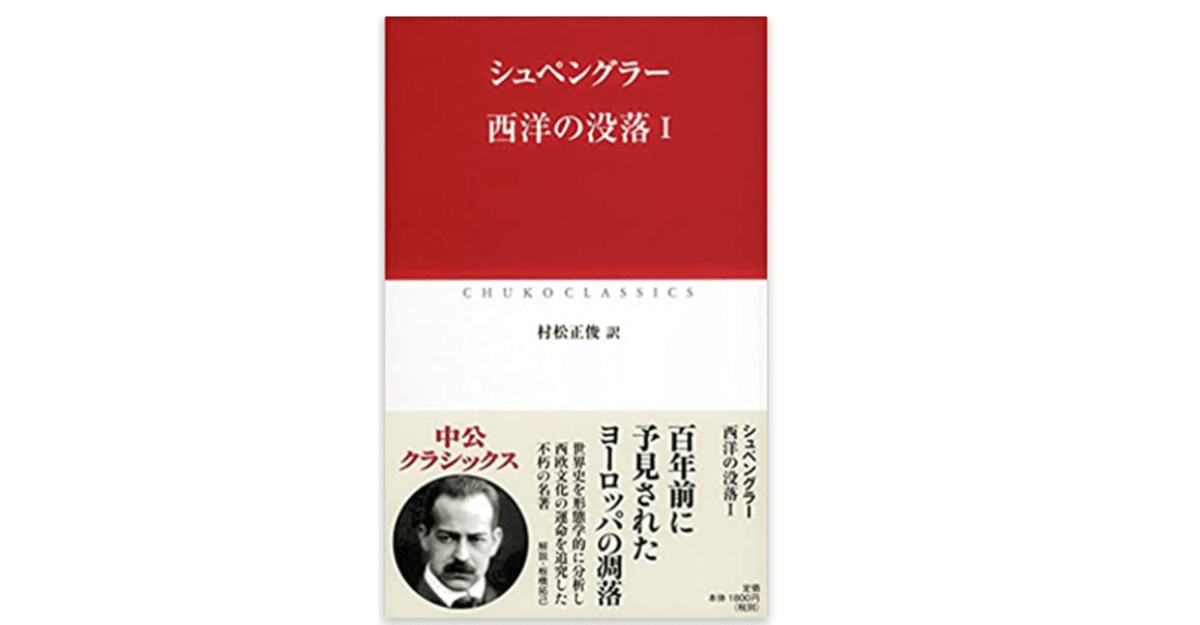
シュペングラー『西洋の没落 Ⅰ』 100年前に、『サピエンス全史』みたいに、人類の営み全体を捉えようとした、スケール巨大な本でした。まだⅠしか読んでないけどね。
しむちょーん、読んだよー。(読書人生の師匠、しむちょんが教えてくれた本を読んだときには、こうやって叫ぶことにしています。)
『西洋の没落 I 』(中公クラシックス) (日本語) 単行本 – 2017/6/7
シュペングラー (著), 村松 正俊 (翻訳)
Amazon内容紹介
「百年前に予見されたヨーロッパの凋落。世界史を形態学的に分析し諸文化を比較考察、西欧文化の没落を予言した不朽の名著を復刻」
いやいや、Amazonさん、ちょっとそっけない。単行本の方の、Amazon内容紹介。
「あらゆる〝文化〟は〝文明〟へと没落し、やがて終焉する――。ヨーロッパ文明の没落の運命を今から百年前に予見し、世界に衝撃を与えた歴史的名著が、新たな編集(膨大な註記、梗概と索引の追加、用字用語の表記の改正、新しい文字組み)でよみがえる。現代日本の読者のためのニュー・エディション。全2巻。」
そう、全二巻のうちの「Ⅰ」しか読んでいないのだが、ここで、いったん感想。
本編の前に、訳者 村松正俊氏の解説がついていて、それがないと、無理、という本でした。
ちょうど100年前に、当時の最新数学、科学などの知見に刺激を受けつつ、人類史全体の中での、自国ドイツ文化文明が、どの様に位置付けられるかを解き明かそうとした、稀有壮大な本でした。
100年前の「サピエンス全史」みたいなスタンスの本かなあ。相対性理論や、エントロピーの法則とかが出てきて、どうも、近代の数学科学が限界を迎えたなあ、という時代に、宗教・芸術(建築・絵画・音楽・演劇・文学)、科学・数学と哲学の間を行ったり来たりしながら、
①今の西洋的なものはヨーロッパ北方の、自然と宗教となんやかんやで形成されたもので、ギリシャ・ローマとは全く対照的なもので、全然ちがーう。ルネサンスでそれがあたかも接続されたように語られるが、全然まったくちがーう。「北方的なものをファウスト的」ギリシャローマ的なものをアポルロン的」として、どれだけ全く対照的かを論じつつ、
②とはいえ、すべての文化は、春夏秋冬、栄えて、衰えるサイクルを描く。文化は、最終的衰退期において文明となる。今、ゲルマン的なものも、ゴシック→バロックの文化の最盛期から、文明の時期に以降しつつある。
という、「巨大な妄想」ともいうべきものを、あらゆるジャンルについての知識をぶちまけて語りまくる、という、怪書でした。
現代においてハラリ氏の『サピエンス全史』『ホモデウス』が、人間遺伝子の全解読などの生命科学進化と、AIの飛躍的進化という科学と技術の飛躍期に、そのインパクトのもとに構想された人類全史ということを、100年前に移行して考えると、本書の成立具合が、なんとなく想像できる。
シュペングラーが、「ミュンヘン、ベルリンの各大学で数学、自然科学、哲学、歴史、芸術を学ぶ」という経歴の中で、それらを統合的に関係づけようとしているうちに、最新の数学や科学が、これまでの近代的常識を全部壊しにかかっていることだけは理解できて、そのインパクトが、自国ドイツの文化、文明、社会にどういう影響をもたらすかを書いた本なのだと思う。ゲーデルの不確定性原理が出てくるのが、この後1930年くらいで、その後の哲学に決定的な影響を与えたことの、さきがけのようなものか。
というわけで、村松氏も書いている通り、今読むと、というか同時代でも、数学や科学の理解については、かなり間違いがあると指摘されまくっているようなのだが、そういうことを超えて、人類史と、人間の営みの全体を理解し切ろうとする、その執念がにじみ出てくるというか、ものすごい迫力で迫ってくる本でした。下巻、読むのも、ちょっと大変そうだけれど、頑張ろう。
なにしろ、登場するギリシャローマから中世からルネッサンスからその後現代までの、哲学者、科学者、数学者、画家、その作品、彫刻、建築、音楽、演劇、知っているのが1割もない。そういう固有名詞が雪崩のようにどんどん出てくる。真面目にいちいちウィキペディアとかで調べていたら、1ページ進むのに半日かかる、というような本なので、もう知らないものは知らん。で、どんどん読み進めちゃいました。真面目にやったら、一冊読むのに半年はかかる。そういう本でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
