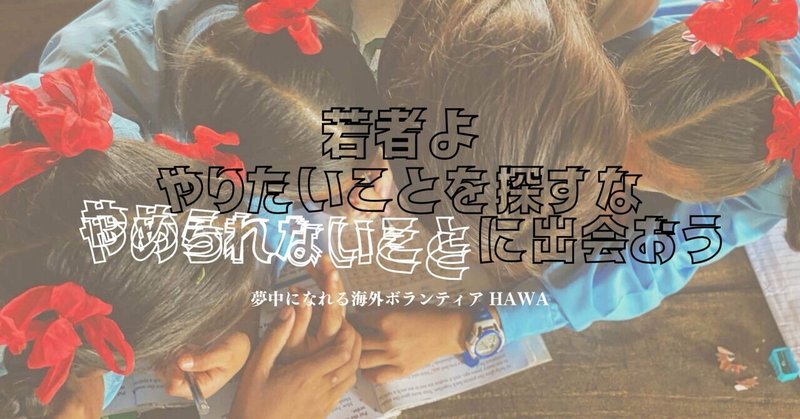
なぜHAWAなのか?〜海外ボランティアの本質の追求〜
「何かが違う」
学生の時海外ボランティアに勤しんでいた僕が
海外ボランティア全体に対して抱いていた感情だ。
「何か」とは一体何なのか分からないまま
社会人となり、学生時代ほどには
時間を割けなくなってしまった。
「何か」の正体が分からなかった理由は、
言語化する機会が無かったからだろう。
同じような違和感を感じる者と
言葉を交わすことで、
その違和感の正体が分かることがある。
僕の場合その相手がようたろうだったわけだ。
さて、「何か」の正体はなんだったのか。
世に溢れる海外ボランティア団体の活動が、
海外ボランティアの本質から
乖離していることである。
海外ボランティアの本質とは何で、
そこからどう乖離しているのか。
「人助け」と「ボランティア」の違いを考えると
海外ボランティアの本質が見えてくるように思う。
人助けはその場その場でも、
誰かを助ければ人助けになる。
道を教えてあげた、
視覚障害の人に肩を貸してあげた、
チンピラに絡まれている女の子を逃がしてあげた…
全て人助けである。
ボランティアは、助ける対象が、
継続的な助けを求めていることが多い。
国内でよくある災害ボランティアを除き、
(今でも能登半島で懸命な努力をしている方々には
大いなる敬意を表したい。)
特に海外ボランティアはそこに継続性は不可欠だ。
抱えている問題があまりにも複雑で、
一朝一夕で解決など到底不可能だからだ。
そして場合によっては、命を預かる場合もある。
学校を建設する場合もある。
生活場所を提供し、学習も支援する。
その人の将来まで担っていると言えよう。
そうすればそこには大きな責任が発生する。
「支援先への継続性の必要」
「責任の大きさ」
ここに海外ボランティアの本質があるといえる。
さて、スパイダーマンが、
「あのヤンキーに絡まれている女の子、
俺が好きな子なんだよね…
今が振り向いて貰えるチャンスだ!」
なんて心の中でつぶやきながら
蜘蛛の糸でヤンキーを吊り上げてみたり
地面に叩きつけてみたりしたら皆どう思うか。
心底落胆するものだろう。
そんなヒーローはもはやヒーローと呼べない。
これと同じことが、海外ボランティアの業界では、
あまりにも多く行われている。
まともに教員育成も進める前に学校の建物だけ
ボコボコ建ててみたり。
支援先であるはずの現地の人々を、
まるで学生の教材用の見世物として扱ってみたり。
子どもが暮らす施設を運営してるのに、
普段通りプログラムが行えない有事の時は
寄付以外収入が無いような 財務にしてみたり。
ボランティアを通して学生を育成すると言いつつ、
もはやボランティア活動なんぞ何ら興味なく、
ガクチカの材料が欲しい学生をかき集めてみたり。
あまりにも支援先のことを何も考えていなくて、
無責任で、とても失礼な団体が多い。
教員もいないのに学校だけ建てたって
そこで教える人がいなければただの環境破壊だ。
望んで教育を受ける機会が無いような環境に
産まれた訳でもないのになぜ見世物にされるのか。
有事でプログラムが出来ないから、
みんなの生活費ありません、なんて子どもたちに
面と向かって言えるのだろうか。
ガクチカ?インターンでもやっとけという話だ。
(そもそもこれだけボランティアが世に溢れている今、ボランティアがガクチカになるという発想が
甘い。そんな甘い考えの学生を集めている団体だと考えればそりゃたかが知れてるのはよく分かる。)
その無責任さ、失礼さによって、
本来なら支援することが本題であるはずの
ボランティアにまで、資本主義の縮図が見て取れる
ようになってしまっている。
結局途上国は、先進国によって食い荒らされる、
そんな運命を辿るのかと。
人は入れ替わりながらでも団体としては、
支援先に継続的に、責任を持って活動することは
できないのか。
海外ボランティア業界に帰ってくるなら、
この2つを追求できる場所で帰りたいと思っていた。
そこで聞いたのがようたろうの壮大な夢だった。
HAWA 〜episode 0〜とも言えようか。
もう1人のエグゼクティブスーパーバイザー(?)
サミルが勤めるBIKAS COFFEEで、
それはそれは美味しいカフェオレを飲みながら
聞いたその夢は、僕の海外ボランティアに対する
願望が、これでもかと言うほど詰め込まれていた。
「継承」という最も大事なビジョン、
考え抜かれた短期、中期、長期の計画。
以前にも書いた通りようたろうとは
物事の捉え方がよく似ているのだが、
(どちらも本質から目を逸らすのを嫌うからだろう。)
ここまでとは思っていなかったのである。
心底成功を祈っていた。
そう、その時はまだ他人事だったのである。(苦笑)
なぜ僕とサミルをエグゼクティブスーパーバイザーに
選んでくれたのかは(特に僕はネパールに関しては
ほぼ門外漢に等しい。)、いつかようたろうに
noteに著してもらうとして、なぜその肩書きを
拒否しなかったかの理由がここにある。
海外ボランティア業界に帰ってくるなら…
その条件が完璧に揃っていた。
拒否する理由が無い。
こうして僕は海外ボランティア業界に帰ってきた。
帰ってくるにあたって、叶えたいと思った夢を、
次回は書いてみたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
