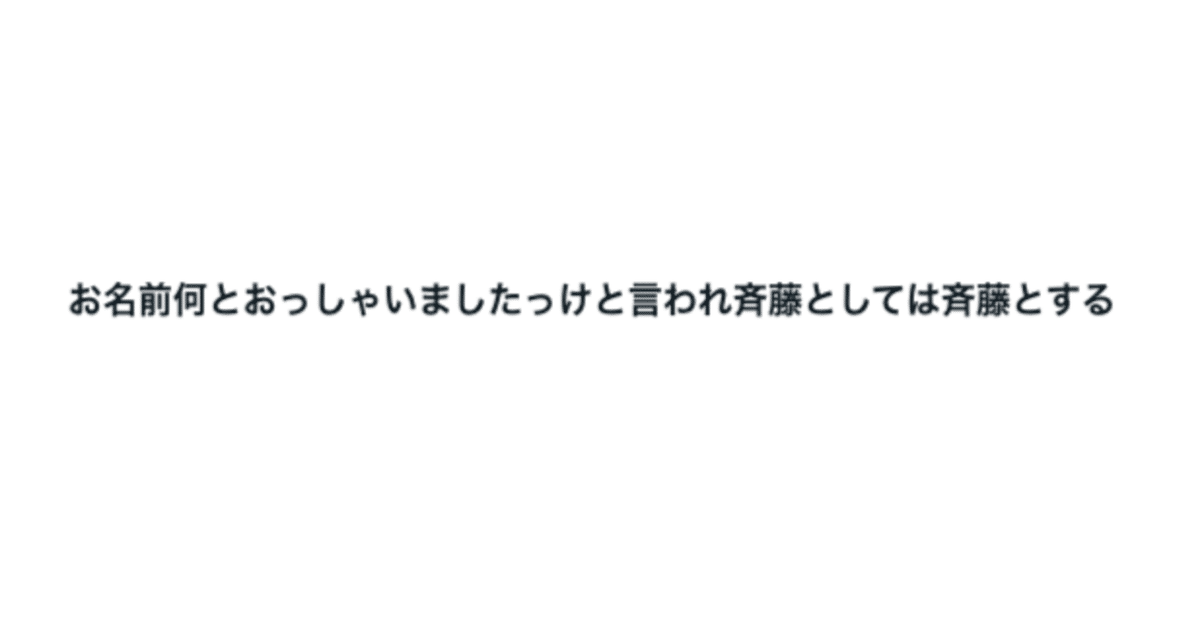
短歌、こわい とぼやく夜
最近、短歌が気になって仕方ない。
中高の教科書で勉強するくらいで、短歌とは、ほとんど接点がない人生だったのだけれど、一冊の短歌集に出会ってから、少し自分の心の旗色が変わってしまった。
この短歌集は、斉藤斎藤氏の第一歌集だ。たとえば、冒頭の1つ目からこんな短歌が収録されている。
お名前何とおっしゃいましたっけと言われ斉藤としては斉藤とする
この歌は、たぶんこの歌集の取説みたいになっているのだと思うのだけれど、おおよそぼくが学生時代にきいた短歌のアカデミックな感じとは対立している。ひたすら斉藤斎藤氏は、作者個人の話を、5・7・5・7・7で語り続ける。
エレベーターの3つのランプが点いて消え2が点く手前わたくしが匂う
うつむいて並。 とつぶやいた男は激しい素顔となった
雨の県道あるいてゆけばなんでしょうぶちまけられてこれはのり弁
短歌はあくまで個人の体験や見たものを、短い言葉の中に押し込めるという究極の私小説だ。小説ではなかろうから、「私テキスト」とでもいうべきか。最近、斉藤斎藤氏の短歌に関する講義を聞いたのだけれど、このお話もすこぶる興味深かった。
「さっき教室に行ったら誰もいなかったよ」
という会話文なのだけれど、日本語で考えると特段違和感は感じない。しかし、他言語(特に欧米の言語)を使う人々にとってみると「それはおかしい。だって、その教室にはおまえがいたんだろ?誰もいないなんて言い方は、矛盾しているじゃないか」となるのだそうだ。
なるほど、確かにその通り。斉藤斎藤氏がいうには、日本語の特異性は、会話の前提に「私」という主語が当たり前に隠れているという点なのだそうだ。
「さっき教室に行ったら(私以外は)誰もいなかったよ」
の(私以外は)を省略しても、文章の意味が通じてしまうのが、日本語の特徴だ。つまり、ぼくらは会話は「自分の話」であることが前提とされている。日本語ほど、私小説に向いている言語はないのかもしれない。
主語を明確にしなくて良い日本語は、短い言葉に情景を押し込める「短歌」にお誂え向きだ。万葉のその昔から「短歌」が、絶滅せずに生息し続けてきたのは、この日本語の性質が関係しているのだ。というのが、斉藤斎藤氏の講義前段の概略だった。そんなこんなで、斉藤斎藤氏の短歌集を皮切りに、メジャーどころの歌集を読み始めた。
ぼくも、恥ずかしながら、戯曲や雑文を書き、不特定多数の方に見てもらう機会がある。文章を書くということは「言葉を尽くすもの」と考えていたが、短い言葉の連なりで何ものかを映し出す「短歌」の世界に触れて、「言語」との関わり合い方がアップデートされた気がする。まだ、「気」だけなんだけれど。
遅ればせながら短歌に触れて、新しい世界が広がることは嬉しいことだ。でも、短歌のロジックやレトリックの深さを、聞けば聞くほど驚愕してしまうのも事実。涼しい顔しながら、言葉を機関銃のように打ちまくる歌人を見ていると、恐怖さえ感じてしまう。
だから、ぼくは、ハラハラどきどきしながら短歌集の次のページをめくる。未熟な自らの内側を撃ち抜かれる覚悟で。
短歌、こわい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
