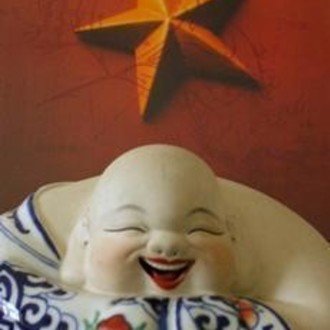【ぶんぶくちゃいな】美荷楼329号室:香港で体験した、今どきの中国若者考
今回は、3月に香港に滞在したときに袖振りあった体験から、「今どきの中国若者考」についてまとめてみたい。
最近になって気がついたのだが、この春で正式に北京での住まいを引き上げてからまるまる9年になる。北京にはその年の夏以来、行けていない。中国全土を見ても、2019年のデモ直前に香港に滞在した際に深センにいる知り合いを訪ねて日帰りして以来、足を踏み入れていない。
つまり、香港や日本で昔からよく知る中国出身の知り合いたちと会って話をすることはあっても、いまこの瞬間に中国国内で暮らしている人たちとネットではなく、生身で付き合う経験が激減してしまっている。
やっとのことでコロナ感染を警戒した各国の往来策が緩和され、航空便の往来も少しずつだが以前のペースに戻りつつある。中国はまだまだ海外からの往来客の受け入れに慎重な態度を取っているものの、経済の回復を急ぐという台所事情もあって、そろりそろりと海外との往来のための門戸を開き始めた。そろそろ、きちんとしたテーマを持って中国にも足を踏み入れたいと思い始めている。
この9年間で中国は大きく変わった。ちょうどわたしが離れた2014年頃からモバイルペイメント全盛期に入り、いまではスマホ1つでほぼすべての生活が成り立つという状況になっている。日本でもこの間、やっとのことでモバイルペイメントが普及したものの、その利用範囲の広さは正直、日本の比ではない。2019年の深センでもある友人は「現金なんて前回手にしたのは…半年前に田舎で姪っ子にお年玉をやったとき以来だ」と言った。
その「スマホ1つで」は、3年間のコロナを経てさらに強化され、コロナ感染対策期間はどこにいくのにも健康証明が必要で、それを提示するにはスマホアプリ一択しか手段がないくらいに統一された。
それだけではない、わたしが親しくしてきたメディアも大きく変化した。事実の報道に真剣な態度を捨てきれないジャーナリストは当時すでに大手メディアから締め出されつつあり、今や引き続きメディアの世界に残っている人はほぼゼロである。中には起死回生を求めて海外に移住を決めた人も少なくない。特にコロナ後の動きは顕著で、海外移住の知らせを聞いて思わず、「ブルータス、お前もか」という言葉が口を突いて出た相手すらいる。
当時ブイブイ言わせていたアリババやテンセントもメッタ叩きにされ、皆の目がギラギラと注がれていた不動産もいまではすっかり…と書けば書くほど、そんな変化を実際にみておきたくなってきた。そろそろ重い腰を上げて行かなければ…
そんなふうに、今どきの中国体験にちょっと飢えているわたしが、ほんの偶然からこの3月に滞在した香港で遭遇した中国の若者たちの姿に、多少カルチャーショックを受け、考えさせられたのでまとめておく。もしかしたらこれを読む日本の皆さまも中国の若者に思わぬところでご一緒する場面もあるかもしれない。そのときにぜひ参考にしていただきたい。
●公共住宅を改装したゲストハウスへ
このアカウントは、完全フリーランスのライターが運営しています。もし記事が少しでも参考になった、あるいは気に入っていただけたら、下の「サポートをする」から少しだけでもサポートをいただけますと励みになります。サポートはできなくてもSNSでシェアしていただけると嬉しいです。