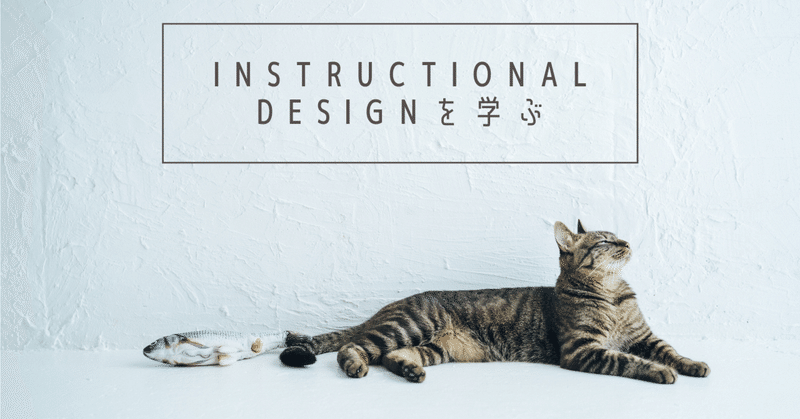
Relevance(関連性) ID学 vol.8
J. M. ケラー(著)・鈴木克明(監訳)『学習意欲をデザインするーARCSモデルによるインストラクショナルデザインー』(北大路書房)
はじめに(vol.6)関連性は道具的動機が大きく関わるけど、道具的な関連づけがなくても内発的動機づけによって意欲を高めることができる、という素敵な章らしいと書き、つぎに(vol.7)自分の経験からして内発的動機づけの工夫が実はすごく重要ではないかと書き、ここ(vol.8)で無意欲から外発的動機、そして内発的動機までの人間の意欲分類と、意欲を構成する3つの基本的な概念を説明したデシの自己決定理論についてまとめようと思う。この理論は非常に有名らしく、Youtubeビデオもたくさんある。
自己決定理論(Self Determination Theory)
動機に必要な要素は3つ(勝手訳)
①Relatedness(所属感、有用感)
②Competence(有能でありたい、能力を発揮したい感)
③Autonomy(コントロール感)
Relatednessは、自分がその集団に受け入れられていると同時に、自分がほかの人の役に立っている、影響を与えているという双方向のコネクションでしょうか。ほかのビデオによれば、学ぶ対象とのコネクションでもあるみたい。
Competenceはこれまで何回か出てきた言葉だけど、ここではホワイトの相互影響動機づけが説明されているように思う。自分が能力が発揮できる環境を見つけ、そこで実際に能力を発揮して達成するという環境と個人の潜在能力との相互作用。Essential to Wellnessの意味するところがイマイチわからなかったけど。
Autonomyは、オートノミーとカタカナで表記されるくらい浸透している言葉。自分で選択できる(した)、自分で学習をコントロールできる(した)という気持ち。
本ではとくに、内発的動機はコンピテンス・自己決定・自律性の欲求と結びついているとした上で、しかし、内発的に動機づけられた活動はこれらの欲求を満たすために行われるのではないと書かれている。すなわち
内発的に動機づけられた行動にのめり込むことは、これらの欲求を満たすための手段であるが、それらは、内発的に動機づけられていない行動によっても満たされ得る。しかし、内発的に動機づけられたままでいるためには、能力と自律の感情を経験することが必要不可欠である。
なんのこっちゃなのであります。だれか教えてほしい。
有機的統合理論(Organismic Integration Theory)
意欲を、無意欲、外発的動機づけ(4種類)による意欲、内発的動機づけの6つに分類している。これらは階層を成しているわけではないので、どの分類からも直接、ほかのどの分類にも移行できるとされている。本では、この理論の重要な結論の1つとして、学習者の動機づけに必要なのは必ずしも道具的関連性ではなく、内容に対する内発的興味、または外発的な刺激が1つでもあれば、意欲につなげることができる点を挙げている。つまり、外発的動機づけのもと経験を積む中で、その要因に共感するとか、内発的な感情を経験するとか、そういうことを通して意欲を高めることは可能だということですね。
ちなみに内発的動機づけ、外発的動機づけについてはこちら。
Deci + TED talks
わたしでさえ再生スピードを上げるくらいの速度で話してくれていて、しかも非常にクリアでわかりやすい。デシは動機は量ではなく質という側面で話されるべきだという。どれだけ学ぶかじゃなくて、どう学ぶか。そして、Controlled Motivation (たぶん外発的動機づけ)と Autonomous Motivation (内発的動機づけ)を比較し、Autonomous Motivation はよりCreativeで質の高い学びをもたらすという。で、このAutonomous Motivationを高めるには、学習者の状況をよく知ること、学習者に選択権を与えること、試行錯誤させること、何か提示する場合は根拠を示すこと、相手を想い関係を築くことが必要。
大切なことは、学習者の動機を高めるのではなく(たぶんできないという意味だろうか)、学習者が自身の動機を高められる環境をつくることである。そして、そのために必要なのは自律性への支援だというお話でした。
関連性を高めるための方略
目的指向性
・学習者にゴールを提示する
・学習者にゴールを定義させる
学習者が直接関連性を感じていなかったとしても、これを学ぶ前と学んだ後での生活の変化について考えさせるなどの活動を通して、創り出すことは可能だという。それには学習者分析も必要になってくる。マインドマップや3×3マスを利用して学習者にアイデアを出してもらい、ディスカッションするなどの活動も有効。
興味との一致
・教師との関係性
・学習スタイルとの一致
・ロールモデルの利用
教師に気にかけてもらっているという実感も動機を高めることができるので、名前を覚えよう、声をかけようというのは誰でもやっていると思うが、それがやる気につながると認識はあまりしていなかった。学習スタイルは達成動機や親和動機などですね。ほどよくMIXすることが大事。ロールモデルに話してもらうなども有効。これらで目的指向性の弱さを補うことが可能と書いてあった。
経験とのつながり
・学習者の経験や既知知識と学習内容を結びつける
・学習内容や方法を学習者自身に選ばせる
教師との関係性はRelatedness、学習者自身に選ばせるのはAutonomyにあたりそう。学習スタイルとの一致はCompetenceかな…
関連性、おしまい。
