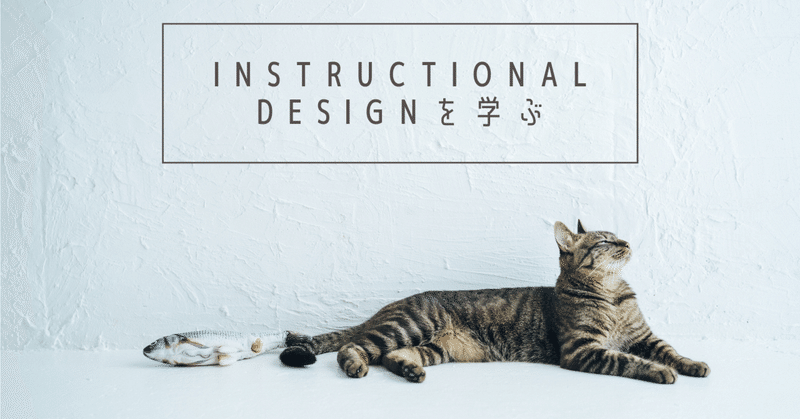
Instructional Designを学ぶ ID学 vol.1
自分だけのちっちゃなプロジェクトを全部ブン投げて、noteからしばらく離れておりました。その間に修士を取り(厳密にはまだ)、モンゴルはおろか、タイも離れ、スリランカでJLPT対策というなんともやる気のでない仕事をちょうど2週間続けたところで急に、noteを書こう!と思い立った。
大学院では主にSLAとCEFRとInstructional Designについて学んだ(つもり)。大学院に入るちょっと前から、Instructional Designになんとなく「いい感じ」と目をつけ、いくつかウェビナーを受けるもなんかしっくりこず(結局どうやって使うわけ?というところが根本的にしっくりこなかったんだと思う)、大学院に入って講義をとったものの、まだしっくりきていなかったところで、鈴木克明先生の対談を聞く機会があり、まさに「目から鱗」的な体験をしたのでありました。こんなチープな感覚でいいのかと思うけど、私ってもともと計画好きで、旅行の計画たてるのも好きだし、勉強の計画をたてるのも好き(英語学習なんて星の数ほど計画のみをたて続けました)。そういう私に、Instructional Designの客観的でシステマティックな設計論がものすごくすとんと落ちるわけです。
A型のわたしは、まずココから始める。
J. M. ケラー(著)・鈴木克明(監訳)『学習意欲をデザインするーARCSモデルによるインストラクショナルデザインー』(北大路書房)
鈴木先生が、ARCSモデルを授業分析に使うのもいいよねと仰っていて、なるほど!と思った記憶がある(しっくりきた瞬間)。それからARCSモデルをかじったものの、オオモトにあたっていなかったので、いつか読もうと思っていた。
ちなみにARCSモデルとは動機理論とか呼ばれたりするものである。
読んだ内容をちまちまと綴ろうという新たなプロジェクトを立ち上げることにした。関連本があと2冊あるし(全部鈴木先生が関わっているのがちょっとコワイ、偏りすぎかしら)、ひさしぶりに英語の勉強も兼ねてMOOCでも勉強するつもりでして、自分の日々の授業にも積極的に活かしていこうという野望でございます。
