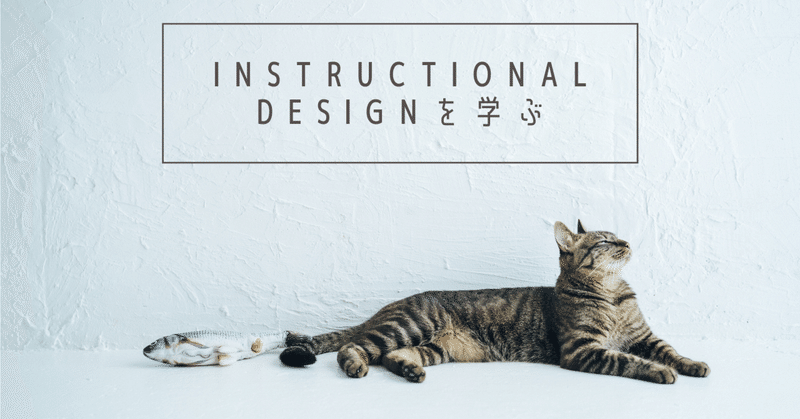
Confidence(自信) ID学 vol.9
モンゴルにいた頃、授業で学生を戦意喪失させた経験が何度かあり、ARCSの中では最も苦手で、最も注目する項目。ハタと気づけば、あまりそういうこともなくなって、単なる経験値の問題かと思うこともなきにしもあらずだけれど、やはりおもしろかった。
J. M. ケラー(著)・鈴木克明(監訳)『学習意欲をデザインするーARCSモデルによるインストラクショナルデザインー』(北大路書房)
統制の所在
人がもつ特性として、統制の所在が内的か外的かという話。自分の能力や努力が学習成果に影響を与えると考えるのが内的、がんばりに関係なく運や他者の評価が結果に影響すると考えるのが外的。内的な特性が、高い学習効果や創造性と関係することは想像に難くない。さらに、内的な学習者は曖昧な学習状況における手がかりやルールの発見が早く、偶発的な学習においても高い成績をおさめるなど、いいことづくし。彼らは成功の要因を内面に求め(自分の能力や努力のおかげ)失敗の要因を外面に求める(課題の難易度が高すぎたとか、説明が不足していたなど)という、なんとご都合主義的なメンタリティと思わずツッコミたくなる特性らしい(ひねくれ者の感性)。一方で、外的統制の所在を特性とする学習者は、成功は外的要因(運が良かったとか課題が簡単すぎたとか)、失敗は内的要因(わたしが悪いのよ…)とする、なんとも健気なメンタリティである。
さて、ここに学校という(一般的に)成績をすべて個人の能力と努力の結果だとする環境と、記憶領域と情報処理負荷という概念を持ち込むとですね、「失敗は外的要因」と考えるはずの内的統制の所在の学習者も「自分の何が悪くて失敗したのか」と自身の内面に検索をかけることになって(メタ認知の使用)情報処理負荷が増大、記憶領域のフル活用、結果として学習成果が落ちる可能性があるそうです。なんか非常に興味深いと思うのです。そのへんのことが書かれているのかもしれない参考文献がこちら。
統制の所在をさらに発展させた原因帰属理論や、特性としての統制の所在に対して、態度や信念として定義する指し手・コマ理論などありますが、とにかく成功の鍵は自分が握っているんだと信じることが大切とまとめてしまおう。
自己効力感 self-efficacy
自己効力感は次の3つの質問で構成される概念
①成功に必要なことを行う能力が自分にあるか?
②成功につながる計画を考えることができるか?
③成功を収めるまでに必要な期間、努力を継続することができるか?
最近、自己効力感という言葉が一人歩きしている感じがしていて、いろいろなところで定義が曖昧な自己効力感を聞くことが多い。そんな中、なるほどと思ったのがこちら。
とくに、自己効力感とは一般的な特性ではなく、学習者が具体的な課題に対してもつ効力感とされている(ほかのビデオでもそう)。知らなかった…
ここでも説明されている通り、自己効力感に影響を与える要因は4つある。
①達成度(過去の成功体験)
②代理体験(共通項のある他者の成功例)
③言葉による説得(メンターやコーチングなど)
④感情的な喚起(失敗への恐怖や不安感、自信過剰など)
4つの要因の中でも①の成功体験が最も重要だとされているんだけれども、興味深かったのは【ある課題に対して効力感の低い人も、ほかの関連性はあるがまったく別の課題において成功体験を積み重ねることで、その効力感を改善する(高める)ことができる】というもの。なんか活かせそうと思って印象に残った。
ゴール指向性
似た概念として課題指向vs自我指向、達成指向vsパフォーマンス指向というのがありまして、要するに自分の能力や知識の向上に意識があるのか、結果(成功・失敗)や自分がどう見られるか(他者からの評価)に意識があるかという特性だと説明されている、このビデオで。
単純にいうと、学びを促進する上では課題指向を強化して、パフォーマンス指向を弱めることがよいとされているんだけど、その方法として【TARGET】という6つのキーワードがある(ビデオの中)。これもまたヒントになりました。
自信を高めるための方略
成功への期待感
・評価基準(何を成功とするのか)を観察可能な行動として記述
・学習者自身に学習ゴールや目標を書かせる
おお、Can-do statementではありませんか。
成功の機会
・教材や構成のわかりやすさ
・妥当性(目標・内容・練習問題などの一致)
・適度な難易度の調整
個人の責任
・学習スタイルやプランなどを自分で選択させる
・教師が学生の成功を信じていることを行動で示す
・学習者が制御した結果(成功)だということを伝える
学習者による学習コントロールは最も適切なものだけを実施と注意書きしてあった。なんでも丸投げすればいいってもんじゃないということかしら。
教師の自己効力感
教師自身の自己効力感が、学生の成功に影響を与えることが実験でわかっているんだって。まず、教師が学生の成功を信じること。そして、教師が自分に彼らを成功に導く教授能力があると信じること。自己効力感の高い教師は、学生のために時間を割き、学習者の努力の継続に注力し、挑戦的な課題を準備し、自主性を尊重し、肯定的な学習環境を整え、新しい指導法を試み、苦しんでいる学生に支援を惜しまず、すべての学生がインクルーシブに学びに関わることを促す傾向にあるそうだ(ちょっと最後のはわからなかったので、インクルーシブというカタカナで誤魔化してみた)。
非常に納得するわけです。最近「わたしは学生を信じているんだけどね」と思うことが多々あったので、より強く納得した。なんというか、自分の指示に従うとか、敬意を払うとか、その結果として嘘をつかない、裏切らないということではなくて、もっと別な次元で信じているのでございます。そういう意味でやっぱり裏切られたことがないから、きっと信じられるのかもしれない。よくわからない(書いておいてなんだけど)。ただ、これって自己効力感なのか… Self-Conceptなんじゃないかと思ったり。だって、具体的な課題に焦点をあてた定義なんだよね、自己効力感って… とまた定義が曖昧になったところで、自信、おしまい。
