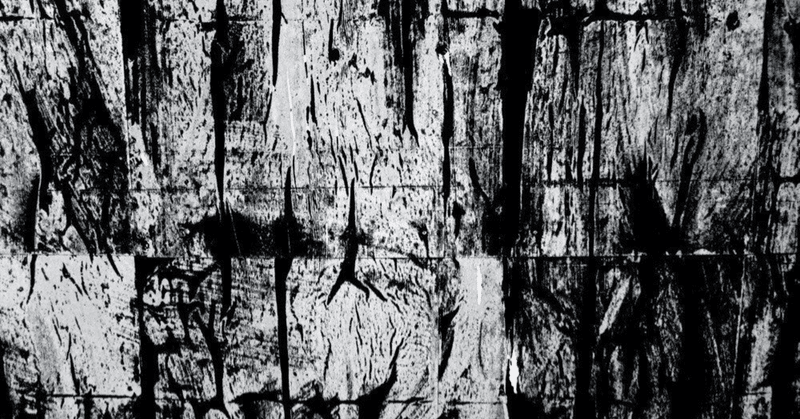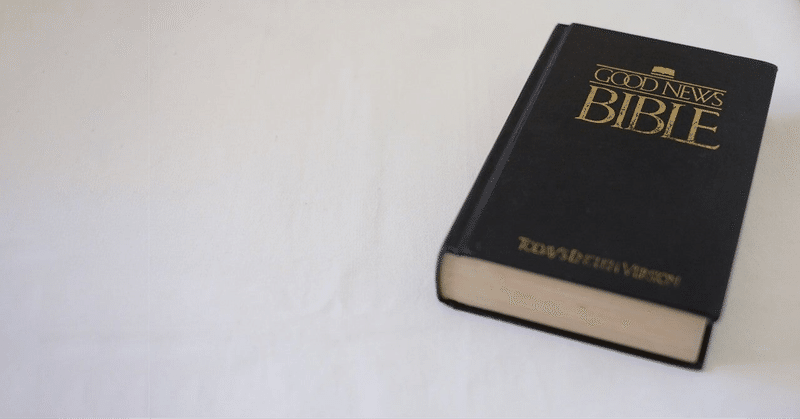#おすすめ名作映画

“秘密の花園はいつでも開かれているのです。目覚め、生きているのです。”_“The Secret Garden”(1993)
イギリスには庭園の文化がある。 以下、「New Wild Garden: Natural-style planting and practicalities (English Edition)」(Prime Reading)から引用。 plight 【名】悪い[ひどい]状態[状況・ありさま]、非常に苦しい状況[立場]、窮状、苦境、窮地 庭の存在は、人の心にどのような効果を及ぼすか。 原作フランシス・ホジソン・バーネットのイギリスの名作児童文学「秘密の花園」は、このテーマに

“君が感じたままを歌うんだ。人々はそういう歌を聴きたいと思い、そういう歌で救われるんだ。”_”Walk the Line”(2005)
ホアキン・フェニックスが吹き替えなしの歌を披露し主演するカントリー・ミュージック歌手Johnny Cashの伝記映画「ウォーク・ザ・ライン 君へと続く道」より。原題の'Walk the Line'は、Johnny Cashのヒット曲'I Walk the Line'から取られている。 1955年テネシー州Memphis(メンフィス)。Johnny Cashは既に一児のパパ。軍を除隊後、家庭用品のセールスマンとして訪問販売をするが、うまくいかない。ベーシストと電気ギターを弾く

“正義とは赤いリボンや金モールには目をやらないもの。殺された女の叫びのみ耳にするもの。“_“THE NIGHT OF THE GENERALS”(1967)
オープニングだけは”ヌーヴェル・ヴァーグの父”アンリ・ドカエのカメラが冴え渡っていて、あとはなんというかひたすら重苦しいだけのジメジメした(142分も必要だったか?)映画「将軍たちの夜」より。 ドイツ国防軍として実際に前線に出た東プロイセン出身のハンス・ヘルムート・キルスト原作。また、ハリウッド作品ながら、出演者は全てイギリス及びヨーロッパの俳優であり、そのことが本作に一種独特の雰囲気を与えているのは、間違いない。 舞台は1942年、 と後世に評される、ナチス・ドイツに根