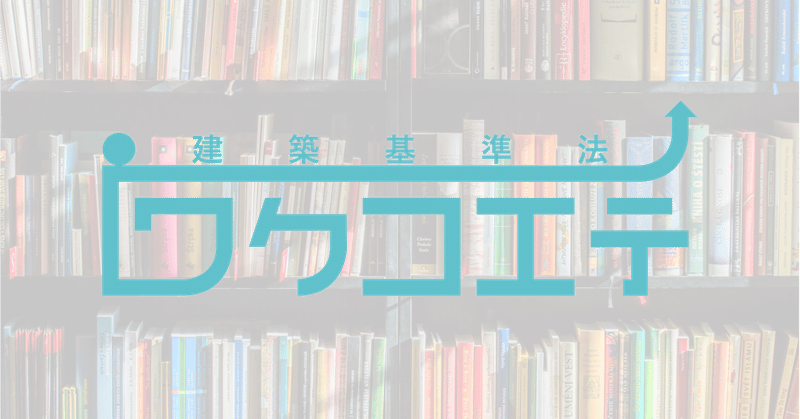
【コラム】避難安全検証法は処方箋にもなるし、毒にもなる
先日、既存建物の相談をうけました。
竣工時は倉庫単独であり、現在は倉庫ではなく違う用途で使われてしまっており排煙設備、歩行距離の規制に適合していない、という趣旨のものでした。
大体既存建物の相談には避難規定が問題として浮上します。
(最近そんな記事ばっかり書いている気がします、、)
大型の物流倉庫であっても倉庫部分であれば、「居室」ではなく「室」に該当しますので、告示1436号ー四ー二ー(1)によりある一定の区画を設けることによって排煙設備を設けることなく、これら規定を成立させることができます。「室」であれば歩行距離の規制は非該当になります。
余談ですが、倉庫という用途であっても検品等の作業が発生する場合は「居室」に該当するケースもありますので、実際の使われ方をしっかり確認しましょう。
竣工後、その倉庫を「居室」として利用する場合、告示1436号をうまく活用できればいいのですが、もともと大空間であった倉庫を活用する場合、ある程度の大空間の居室スペースとして利用する計画も多いかと思います。
「しかし、既存の倉庫には排煙設備が設けられていない!」
ここで処方箋としての役割を果たすのが「避難安全検証法」です。
検討の詳細は、解説書等を参考にして頂きたいのですが、ザックリ言えば「煙にさらされる前にそこにいる人がその居室/区画/階/建物から避難できるか」ということを検証を行うというものです。その検討を行うことによって排煙設備や歩行距離等の規定が緩和(トレードオフ)されます。
倉庫等は天井が高く、蓄煙量が多くなるため避難時間を確保しやすく、避難安全検証法とはとても相性が良い。今回の遵法性が確認できなかった部分は「階避難安全検証法」を検証することで遵法性が確認できました。
では、すべての排煙設備が成立されていない案件について、避難安全検証法を使えば成立するのか、という疑問が生じるかと思いますが答えは「NO」です。例えば階避難安全検証法であれば、すべての居室においてその在館者が煙にさらされることなく避難を行えるかという検討、また階全体の在館者がその階のすべての火災室の部分で出火しても避難することができるか、という検討を行います。そうなるとプラン的に成立しない部分やそもそも避難安全検証法を使用することが出来ない用途等に該当し成立しないケースもあります。
また「避難安全検証法」の検証するにはある程度のノウハウが必要となります。計算式は告示(ルートBの場合)にありますが、その告示だけ読んでもこの検討を行うことは困難ということが分かるかと思います。
最近多いやり方としましては、検証法を専門とされているいわゆる「防災屋」さんにアウトソーシングされることも多いようです。ソフトウェアも市販されていますので、頻度が多い方は購入して内製化するのもいいかもしれません。
最後に簡単に「毒」の部分について。
「避難安全検証法」を活用した案件に関しては、簡易な間仕切り変更を行う際も、その遵法性を容易に確認することができません。要は間仕切りを変更するたびに検討をし直さなければならないということです。
それが顕著なのが「工場」案件です。工場は生産施設ということもあり外部に窓等を設けること困難のケースがあります。また天井高さもある程度あるのであらかじめ避難安全検証法にて検討されているケースが多いです。しかし工場は生産ラインが変わったり、増築が行われたり、その後の改変が多くそれをケアしきれていない施設が多くあります。間仕切り変更だけであれば確認申請が伴わない為、その遵法性を問われることがないため、検証法の検討を無視して変更されてしまっている、それら状況が増築を行うときに明るみなるという事態はよく聞く話です。
このように「避難安全検証法」は問題を解決することもできる、という処方箋として活用できる反面、それを継続してケアしていくことにはノウハウが必要、またそれを行わないと違反という毒の部分もある、ということをお伝えいたします。
===========================
建築基準法に関するコンサルティングサービス一覧はこちら
===========================
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
