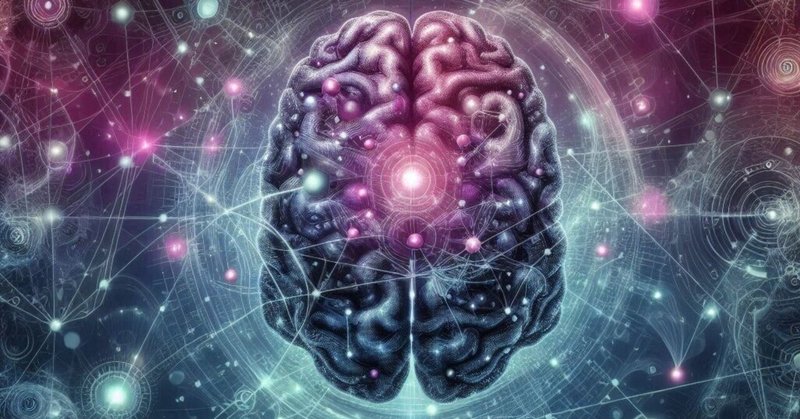
自由意志に対する研究まとめ
概要
グーグルで「意識 仮説」などと検索すると「受動意識仮説」の記事が大量に引っかかります。しかし、意識を単に受動的な現象と捉えるような見方は必ずしも意識研究の主流ではありません。
以下では意識研究の中でも「自由意志」に対する研究に絞り、主な研究や仮説を年代別にまとめます。
1960年代
ウォルター・ミシェル (Walter Mischel)「人間の意志決定に無意識的要因が関与することを示唆する実験的研究(Delay of gratification experiments showing unconscious influences on decision making)」
報酬を先延ばしする実験を通じて、意志決定における無意識的影響を示しました。
1980年代
ベンジャミン・リベット (Benjamin Libet) の実験
脳波計測により「準備電位」を発見、意識的な意志決定に先立って無意識的な脳活動が生じている証拠を実証しました。
現代の自由意志研究はすべてこの研究から始まったと言っても過言ではありません。大変重要で衝撃的な研究です。
デビッド・ロスキー (David M. Roske) 「意識の多重ドラフトモデル (Multiple Drafts model of consciousness)」
意識は一時的で並列的な「ドラフト」の集まりであり、意識内容は瞬間瞬間で「編集」され、再解釈される、というモデルを提唱しました。
この考え方は、意識が単一の同期したプロセスではなく、動的で分散された性質を持つことを示します。自由意志についても、意識化の並列処理から生じる一時的な産物として捉えられることになります。
1990年代
ダニエル・ウェグナー (Daniel Wegner) 「思考による行為モデル(Thought-Induced Constraint on Action)」
無意識が行為のきっかけを作り、意識的思考がそれに「制約」を加え、行為をある程度ガイドすることで、我々は自分の意志で行動したと「錯覚」する、としました。
2000年代
ダニエル・デネット (Daniel Dennett) 「随伴起源の自由(Concept of "Freedom Evolves" (Willusional free will arising from evolutionary processes))」
自由意志が進化の産物であり、意識的な認知プロセスからではなく、むしろ無意識的なプロセスから生じてきた、という独自の見解を示します。
自由意志は錯覚であるが、その錯覚自体が進化的に有利に働いた、とします。
マイケル・ガザニガ (Michael Gazzaniga) 「ヴェトー仮説(Veto hypothesis)」
意識と無意識の相互作用によって自由意志が形作られるというモデルを提案しました。
まず、無意識的な過程が潜在的な行為の選択肢を生成し、並列処理によって優先順位がつけられます。そして最も優先順位の高い選択肢が意識に顕在化します。
ここで、意識はこの選択肢を「承認する」か「ヴェトーを入れる」か決定できる、とします。ヴェトーを入れた場合、次に優先順位の高い選択肢が顕在化します。
そして最終的に承認した選択肢が、行為として実行されます。
つまり、無意識による「提案」に対し、意識が最終的な「許可/拒否」を行う、という構造です。
この仮説は脳分離症候群の研究などから導き出されました。
マイケル・コーエン(Michael S. Cohen)「大脳皮質-線状体-視床回路モデル(Cortico-basal ganglia-thalamic" neural circuit model)」
自由意志がどのように脳内の神経回路によって生成されるのかを説明しようとしました。
具体的には、
・大脳皮質:様々な行為選択肢が並列して表象される
・線状体:これらの選択肢を統合し、優先順位付けを行う
・視床:優先度の高い選択肢を大脳皮質にフィードバックし、意識化する
・大脳皮質:意識に上った選択肢に対して「承認/拒否」を下す
・承認された選択肢が、運動野を経て実行に移される
このモデルでは、自由意志を神経回路の動的なプロセスとしてとらえ、脳の各部位の相互作用に着目しました。無意識と意識の両方のプロセスが関与する自由意志の神経基板を提示しています。
チューン・スーン (Soon Chun) の機能的磁気共鳴画像診断(fMRI)実験
機能的磁気共鳴画像診断(fMRI)の研究により、意識的な決定に先立つ無意識的脳活動の存在を実証しました。リベットの実験結果の正しさを立証すると共に、さらに詳細な無意識的活動のタイミングと局在を明らかにしました。
さらに、この無意識的な活動パターンから、被験者が後に選択する行為を高い確率で予測できることも明らかにしました。
2010年代
デヴィッド・M・ローゼンタール (David M. Rosenthal) 「意識の高次思考理論(Higher-Order Thought" theory of consciousness)」
ある精神状態が意識的になるためには、その状態自体に加えて、その状態に対する「高次の思考」が必要だと考えました。
意識は何らかの内省的なプロセスが関与することで生じると考えます。
パトリック・ヘイウッド (Patrick Haggard)「ナラティブ統合モデル(Narrative Integration)」
脳内の複数のプロセスの出力を意識が統合することで意志決定が形作られるとしました。
具体的には、
・行為選択に関わる様々な脳内プロセス(運動準備、注意、記憶、価値判断、等々)が並列して進行する
・これらのプロセスから出力された断片的な情報が集積される
・意識は、これらの情報の断片を時系列的に統合し、ある種の「ナラティブ」を構築する
・この主観的なナラティブが、意識的な意志決定の体験となる
すなわち、意識下の複数のプロセスの出力が、意識によって一つの物語(ナラティブ)にまとめ上げられることで、意志決定の一貫した体験が生じるとします。
このモデルは、脳損傷患者の症例などから導き出されました。意志決定は単一の同期したプロセスによるのではなく、分散した情報源の統合によって形作られる動的なプロセスである、と考えます。
ジョン・マーティン・フィッシャー (John Martin Fischer)「直面性(Concept of "Modest Libertarianism" and "Actual-Sequence Incompatibilist" view)」
自由意志と決定論の両立可能性について、独自の解釈を行いました。
行為者が複数の選択肢に「直面」し、それに情報が適切に与えられ、かつそれについて熟考できるとき、制限された意味での自由意志が生まれる、としています。
まとめ
「意識によるトップダウン指令」という自由意志の形は、リベットの実験によって否定された。これが現代自由意志研究の幕開けである。
無意識による「提案」がまず先に起こる。
意識は無意識の「提案」に対して、「承認/修正/否定」などのフィードバックを行う。
この無意識と意識の動的な相互作用が、意志決定を形作る。
このような考えが主流の見解として共通すると考えられる。
意識と無意識がどの程度関与するか、相互作用の詳細など、研究によって見解の違いはある。
関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
