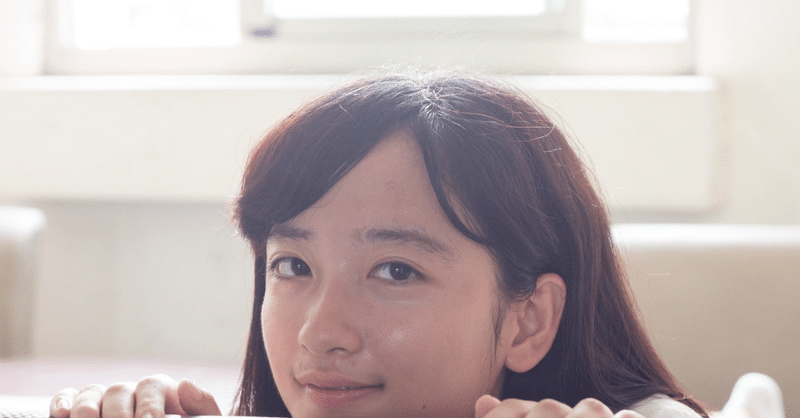
【推理しない探偵小説】探偵里崎紘志朗 shiny day(1/2)
■
春だ。
今日から春、と主張してくるような陽気。
午前10時。朝から気分がいい。
私は、事務所兼住居である東京・神谷町のビルでコーヒーを点てていた。
毎朝、神谷町から皇居まで走る。皇居ランナーと一緒に外堀を走り、1周して帰ってくる。
エレベーターを使わずに、外階段を使い、4階の事務所へ帰る。その後部屋で、ウェイトトレーニングをみっちり2時間やり、ストレッチをやって、終わりにする。
その後、シャワーを浴び、髭を剃り、服を着る。
朝食は、多め。キッチリとバランスをとる。
食事を終えて、今はコーヒーを点てている。
私はコーヒーが好きだ。あまり摂り過ぎると、カフェインが悪影響を及ぼすのは分かっている。
しかし、コーヒーだけはやめられない。
豆にはこだわる。今は、清澄白河で見つけたコーヒー焙煎専門店のオリジナルブレンドがお気に入りだ。
ネルドリップで1杯分。
ゆっくり時間をかけ、コーヒーを入れる。
インターフォンが鳴った。
来客の予定はない。
インターフォンの画面を見た。
小学5、6年生だろうか?
どこかの私立学校の制服を着ている。
「どちら様ですか?」
「あなた、探偵?」
「そうですが…」
「お母さんを捜してくれる?」
「お母さん?お母さんがいなくなったんですか?」
「そう。」
「いつ?」
「一昨日。」
「一昨日…警察に届けは出しましたか?」
「警察には行きたくないの。」
「何故?」
「どうしても。」
「探偵を雇うにはお金がかかるんだよ。お父さんと一緒に来なさい。」
「お父さんはいない。お金ならあるわ。」
少女には、強い意志が感じ取られた。
私は、ビルのエントランスのロックを解除した。
「4階。412号室。」
少女はビルに入り、エレベーターに乗った。
■
少女は、机越しに置いてある依頼人用の椅子に腰かけた。
小学生は間違いない。ランドセルがある。
でも、それがなければ小学生だと言い切れないような雰囲気の子だった。
まず、背が高い。おそらく160㎝は超えているだろう。
大きな二重の目。シャープな顎のライン。メイクアップすれば、ティーンエイジャーと言っても良いのではないか。
それほど、美しく大人びた女の子だ。
私は自分の椅子に座り、彼女が自分の居心地の良い姿勢になって、私の顔を見るまで、黙って彼女を観察していた。
「何か、おかしい?」
「ん?」
「どうして、私の顔を見てるの?」
「いや、大人びた子だな、と思って…」」
「そうかも。普通の小学生とはちょっと違っているかもね。それで、お母さんを捜してほしいの。出来る?」
「出来るかどうかは、今は分からない。詳しい話を訊いてみないとね。君、名前は?」
「舞岡亜理紗。」
「いくつ?」
「11歳。今度の5月で12歳になるわ。」
「小学6年生?」
「そう。」
「学校の名前は?」
「何で、私の事ばかりを訊くの?お母さんの事を訊いてよ。」
「君の事をまず訊くのは、君がそこに座っているからさ。話す相手が何者かをハッキリさせないと、依頼内容を信じる事ができない。いいかい?」
「分かったわ。」
彼女の学校は、幼稚園から大学までエスカレーターで進めるミッション系の名門女学校だった。
「クラスは?」
「6年A組。」
「担任の先生の名前は?」
「川村勇作先生。」
「後で学校に電話をかけて、全部確認する。いいかい?」
「私が話したと学校にバレないと約束するなら、いいわ。」
「どうして、バレたらまずいんだい?」
「今日、学校をずる休みしたからよ。バカね、そんなことも分からないの?」
「いやあ、すまんすまん。分かったよ、学校にはバレないようにうまく話すよ。これでいいかい。」
「上手くやってくれるなら。」
「分かった。約束するよ。」
「お願いよ。」
「じゃあ、君のお母さんの事を訊こうか。お母さんの名前は?」
「探偵さん、舞岡いずみって、知ってる?」
「舞岡いずみ?あのミュージカルスターの?」
「そう、よく知ってるわね。探偵やってる人って、ミュージカルなんて興味なさそうなのに…」
「それは偏見だね。僕は音楽は好きだよ。特にジャズ。」
私は、仕事がない平日の夜、よく六本木のジャズクラブでピアノを弾く。
「舞岡いずみさんは、ジャズの名曲を集めたアルバムを出したことがあるだろう。だから余計に知ってる。」
舞岡いずみは、有名なミュージカル女優。日本有数のミュージカル劇団で初舞台を踏み、初めてヒロインを演じたミュージカルで高い評価を受け、独立。今では舞台、テレビ、映画で活躍している。
年は多分私と同世代、40代半ばぐらいだろう。
「君はその舞岡いずみさんの娘なのか?」
「そう。」
「という事は捜してほしいのは、舞岡いずみ?」
「そうよ。」
「そうだとすれば、僕の出番はないね。彼女ならマスコミが黙っていないだろう。彼女ほどの大スターがいなくなってるんだぜ。日本中が大騒ぎするはずだよ。警察に連絡しなさい。」
「だから、それはできないの。」
「お父さんは?間違いなければ、お父さんはプロ野球選手だよね。」
「今年の初めに離婚したけどね。」
舞岡いずみの夫、矢崎真也は、東京のプロ野球球団の元スター選手。数年前まではクリーンナップを打ち、1500安打は達成したはずだった。守備はライトで、強肩。足も速く、これまでのキャリアで2度、トリプルスリーをやっているほど。しかし、2年ぐらい前に守備で膝に大怪我を負い、それからはずっとリハビリ中のはずだ。
勿論、今期もまだ、1軍の試合に出場していないはず。彼もまた、40歳を過ぎており、選手としてはピークを過ぎている。
「離婚したのか?ニュースにはならなかったね。で、君は舞岡亜理紗なんだ。」
「そう。」
「でも、離婚したとはいえ、お父さんは東京にいるんだろう?相談できないのかい?」
「出来ないんじゃない。したくないの。」
「理由は?」
「お母さんがいなくなったことに、お父さんがかかわっていると思うからよ。」
「詳しく聞こうか。コーヒー飲む?」
「コーヒーなんて、身体に悪いわ。飲み物、他に何があるの?」
「牛乳、水、炭酸水、グアバジュース、プロテイン。」
「グアバジュースをいただくわ。」
私は、自分の分のコーヒーと彼女のグアバジュースを取りに、隣の居住スペースにあるキッチンへと向かった。
■
コーヒーを新しく点てるのに多少時間がかかった。
コーヒーと彼女のグアバジュースを持って、事務所の部屋に戻ると、彼女は私の椅子に座っていた。
「何をしているんだ。そこは君の場所じゃない。自分の椅子に座ってくれないか?」
「探偵さん、ピストル持ってるの?」
「持ってないよ。知ってるだろう。日本じゃあ、警察官以外はハンドガンの携帯は許されていない。」
「じゃあ、引き出し全部にカギがかかっているのは何故?」
「引き出しを開けようとしたのか?悪い子だね。僕の仕事は、依頼人の秘密を守らなければならないことが多いからね。用心のためさ。」
「ピストル持ってなくて、どうやって敵と戦うの?」
「敵?敵なんていないよ。僕は人探し専門だぜ。戦わなければならなくなることは少ない。」
「少ないって、たまにはあるの?」
「時々ね。」
「その時は、どうするの?」
「目をつぶって、当たれって祈りながら拳を出すのさ。ビビりながらね。」
「嘘ばっかり…いいわ。それで。」
亜理紗は自分の席に戻った。
私は彼女にグアバジュースが入ったグラスを手渡した。
やっと、自分の席に戻った。
コーヒーをまず、1口。
美味い。
「それじゃあ、訊こうか?一昨日、何があったんだい?」
「夜遅くにお父さんが来たの。離婚して家を出ていってから初めての事よ。」
「何時ぐらい?」
「分かんないけど、真夜中。」
「それで?」
「私は、寝てたの。夜まで、稽古があったから、もうへとへとで。」
「稽古?」
「あっ、私もミュージカルに出るのを目標にしているの。その日は、夕方からダンスのお稽古。」
「そう。それで、お父さんが来たの、いつ気がついた?」
「なんかの物音がして、目が覚めたの。部屋を出たら、お母さんの部屋のドアが少しだけ開いてて…お母さん、起きてたの。誰かと小さい声で話しているのが聞こえてきて…」
「それがお父さんだった?」
「私、何だか見てはいけないものを見ているような気がして…ドアの隙間から見てたの。」
「そう。それで?」
「そしたらね、何だか甘い匂いがしてきたの。何かが焼けて甘い匂いを出しているような…」
「匂い?何が焼けているようだと思った?」
「分からない。でも、甘い匂い。」
「ベッドにいるお母さんが見えたわ。お母さんの顔の下半分が急にキラっと輝いて。」
「顔が輝いた?どんな風に?」
「何かが光に反射しているような感じ。」
「光って、ベッドサイドのライトとか?」
「そうだと思う。でね、お父さんが、お母さんにごめん、ごめんって、謝りだしたの。」
「謝る?何について、謝ったんだろう?」
「分からない。でも、泣きながら、ごめん、ごめんって。お母さんは、いいのよ、って言って。」
「泣いたのか?何故だろう?」
「分からないわ。お父さんが泣くとこなんて、初めて見たもの。」
「そうか。それで二人はどうしたんだい?」
「お母さんが、ルームウェアを着替えて、二人で出ていった。」
「それから、ずっとお母さんが帰ってこないんだ?」
「そう。」
「何で、お父さんに尋ねないんだい?」
「何だか怖くて…」
「なるほど。」
「ねえ、引き受けてくれる?お母さんを捜すの。」
「まずは、お父さんに会おう。」
「えっ?」
「僕の料金を支払ってもらわないといけない。」
「だから、それは私が出すわ。お小遣いならいっぱいもらってるから。」
「子供からお金はもらえない。」
「何で?」
「それが僕の主義だからさ。大体、お母さんの行方はお父さんだけが知ってると思う。そう思わないか?」
「思うわ。」
「だったら、お父さんに直接聞くのが早い。経費の請求の話もね。」
「分かったわ。じゃあ、行きましょう。」
「どこへ?」
「お父さんのいる2軍の練習場。」
「君も来るのか?」
「探偵さんも一緒なら、怖くないもの。」
「お父さんは、前からずっと怖いと思っていた?」
「ううん。普段はとてもやさしいお父さんだわ。今回だけちょっと怖い。」
「なるほど。でも、今日は僕だけで会うよ。君は家に帰ってなさい。電話番号を教えてくれるかな。会った後で電話で、報告するよ。」
「報告?」
「探偵の義務だ。」
■
彼女は、グアバジュースを飲み干し、「ごちそうさま」と言い、私に自分の携帯の番号を教え、「ホントはLINEの方がいいんだけど…」と言った。
私は、「中間の報告は口頭に限っている。」と説明し、何とか納得させた。
そして、「電話を待ってる」と、何度も言い、オフィスを出ていった。
私は一人になった。
部屋にはなんとなく彼女の髪の匂いが残っていた。
私は、自分の椅子に座り足をデスクに投げ出して、残っているコーヒーを飲んだ。コーヒーはすっかり冷めてしまっていた。
まず彼女の学校へ電話して彼女の話の裏づけを取った。彼女の言う通りだった。その後、次の行動について本格的に考え始めた。
彼女の話から、父である矢崎真也が、母である舞岡いずみに覚せい剤を焙って嗅がせたのは間違いないと思う。
顔の下半分がキラキラと輝いたのは、焙っているアルミフォイルを鼻に近づけたせいだろう。
問題は、何故離婚して暫く家に来たこともなかった矢崎が、真夜中に突然現れ、いずみに覚せい剤を嗅がせたのか?という事になる。しかも、いずみだけに嗅がせた。
自分は、泣きながら「ごめん、ごめん」と言って…
何故だ?
分からない。
仮説を色々と構築してみようとしたが、それにはあまりに証拠が足りない。
私はあきらめて、出かけるために上着を取りに居住スペースに向かった。
■
ダークブルーのジャケットを着た。
トラウザーズは、ライトグレー。オフホワイトのベスト。黒のウィングチップ。
これで何とかスポーツ記者に見えるようにと願った。
ジャケットにトラウザーズ。
日本では、そのような格好で歩くと誰にも怪しまれない。
街に溶け込んで見えなくなる魔力があるのだ。
準備はできた。
矢崎真也に会いに行くため、私は部屋を出た。
■
外に出ると、私はくすんだ水色のスプリングコートを羽織った。まだ、コートなしでは些か寒い。
「探偵さん。」
エントランスの陰から亜理紗が出てきた。
「まだ、帰っていなかったのかい?」
「だって、今ごろ帰ったら、君島さんにバレちゃう。」
「君島さんって?」
「うちのお手伝いさん。とっても怖いの。ねえ探偵さん、やっぱり私も連れてって。私が一緒なら球場が顔パスになるし。」
「それはできないよ。お父さんとは僕だけで会う。」
「何故?」
「仕事柄、つじつまを合わせるために細かく嘘をつくからさ。」
「もっともらしい感じで?」
「そう。子供の前で嘘はつけない。」
「何で?」
「嘘はつかない方がいいからさ。」
「じゃあ、連れていくだけ連れてって。お父さんとは探偵さんだけで会っていいから。」
「仕方ないな。じゃあ、来なさい。車で行こう。」
私は電車を乗り継ぎ、2軍の練習場を目指すつもりでいた。
しかし、制服を着た小学生を連れて、平日の電車には一緒に乗れない。
どんな変態扱いされるか、分かったもんじゃない。
ビルの地下の駐車場へと向かった。
■
私は車が好きだ。
いろんな国の色んな車に乗ってきた。しかし最近では、専ら日本の車ばかり乗り継いでおり、今は、日産の電気自動車に乗っている。
亜理紗に後部座席に乗るように指示をした。
スタートボタンを押す。
動いているのか、どうかも分からないような静かさ。
滑るように動き出し、ビルのスロープを音もなく登る。
霞が関から首都高に入り、3号渋谷線から東名高速へと乗り入れた。
高速に入り速度が上がると、車は独特のキーンという音を出す。
ジェット機に乗り、音速で空を滑っているような感覚。
不思議なドライブを楽しみ、私は球場に向かった。
後部座席では、亜理紗はずっとスマホを見ていた。
■
2軍の練習場は、東京近郊にある。
私は、球場に隣接する駐車場に車を止めた。
「着いたの?」亜理紗が訊いた。
「そのようだね。寝てた?」
「この車のせいよ。静かすぎるんだもん。寝ちゃうわよ。ねえ、探偵さん、お腹が空いたんだけど…」
「そう、じゃあ、何か食べるといい。あそこにレストランがある。」
球場と反対側、道沿いにレストランがある。
「僕も一緒に行こう。それで、君が食べるものをオーダーしたら、僕は球場に行く。君はレストランで食事をして、その後は車で待ってる。OK?」
「OK。」
2人で歩いてレストランに向かった。
昼時を少し過ぎているせいか、レストランには客がいなかった。
愛想のよい女店主らしき人が、オーダーを取りに来た。
「食事は娘だけがします。僕は球場にちょっと用があるので、このまま向かいます。」と私が言った。
「分かりました。結構ですわよ。なんなら、お父さんが用を済ませている間、うちで待っててもいいわよ。」
娘? 亜理紗が僕の顔を見て、意地悪く微笑んだ。
子供の前じゃあ、嘘はつかないんじゃなかったっけ?
TPOによるよ。
「いいんですかあ?じゃあ、そうします。私、ボンゴレビアンコと、レモネード。」
「レモネードは食事と一緒?それとも後?」
「一緒でいいです。」
私が言った。「じゃあ、代金を先に払っておきます。」
「そう?じゃあ、入口のレジで。」
私は席を立った。亜理紗に「終わったら電話するから僕からの電話はできるだけ早く出てほしい。」と伝えた。
「分かったわ。パパ。」
ちくしょう。
私はレジで代金を払い、球場に向かった。
■
球場の関係者用通用口の管理は厳重だった。
記者は皆、専用のIDパスを首からぶら下げていたし、お互い顔馴染みのようで、私が付け入る隙は全くなかった。
そこで、私は奥の手を使った。
ただ2軍選手の練習を見に来た一般の熱狂的なファンのように、外野の芝生席に入り込んだのだ。
春の野球場。天然芝が青々と茂り、土と絶妙なコントラストを描いている。
芝生が吸った陽光の照り返しが眩しい。
気温はおそらく17℃ぐらい。日差しが暖かい。
グランドの中を見渡した。
今は守備練習の真っ最中のようだ。
外野と内野の連係プレーの反復練習をやっている。
ノッカーの檄が飛ぶ。
外野手が右へ左へと走り回り、捕ったボールを素早くカットマンに投げ返す。カットマンはそのボールをサードへ。ランナーとクロスプレー。
練習ながら、本番さながらの緊張感がグランドの中に漂っている。
3塁側のファウルグランドの辺り、目指す19番を見つけた。
矢崎真也、背番号19。30代半ばで2千安打を達成すると目されてきたスラッガー。
彼はフェンスに取り付けたゴムチューブを足に巻き付け、足を上下に動かしていた。
私は、3塁側のスタンドへと向かった。
「矢崎さん。」
練習中。私の呼びかけは聞こえないかのように無視。
「里崎と言います。亜理紗さんから頼まれてきました。」
「亜理紗?どういうことですか?」矢崎がやっと、私の方を向いて言った。
「少し二人だけでお話しできませんか?5分で済ませます。」
「分かりました。このメニューは後15分ぐらいで終わります。そしたら、球団広報にあなたを迎えに行かせます。お名前は、里崎さんで良かったですね。」
「そうです。里崎紘志朗。探偵です。」
■
どこからか、トウモロコシを焼く醤油の香りが漂ってきた。
腹が減ったな…
無理もない。午後2時。今日は、ルーティーンが守れない。
芝生に腰を下ろし、バッティング練習を見ていると、後ろから声をかけられた。
「里崎さんですか?」
振り向くと、球団のスタジアムジャンパーを着た、ひょろっとした青年がいた。ジャンパーが、1サイズ大きすぎる。
「そうですが」
「うちの矢崎選手がお呼びです。ついてきていただけますか?」
選手は球団職員にとって、偉いのだろう。変な日本語だ。
「もちろん。」
ぶかぶかジャンパーの青年の後をついて、球場の中に入った。
応接室とあるドア。
「こちらの中でお待ちください。矢崎選手は間もなく来られるはずですから。」
「分かりました。ありがとう。」
私は部屋の中に入った。
安い応接セット。お尻が痛くなりそうなソファーに腰かけた。
窓の外はグランドだが、ここにはブラインドがあり、何故だか今は全部閉まっている。
?
背中に殺気。
横に飛び込んだ。
ガシャコン!!!
ソファの背もたれにバット。背もたれは砕け、もう誰の背中も支えられないようになった。
矢崎だ。彼は真っ赤な顔をして、私を睨みつけている。
私はジャケットの内ポケットから伸縮する特殊警棒を出した。
振り回されるバット。まともに頭に当たったら死ぬ。
「矢崎さん‼矢崎さん‼落ち着いて、落ち着いて。」
「何だあ!お前はあ!亜理紗をどうしたんだ!」
バットが迫る。警棒でうまく払い落とした。
カランカラン。床を転がるバット。
「私は探偵です。亜理紗さんに今朝雇われました。」
「亜理紗があんたを雇っただって?何でだ?」
「お母さんを捜してほしいって。あなたの奥さん、舞岡いずみさんを。」
「亜理紗が…」
矢崎は腰から床に崩れ落ちた。
「やっぱり、やっぱり無理だ…やっぱり」
「何が無理なんですか、矢崎さん?」
「明日、発表する予定だったんです。」
「発表って、何を?」
「やっぱり。やっぱり、僕にはできない。いいでしょう。里崎さん、本当の事を話しましょう。いずみにも会わせます。今から出かけます。」
「どこへ?」
「いずみのいるところへ。いずみと一緒に本当の事を話します。亜理紗に伝えてもらいたいんです。」
「分かりました。参りましょう。」
■
矢崎は、「ちょっとしたドライブになる。」と言った。
私は「自分の車があるので、矢崎の車の後をついて行く。」といい、球場前で待ち合わせをすることにした。
私は亜理紗に電話した。すぐに車に戻るようにと伝えた。
車に着くと亜理紗がいた。
経緯を話し、しばらくは後部座席で体勢を低くしているようにと指示をした。
亜理紗はフロアに蹲った。
後部のウィンドウは、薄くスモークガラスになっている。
走り出せば、見つかる心配はないだろうと判断した。
矢崎の車は球場前に止まっていた。レクサスのSUV。ガンメタリックのシルバーだ。
矢崎が運転席から顔を出した。
私は矢崎に後部座席が見えないように矢崎の車の後についた。
「じゃあ、出かけます。東名に乗ります。」
「どこへ行きますか?」
「伊豆です。」
レクサスは滑らかに走り出した。
私の車も音もなく発進した。
亜理紗はフロアで体を小さくしながら、何故だか小刻みに震えていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
