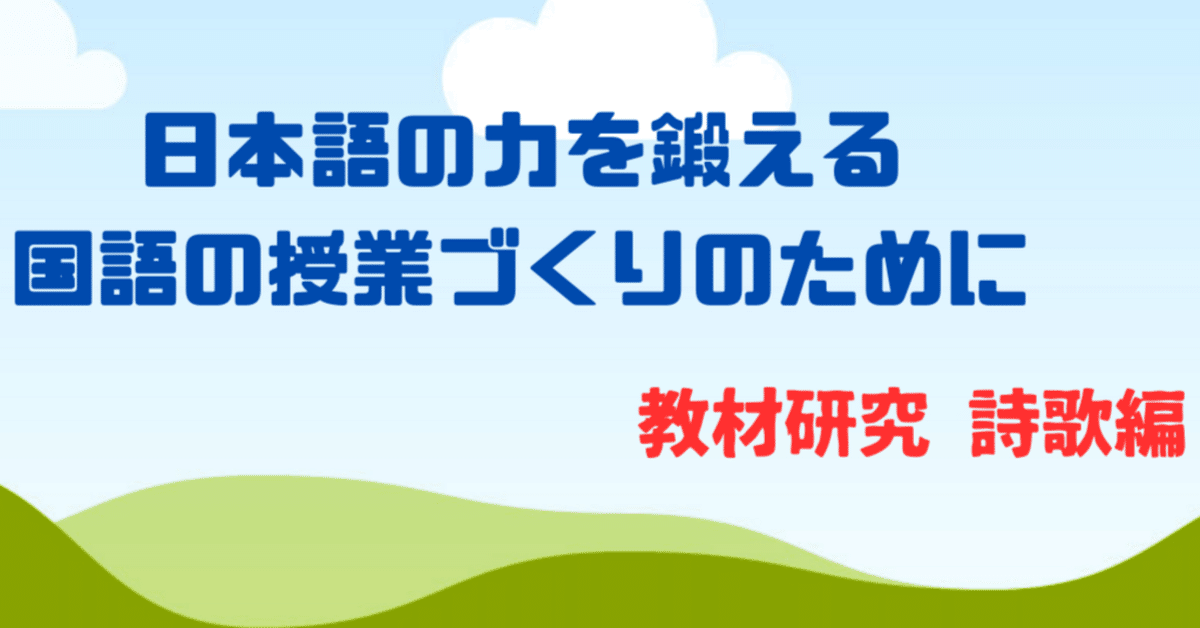
短歌を読む 2 くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の針やはらかに春雨のふる(正岡子規)
『竹乃里歌』の明治33年「庭前即景(四月廿一日作)」10首中の一首である。
三省堂の中学2年の教科書「短歌十首」、東京書籍の中学2年の教科書「短歌五首」に収められている。
子規の歌としては、よく知られたものの一つである。
1 句切れなし ―― 歌の構成を読む
まず、どのようなことをうたっているのか、歌意を考える。
某社の教師用指導書には、次のようにある。(以下、便宜上A~Dとする)
A くれないの二尺ほど伸びている薔薇の新芽のまだ柔らかなとげにしっとりと春雨が降り注いでいる。
次いで、私が持っている短歌の鑑賞辞典数冊から引用する。
B 冬を超えた薔薇の茎から新芽が力強く伸びている情景を詠んでいる。紅の色の新芽は驚くほど太い。それが二尺の長さもあろうと思って眺める喜びは大きかったであろう。真直ぐに伸びている芽は紅であるが、やがて緑の色に変わる堅い針もまた今は紅で、いかにも柔らかい感じである。そして折からの春雨に濡れてみずみずしい。
C くれないの二尺ぐらいに伸びた薔薇の新芽のやわらかな針(とげ)に、春雨がしとしととやわらかに降っているよ――というのである。
D 紅に二尺ばかりにも伸びた薔薇のやわらかな新芽に春雨がしとしとと降りそそいでいるという情景をとらえたものである。
Aは、歌の順序に言葉を並べているので一見わかりやすいように見えるが、そのために言葉の係り受けが曖昧になっている。「二尺ほど伸びている」のは「薔薇」なのか、それとも「薔薇の新芽」なのだろうか。また「やはらかに」を「まだ柔らかなとげにしっとりと」と工夫していることはわかるが、「やはらかに」は春雨にはかからないのだろうか。
Bで気になるのは、「それが二尺の長さ」の「それ」が何を指しているのかということである。「新芽」なのか「薔薇」なのか。素直に読めば「新芽」を指すようにも思える。しかし、どう考えても新芽が二尺もの長さになっているというのはおかしい。
CもAと似て、歌の順序に言葉を並べており、係り受けがわかりにくい。
Dも「紅に」としたことで係り受けをわかりやすくしようとしたことは理解できるが「薔薇」なのか「新芽」なのかはっきりしない。また「やはらかに」を春雨にだけかけている点が不満である。
この歌に限らず歌の解釈には、しばしばわかったようでよくわからない表現が見られる。何となく理解するというのであればそれでよいのかもしれないが、少なくとも国語の授業においては、いい加減な解釈で済ませては子どもたちの言葉の力を鍛えることはできない。
初句「くれなゐの」は、どこに掛かるのか。「くれなゐの」は、「芽」に掛かっていく。このことに異論はないと思うが、念のために確認しておこう。
薔薇の茎と解釈しているものもあるが、「くれなゐの」薔薇といえば、私たちがまず思いうかべるのは薔薇の花であろう。くれなゐの薔薇の茎というのであれば、茎を明示しなくては読み手にはわからない。そうなるとくれなゐの薔薇の芽と解釈するのが自然といえる。
二句「二尺伸びたる」は三句の「薔薇の芽」に掛かる。ここで問題なのは二尺伸びているのは「薔薇」なのか「芽」なのかか。二尺といえば約60センチ、既に述べたように芽の長さとしては長すぎる。そうすると「二尺伸びたる」のは薔薇の枝であり、そこに芽があると考えるしかない。三句から四句にかけての「芽の針」とは、薔薇の芽の中にやがてはとげになる針の子どもがあるのだ。
このように考えてくるとこの歌は、次のような意味ととれる。
二尺ほど伸びている薔薇の枝にある、くれない色(鮮明な赤色)の芽の中にある針が「やわらか」で、そこに「やわらかに」春雨が降っている。
このように考えてくると、「やはらかに」がこの歌の解釈の要とわかる。句切れはない。ないのだが、「やはらかに」の前と後が大きく変わっており、その変化を「やはらかに」がつなぎ合わせている。「やはらかに」の前では、薔薇の芽の針という非常に微細なところに焦点化し、「やはらかに」の後は針に降る雨から視野を広げて、庭全体に春雨の降る景色を描く。微細な景物と庭全体の景物の二つを「やはらかに」が見事に結び合わせている。
2 「やはらかに」を読む ―― 技法を読む1
前半は、薔薇の芽の針へと焦点化していく。二尺伸びた薔薇の、紅色の新芽、そしてその中にかすかに見てとることができる針。芽が紅色であるのだから、その中にある針も紅色である。
紅という色から語り始めることで、まず鮮やかな印象を読み手に提示する。そして「芽」は、この先の薔薇の生長を当然のこととして予感させる。生長の暗示といってもよい。
針といえば、するどく刺すもの、刺さったら痛みを感じるものである。しかしその針が「やはらか」であるということは、形状としては針であっても、まだ完全には針になっていない。とがっていても、突き刺すかたさはない針として人を遠ざけたり拒むものにはなっていないということである。やわらかな針は触れても痛くはないし、むしろ心地よい感じすらする。その鋭さと柔らかさが共存するところにアンビバレンツな魅力がある。
そして春雨が「やはらかに」降るのである。薔薇の芽に、そして針に、さらには薔薇全体に、そして庭にある木々に春雨がふりそそぐ。「やはらかに」であるから、はげしい降りではない。しっとりと濡れそぼるような降りである。
「やはらかに」が前にも掛かり、後ろにも掛かっていくという二重性を持つところにこの歌の最大の工夫がある。後述する子規の推敲を見ても、それが意図的になされたものだと推察できる。
3 「春雨」を読む ―― 技法を読む2
春雨は、狭義には技法というよりも、文化的伝統といった方がよいのかもしれない。
子規の明治34年の作に次の歌がある。
春雨はいたくなふりそみちのくの孝子の車引きがてぬかも
この場合春雨は、単に春に降る静かな細かい雨をいう。しかし春雨が植物と重ねて歌われるとき、その生長を促すものとしての意味を持ってくる。
『古今和歌集』の春の部に以下の歌がある。
20 梓弓おして春雨けふふりぬあすさへふらば若菜つみてむ
25 わがせこが衣はるさめふるごとに野辺のみどりぞ色まさりける
春雨が降ることで、若菜が生長し、摘むにふさわしいものに生長する。春雨が野辺の草を生長させ、緑の色をより濃くする。言い換えれば、ここでの春雨は植物の生長を促すものとして降るのである。
歳時記でも春雨は、以下のように説明されている。
春雨という言葉は、古くから使われてきた艶やかさ、情のこまやかさをもっている。土をうるおし、草木を育て、暖かさをもたらす雨である。
そのように考えるならば、この歌の春雨も薔薇に降ることによって、薔薇を生長させる。春雨が芽を育て葉を繁らせるのであり、その結果として針もかたく鋭いものとなる。そして、やがてはきれいな花を咲かせる。春雨は、そのような未来のイメージを読み手にもたらす。
4 「の」を読む ―― 技法を読む3
「の」について、先に引用した指導書や鑑賞辞典では以下のように述べている。
A 助詞「の」の多用がリズムを形成する。
B 上句に「の」を重ねて直線的に詠んでいるところにこの作者らしい気力を籠め、「針やはらかに春雨の降(ママ)る」と視点の中心を置いているのが巧みで、気分を集中させている。
C 「くれなゐの……薔薇の芽の」と、上句は「の」音で続けたのびのびとしたリズムを為している。
D 記述なし
それぞれの記述に異議を挟むほどではないが、少し補足したい。
まず、「気力を籠め」「視点の中心」「のびのびとしたリズム」といった表現は、私にはわかりにくい。このような感覚的表現が、短歌をわかりにくくし、一部の人だけのものにしてしまう。
この歌に「の」は4回出てくる。しかし4つ目の「春雨のふる」の「の」は、働きが異なる。文法的には主格を表わすもので、「春雨がふる」と「が」に置き換えても意味は変わらない。
それに対して1~3つ目の「の」は連体的な用法である。これを多用することで、芽の針に焦点化していく。時代は下るが、佐々木信綱の下記の歌も同じである。
ゆく秋の大和の国の薬師寺の塔の上なる一ひらの雲
「やはらかに」の前後で「の」の働きが異なっている。既に述べたように「やはらかに」の前では針に焦点化していき、微細なものを描こうとする。そして「やはらかに」の後は、春雨のふる全景を描く。「の」の働きの違いが、歌の前半と後半の違いを裏打ちしてもいるのである。
それゆえ「の」のリズムをいうときは、「「の」が4つあるね」ではなく、前3つと後の1つの働きの違いを明らかにすることが必要となる。
5 初出との比較
『子規全集』(講談社)によると、この歌が新聞『日本』に発表されたとき(明治33年5月8日)、つまりこの歌の初出は次のようであったという。
くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の針くれなゐにやはらかに春雨のふる
四句が「針やはらかに」ではなく「針くれなゐに」であったというのだ。それが『竹乃里歌』におさめられる際に、現行のようになったのである。このことからも子規による推敲が実に的確に行われたことがわかる。
ここまで書いてきたとき、松山市立子規記念博物館がデジタルアーカイブで子規自筆の『竹乃里歌』を公開していることを知った。それを見ると、四句目の「くれなゐに」の箇所を墨で消し、その横に「やはらかに」と書き込まれており、子規自身の推敲の後がはっきりと確認できるのである。
初出「針くれなゐに」であれば、四句は針を形容しているだけである。初句の「くれなゐの」が芽に掛かかり、その芽の中にある針も当然のこととしてくれなゐである。それを四句でもう一度繰り返すことで、針がくれなゐであることを改めて強調する。しかし、「くれなゐに」はその後の春雨を修飾する言葉にはならない。針から春雨への微細なものから大きな景物への変化とはいえるものの、「やはらかに」のように二つの景物を結びつける働きはしないのである。
「くれなゐに」から「やはらかに」への変更により、二つの景物のあり様を修飾しつつ、見事に二つの景物を結びつける歌となったといえる。
6 歌の主題を考える ―― 鑑賞・吟味する
薔薇の芽の生長をうたっている。芽から葉が生まれ、かたく鋭い針が育ち、蕾ができ、花が咲く。薔薇の芽は生長し、やがては美しい花を咲かせる。いま薔薇の芽に降りそそいでいる春雨を眺めながらも、春雨が薔薇を生長させることを思い描いているのである。薔薇の芽の成長への期待、予感が主題といえる。
すでに見たように「やはらかに」が芽の針と春雨の両方に掛かることで、二つの景物を見事に結びつける働きをしているところに、この歌の最大の工夫がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
