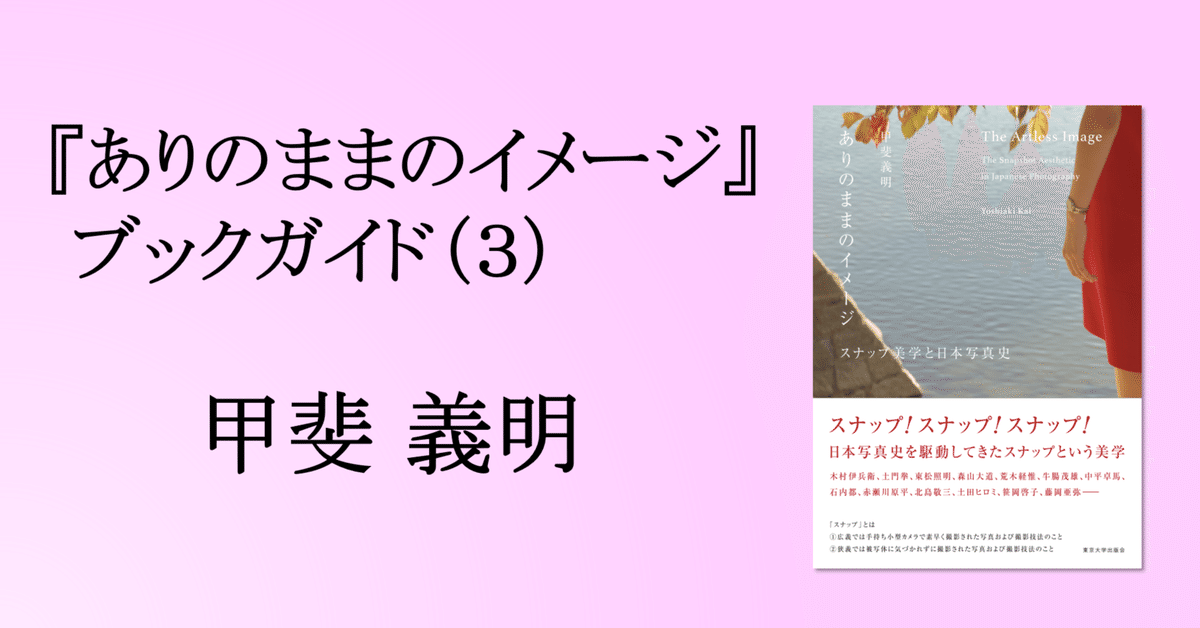
『ありのままのイメージ――スナップ美学と日本写真史』ブックガイド(3)/甲斐義明
甲斐義明『ありのままのイメージ――スナップ美学と日本写真史』の日本写真協会学芸賞受賞の記念も兼ね、甲斐先生に本書に関連する「ブックガイド」を作成していただきました。本書の背景や展開を知るための写真論、イメージ論、視覚文化論等に関する書籍が充実した解説とともに紹介されています。ぜひご一読ください。
[4]美学
4-1:小田部胤久『美学』東京大学出版会、2020年
「技術」(という目的によって根拠づけられた営み)がこうした目的に縛られることなく、「偶然」(という自然の特質)を呈するとき、あるいは逆に、自然(という「偶然」なもの)があたかもそこに〈意図〉を前提とするものを呈するとき、それは「予期せざるもの」である。カントにとって「美しいもの」とはまさにここに成り立つ。
こうしてカントは、美しいものにおいては自然と技術が共存していなくてはならない、と主張する。それは一方で、自然らしさを欠いた技術――規則を常に意識せざるをえず、規則によって縛られている技術――は強制された合目的性として、態とらしいもの(gekünstelt)に堕す、ということであり、また他方で、技術を欠いた自然もまた秩序なき自然として、けっして美しくなりえない、ということであろう。(325頁)
「美学」を『広辞苑』(第7版)で引くと「自然・芸術における美の本質や構造を解明する哲学的学問」と「美しさに関する独特の価値観・こだわり」という二つの意味が挙げられている。美学者の吉岡洋は後者の用法について、「モノや行為について、それが何か特定の目的に役立つという意味での価値、つまり「効用」としての価値ではなく、モノや行為が「それ自体」として持つ価値に注目するような観点のことを、美学と呼んでいるらしいことがわかる」と解説している(吉岡洋「刊行にあたって」、美学会編『美学の事典』丸善出版、2020年、i頁)。
芸術に関する専門書のタイトルで「美学」という語が用いられている場合、多くは「自然・芸術における美の本質や構造を解明する哲学的学問」の意味である。美学と美術史が同一の学科で教えられている大学も多いなか、東京大学文学部では両者は別学科で、私は美術史だったため、美学は学問分野としては長い間「詳しくは知らないが、気になる隣人」といった感じであった。拙著の副題にある「スナップ美学」という複合語は、過去に写真評論家の渡辺勉や重森弘淹らが用いており、私の造語ではない。それらの先例では、「美学」には二番目の意味、すなわち、スナップの美的特質をめぐる価値観という意味が込められている。拙著では先例をふまえたうえで、スナップ美学を「写真媒体の最大の芸術的可能性をスナップに見出す傾向」と定義した(4頁)。したがって拙著のタイトルにおける「美学」は、芸術に関する専門書としてはめずらしく二番目の意味でこの語を用いていることになるが、本の中で行われているのはスナップという技法/ジャンルの美的特質についての考察でもあるので、一番目の意味も兼ね備えている。
「スナップ美学」と良く似た英語に「snapshot aesthetic(s)」(スナップショット・エステティック、もしくは「スナップ写真の美学」)がある。「snapshot aesthetic(s)」は、素人が撮影したように見える写真に美的魅力を見出し、ファッション写真やアート写真として流用したり、そのスタイルを模倣したりすることを指す。英語の「aesthetics」にも「美の研究、とりわけ芸術における美の研究(the study of beauty, especially beauty in art)」と「美または芸術に関する一連の原則(a set of principles about beauty or art)」の二つの意味があり(ただし単数形「aesthetic」の場合は後者のみ)、「snapshot aesthetic(s)」における「aesthetic(s)」は後者の用法である(語義は『Longman Dictionary of Contemporary English』[6th edition]より引用)。「スナップショット・エステティック」の存在が示しているのは、写真を「美しさに関する独特の価値観」によって評価するというのが、何も日本のスナップ美学に固有の現象ではないということである。それどころか、メディア理論家のレフ・マノヴィッチがそのインスタグラム論において強調しているように、現代の写真実践は、写真を撮ることの有用性とは別に、ある特定の美学(2番目の意味での「aesthetic」)によって特徴づけられていることが多いのである(レフ・マノヴィッチ「インスタグラムと現代イメージ」、久保田晃弘・きりとりめでる編訳『インスタグラムと現代視覚文化論――レフ・マノヴィッチのカルチュラル・アナリティクスをめぐって』ビー・エヌ・エヌ新社、2018年)。
「スナップショット・エステティック」とスナップ美学の共通点と差異については拙著第9章で詳しく論じているので、そちらを見ていただくとして、ここで提起したいのは、写真についての(2番目の意味での)「美学」が、美や感性についての学問としての「美学」に接続する可能性である。より具体的には、個々の写真イメージに対して私たちが日常的に下している美的判断の根拠について考察するうえで、美や感性についての哲学的議論の蓄積はどのようなヒントを与えてくれるのだろうか、という問題である。もちろんこれまでの写真論においても哲学は参照されてきた。しかしそこではヴァルター・ベンヤミン、ロラン・バルト、ジャン・ボードリヤールといった限られた名前が繰り返し登場する傾向があり、そのことはかえって写真の美学的・哲学的考察に新規開拓の余地があることを示している。
人の手によって作り込まれていないイメージとしてスナップを重視することは、「アケイロポイエトス」を崇敬する心性と親近性があることを上で指摘した。両者において共通しているのは、人工物であるはずのイメージをある種の自然物として捉える態度である。こうした態度を共有し、なおかつ、この態度について反省的に考察しているのが、イマヌエル・カントの『判断力批判』(1790年)における芸術美をめぐる議論である。『判断力批判』を、カント以前の美学的言説、および『判断力批判』が後代の美学に与えた影響の二者との関係から論じた小田部胤久によれば、カントは「美しいものにおいては自然と技術が共存していなくてはならない」と考えていた。
ヘーゲルの美学を筆頭に、19世紀以降の西洋の美学は、芸術美の分析をその中心的課題としていた。そのような中、自然美を芸術美の上位においたカントの美学は、英語圏の分析美学の一分野として生じた環境美学(environmental aesthetics)において新たな関心の対象となっている(Allen Carlson, Nature and Landscape: An Introduction to Environmental Aesthetics, [New York: Columbia University Press, 2008])。(環境美学についての日本語文献としては以下を参照のこと。青田麻未『環境を批評する:英米系環境美学の展開』春風社、2020年。)「自然の鉛筆」(写真の発明者のひとりであるヘンリー・フォックス・トルボットが自身の写真集に与えたタイトル)たる写真メディアの美的特質について考えるうえで、18世紀後半のドイツで生まれたカントの美学にまで立ち返るのも、決して無駄ではないように思われる。
4-2:マイケル・フリード『没入と演劇性――ディドロの時代の絵画と観者』伊藤亜紗訳、水声社、2020年(原著1980年)
〔…〕彼〔=ドニ・ディドロ〕は、当時の劇場に対する嫌悪を口にし続け、絵画について書いた文章の中では、「演劇的なもの(le théâtral)」という語を、見られている意識というニュアンスを持たせながら、偽りと同じ意味で用いるのである。しかめつら、わざとらしいもの、そして演劇的なものの反対にあるのが「ありのまま(le naïf)」である。『絵画論断章』でディドロはこれを「崇高に非常に近い」と特徴づけ、こうまとめている。「ありのままとはある物、ただし素のままその物であり、いかなる手も加えられていないような状態のことである。技=芸術はもはやそこには存在しない」。ありのままという語で彼は、一般的に言われるような見た目に忠実であるということよりも、もっとはっとするような、明瞭な何かを意味していたのである。〔中略〕彼ら〔=「反ロココの批評家や理論家たち」〕が実際に言わんとしていたのは、個々の人物だけでなく絵画全体、つまりタブローそのものが、自分は観者に気づいていない、あるいは観者のことを忘れている、と表明すべきであるという要求なのだ。(163-164頁)
ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論と並んで、拙著を書きながら常に意識していたのが、アメリカの美術史家マイケル・フリードの一連の著作である。18世紀フランスの批評家ドニ・ディドロが、ジャン=バティスト=シメオン・シャルダンやジャン=バティスト・グルーズら、同時代の画家の作品について論じた批評を分析することで、フリードは当時のフランスにおける絵画の評価基準を明らかにしようとする。彼によれば、「観者がそこにいることを否定」し、「観者の不在ないし非実在という虚構を打ち立てる」ことができているかどうかが、ディドロにとって優れた絵画の基準であった(168頁)。 その反対に、その前に立つ観者を意識しているように見える絵は「わざとらしく」、「演劇的」なものとして批判された。このような主張を行うことでフリードは、1967年の自身の論文「芸術と客体性(Art and Objecthood)」で行った、有名な(あるいは悪名高い)ミニマル・アート批判と、18世紀半ばのディドロの美術批評を、暗黙のうちに結び付けている。2009年に行ったインタビュー(以下の「補足」を参照)では「『没入と演劇性』を書き始めたとき、「ああ、これが私の由来なのだ」―─私はディドロの系譜にいる批評家なのだ―─と思いました」と、フリードは率直に語っている。
「芸術と客体性」でフリードは、ロバート・モリスやドナルド・ジャッドのミニマリズムの立体作品を「演劇的」と批判していた。一見そっけなく、周囲の環境から超越しているようにも見えるミニマル・アートは、実際のところ、それを鑑賞する観者(beholder)の身体を想定して、すなわち、観者と作品がどのような位置関係を取り得るかを周到に計算して作られており、その結果、ミニマル・アートの経験は「観者を含んでいる」ことになるとフリードは言う。彼にとって、それは望ましい作品体験ではない。なぜなら、そのような仕方でしか経験することができないミニマル・アートには「押し付けがましさ」があり、「攻撃的」で、作品を「真剣に受けとめることを要求」してくるからである。それとは反対に、フリードが評価するモダニズムの絵画や彫刻は「観者には閉ざされ」た状態で存在し、なおかつ「どの瞬間にあっても、作品それ自体が完全に明示的」である(マイケル・フリード「芸術と客体性」川田都樹子・藤枝晃雄訳、『批評空間別冊 モダニズムのハード・コア』太田出版、1995年、71-73、84頁)。
フリードの主張――ディドロも自分と同様に「演劇的」で「わざとらしい」作品が嫌いだった。だから自分は「ディドロの系譜にいる批評家なのだ」――に危うい点があることは否めない。フリードは自分の美学をディドロに投影しているだけではないか、あるいは少なくとも、自分とディドロの共通点を誇張しているのではないか、という批判も当然、あり得るだろう。そうした危うさをふまえたうえで、私自身は、フリードが「反演劇性の伝統」と呼ぶものは決して彼の妄想ではなく、日本の写真表現にまで波及した、ある程度普遍的な感性なのではないか、と考えるようになった。フリードは2008年の『Why Photography Matters as Art as Never Before(なぜ写真はいま、かつてないほど美術として重要なのか)』で現代写真の「反演劇性」についても新たに論じているので、スナップ美学と「反演劇性」の関係は複雑なものとなる。少なくとも両者は同一ではない(それについては第3章で論じた)。
ただし拙著において重要だったのは、スナップ美学がどの程度、フリードの言う「反演劇的」感性と重なるものであるかということよりも、「反演劇性の伝統」を弁証法的な展開として捉えるフリードのアイデアである(もうひとつはフリードによる作品記述の方法であるが、それについては後述する)。すなわち、どのようなイメージが「わざとらしい」と判断されるかに絶対的な尺度はなく、それまで「ありのまま」に見えたものが、歴史のある時点で急に「わざとらしく」見え始め、その結果、作品を「ありのまま」に見せるための別の手段が必要になってくる、というのが、フリードが『没入と演劇性』やそれに続く『Courbet’s Realism(クールベのリアリズム)』(1990年)や『Manet’s Modernism: Or, the Face of Painting in the 1860s(マネのモダニズム、あるいは1860年代における絵画の表面)』(1996年)で強調している点のひとつである。同様の弁証法的展開が日本のスナップ写真史にも見て取れることを気づかせてくれたという点で、拙著はフリードの著作に多くを負っている。
そもそも私がフリードに関心を持ったのは、写真家たちによる自主ギャラリーであるphotographers’ galleryが発行していた『photographers’ gallery press』でフリードの仕事が紹介されていたことがきっかけである。2006年4月発行の第5号には前年に横浜のBankARTで開かれたシンポジウム「写真のシアトリカリティ」での発表が再録されており、そこでは倉石信乃、林道郎らが「芸術と客体性」における「演劇性」の概念を取り上げていた。ちょうどその頃、フリードは(2008年に『Why Photography Matters as Art as Never Before』としてまとめられる)ジェフ・ウォールをはじめとする現代写真についての論考を次々と発表しており、美術史学科で写真を研究する大学院生にとって、フリードに注目するのは自然なことと思われた。2009年11月にはphotographers’ galleryの依頼で、ボルチモアまでフリードを訪ね、インタビューを行った。その準備のために『没入と演劇性』から、『Menzel’s Realism: Art and Embodiment in Nineteenth-Century Berlin(メンゼルのリアリズム:19世紀ベルリンにおける芸術と肉体化)』(2002年)に至る彼の美術史研究を読み、また、インタビューを通して彼の人柄や思想の一端に触れたことで、「演劇性」をめぐるフリードの美術批評についての自分の考えを改めることになった。
シンポジウム「写真のシアトリカリティ」でもそうだったが、フリードの「芸術と客体性」が現在参照されるとき、そこでモダニズム美術の特質として挙げられている「瞬間性」や「現前性」といった概念が隠蔽したり、抑圧したりしているものが指摘されるのが常となっている。つまり、「芸術と客体性」の議論は最終的に乗り越えられるべきものとして、通常理解されている。しかし、フリードの「反演劇性」概念を肯定的に自説に採用するにあたって、必ずしも彼のミニマル・アート批判に同調する必要はなく、「わざとらしい」作品一般に対する違和感を共有できれば十分である。もちろんフリードの価値判断を逆転させて、むしろ作品の「わざとらしさ」を評価するという美学もあり得るが、それについては最後に述べる。
4-3:赤瀬川原平『芸術原論』岩波現代文庫、2006年(初版1988年)
〔…〕人間の目にウケようとして作られたものは、その作った人間の押しつけ、にじり寄り、あるいは見る者を逃がさぬための投網のような、どうしてもある種の鬱陶しさにつきまとわれてしまう。それは凡百の芸術作品の一般を見れば明らかである。
これは何故だろうか。
自然との関係だと思う。
自然の力は森や野原にだけあるのではなくて、人工の都市にもあらわれてくる。人間の力ですべて統御しているはずの建物、街、経済関係、政治組織といったものにも、そこに働く人工の力を通して自然の力はあらわれて作用する。〔中略〕
人工の力では統御されない未知の力といってもいい。
その黎明を身に浴びる高揚感といってもいい。(「植物的無意識の採集」216-217頁)
拙著第9章「〈もの〉のスナップ」では、美術家の赤瀬川原平による路上観察の記録写真をスナップ美学との関連から論じた。赤瀬川のよく知られた「トマソン」(「純粋階段」や「純粋庇」などに分類される路上の「無用の長物」)の必要条件のひとつは、それが意図的に作られたものではないことである(「トマソン」の定義は以下を参照。赤瀬川原平「我いかにして路上観察者となりしか」、赤瀬川・藤森照信・南信坊編『路上観察学入門』ちくま文庫、1993年、13頁)。コンセプチュアル・アートの登場後に「形骸化」し、「芸術の特権構造が、その展示物をめぐる送り手と受け手の努力によってのみ支えられていることの滑稽さ」を隠しきれない現代美術のパロディとしての側面も、「トマソン」には確かにあるが(「脱芸術の科学――視線をとらえる視線」『芸術原論』167、173-174頁)、そこにとどまらない美学的射程もそれは備えている。「人間の目にウケようとして作られたもの」を拒絶し、人工物に現れ出た「自然の力」を賛美する赤瀬川の感性は、スナップ美学だけでなく、カントの美学や、フリードの「反演劇性」にも通じるものである。
それらの書物が教えてくれるのは、「ありのまま」はイメージがある対象を正確に表象していることを示す認識のカテゴリーであると同時に、美的なカテゴリーでもあるということである。美的カテゴリーとしての「ありのまま」の形成に、写真というメディアは深く関わってきた。しかし、写真の分析だけでは、このカテゴリーの本質は解き明かせないだろう。写真史の本を書いて得た結論のひとつは「写真のことだけ考えていたら、写真はますますわからなくなる」というパラドックスである。
4-4:堀江秀史『寺山修司の写真』青土社、2020年
〔…〕寺山〔修司〕が写真に求めるのは、あるがままの世界から、ふいに視線を向けられ押しつけられる「イメージ」ではない。あるいは、そうであったとしても、より重要なのはそれを受け止める写真家の主体である。寺山が欲するのは、写真家が被写体を燃やすほどに両者が関わり合い生まれる写真であった。(148頁)
拙著は日本におけるスナップの歴史について書いた本ではあるが、日本写真史はスナップの歴史のみによっては語れないこと、言い換えれば、スナップ美学が日本写真史を形成する唯一の「美学」ではないことも、本の中では強調しておいたつもりである。日本の写真表現においては、スナップ美学と無縁なばかりか、明確に反スナップ美学的な作品や動向も時折、生み出されてきた。それらの多くは(スナップ撮影においては禁忌とされる)演出を撮影の方法として採用し、「ありのまま」よりは「わざとらしさ」を追求する。つまりそれらは意図的に(フリード的な意味で)「演劇的」なものとして作られている。
そのひとつの例が、寺山修司の研究者、堀江秀史が一冊の本を捧げて論じている、寺山の写真である。堀江によれば、「あるがままの世界」を追求する中平と森山の写真観に共感できなかったことが、寺山がある時期を境に彼らと疎遠になった一因であり、その後制作された寺山自身の写真作品では、カメラは「演劇的な虚構」を作り出すための装置として用いられている(173頁)。寺山にとって撮影行為とは、それを通して自己と被写体が変革するためのプロセスであった。寺山が森山に投げかけたという「モリヤマ・ダイドーはレンズで何を燃やしている?」というよく知られた問いかけは、そのような寺山の写真観を表明したものだと、堀江は解釈している。
また、本の中でも指摘したとおり(第9章)、石内都のように、スナップに分類される撮影技法を用いながらも、「眼の前にあるモノを写し変える作意が、写真には満ちみちている」ことを肯定的に捉えた写真家もいる(石内都『モノクローム』筑摩書房、1993年、10頁)。「虚構」や「作意」をその中に織り込んだ写真作品は、時には、スナップ美学それ自体のイデオロギーを明るみに出す力を持つ。いかなる言葉からも超越しているように見える「ありのまま」の美学も、実際のところ、言語と無関係には存在しない。『イメージの運命』のジャック・ランシエールの言葉をあらためて引くならば、「現前の諸々の「無媒介性」から成る可視性の体制は、その布置をやはり言葉の媒介によって定められる」のである。しかし、私たちが写真を撮るとき、言葉で得られる以上のものを求めていることも確かである。言葉と言葉を超えたもののあいだで常に動き続けるのが人間の定めなのかもしれない。
補足:書くことと撮ること
マイケル・フリード、甲斐義明「コンテンポラリー・フォトグラフィーと反演劇性の伝統――マイケル・フリードに聞く」『photographers’ gallery press』no.9、 photographers’ gallery、2010年、10-51頁。(同インタビューは『photographers’ gallery press』No.13、2015年にも再録)

〔甲斐〕〔…〕写真について書くことは挑戦だったのではないでしょうか。なぜなら写真は、写実的ではあっても、あなたが〔ギュスターヴ・〕クールベの作品について書いたような仕方で、そうではありませんから。むしろ、写真はオートマティックな映像ですし……。
〔フリード〕ええ、その通りです。非常に繊細な質問ですね。私はそれをどうやって行うか、学ばなければなりませんでした。本を書き始めたとき、いくつかの写真について──〔ジェフ・〕ウォールについてさえも──自分が過度に記述していることに気づきました。細部に入り込みすぎていたのです。実はある若い女性、私のゼミにいた大学院生がメールを送ってきました。「先生が図像を記述するのが得意なことはみんな知っています。けれど、ウォールについてそこまでしなくてもいいのではないですか。もっと少なくていいですよ」と。自分がしていることはどこか間違っている、という引っかかる気持ちがすでにあったので、そのことについて考えてみました。そして、彼女の指摘は的を射ていることを理解したのです。これらの写真家の多くについて、一方でとても記述的でありながらも、他方では3人の偉大なリアリスト、つまりクールベ、〔アドルフ・〕メンゼル、〔トマス・〕イーキンズについて私が行ったことを繰り返さないようなアプローチ、議論の進め方を工夫しなければなりませんでした。つまり、それぞれの形態、それぞれのメディウム(媒体)が分析装置の一定の調整を要求する、ということです。しかし、そこがややこしいところでした。例えばあなたも、ウォールの《見えざる男(Invisible Man)》のような写真に写っているすべての物体を、一つ一つ名指してゆくことはできますが、ある地点までくると、それは完全に非生産的なものになります。その地点に達したら、あなたの記述は死ぬわけです。(24頁)
以前から疑問に感じていたのは、日本語でこれまで書かれてきた写真史や写真批評の多くに、個々の写真画像に対する詳細な記述や分析がほとんど見られないということだった。これはおそらく、日本では写真史と写真批評が一般に、美術史、とりわけ大学で教えられているような美術史からは離れた場所で書かれてきたことと無関係ではない。図像の「記述(description)」は美術史研究の基本と教えられる。的確な記述こそが、作品の秘密を解き明かしてくれる。だが同時に、フリードもここで述べているように、イメージの記述は「非生産的なもの」にもなり得る。非生産的な記述は、書き手の誠実さをアピールするための手管に成り下がってしまうこともある。
ともに美術史をバックグラウンドに持つフリードとバッチェンのテクストを意識して、拙著でも個々の写真イメージの特質を言葉でできるだけ正確に説明することを心がけた。そこに見えているものを言葉で記述するというのは、イメージにコミットするためのもっとも確実な手段である。絵画や彫刻作品について書く場合、通常は、複製図版を手元に置き、その場に不在の実物を思い浮かべながら、それを行う。それに対して写真の場合、写真集のようにそれ自体をオリジナルの一形態とみなせる場合はもちろん、そうではない場合(作品が複製困難な表面の質感を持っていたり、決められたサイズ以外で見ると写真の見え方が大きく変わってしまったりする場合)であっても、実物の不在をそれほど強く意識させられることはない。それは単に写真が複製可能なイメージだからではない。写真をじっくりと見るときにむしろ意識させられるのは、被写体の不在であり(写真に写っているものの多くはすでに失われてしまっている)、そのことがかえって、「オリジナル・プリント」の不在を、すなわち、自分が今見ているのは「オリジナル・プリント」ではないことを、忘れさせてくれるのである。
入念な記述を行うことで、その写真が「わかった」気になることがある。そのとき、私は撮影者(写真家)を差し置いて、その写真の秘密を握ったつもりになっている。もちろんそれは客観的に見れば、妄想にすぎない。だが、写真という媒体の特性も手伝って、写真の記述は人をイメージの中へと深く入り込ませるのも確かである。イメージへのそのような没入は他の視覚媒体の記述では不可能とは言わずとも、きわめて困難なことである。
拙著の課題のひとつは「見るもの」というよりはむしろ「撮るもの」としての写真の歴史を書くことであった。鑑賞物としての写真ではなく、実践としての写真の歴史。その動機のひとつは、これまでの写真史があまりにも、眺める対象としての写真を論じることに偏っているように思われたことにある。だが言うまでもなく拙著も、有名写真家の代表作からカメラ雑誌の作例に至るまで、様々な種類の写真を「見る」ことによって書かれている。写真を見ることと撮ること、さらに言えば、イメージを見ることと作ることは、互いに切り離しがたく結びついている。
他人の撮った写真について書いたり、考えたりすることと、自分で写真を撮ることは、確かに行為の形態としては大きく異なっている。そのどちらかにしか関心がないという人がいるのも理解できる。しかし、写真というメディアには、「自分が撮った写真」と「他人が撮った写真」の区別を無効にし、さらには、「写真の作者」という概念自体を疑いに付すような力があることも指摘しておきたい。そのことを実感したひとつのきっかけは、十代の頃に撮影した写真のネガフィルムの束を1年近くかけてスキャナでパソコンに取り込んだことだった。それらの多くはカメラ雑誌や撮影ガイドを参考にしながら、マクロレンズで植物を写したもので、撮影地のメモは残っているものの、実際にどのような状況下で撮ったのか記憶しているカットは少ない。久しぶりに見返して、それらはとても「自分の」写真とは――少なくとも、自分の感性や思考が投影されたイメージとは――思えなかったが、他方で、過去の自分がこれらのイメージの生成の瞬間に立ち会っていたという事実は、それらを何かとても大切なものに感じさせた。言い換えれば、それは懐かしさとよそよそしさが奇妙に入り混じった写真群であった(そして自分以外の人間にとっては、それらは、ある程度器用に撮影された平凡な花の写真以上でも以下でもないことも知っている)。
今回、この気づきをさらに深めるために、それらの写真を素材にウェブサイトを制作した。
これは私が「プロジェクト」と呼んでいるもののひとつである。「プロジェクト」は研究や批評ではなく、かといって「作品」とも積極的には呼びたくない、個人的な写真実践の産物である。こうした「プロジェクト」は自分にとって、写真について考えたり、書いたりするための大切な手段であり、原動力となっている。そしてそれは多くの人にとってそうであることを、すなわち、各人がそれぞれの「プロジェクト」を通して、写真やイメージに対する思考を育む契機となると信じている。
関連記事
『ありのままのイメージ――スナップ美学と日本写真史』ブックガイド(1)/甲斐義明
『ありのままのイメージ――スナップ美学と日本写真史』ブックガイド(2)/甲斐義明

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
