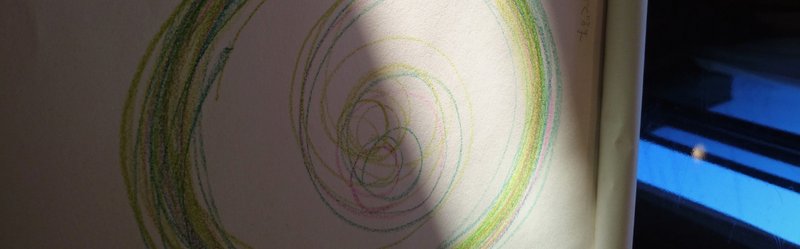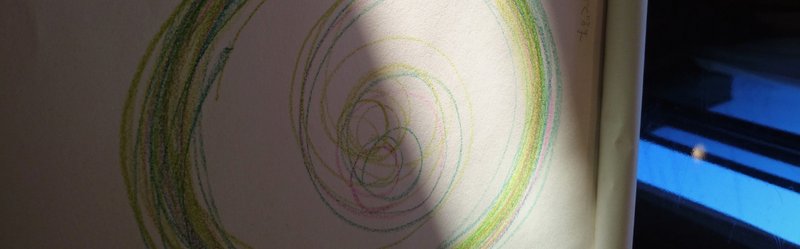音楽と”触れる”こと
数年前に、真っ暗闇のなかを歩いていく「ダイヤログ・イン・ザ・ダーク」の体験に行ったことがあります。
純度100%の暗闇のなかを、その道のプロ(つまり視覚に頼らない生活をしている人)に誘導してもらいながら、恐る恐る足を踏み出しました。
それは視覚を奪われた欠けた世の中だったでしょうか?
とんでもない!
そこから広がる、なんともファンタジックな世界!
聴覚と共に、触覚がうんと働きはじめる・・
その時、普段見ることに隠れて主体として表立って感じることのすくない
「触れる」という感覚