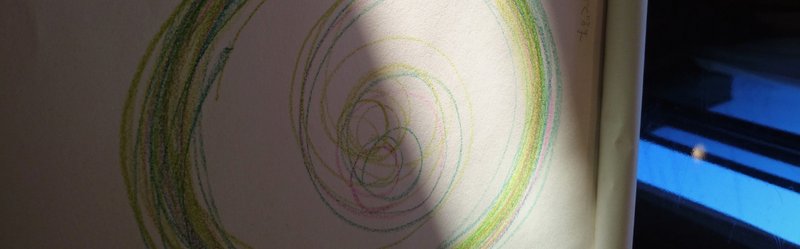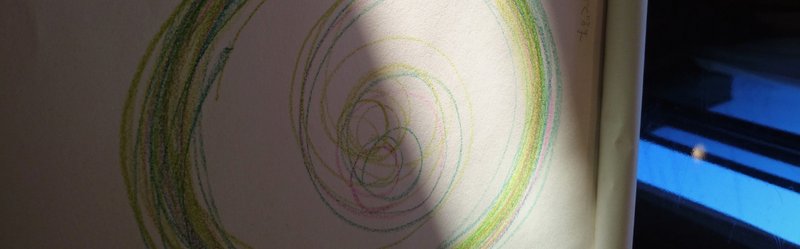ピアノの発表会までにすること
生徒たちがそれぞれ、10月初めの演奏会にむけて、暗譜が仕上がってきました。
ここから、誰かに演奏を聞いてもらう、という体験までに
どんなことができるだろうか、ということ
この段階だから修正できること、伝えられること
たくさんありすぎて、レッスン時間いっぱい
フル回転です。
「間違えなくなるまで、何度も練習する・・」なんてことは
utena music field には眼中にありません。
今だから、この曲だから、何をつたえられるか。
普段ゆるめの音楽室も今は熱い。
みんななかな