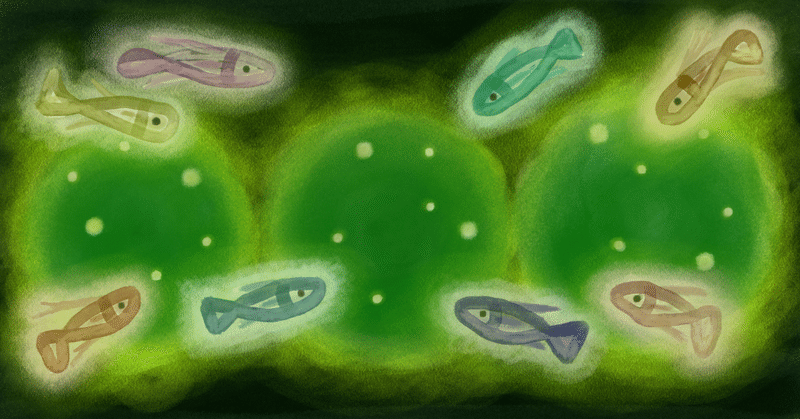
龍宮のマリモ 【小説】
第一章
オリガは、地下鉄の月島駅を降りて、肩にチェロのケースを背負い、車輪のついたスーツケースを引きずりながら、三月下旬のまだ肌寒い深夜の道を歩いていた。
彼女はパリでの二年間の留学を終えて、その日の夕方に成田空港に到着し、電車を乗り継いで自宅に帰るところであった。
運河沿いの街区の一画にある、古いモルタル造りの内科医院が彼女の自宅であった。
この内科医院は、オリガの祖父が開業したものであった。
今は彼女の父が、亡くなった祖父を継いでいた。
彼女の父タイスケは若い頃ベルリンに留学し、下宿の傍のカフェで働いていたロシア人の女性ベラと知り合った。ベラはソプラノ歌手を志望して、ウエイトレスをしながら音楽学校に通っていた。
オリガの祖父母は、ベラが日本でタイスケと暮らすという意向であることを知って、タイスケとベラの結婚を許した。
タイスケとベラとの間には、オリガの姉にあたるナオミとオリガの二人の娘が生まれた。ナオミは将来医院を継ぐべく、大学の医学部に進学し、今は川崎の大きな病院でインターンとして勤務していた。ナオミは勤務先のそばにワンルームマンションを借りて住んでいたので、月島でオリガの帰りを待つのは、タイスケとベラだけであった。
オリガは、ベラの影響で幼少から音楽を好んだ。オリガは五歳からバイオリンを習っていたが、ベラのドイツでの知人が日本の音楽大学でチェロを教えていた縁で、オリガは八歳からチェロを習うことになり、寸法を縮小したチェロを担いで、毎週ベラの知人の教えるチェロ教室に通った。
オリガは、チェリストとしては、オーケストラに入るのではなく、ソリストとして活動することを志望した。彼女は日本の音楽大学を卒業すると、パリの音楽学校であるコンセルヴァトワールに留学した。
彼女のこの度のパリへの留学は、二度目であった。一度目もコンセルヴァトワールに留学し、帰国後に若手チェリストとしてある程度世間で認められた彼女は、さらに研鑽を積むためにもう一度留学したのであった。そして彼女は今年で二十九歳になった。
オリガは自宅に到着し、父母の出迎えを受けて、自室に荷物を置いてから、ダイニングルームで父母と夜食を摂った。
タイスケが、甘口の白のドイツワインのグラスを傾けながら、オリガに尋ねた。
「オリガ、それでパリでは彼氏はできなかったのかい?おれと母さんとは留学先で知り合ったから、オリガもそういうことになるんじゃないかと思っていたんだが・・・」
「あら、残念ながらそういう話はなかったわ。学生同士、みんなライバルなのよ。」
豊かな銀髪をシャンデリアのライトで輝かせているベラが尋ねた。
「学校の外ではボーイフレンドはできなかったの?」
「東洋人の女の子が独りでカフェに入ると、目立つみたいで結構声をかけてくるやつはいたよ。でも、みんな下心が見え透いてるから、こっちから願い下げ。」
タイスケとベラは顔を見合わせた。タイスケが言った。
「オリガは二年の留学で少しは変わるのかと思ってたけど、負けん気は変わらないね。」
「わたしはわたし、変わりようなんてないよ。自分の音楽の表現を思い通りにやりたいだけ。わたしにはそれしかできないし、そのほかのことには興味ないもん。」
「あいかわらずだな。芸術家というのはそういうものなのかねえ。聴いてくださる人の気持ちもあるだろう?」
オリガはベラの作ったカナッペを頬張りながら答えた。
「聴く人に説明するようなことはしないわ。わたしはわたしの表現をする、それだけ。その表現を聴衆がいいと思うかよくないと思うか、わたしには興味ないわ。」
タイスケは、それはオリガが収入の心配がないから言えることで、プロとしてはお客さんの共感をどうやって獲得するかの真剣勝負をしなくてはいけないのではないかと思ったが、帰国早々のオリガと議論するのもどうかと思って、口には出さなかった。
彼は、ここ数年、オリガがたとえばサンサーンスの白鳥とか、バッハの組曲とか、彼が楽しめるものを一切弾かないで、メロディーらしいもののつかみどころのない現代の作曲家の音楽ばかりを弾いていることを思い出した。彼としては、彼女の弾く音楽をどうやって鑑賞してよいものやら、いつも当惑して黙って聴くだけであった。
オリガは、音楽の上では、決して聴衆に媚びるようなことはなく、自分の好む曲を、自分の流儀で演奏することに拘った。彼女が独演で演奏するのは、多くは現代の作曲家の手がけた曲がほとんどであり、それを好んで聴く聴衆は日本ではほんの一握りであった。彼女が独演する演奏会は採算が合うものにはならなかったが、父親のタイスケがいつも払ってくれるので、彼女はチケットを売ることを意識したことはなかった。彼女は独演だけでなく、カルテットのメンバーとして演奏することもあった。その時は、演目も集客を考えて、ある程度知られているモーツァルトやベートーヴェンの弦楽四重奏曲を入れるので、聴衆はそれなりの人数が集まって、タイスケが資金援助する必要の生じることはなかった。
オリガの演奏は、ある批評家に、男性以上に男性的で、往年の名演奏家シュタルケルを想起させる骨太の表現の中に、ロシア的あるいは東洋的な情念を感じさせる節回しがあると評された。本人は滅多に演奏しなかったが、チャイコフスキーのようなロシア音楽は、批評家や聴衆の評判が良かった。
ベラがぽつりと呟いた。
「芸術と、歌とは、ちがうよね。わたしは歌が好き。」
オリガはカナッペをワインで喉に流し込みながら言った。
「ママとわたしは違うわ。」
彼女はカナッペを飲み込むと、付け加えた。
「でも、わたしはママの歌うアリアは好きよ。」
オリガはダイニングルームから自室に戻ると、荷物はそのままにして、スマホを開けてインスタグラムに先ほど成田空港に到着した時に撮った写真を掲載して、自分が帰国した旨を書き込んだ。
彼女はフォロワーが二千人ほどあって、彼女の投稿にはいつもたくさんのコメントが書き込まれた。しかし、彼女は、インスタグラムを使うのは自分の演奏活動や考えを発信するためと考えていて、コメントは一応斜めに目を通すだけで、返信することはなかった。彼女自身がフォローしている相手先はゼロであった。
この日は、彼女はつぎのような一文を書き込んだ。
「留学してわかったのは、結局は他人から習うことなんてなくって、自分で信じる表現をしるしかないってこと。」
彼女は毎晩習慣になっているインスタグラムへの書き込みをいつものとおり淡々と終えると、スーツケースを開けて、パリの下宿で畳んできたパジャマに着替えた。
次の日は日曜日で、オリガは午前十一時頃にベッドから起き上がって、スマホでインスタグラムに寄せられたコメントのチェックをしていた。
そのなかに、いつもコメントを寄せてくるファンの一人の発信があるのに気が付いた。
その文面には、つぎのように書いてあった。
「オリガさん、お帰りなさい。フェイスブックで帰国されたのを知りました。また日本の舞台に上がられるのを楽しみにしています。ご自分が探していたものは何だったのか、発見されましたでしょうか?」
彼女は、それを読むと、
「別に探しているものなんかない。」
と思った。
彼女は、その男性は、自分が東京で行うコンサートには必ず来て、終演の時になにがしかの花束を舞台に持って来る人物ではないかと見当をつけていた。彼の名前、ヨシミチは、その花に添えられたカードで覚えた名前であった。彼女は、送信された文面を見ながら、以上のことを漸く思い出した。
彼女は、舞台の下の暗いところから自分に花を渡す人物の顔は、この人物に限らず、さだかには認識することがなく、ヨシミチの顔も記憶に浮かばなかった。彼がいつも背広であることはわかったので、彼女は、たぶんこの人は役所の職員とかの勤め人の類であろうと想像したが、それ以上の興味は持たなかった。ヨシミチは、コンサートに現われるだけでなく、彼女のインスタグラムへの投稿には頻繁に何事かコメントを書いてくるのであったが、それ以上の接触を求めてくるようなことはなかった。彼女は、送信されるコメントをいちいち読んで覚えているわけではなかった。たぶんコメントを連続して読めば、彼が自分に何を期待しているかがわかるはずであったが、彼女はそういうことをする気持ちには誰のコメントに対してもならなかった。
だから、今回のヨシミチの発信に、オリガが返信をすることはなかった。
オリガは、インスタグラムの中で、自分用にコレクションに入れている写真を開けた。
彼女は、音楽家として、男性の音楽家との付き合いは多かったが、彼女の好みの男性は芸術家タイプとは全く異なる、スポーツマンであった。集めた写真にはアメリカのバスケットボールの選手のスナップが多かった。
彼女は、男性でも、特に年配で自分に先生としてあれこれ教えようとするような男性が嫌いであった。
それは、彼女が中学生の頃から続いていることであった。学校の教師の中に、自分で考えたことではないのに、世間で通り相場になっていることをそのまま教えて聞かせながら、自分が世間そのもののような気分になって、優越感を覚えるような人がいる・・・彼女はそのように感じた。それは、彼女が音楽という、言語における文法と同様に楽典の約束事の上に成り立ちながら、言語におけるような意味とは離れたものの世界を自分の世界にしていることと関係していた。彼女は、言葉というものがその有する意味によって、人を抑圧しているように感じた。つまり、言葉とは、意味すること以外のものとして扱われることを禁じていると思った。彼女は、人にものを教えたがる人、特に年配の男性は、相手に禁圧を与えることで自分の万能感を得たいだけで、意味なんて本当のところどうでもよいのだと思っていた。
彼女が自分のフェイスブックやインスタグラムへのコメントや、メッセージを斜めにしか読まないのは、言葉自体の虚しさと、言葉を伝える人の下心とによって、自分が支配されるのを嫌ったからであった。
彼女はそれゆえに、口数の少ない、考えの単純なスポーツマンが好きであった。彼らは、少なくとも、自分に対して先生のようにものを言うようなことはしない、と思っていたからであった。
オリガは、他の音楽家と共演する機会は多かったが、共演者と親しく会話することはなかった。共演者が男性の場合は特にそうであった。
彼女は、チェリストとしての自分へのファンが、およそスポーツマンタイプではない男ばかりであることを知っていた。だからこそ、彼女はインスタグラムでは、ことさらに自分の肉体の美しさを印象づけるような写真を掲載した。彼女は、チェリストとしてではなく、女性としてのオリガを好むファンがほしいと思ったのであった。彼女は自分の姿を自分で撮影するだけでなく、彼女の演奏会のプログラム用の写真は、いつも同じプロの女性の写真家に依頼していて、その写真家のスタジオで、インスタグラムのための写真を撮ってもらうこともあった。写真家は、オリガの彫りの深い顔立ちに微妙な陰影を工夫した写真が得意であった。写真家は、モノクロームの写真を撮ることもあったが、モノクロームは、オリガの肌の白さをさらに強調する効果をもたらした。彼女には、彼女の演奏を録音であっても一度も聴いたことがないであろう男性のファンがたくさんついていた。インスタグラムのコメントを見れば、そういうファンは、「美人だ」とか、「つきあって」とか、ハートマークだけをいくつか並べるとか、つまり言葉が少なかったり、まるで言葉がなかったりするので、彼女にはすぐにわかった。彼女はそういうコメントが何十と集まるのを見て満足を覚えた。
彼女は、投稿する写真には、何か一言添えることにしていた。彼女にとって、言葉は意味というよりも音楽であったので、その時の気分でメロディーを一節添えるつもりで、その意味に思いをいたすことなく、感覚のままに書き込むのであった。
たとえば、彼女が
「八重桜が散って空に帰ってゆくとき、人は自らの蒸発を願うものです。」
といった文を書き込むと、ファンは彼女が精神的に悩んで自信をなくしでもしているのではないかと心配して、彼女を気遣う書き込みがたくさんなされるのであった。彼女はコメントを流し読みにしかしないこともあり、ファンが自分を心配しているということ自体意識したことがなかった。
第二章
ヨシミチは、東京の文教地区にある私立の中高一貫の男子校で、美術の教師をしていた。
彼の勤務する学校は、いわゆる受験校であった。この学校は、中高六年間のカリキュラムを高校二年までに終わらせて、高校三年の一年間は大学受験準備に宛てるという教育方針で知られていた。
ヨシミチの担当している美術という科目は、この受験校に通う生徒がめざす大学の入試にはあまり関係のない科目であった。彼の授業時間は、生徒たちにとって、受験科目の授業の合間の息抜きの時間であった。美術の授業中には、ほかの科目の勉強をしていたり、睡眠をとっていたりする生徒が多かった。彼は、前任の老教師から、
「この勤め先でのこの科目の教師の役どころは、とにかく生徒に負担をかけないこと」
と引き継がれた通りに実践した。そして、いつも少し困ったような笑顔で、ざわつきがちな美術教室の教壇に立った。ただ、理系をめざす生徒の中に、少数ではあったが、将来写生や製図の技術が必要になることを知っていて、実技の指導をまじめに受ける者もあったので、彼は自分の力を専ら彼らのために傾けた。
彼は、芸術系大学を卒業し、もともとは洋画家をめざしていた。大学での評価はまずまずであったので、彼は自分の将来に期待するところがあった。彼は、いきなり画家として独立するだけの財産がなかったので、教師をしながら画家をめざすことにした。大学の成績がよかったので、彼は東京のこの有名進学校に運よく職を得ることができた。彼は教師をする傍らで美術展に出品を続けていたが、賞は一向にとれなかった。
彼は、その年三十一歳になった。妻子はおらず、学生時代から同じアパートに住み続けていた。彼の実家は山梨県の兼業農家で、彼は次男坊であった。彼の上に長男の兄、下に妹がいた。父親は彼が大学生の時に死んだが、父親の死後、実家の田畑は長男のものになって、彼には財産らしいものは残されなかった。
彼の描く絵は、抽象絵画であったが、必ず具象のモデルから入って、その意味を抽象化して表現するという手法をとった。彼は、自分の絵画は、意味のコラージュであると考えていた。人間の認識する物事の像には、すべからく意味があって、絵を描くということは、そういう意味を抽出して、画面にいわば貼り付けることであると思っていた。彼の見解では、人は、竹を認識すれば必ず竹の意味を認識しているはずで、その意味を自分の目で明確に認識するために、具象を観察することに時間をかけた。
彼のこのような物事の捉え方は、日常生活でも折々表れた。彼は、ほかの人が発信する言葉を、一旦は虚心に真に受けて、どういう意味がそこに込められているかを、努めて正確に認識しようとした。しかしそれは、彼が言葉をいつも文字通りに解するだけであったということでは決してなかった。彼は、地口や冗談に笑うことはできたし、詩を読んでその隠喩するところを感じ取ることもできた。ただ、彼は言葉というものにいつもまじめに向き合う姿勢なので、彼の同僚は、以前思い付きで口にしたことと、後日の発言との齟齬を彼に指摘されて面食らうことがしばしばあった。彼は言葉と意味とがわざとずらされる事態、すなわち嘘というものに敏感であった。
彼は、女性への興味というものが淡白であった。彼はピカソなど色欲の旺盛な画家の伝記を読むたびに、自分は淡白だから絵を見る人に訴える力も貧弱なのだと思った。彼はいつも同じトレーナーに、元は背広のズボンであったスラックスという身なりで、しかもどちらも油絵具で汚れていた。彼は、身長は人並みであったが、体に筋肉があまりついておらず、華奢で細い体は中学生の少年のような印象を与えた。二重瞼の大きな目は、自分で合わせ鏡を見ながらおかっぱに切りそろえた黒い髪の下で、年齢に似合わないつぶらな光を放っていた。彼の容姿は、かつて美少年といわれたことのある、高校生の頃の面影をほとんど変えていなかったが、男性としては未熟に見えた。彼は、自分では、同年代の女性から男性としての関心を抱かれたことはないと認識していた。
しかし、彼は女性とまるで付き合いがないわけではかった。女性は彼には男性としての警戒を抱かないせいか、友人として付き合う女性はこれまでも何人かいた。彼は女性と会話するのが男性と会話するよりもずっと楽であった。勤め先の学校の会計の事務員や図書室の司書は、美術室で彼と昼食の弁当を共にして、世間話に笑い興じる仲間であった。彼が学校に勤務する女性と仲良くなれたのは、受験校として友情よりも競争という殺伐とした雰囲気が教職員にも生徒にも満ち満ちているなかで、およそ殺伐とは無縁でいたからであった。この学校には、ほかにも受験に関係のない体育や音楽の教員がいたが、彼らは風紀担当であったり体育会系の課外活動の顧問であったりして、やはり殺伐とした男ばかりの組織の一員だったからであった。
会計の事務員のマイカや司書のマチコが彼と昼食を共にするのは、彼が美術室に置いている電気ポットの湯と、彼がいつも切らさないちょっとした甘味のためでもあった。
ある日、昼食が終わってポットの湯で淹れた紅茶を飲みながら、彼はマイカとマチコに尋ねた。
「ねえ、オリガって音楽家、知ってる?」
マイカが尋ねた。
「ええ、知ってます。セレブですよね。この間演奏会になんとかの宮様が来られたって、美容院で見た雑誌に書いてありました。」
マチコが半生菓子の賽子ほどの大きさの最中を食べながら言った。
「お金持ちの娘さんらしいけれど、外国では日本よりももっと有名らしいわね。十代でどこかのチェロのコンクールで賞をとったんですってね。けっこう男の噂があって、歌舞伎俳優のイチムラ・キクエモンと六本木のスタンドバーで隠し撮りされた写真が週刊誌に出てましたよ。」
マイカが紅茶をすすりながら言った。
「マチコさんは週刊誌ネタは強いね。司書だからいろんな週刊誌を読むからよね。」
ヨシミチはマチコとマイカにティーポットから二杯目の紅茶を注ぎながら言った。
「ぼくは芸能ネタはあまり得意じゃないから、きみたちの話は勉強になるよ。」
マイカが尋ねた。
「それで、ヨッシーさんは何でオリガのことを聞いたの?」
ヨシミチはマイカとマチコにはヨッシーさんと呼ばれていたのだった。
「うん、チェリストの絵が描きたくて、この間オリガのコンサートに行ってみたもんだから。」
マイカが尋ねた。
「チケット高かったんじゃない?クラシックでしょ。退屈しなかった?」
「退屈はしなかった。曲目は現代音楽ばっかりだった。」
マチコが言った。
「わたし、インスタグラムでオリガの写真を見たけれど、なんか世間離れしたような、詩みたいなことを書くのが好きな人みたいですね。車のコマーシャルに出たりして有名だし、マネキン人形みたいにきれいだから、フォロワーはけっこういるけど、わたしは肌に合わないから、オリガはフォローしてないです。ヨッシーさんはオリガのこと、気になります?」
「気になるとかじゃなくて、絵のモデルにしてるだけ。おかげで現代音楽は聴いて少し楽しめるようになった。」
マイカとマチコは、いつものように、ヨシミチが男性であることをまるで意識することなく、賑やかな昼の会話を終えて職場に戻って行った。
彼がオリガという音楽家のことを二人に尋ねたのには、つぎのような経緯があった。
ヨシミチは、自分の作品をインスタグラムにしばしば投稿したが、反応を示す者は片手の指に収まるほどしかいなかった。彼は、反応の少なさを見るたびに自信を失って行った。彼は自分の作品に人気が出ないことを悩むのではなかった。彼は、他人の反応が少ないということは、自分の作品の表現する意味が通じなかったということだと解して、自分の意味を伝える力の拙さを残念に思うのであった。そして彼は、画家としての将来を諦めかけていた。
ある日、ヨシミチは、上野駅に、オリガというチェリストの演奏会のポスターが貼ってあるのを目にした。
彼の記憶では、オリガといえば、日本人の父親とロシア人の母親を持っていて、十代のうちに国際的なチェロのコンクールで優勝し、それからは音楽界にとどまらず、いわゆるセレブリティとして、自動車のコマーシャルに出たり、雑誌の取材に応じたり、日本では彼女のことをタレントとして知っている人の方が多いはずであった。彼女は舞台では黒いローブデコルテを着て、腰まである艶やかな黒い髪を束ねることなく靡かせ、やや秀出でた白い額と睫毛の長い大きな黒い瞳、そして細い腰部から長く伸びた脚が、騎馬を操る精悍な異邦の民族の血を引いていることを物語っていた。
彼は、オリガがチェロを奏でる白黒写真を見て、オリガをモデルにして音楽を演奏する人物像を描いてみたいと思った。彼は音楽には詳しくなく、演奏会に並んだ現代音楽の曲目の中に彼が知っているものは一つもなかった。彼は全くデッサンするだけの目的で、その音楽会に行ってみることにした。
彼が当日、銀座の楽器店の小ホールで、当日券を買って客席に入って、開演を待った。客席は百席ほどあったが、開演までに埋まったのは三十席ほどであった。
当日の曲目は、ハンガリーの作曲家コダーイのチェロソナタをはじめ、現代音楽ばかりであった。
彼は、オリガの姿をデッサンすることが目的であったから、画帳を開いて鉛筆を構え、オリガがチェロに弓を当てるのを待った。
オリガの弓がおもむろに引かれると同時に、雄の獅子が咆哮するかのような、野性味のある低音が響き出して、コダーイのソナタが始まった。
その曲はヨシミチが初めて聴く曲であった。彼は、構えた鉛筆を動かすのを忘れて、獅子が言葉によらないで思索するかのような音の流れを、ひたすら聴いていた。
オリガの奏でる音は、ひとところに止まったり、ドミナントの和音に解決したりすることなく、連綿と展開して行った。ヨシミチは鉛筆を動かすことなく、精神を集中して曲を聴いた。そして、彼は、この音楽に意味があるとすれば、その流れのプロセスが全体において示すもの、あるいは刻々変化する展開それ自体というほかはない、この流れを絵にすることができれば、と思った。
ヨシミチは、結局曲の終わるまでの四十分ほどの間、デッサンをすることはなかった。彼は曲が終わった後の休憩時間に、舞台を思い出しながら、備忘程度の簡潔なデッサンを描いた。
彼がオリガに持った興味は、絵画のモデルとしての興味であった。彼の画家としての意欲は、音楽という動きのあるものの意味を、平面の上に画像として貼り付けてゆくことに向かっていたのであった。そして、音楽を視覚に表すための対象として、オリガの演奏する姿が彼には必要であった。
彼は、自分の絵画の参考にするために、オリガのインスタグラムの閲覧を始めた。オリガの写真には必ず何か一言彼女の言葉が添えられていたが、彼はそれらの言葉を、あたかも彼女の演奏する曲が獅子の思索の連綿たる展開を思わせるのと同じように、意味の展開としてとらえた。
「冬の海は独りで眺めるものだ。」
「なつかしい街の灯、でも自分を迎えるために灯ったものはひとつもないのだ。」
「親友がドイツに帰国するのを送った。わたしの魂の半分が地球の西に飛んで行くのを地上から眺めた。」
「わが愛する相棒、世界でただ一人のパートナー、それがこのチェロだ。自分は夜中にチェロを相手に会話することがある。チェロは深夜にはたしかに言葉を話すのだ。」
「ああ、わたしの表現!たとえ誰にも愛されなくても、わたしの表現は、ひとりぼっちで立派に地球に立っている。拍手なんて要らない。」
ヨシミチは、このような写真に添えられたコメントを、ひとつの思索の流れとして読んだ。
彼は、この演奏家は、たえず自分を次の高みに上げるために、孤独な戦いを続けているのだと思った。二か月ほど経つと、彼はこの演奏家の成長を聴衆の一人として応援したい、という気持ちになってきた。彼は、オリガの思索という音楽の展開をさらに続けて聴くために、必要なことだと思ったのであった。
彼は、彼女のコンサートは必ず聴きにゆくことにした。彼はコンサートには小さな花束を持って行って、演奏が終わると彼女にそれを渡した。花束に添えるカードには、自分の名前だけを、活字のような四角い文字で書き込んだ。
ヨシミチの描く油絵は、オリガのコメントを読むたびに少しずつ変化して行った。デッサンをもとに、キュビズムの手法で多面体をひとつの平面に展開するように描き始めたのであったが、次第に色も形も最初から変化して行った。形がさらに抽象化して行って、演奏者の形は三角形の基本パターンを連ねた螺旋形に解消して行った。そして、螺旋はねじれるごとに色調を変え、上空に登ってゆくのであった。
彼は、オリガのインスタグラムには、できる限り毎回、自分のコメントを付した。
「海の色は誰にとっても自分の色ですね。」
「でも街の灯はあなたを拒みはしない。」
「魂が地球の大きさになりましたね。」
「自分も絵筆と会話しています。」
「それでもわたしは拍手を続けますから。」
オリガはそれからパリへ留学したが、その留学中もインスタグラムでの投稿を続けた。
彼女の帰国の直前の写真は、パリの下宿から向かいの建物の屋根を写したものであった。そこにはつぎのような言葉が添えられていた。
「わたしの探し物はなんだったのでしょう?わたしはそれを鞄に詰めたのでしょうか?」
ヨシミチはその言葉を見て、つぎのように書き込んだ。
「オリガさん、お帰りなさい。フェイスブックで帰国されたのを知りました。また日本の舞台に上がられるのを楽しみにしています。ご自分が探していたものは何だったのか、発見されましたでしょうか?」
彼は、このように書き込みを続けていたが、オリガからは読んだというレスポンスが一度も来たことはなかった。彼としては、オリガという有名人に、ファンが何か書いて送ったところで、たぶん何千人のファンの一人にすぎず、目にも留まることはないだろうと思っていた。それなのに、書き込みを続けていたのは、彼としてはオリガの発信に対して、自分の理解した意味を記録しておきたいと思ったからであった。それは、そうしなければ、オリガが発信した意味を置き去りにして奔放に飛んで行くような気がしていたからであった。彼は、ここ数年、オリガをモデルにした一枚の油絵を、描いては直し色を塗っては直しという作業を続けていたが、彼が画面にイメージを定着しようとすると、オリガはそこを置き去りにして新たなオリガになっている、その繰り返しであった。
第三章
帰国後のオリガは仕事で多忙であった。雑誌の取材、テレビコマーシャルへの出演、自分が講師を務める公開レッスンといったスケジュールが立て続けに入った。
オリガは、元々はチェロ教室の弟弟子にあたるジョウという青年をマネジャー兼運転手として雇っていた。ジョウはクラシック音楽の道に進まず、音楽の専門学校で作曲を勉強していたが、アルバイトとしてオリガの秘書を務めているうちに、それが本業になったのであった。
ジョウは専門学校の時の同級生であった女性と結婚していた。彼の妻はヴォーカルで、主にバックコーラスの仕事をしていた。彼らには子供はいなかった。
ジョウは身長が二メートル近くあり、インパラのような敏捷そうな長い脚に、いつも黒革で光沢のあるブーツを履いていた。銀色に染めた髪は肩甲骨のあたりまであって、彼は仕事の時にはゴムで一つに束ねていた。彼は無口な性質であり、オリガとは仕事の話以外はあまり会話をしなかった。しかし、仕事の相手との打ち合わせには卒はなく、スケジュール管理が行き届いていて、オリガはいつも体を仕事場所に運びさえすればよかった。
マスコミ関係者には、ジョウが一流のホストのようにオリガに仕えるさまを見て、オリガとジョウとの男女関係を疑う者も多かった。しかし、彼らはスキャンダルとしては、マネジャーとの関係ではニュースバリューが高くないと思ったのか、二人の関係を追及するよりも、オリガと俳優とか歌手とかの関係の詮索に忙しかった。
ジョウがオリガに対して秘密にしていることが一つあった。それは、彼がオリガの姉のナオミと時々二人きりで会っていることであった。
医師のナオミは、心療内科を専門にしていた。心の問題によって体の臓器に症状が出る患者の治療が彼女の研究課題であった。
ナオミが初めてジョウにあったのは、オリガが主催する船上パーティーの席上であった。
オリガは、竹芝埠頭を出発する湾内遊覧船のレストランの一室を借り切って、日ごろ世話になっている関係者を二十人ほど招待した。
オリガは漆黒のカクテルドレスを着て登場し、アナウンサーとみまがうばかりの弁舌で、自らパーティーの進行を行った。彼女はマイクの前に招待客を次々に読んでは、一言スピーチを依頼し、スピーチが終わるたびに、その人と彼女との関りのきっかけや、思い出のエピソードなどを一言添えた。
ナオミは、このようなパーティーではいつもそうであったが、ごく自然に彼女の周りに二、三人の男性が取り巻いて、バーティ―の進行とは関係のない会話がはずむのであった。彼女は、オリガのように、自分好みのハンサムな男性を何人でも手に入れておきたいとは思わなかった。彼女はそれよりも、目の前に現れる男性の魅力を楽しむ方で、自分の魅力で気に入った男性を惹きつけるのであった。彼女は、そのような男性への接し方は、自分の心の底から突き上げてくる欲望から発していることを自覚していた。そして彼女は、自分は男性に愛されたいという気持ちが強いことも自覚していた。彼女は、どのようにすれば男性の受けがよいか、身に着けるものにも、身のこなし方にも、話題にも細心の注意を払った。そして、頼らせてくれそうな男性を前にすると、自ずとその男性の意を迎えるように振舞った。だからナオミはこれまでも何人もの男性と関係してきた。それらの関係はどれも長続きしないで終わったが、いずれも彼女が興味を失って切ったのであった。
ナオミは、オリガと自分との違いをしばしば比較した。彼女は、妹のオリガは、とにかく欲張りで、何でも自分の思う通りにならないと気に入らない性格であると思っていた。チェリストとしての才能と名声だけでは足りないで、セレブリティの仲間に入って積極的にマスコミにも登場し、何人ものボーイフレンドを同時にかけもちしているのは、欲張りの証拠だと思った。そして、オリガがすごいのは、その欲望を達成するために、人一倍の努力をすることであった。オリガは、毎日三時間のチェロの練習はもちろんのこと、語学も世界の一流の音楽家と対等な会話ができるレベルまで熟達していた。ナオミは、将来父の医院を承継するという使命で精一杯であるのに比して、オリガの努力は並外れたもので、自分は到底真似ができないと思っていた。
ナオミは、その一方で、オリガは自分をいつも大きく見せたいという願望が必ずしも満たされないで、フラストレーションを抱えていることを知っていた。特に、オリガは世間が自分を偉大な音楽家として尊敬するのではなくて、有名タレントの一人としてもてはやすことが内心我慢できないのを知っていた。オリガは、世界的芸術家としてふさわしいと考える言葉を、その場その場の気分で発するのが常であったが、マスコミやファンは、その言葉をまともに捉えて何か反応を返すということがなかった。しかしオリガは、たとえ大向うから反応があっても、その内容が知りたいというのではなくて、称賛の反応があったという事実だけが欲しいのであった。
だから、ナオミは、本当に男性に好かれるのは、オリガではなくて自分の方だと思っていた。ナオミはオリガと容姿が似ていて人目を惹くことは同じであったが、オリガよりはやや大柄で、肉付きはオリガよりも豊かで、人にはおおらかな印象を与えた。ナオミは男性に決して女王様のように振舞うことはせず、目の前の男性の期待する、かわいい女性にいつもなってみせるのであった。ナオミは、本当のところオリガには男性との深い交際が一度もないことを知っており、それに比べれば、自分はこれまで数多くの恋愛経験を持っていることで、妹に密かな優越感を感じるのであった。
ナオミは、船上パーティーでオリガが見事に進行を取り仕切っているのを見ながら、このような比較を胸中で繰り返していた。
ナオミは、オリガがジョウというマネジャーを雇っているのは知っていたが、実際に顔を合わせるのはその船上が初めてであった。
ジョウは、パーティーに準備された酒食に一切手を付けることなく、滞りなく進行するよう細かく気を配っていた。
そのようなジョウの様子に、ナオミは気を惹かれた。彼女は、その人物が、オリガの言っていたマネジャーのジョウであることを察した。
ナオミは、ジョウが自分から招待客に用事ではない話を気軽にするような性格ではないことを察して、自分からジョウの隣に寄って行った。
「ジョウさん・・・ですよね。」
「はい。」
「いつも妹がお世話になっています。」
「ああ、ナオミさんですね。先生からお聞きしています。」
ジョウはオリガのことを「先生」と呼んでいたのであった。
ナオミは、このタイプの男性は、自分の方から話を展開してゆかないと、すぐに黙ってしまうだろうと思った。
「オリガが留学中は、ジョウさんはどうされていたのですか?」
「向こうでも取材の準備や、音楽家の方との顔合わせの段取りがありましたから、結局パリとの間を何度か行き来しました。たぶん延べで先生の留学中の二、三割ぐらいは自分もパリにいたことになります。」
「そんなにお世話になっているのに、今までお目にかかる機会がなくって・・・」
「お医者様でいらっしゃいますから、お忙しいでしょう。」
「私の専門は急患があるわけじゃないから、決まった時間拘束されるだけです。」
ナオミは話しながらジョウの手を見ていた。ジョウの手は細くて、手の甲には血管が浮き出ていたが、よく見ると、しっかりと太い骨格を白い肌で包んだ武骨な手であった。ナオミは彼の手が自分の肩に触れる瞬間を想像した。
ナオミは続けた。
「ジョウさんは拘束時間が長いんじゃない?オリガに振り回されているんじゃないかしら?」
「いえ、忙しくない時は何日も先生とお話しないこともあります。」
ジョウはこう言いながらも、オリガと招待客との会話の様子には目を離していなかった。
ナオミは何げなくつぎのような言葉を口にした。
「オリガは、自分は時間に縛られるのがいやなのに、人のことは平気で縛るんだから。」
「縛る、ですか?」
ナオミは、その時、ジョウの目に、マネジャーとしてではない光を感じた気がした。それと同時に、彼女は恐怖と紙一重の戦慄を感じていた。
彼女は咄嗟に自分の戦慄の原因を探した。彼女は、普段医者として、患者の心の悩みを探る際に、キーワードに注意する訓練を積んでいた。
彼女は即座にその原因をつきとめた。それは、「縛る」という単語であった。
それによって、彼女は、ジョウという人物が、何に享楽を感じるのであるか、見当をつけることができた。それと同時に、彼女は自分もその単語の裏に潜むものに共鳴したのか、わずかに眩暈を覚えた。彼女は、それはパーティーの行われている船の揺れによる起きた眩暈ではないことに気が付いていた。
ジョウの方は、ナオミにも増して、目の前の人物が自分と同様あるいはその裏返しの享楽を覚える人物であるかどうかの嗅覚が鋭かった。彼はその単語を発した時の彼女の表情のわずかな震えを見逃してはいなかった。
しかし、彼は用意周到な性質であった。このような話題は、世をはばかるものであり、このような衆目のある場所で、初対面の人物と即席に何らかの発展があるべきものではないと思っていた。
ジョウは普段あまりはっきりとは笑わない目でナオミの目をじっと見つめた。
「先生は人のことを縛ったりはされませんよ。先生が必要と思われた時に、自分は必要なことをして差し上げればよいのです。」
「ジョウさんはやさしいですね。そうでないと、オリガとは何年も仕事できませんよね。」
「さあ、やさしいかどうかは・・・」
ナオミは、ジョウと付き合うとすれば、自分が経験したことのない、怖いことになるのではないかという予感がした。それと共に、どう怖くなるのか、期待する気持ちも生じた。彼女は、自分の心にそういう怖いものを求めるものが潜在していることを、これまで自覚したことがなく、そういう自分の心の動きをこれからどのように扱えばよいのかわからなかった。
やはり彼女には用心が先に立った。
「妹のこと、引き続きよろしくお願いします。」
「わかりました。」
ナオミはジョウに会釈してその場を離れた。彼女は、今度どこそこで会うといった話をしないでよかったのだと思った。その時、船がまた一揺れした。
ナオミが振り返ると、ジョウはいつもの職業的な微笑みに戻っていたが、彼の目はナオミの目と一瞬合った。そして彼はすぐにオリガの方に向き直った。
ナオミとジョウとは、この船上バーティ―の後にも、オリガのコンサートの打ち上げの折に顔を合わせることが何回かあった。二人はそのたびに、あたりさわりのない会話をするにとどめていた。
ナオミとジョウとの関係が急に進展したのは、船上パーティーから九か月ほど経過した翌年の四月の終わりで、オリガの演奏するチェロ曲集の録音が完了した打ち上げパーティーの席であった。
パーティーが行なわれたのは、スペイン語の書物を輸入する会社が副業で営んでいるスペイン料理店で、学者や芸術家の固定客の多い店であった。
オリガは、その場の思い付きで、二十名ほどの出席者を男女が隣り合うように着席させた。
「いつも会話している人とは違う人と隣り合えば、きっと新しいセッションが生まれます。今日のパーティーを、みなさまの新しい発見の場にしていただければうれしいです。」
オリガはこう言って、客の一人ずつに、座る席を指定して行った。
ジョウは立場上最も末席に座ることが決まっていた。ナオミは長いテーブルの左の端に座ったジョウの右隣に席を与えられた。ナオミの右隣は音楽評論家の老紳士で、ナオミに軽く会釈はしたが、もっぱら自分の右隣に座ったオリガと話をした。
ナオミとジョウとは差し障りのない、オリガの仕事についての話をしていたが、メインディッシュが終わると、そうした差し障りのない話題も話しつくして、二人の会話が途切れた。
そこで、ナオミが話題を転じた。
「ジョウさん、相変わらず無口なんですね。」
「いえ、皆さんの会話を注意して聞いているものですから。仕事です。」
「今日はそんな気遣いは要らないわよ。オリガが気を付けてもてなさなくちゃいけないお客さんは、隣の評論家の先生だけでしょう。オリガに任せておけばいいのよ。」
「はい・・・」
「でも、ジョウさんにはジョウさんの美学があるみたいね。」
「ナオミ先生、心療内科の先生ですよね。人の心は何でも見通せるんですね。」
「何でも、ではないわ。それに、身体に症状が出ている方の心の原因を探るのと、そうではない人の心を知るのとは、同じじゃないわ。」
「でも、応用が利くんでしょう。」
「いつもじゃあないわ。それで、ジョウさんはお仕事で、自分の美学を追求しているんじゃないの?」
「わかりますか?そうです。自分としては、この段取りはこうでなくちゃ、とか、この取材はこういう運びじゃなくちゃ、とかいうことがいつも気になるんです。」
「それで、その通りにならないと、いらいらするでしょう?」
「自分を責めることが多いですね。」
「こうでなくちゃ、というのも、自分で決めてるんでしょう。自分で決めて、自分で自分を許せないのね。」
「自分で決めているんじゃなくて、自分の中の他人が決めているような気がします。こうでなくてはいけない、と思っているのにその通りにできないと、気になってしようがありません。眠れないことや、胃が痛くなくこともあります。」
「ジョウさんの美学は、奥さんはどう思っているのかしらね?」
ジョウの目から、慇懃な柔らかさが消えた。
「あいつとは、美学は合わないです。」
ナオミはその答えを聞いて、ぬらりとした何かに手が触れたような気がした。
「私、あなたの美学に少し興味があるのよ。」
「ぼくの仕事をご覧になれば、それが美学の通りです。それとも、そちらとは別の美学・・・のことをおっしゃってるのかな・・・」
ジョウは一旦言葉を切ると、声を低めて早口で続けた。
「ナオミ先生はお見通しのようですね。ぼくは、いつもこうやって自分に命令ばかりしている、自分の中の声に、本当は反抗したいんです。だから、そいつが自分を束縛するのと同じように、自分が他人を束縛してやりたいと思うんです。言葉で言うとこんなことになりますが、自分の衝動をあえて言葉にすると、こういうことなんだと思います。ぼくはコレクションしているものがあるので、それはよろしければお見せします。八丁堀のオフィスに置いてあります。オリガ先生はオフィスには滅多においでになりませんから。」
八丁堀のオフィスは、ナオミとオリガの父のタイスケの所有するワンルームマンションで、オリガの芸能活動の事務所として使われていた。
「コレクションっていうと?」
「絵が多いですね。伊藤晴雨の日本画とかの複製です。」
「一度見せてもらってもいいかしら?」
「いいですけれど・・・」
ジョウの目が一瞬ぎらりと光った。
「いいですけれど、ちょっと怖いかもしれませんよ。オフィスは密室で、ご心配もあるでしょうから、コレクションからいくつか見繕って、喫茶店かどこかでお見せしましょう。」
「それがジョウさんの美学ならば、そうさせてもらおうかしら。」
ジョウは、そこで会話を打ち切ると、思い出したように自分のスマートホンを取り出して、オリガのスケジュールの確認を始めた。スマートホンの待ち受け画面は、薄紫色で花弁の尖った花が数輪写っていた。
ナオミが尋ねた。
「待ち受け画面、お花なんですね。」
「はい。鉄仙です。クレマチスとも言います。」
「いつごろ咲く花なの?」
「五月の初めごろでしょう。ナオミさんは、この花の花言葉、ご存知ですか?」
「いいえ。何て言うの?教えて。」
ジョウは、一呼吸あけてから、さらに声を低めて囁いた。
「花言葉は、甘い束縛、です。」
ジョウはそう言いながら顔をスマートホンから上げて、ナオミの目を見た。
ナオミは、目が合った瞬間に、船上パーティーの時に感じたのと同じような戦慄を背中に覚えた。
ナオミは、それから月に一、二度、ジョウと二人で会うようになった。会うと言っても、いつもジョウは、いわゆる責め絵というジャンルの日本画の新たなコレクションを持参して、ナオミにどこが美しいかを淡々と説明するというものであった。
ジョウはナオミにつぎのような話をした。
「足首に喰い込んだ綱が、白い肌との境目に作る影のところ、よく描けているでしょう。子の影が、女の体と外の世界との境目で、そこがとても大事なんです。」
「こうやって天井から逆さにつり下がって揺れている和服の女に、どうしてぼくは惹かれるのか、自分にはわかっています。それは、ぼくと、ぼくにとっての母性との合金、アマルガムだからです。ぼくの生まれる前の世界の幸福、万能感、それを思い出すからです。もちろん、こんなこと、けしからんこと千万なことはわかっています。」
「体と外の世界との、影と光との境目、そこに全ての人間の欲望の秘密があるんです。」
ナオミは、ジョウと喫茶店で三度目に会った日の夜に、つぎのような夢を見た。
・・・ジョウは、都内の古い日本旅館の和室を予約し、ナオミと待ち合わせた。
ナオミが到着すると、ジョウは先に来て待っていた。
ジョウは、紺の絹物の着物に、羽織と袴は付けず、白足袋を履いていた。
ジョウは畳の上の座布団にナオミを座らせ、自分は座布団を当てないでナオミの前で畳みに手を付いて一礼してから、ナオミに当日の段取りを説明した。
「責めというものは、いかに相手を思いやって丁寧に縛ってゆくかが大事なんです。少なくともぼくの教わった流儀では、相手にけがをさせないよう、必要以上の負担をかけないよう、それでいてみっちりと責めに遭っている感覚を醸し出すよう、しっかりと段取りが決まっています。
まず、ナオミ先生は、ここに用意した白絹の襦袢に着替えて、白足袋を履いていただきます。
それから、両腕を後ろに回していただいて、そこから麻縄で作法に則って縛ってゆきます。痛さに耐えられない時にはおっしゃってください。美学として行うことですから、責めに会っている感覚だけで十分で、健康状態に不良な変更を生じさせることは、まったく必要ではなのです。縄は腕から体の前に掛け渡してゆきます。絵でご覧になると随分締めているように見えますが、実際はそうでもありません。
最後は梁から体を吊る形になります。自分は中級者ですので、体が完全に宙に浮いた形は危ないですからいたしません。膝を座布団についた形で、上半身を吊ります。
モデルを使う場合は、そこから撮影をいたしますが、ナオミ先生は差し障りがあるでしょうから、そこで打ち切りです。
あらかじめお約束した通り、ぼくは縛るのに必要な場合以外には、体を接触させることはいたしません。」
ナオミは説明を聞いて、これから茶道の点前でも執り行われるかのような気がした。
ジョウは段取りの通りに作法に則ってナオミの体を縛って行った。
ジョウの手つきは慎重であったが、体に掛けられた縄にその続きの縄の端を差し挟むときは、縄の端を指できゅっと素早く引いた。
ジョウは、腕に、肩に、胸に、太腿に、縄を掛けては、結び目を作って行った。
ナオミは、それにつれて少しずつ縄が締まって来る感覚に、鳥肌の立つのを覚えた。それはやはり痛みを伴うもので、自分の体の自由が次第に利かなくなって、体の関節が折り畳まれて行く感覚は、責めという言葉の通りのものであった。その感覚は、自分が道具すなわち物体として扱われていることをナオミに思い知らせるものであった。
ジョウはナオミの上半身を梁から吊るしながら言った。
「この部屋は、梁がしっかりしているので、愛好者はよく使っています。」
彼はナオミを吊るし終わると、彼女の前に正座して一礼し、それから畳の上を座位のまま移動して、ナオミの姿を鑑賞した。そしてジョウは言った。
「見事なお姿です。」
ナオミは縄に吊られてわずかに揺れながら、淡々としたジョウの言葉の裏に隠された黒い享楽の響きに共鳴していた。
ナオミは苦しい息の下から言った。
「写真、撮ってもいいわよ。後で見せて。」
彼女は、子宮の中で臍の緒に繋がれているかのような姿勢の苦しさに耐えながら、つぎのような思考が脳裏に巡るのを覚えた。
生きる道理としては、母体回帰から子供を引き離すことが正しい。正しさとは、生きるための道理だ。ジョウは、手続的にはあくまで厳密であるが、それは生きる道理ではなく、母体回帰の論理、すなわち生まれる以前の世界への回帰のために奉仕するための厳密だ。それは生の道理ではないから、裏返しの死の論理だ。
自分の体は今、かつての屈葬の遺体とそっくりの形で、物体と化している。では、なぜ物体化なのか?それは、母親を、父親の許にも、まして他の男の許にも行かせないで独占したいから?自分だけのものとなった母親に、自分も同じく物体となって回帰したいから?
自分は苦痛に喘ぎながら、悦びに震え、心臓は早鐘を打っている。今は、自分は生きていて、回帰が完成しているわけではないから、これは生まれる前の悦びそのものではない。苦痛は苦痛であって、甘い蜜の味がするようなものではない。それならば、自分は、生の道理に反していること、つまり「いけないこと」をしている、それを悦んでいるのか?
ジョウは自分に苦痛を与えることに悦びを感じながら、縄を掛けていたに違いない。それは生の道理に反していることを行っていることを悦んでいるのか?
ナオミは、この儀式における官能の正体について、このような言葉を脳裏に巡らせながら、物体と化した自分の体が官能に溺れていることを感じていた。
ジョウは頃合いを見計らうと、
「ご苦労様でした。それでは解いて行きます。」
と声を掛けた。
ジョウが縄を縛る手順とは逆回しの手順で解き終わると、ナオミは別室で襦袢を脱いだ。さすがに体には縄の跡が赤く残っていた。
ナオミは洋服に着替え終わると、ジョウに言った。
「確かに怪我はなかったけれど、息が苦しくなるし、曲げた関節は痛くなるわ。でも、その苦しみが・・・たまらないわね。」
「拙い技で申し訳ありません。」
「苦しいのを承知の上でモデルになったんだから、謝ることはないわ。それで、私はモデルとして気に入りましたか?」
「それはお綺麗なお姿でした。ほら、このとおり。」
ジョウはデジタルカメラの画面で、撮ったばかりの写真をナオミに見せた。
ナオミは、写真を丁寧に見ながら言った。
「照明の光が、体の折り曲げられた部分の暗さを引き立てているみたい。」
ジョウは静かに微笑を湛えながら答えた。
「おわかりいただけましたね。まさに、ぼくが撮りたかったものが撮れました。」
ナオミは、ジョウの微笑を見ながら、彼が縄で縛るのに必要な時以外に一切自分の体に触れなかったのは、なぜだろうと考えた。彼女は、それは彼が死の論理に自滅してしまわないで、この世に一歩踏みとどまっているところではないか、と思った。しかし、彼女には、彼は苦痛を与えることに悦びを感じていて、それで満足しきっているのかもしれない、という考えも浮かんだ。
ナオミは思い切ってジョウに聞いてみた。
「あなたは、私には約束通りこの儀式に必要なこと以外では手を触れなかったわ。それでいいの?私は女性として魅力がないのかしら?」
ジョウは淡々と答えた。
「ナオミ先生はとても魅力的です。でも、自分のこの世界はイメージの中で完結するものです。肉体的な関係ということをお尋ねであれば、それを取り結ぶことを必要としていません。それに、そうでなければ、今のような関係をこの世で持続することはむずかしいでしょう。このような関係でお厭でなければ、またお付き合いいただくことはできますか?」
彼女はジョウに答えて言った。
「よくわかったわ。よかったら、またモデルにしてもらえるかしら?」
ジョウは莞爾と笑った。
「ありがとうございます。次の時までに新しい技をよく練習しておきますから、また美しいひと時をご一緒いたしましょう。」
・・・ナオミの夢はそこで途切れた。彼女は両脇にじっとりと汗をかいていることに気が付いた。彼女は、このような夢を見たことで、自分の内心にジョウの相手になるような願望があるのだろうか、と自問した。そして、そうだとすれば、そのような自分自身を救い出さなければならない、そうしないと、ジョウと一緒に夢の中に引き込まれて自滅してしまうだろう、と思った。彼女は、ジョウとはこれ以上彼とは個人的に会わない方がよいと思った。
第四章
ナオミとオリガの父親であるタイスケは、内科の医師であったが、副業に不動産会社を経営していた。彼は、父親が戦前手に入れた築地の小さな土地に貸ビルを建てたのを手始めに、付近に三棟の貸ビルを保有するようになり、さらに投資用のマンションを四室保有して賃貸していた。彼はその財力を背景に、医師会の政治活動に参加し、保守党の国会議員の選挙活動を手伝い、自らも演説に立つこともあった。
彼の演説は、その時その時の社会の話題に対して、誰でも思いつくような対策を調子よく仕立てたもので、毎回続けて聞くと、まるで辻褄の合わないものであった。
「わが国の医療は世界一。社会保障は国の基本。われわれ医師の立場は、患者になられる国民の皆様とは、寸分も異なっていないのです!」
「みなさまの負担を上げることなく、社会保障を充実することが大切です。そのためには、専門家である医師が国会で活躍することが、どうしても必要なのです!」
「国政に医師の代表を送りましょう。みなさまの安全と健康を第一に考えるわれらの党に投票しましょう!」
内容は空疎だが調子のよいタイスケの演説を聞いて、政党の幹部は、彼を都議会議員候補に立つように頻りに進めた。タイスケは満更でもなかったが、家族全員が反対で、自分も医院と不動産会社との二つの経営者の立場にあって現実に手が放せないことから、立候補はいずれナオミに医院を譲った後の楽しみと考えることにしていた。
タイスケの妻で、ナオミとオリガ二人の母親のベラは、母親としての自分に満足していて、家庭の中でほぼ完結する生活を送っていた。ベラは、故郷のロシアに二年に一度ぐらいの割合で帰国して自分の老母に会うのが楽しみで、四人の子供を産み育てた老母を愛していた。そして、自分も老母のような母親になることを望み、彼女の人生はその通りになった。
ベラは、子供たちが小さい頃は、二人とも自分と同じように母親になることを夢見るものと思っていたが、結局は二人ともベラの性格は受け継がなかった。
ベラは、成人して久しい子供二人について、つぎのように考えていた。
ナオミについては、小さい時からタイスケの言うことをよく聞く優等生であったが、男性に依存する気持ちの強い性格であると考えていた。そして、ナオミが特定の男性に腰を落ち着けるつもりがないことを心配していた。ベラは、ナオミがこれから先もいろいろな男性との色恋沙汰に明け暮れるであろうと予想した。
オリガについては、ベラのように母親になりたいわけでも、ナオミのように男性に依存するのでもなく、端的に言えばタイスケのようになりたいのだ、と思っていた。ベラは、オリガの性格がタイスケによく似ていると思っていた。そして、オリガが男性に対しては自分の手駒とすること以上の興味を持っていないことを知っていた。
ベラには、ナオミのように男性に依存する気持ちも、オリガのように父親のようになろうとする気持ちも、頭では理解できても共感ができなかった。ベラにとっては、二十年前にナオミとオリガの二人の子育てに明け暮れていた時代が最も幸せである気がしていた。彼女は、今は愛犬を子供のようにかわいがりながら、孫ができるのを心待ちにしていたが、それが当分叶う見込みがないこともわかっていた。
オリガは、ベラとナオミのことを、二人とも男性の風下に立つことをよしとしていて、自分とは違って小さな人生を送っていると思っていた。オリガは、父親のタイスケが自分に、あれはするな、これをしろ、といったことを言うたびに、反発して口論するのであった。彼女は、年上の男性が自分に何か教えようとすると、それがたとえ親切心から出ているということを感じていても、聞く気がしないで拒絶してしまうのだった。彼らが言う言葉は、いかに正しそうであっても、言葉の意味を自分に押し付けていて、言葉の意味すること以外のことを排除していると感じるのであった。このごろはその感覚がさらに鋭敏になっていて、たとえば、
「これは椿だよ。」
と言われるだけで、その赤いものを椿ではないものとして受け止めることを禁止しているように思った。彼女は、言葉とはもともとそういうもので、意味によって人を縛るものであると思っていた。彼女は、そのことはしようがないということはわかっていたが、年上の男性の口から発せられる時には、言葉の宿命ともいえる抑圧性を強く感じて反発を覚えるのであった。言葉の抑圧性に敏感だからこそ、意味というものから離れることのできる音楽の世界が好きなのであった。しかも、過去の楽典と作例の約束事で、音の動きに意味が付着しやすい古典よりも、現代音楽を好むのであった。
オリガは、姉のナオミについては、いつも男の人の目を意識していること、特に朝も早くから起きて二時間ぐらいかけてメイクアップをするのが、嫌であった。ナオミは、気に入ったメイクアップが完成しないと、他人の前に顔を出せないのであった。オリガは、そんなことは、自分で自分を束縛しているだけのように思えた。オリガは、いつも薄化粧で、髪も簡単に首のところで束ねるだけであったが、自分はそれで十分に美しいと思っていた。撮影の時は多少メイクの専門家が手を加えることもあったが、姉ほど念の入った支度をすることはなかった。
ナオミは、医師として、いろいろな心の問題を抱える患者に接しながら、臨床の問題の解決の必要から、精神分析関係の文献を当たるうちに、人の性格の分析の方法を自ずと身に着けていた。彼女はその方法を応用して、ベラやオリガと自分との違いをつぎのように分析していた。
およそ人間の基本的な性格を決めるのは、子供と母親との関係、そして子供による母親の独占を引き裂く第三者である父親との関係である。父親は、子供を母体回帰から引き離す、生の道理である。人間は、子供と母親とが一体であった時代の幸福をこの世に置いて取り戻したいという欲望があり、一方で生きたいという欲望がある。その二つの欲望のバランスをどこでとるかによって、人間の性格が決まる。ベラは、その幸福を取り戻すために、自分が二人の子供の母親となることによって、かつての一体を再現しようとしている。オリガは、自分が父親になることで、本物の父親を差し置いて母親を独占しようとしている。そしてナオミは、女性として男性と関わることで、父親に対する女性としての母親に、同化しようとしているのだ。フランスの高名な精神科医は、女性のあり方は一つであるととらえることはできない、ということを言ったが、ナオミは自分たち家族の女性三人のあり方がそれを実証していると思った。
ナオミはこのように自分を含めた三人の性格の分析をしてみたが、だからといってそのどのあり方がすぐれているとか、自分のあり方を改めなければといった考えは持たなかった。このような性格の違いは、人が意識して動かせるものではないと思っていた。人間誰もが、生まれる前の世界に戻ろうとする力と、この世に生きようとする力とをどうバランスさせるか、その人なりの解決を図っているのだ。そして、自分のような男性に依存的な性格は、まさにそうあることでバランスがとられているのだから、意識の上でたとえ嫌だと思っても、何とか共存してゆかざるをえない。
ナオミは、女性が一つのあり方ではないのと同様、男性も一つのあり方ではないと思っていた。
タイスケは、自己拡張の意欲が強く、何でも支配しないと気が済まない性格である。それは、母親の代わりとなりうるものを、物質でも、名誉でも、愛人でも、何でも力ずくで手に入れたいのだ。タイスケは、生きる道理に従うのではなく、生きる道理を告げる内心の声に対して勝りたいのだ。
ジョウは、自己への束縛が強い性格である。それは、自分に命じる内心の声の要求を満たせないことによって、その声の主によって母親から分離させられることを恐れているのだ。ジョウの場合はその恐怖に耐えられないで、自分を束縛する内心の声の主に自分が成り代わって、母親と自分とが分離しがたいほどに堅く縛り合わされたアマルガムの形を作り出そうと、空想するようになったのだ。そして多分、他人に苦痛を与えることで、内心の声に反することに悦びを感じているのだ。
そして、人間はこのように多様であるから、他人の話を聞いた時には、それぞれがその言葉を自分の文脈の中に取り込むので、話し手の意図している意味がそのまま聞き手に移し替えられることはないのは明らかだ。だから、何でも話し合えばお互い歩み寄れるというのは、現実には起こりえないのだ。ナオミは、少なくとも、タイスケとオリガは、他人の話を聞いて自分の考えを改めるようなことはなかったので、自分のこの仮説は当たっていると思った。
第五章
美術教師のヨシミチは、妹のリオンを自分の部屋に住まわせることになった。
リオンは、重度の拒食症で、治療のために東京の病院に通うことになったからであった。
リオンは、小さい頃から学校の成績も良く、見たところはおとなしそうな頭の良い女の子であった。
しかし、彼女はひとたび激高すると、相手を汚い言葉でののしった。
彼女が思春期に入ってから、激高の頻度が増加した。
ヨシミチが見るところ、彼女が激高するのは、いつも、あることがきっかけであった。
そのきっかけとは、家族でも教師でも友人でも、彼女が他の人とどこか変わったことをしている時に、それを直すように彼女に言うことであった。それも、普通の会話であれば自然に流れるであろうと思われる話題の時に激高が起こるのであった。
たとえば、母親が彼女に、
「裁縫は、多少はできないと困るよ。みんな多少はおうちで習っているから、うちでもかあさんが教えてあげる。」
と言ったことがあった。
リオンは、激高して、普段とは全く別人のような、太い大きな声を出して、母親につぎのような言葉を投げつけた。
「こっちがなぜ人並みに裁縫ができないか、世の中をなんとか回してゆくためにどんな思いをしているか、わかりもしないで。どうせ誰かに言わされているんだろうが、そんなことで世の中を変えられると思ったら、大間違いだわ。」
このような言葉を投げかけられた者は、その意味を理解することができず、リオンの激高に巻き込まれて不毛の口論を始めるのであった。リオンは、自分が世界の枠組みを支えるために犠牲になっていて、敵方はその枠組みに絶えず攻撃を加えてくるので、自分はその防御のために精いっぱいである、と言っているように聞こえた。彼女の前提としている世界は、他の者には理解のできないものであった。リオンは同じ内容を何時間でも繰り返して強い口調のまま倦むことなく繰り返すので、相手はだいたい根負けして、リオンの前から姿を隠すのであった。
激高していない時のリオンは、おとなしい知的な女性であり、花の栽培を好み、ペットの犬をかわいがり、時に家族と談笑することもあった。
ヨシミチは、何度となく自分も激高の対象となるうちに、気が付くところがあった。
激高を招くのは、こちらの言葉の意味に反発しているのではない。リオンの言葉も、何かの意味を伝えようとしているのではない。彼女は、自分に他人と同じようにしろと指示されること自体を、敵の攻撃ととらえているのだ。彼女は、彼女を中心とする独特の世界の枠組みを前提にしていて、その中心に彼女自身が主催者ないし支配者として君臨しているのだ。彼女に他人と合わせるように言うことは、その枠組みに口を出すことに外ならず、すなわち敵の攻撃以外の何物でもないのだ。逆に、彼女の世界の枠組みに抵触しないことを心得ている人には、むしろやさしかったりするのだ。
ヨシミチには、リオンの激高した忘れられない思い出があった。
それは彼女の高校卒業を祝う、十人ほどの親族の集まりの席上であった。
親族は、彼女の卒業を祝う言葉を一通り述べ合った後で、酒の入った宴会になった。
大人たちは酔いが回って、それぞれ勝手なことをリオンに構わず話し出した。
帰省してこの宴会に列席していたヨシミチは、母親の兄すなわちリオンの伯父が、ほろ酔いの赤ら顔で、
「リオンちゃん、器量よしだから、すぐにいいお婿さんが見つかるよ。」
と言った時に、リオンの額に青筋が立ったのに気が付いた。
器量よしという言葉については、事実、リオンは学校では男子生徒に人気があった。彼女は小柄で、おかっぱに切りそろえた黒髪が、小柄な容姿とバランスがとれていた。白い細面の顔には、二重瞼のヨシミチとは異なり、切れ長の細い目と、小さな赤い唇が古風な美しさを湛えていた。彼女の姿に、たとえば伝説の雪女や、能に出て来る小面をつけた姫君のような、一種神秘な威厳が感じられた。
リオンは、突然無表情になると立ち上がり、まるで巫女が託宣を告げるかのように、つぎのように言った。その声は、彼女の小柄な体のどこから発せられるのかと思われるほど、太く低い声であった。
「おまえたちがあいつらの仲間ならば、すぐにここから立ち去れ。さあ、早く立ち去れ。」
リオンと同居していない親族は、リオンの激高に慣れていないため、どう反応してよいかわからず、やがて残った料理を手早くタッパーに詰めると、逃げるように帰って行った。帰る親族に、母親とヨシミチの兄が平身低頭して謝った。
ヨシミチは、親族が彼女をこの世の主宰者としてではなく、高校を卒業した親戚の少女として扱ったことが、激高を招いたのではないかと推察した。
彼女は、自分の世界の枠組みとの抵触に遭遇した時には、それが正しいか正しくないかの判断を行うのではなく、その手前の門前において、その発言者が敵か敵でないかの判断をして、敵であればそれを強烈に排斥するのであった。
リオンは地元の郵便局の事務員となったが、働き始めて間もなく欠勤が続き、解雇された。彼女の仕事は、マニュアルに記載された通り正確で丁寧であったが、ほかの局員の仕事の流れに合わず、それによって生じた摩擦が原因と推察された。それからしばらく彼女は母親と長男である兄との三人暮らしで、家事を担当して暮らしていたが、食が細くなった。極端に痩せてきたことから、母親がリオンを医院に連れて行った。彼女は重い拒食症で、地元の医師は、できることならば東京の病院で診てもらったほうがよいと勧めた。
リオンは、ヨシミチの自宅のアパートに近い、東京の文京区の大学病院の心療内科に週一回通うようになった。
オリガの姉のナオミは、川崎の病院から最近この病院に転勤していて、リオンはナオミのこの病院での初めての患者となった。
ヨシミチは、リオンの通院には、勤め先の許可をとって学校を早退して付き添った。
ナオミは、リオンを一通り診察してから、リオンのいない別室で、ヨシミチからリオンについての話を聞いた。
ナオミは言った。
「こういうケースの場合、拒食症のような本人の目にもはっきりした症状が出ないと、本人が医者に診察してもらうことをなかなか承諾しないでしょう。本人に自覚症状のない場合、ご家族が何十年も誰にも相談できないで苦労されていることもあります。ですから、このたびは自覚症状が現れたことで、よい方向に転じるきっかけになるかもしれません。拒食症自体は薬や栄養剤である程度回復させることはできますが、その原因の部分を解きほぐすことができれば、さらに治療効果が高まります。」
ナオミはヨシミチから、リオンの激高についての話を一通り聞き取った。
ナオミは質問を続けた。
「それで、リオンさんが日常にされていることで、他に気になることはありませんか?」
「そうですね。私が勤めに出ている間は、家事をやってくれています。近所の買い物にも出ています。それから、スケッチブックに絵を描いて、そこにびっしりと何か文章を書いているようなのですが、私には見せてくれません。」
「無理にスケッチブックを覗くのはまずいですね。でも、どんな絵を描かれているか、様子だけでもわかりませんか?」
「黒い楕円の石のようなものをいくつか描いている様子でした。背景が青緑で、水の底のような絵です。湖の底にマリモがいくつかある、そんな感じでした。」
「そうですか。マリモですか・・・」
「あとは、よく窓を開けて外を見ているようです。本人は自分の手下のような者と連絡をとっていると思っている節があります。それは、自分がいつもより学校から早く帰ったりしたときに、
『また中断か、後でな』
といったことを呟いたことが何度かあったから、そう推察しているのです。」
「そうですか。幻聴があるのかもしれませんね。」
「そのほかには、別に暴れるとか、近所の人とトラブルを起こすといったことがないことはわかっているので、自分も昼間は妹を独りにして出かけているんです。」
「あなたは、学校とおっしゃいましたが、どこか学校に行かれているんですか?参考のためにお聞きするので、お答えになりたくなければけっこうですが。」
「私は教師です。」
「なるほど。それで、平日の昼間はリオンさんはお独りで過ごしているのですね。」
「夜間や休日も、リオンのことが心配ですから、私の部屋で彼女を引き取ってからは、私は一人で学校以外に外出することはほとんどなくなりました。」
ナオミは今日のところは話を打ち切ることにした。
「治療は場合によると長くかかるかもしれません。本人と口論したりすると、悪化することも考えられますから、なるべく平穏に過ごせるように気を付けてあげてください。」
「わかりました、私はこつをつかんでいますから、ここ数年は私に対しては激高したことはないのです。引き続きよろしくお願いいたします。」
ヨシミチはこう言って頭を下げて辞去した。
ヨシミチは、家族が長年抱えていた問題を、初めて第三者に打ち明けることができたことで、心の荷が軽くなった気がしていた。当人に不調の自覚がない限りは、当人は医者に行くことを承知するはずがなく、家族は誰にも言えないで当人の問題を抱えているほかなかったのであるが、拒食症という症状が出て、本人も医師の診療を受けることを容認したからこそ、初めて第三者に話すことができたのであった。彼はもとより、リオンが一朝一夕に回復することは期待していなかった。それよりも、自分の話をナオミ先生に聞いてもらったことで、自分の中にいつも通奏低音のようにあった抑鬱が少し癒された思いであった。そして彼は、人の心の問題を預かるナオミの仕事は、目に見えない激務であろうと想像した。
ナオミは、リオンの病気は拒食症であって、自分の任務はそれを治療することであり、彼女の激高については治療の参考として考慮するという方針をとることにした。そして、今後激高の方で問題が大きくなるようであれば、その時には専門の医師を紹介しようと考えた。
第六章
四月の中旬の夕方に催された、上野奏楽堂のコンサートの演目は、フランスのラヴェルとドビュッシーの作曲した絃楽四重奏曲二曲で、オリガはチェロのパートを受け持っていた。
ヨシミチは、上野奏楽堂は自宅から徒歩で行ける距離にあり、チケットの価格も手ごろであったので、気分転換にリオンを伴って、このコンサートを聴きに行った。
開演前にヨシミチとリオンが席に向かって歩いているとき、後ろから声をかける女性があった。
リオンは振り返ると、すぐに誰だかわかって、小さく手を振りながら答えた。
「ナオミ先生!」
「リオンさん、あら、お兄さまも。」
リオンは半年の間毎週ナオミの治療を受けていて、すっかりナオミと顔なじみになっていた。
ヨシミチも挨拶をした。
「どうも。こんなところでお会いするとは。いつも病院ではお世話になっています。」
「いえいえ、とんでもない。お二人はコンサートにはよく行かれるのですか?」
ヨシミチが答えた。
「いえ、リオンが上京してから、今夜が初めてです。先生はよく行かれるのですか?」
「ああ、私は、サクラで来ているのよ。今日妹が演奏で出ているから。」
「カルテットの四人のうちのどなたかが妹さん・・・ということは、ナオミ先生はオリガさんのお姉さんですか?」
「そうです。よくおわかりになりましたね。」
「だってバイオリンの二人とビオラは男性ですからね。」
「そうか。すぐわかるわよね。今日のコンサートはオリガの名前では出ていないから、お客さんがあんまり集まらないので、切符を買わされたんです。オリガは、自分目当てのお客さんばかりになると、カルテットのあとの三人に悪いから、これでいいと言っていました。今日はわりと自分のような素人にも聴きやすい曲でよかったです。もともと自分は音楽よりも美術の方が好きなんですが・・・」
ヨシミチはその言葉で思わずつばを飲み込んだ。
「美術がお好きですか。自分は美術の教師です。本当は画家と名乗りたいんですが、画家としては独立できなくて、教師をしています。」
「そうだったんですね。リオンさん、そんな話、先生にはしてくれないものだから。」
リオンは穏やかに笑っただけで、言葉は返さなかった。
「お兄さまは、画家ということは、油絵ですか?」
「はい。抽象画も具象画も描きます。私はオリガさんをモデルにした絵を描いていて、以前は時々コンサートには、聴くというよりも、舞台を見るために行っていました。」
「オリガのファンでいらっしゃるのね。ありがとうございます。でも、ファンになっても甲斐がないでしょう。オリガは自分からファンに何かするということはないから。」
「セレブの方はだいたいそうでしょう。気にはしていません。
そろそろ開演の時間です。終演後はお目にかかれないでしょうから、こちらで失礼いたします。」
「どうも、失礼いたします。」
ヨシミチとリオンが席に着くと、リオンがやや吊り上がった目でヨシミチの目を見ながら、つぎのように言った。
「お兄ちゃんとナオミ先生は、こうやって出会う手筈にしてあったのよ。私に感謝してね。」
ヨシミチは例によって意味が理解できないままその言葉を受け止めた。ひとつ確かなのは、リオンは自分とナオミとが会話したことに腹を立てたりはしていないことであった。
カルテットの演奏は、ヨシミチには、個性の強いオリガのチェロを、バイオリン二挺とビオラ一挺で辛うじてバランスをとっているように聞こえた。
ラヴェルの絃楽四重奏曲の第三楽章は、日本の子守唄を思わせるゆっくりした静かな曲で、リオンはヨシミチの肩におかっぱの頭を預けて、すやすやと寝息を立てて居眠りをしていた。彼は、妹が音楽を聴きながらリラックスしている様子を見て、コンサートに連れて来てよかったと思った。
カルテットの高音部が、努めて和音の組み立てをいわば立体的に聞かせようとしているなかで、低音のチェロは音楽としての流れを促すように流麗に歌っていた。ヨシミチは、直感的に、一つの楽曲に総合されたこの二種の差異を、自分の芸術とオリガの芸術の違いになぞらえて受け取っていた。
ヨシミチの絵の描き方は、まず実際に見えるもののスケッチから入って、その姿と、その意味とを自分の中によく焼き付けられたうえで、今度はその焼き付けられたものが、自分の感性のフィルターを通して再び立ち昇る形に仕上げてゆく、という手法であった。そのため、彼としては、抽象画も、具象画の入り口を通って初めて成り立つものであった。具象とその意味とに基づかないとすれば、見る人が作品に共感する糸口がなくなってしまうだろうと思っていた。
ヨシミチの想像するオリガの芸術は、そうではなくて、絵画にたとえれば、芸術家の心の中から立ち昇るものをそのまま画面に表現するものであった。それは、いわば他人に代わって夢を見て、それを表現して見せるということでもあった。そのため、意味というものは、香水の薫りのように全体において漂ってはいても、表現自体をコントロールするものではなかった。意味という、観客の共感を得る糸口を初めからあてにしない表現で、なおかつ共感を達成するとすれば、それは絵画と音楽との違いにとどまらず、オリガの才能の表れであって、自分には真似のできないものだと思った。
コンサートが終了すると、リオンはヨシミチに言った。
「私は先に帰る。お兄ちゃんは、ナオミ先生を見つけて、声を掛けるのよ。オリガの方じゃないわよ。いいわね。」
彼女は早口にこのようにヨシミチに言いつけると、足早に奏楽堂を出て行った。
ヨシミチは、リオンの言うことは、いつも基本的には従うことにしていた。それは、彼女の言うことに逆らうと、後で彼女が激高する可能性が極めて高いからであったが、最近は、彼はリオンの言う不思議なことを何か巫女の託宣のようなものとして受け止めて、それには理解できる限りでは素直に従わないといけないような気持になっていた。
彼は、奏楽堂の客席の出口で待っていると、ナオミが現れた。彼はナオミに声を掛けた。
「演奏、よかったですね。これからオリガさんの楽屋に行かれるのですか?」
ナオミは、ヨシミチに声を掛けられて、特に驚く様子を見せなかった。
「リオンさんは?」
「一足先に帰りました。」
「私は楽屋には寄りません。オリガは仲間と多分打ち上げにどこかに繰り出すつもりです。私は邪魔になるだけですから、普段から楽屋には立ち寄らないんです。」
「それならば、ご迷惑でなければ、駅までいっしょに歩きませんか?」
「リオンさんがおうちで待っているんじゃないかしら?」
「実はリオンがそうしろと言うので、ナオミ先生に声を掛けたんです。」
「わかりました。いっしょに歩くぐらいのことであれば、リオンさんに逆らってはいけませんね。」
二人が奏楽堂から外に出ると、すっかり青葉になった桜の木が少し強い春風に揺れて、暗くなった空には三日月が青白く上がっていた。
「お兄さま、駅はお宅とは反対方向なんでしょう?」
「そうですが、構いません。それから、お兄さまというのでは、呼びにくいでしょう。自分はサエキ・ヨシミチという名前です。」
「じゃあ、サエキ先生とお呼びした方がいいわね。」
「『先生』はつけなくていいです。生徒には、陰で自分のことを呼び捨てにしているやつもいます。」
ナオミはふふっと笑った。
「ならば、私のことも、『先生』はつけないで呼んでください。」
「ナオミさんとお呼びするのもちょっとなれなれしいので、苗字でイチハラさんと呼びましょう。」
「ナオミさんでいいです。みんなそう呼びます。サエキさんは、私と同級生ぐらいかしら?」
「今年で三十三歳です。」
「あら、当たったかもしれない。早生まれ?」
「いいえ。七月生まれです。」
「私は九月です。お宅には奥様はおられないの?」
「独り者です。リオンを預かってからは、近所のお店では私が嫁さんをもらったと勘違いして、お祝いを言われたりして、面食らいました。」
「私も独り者。今の病院に移るまでは独り暮らしをしていたんですけど、今は実家に戻って母親に家事をやってもらっています。」
二人の傍を、応援団と思われる詰襟の身なりの一団が、大分酔っぱらって、昔の寮歌のような古い歌を放吟しながら通り過ぎた。
「随分と古風な学生ね。」
「このあたりは学校が多いから、いろいろな子を見かけますが、それにしても時代がかっていますね。大正か昭和の初めの歌でしょう、意味がわかって歌っているのかな?」
「意味なんかわからなくても、勢いで歌っているんでしょう。ところで、サエキさんは、お酒は強いの?」
「お付き合いでは飲みますが、自宅で飲むことはないです。リオンも飲みませんし。」
「私、お酒は、ウワバミ。仕事柄、患者さんが良くなるばっかりじゃないから、ストレスがたまるんで、お酒の量が増えてもしようがないっていうのが、言い訳なの。」
「今日はこれから飲まれるんですか?」
「女一人で居酒屋には入りにくいから、ワンショットバーとか、入りやすい店をいくつか見つけてあって、そこに寄ろうと思っていたのよ。でも、サエキさんが一緒ならば、居酒屋に入れるわね。」
「ご迷惑でなければ、お付き合いしましょうか?」
「迷惑なんて、とんでもないわ。お酒、あまりお好きじゃないんだったら、逆にご迷惑じゃない?」
「いえ、お酒の席の雰囲気は好きなんです。」
「私、さっきの学生さんが入るようなお店がいいわ。私が学生だった頃は、まわりの男子はみんな医者の息子で、高そうなイタリア料理とか寿司屋とか、そういうところにばっかり連れて行かれて、居酒屋は知らないのよ。」
「それならば、教師仲間で行く店があります。学生が行く店よりももうちょっと静かですが、そんなにきれいな店ではありません。そういうところでよければご案内しましょう。タクシーで五分ぐらいのところです。」
ヨシミチは、スマートホンで店に電話をかけて席の空きを確認すると、駅前でタクシーを拾い、ナオミを乗せて店に向かった。
ヨシミチの連れて行った居酒屋は、黒い板壁の木造の建物で、芝居に出て来るような縄のれんがかかっていた。
ヨシミチとナオミはカウンターに着席した。ナオミは店内を珍しそうに一通り眺めてから、言った。
「ここならば、うちの病院からも近いわね。」
「多分、同僚の先生方もこの店に来てるんじゃないでしょうか?」
「こういうところ、誰も私を連れて来てくれないのよ。」
確かに、ナオミはウワバミを自称するように、つまみはあまり食べないで、熱燗の日本酒の徳利を次々に空けて行った。
「私、半分はロシア人の血が入っているんです。向こうではウオッカは男女を問わないで飲むから、アルコールに強い体質を私は受け継いでいるんです。」
ナオミは、半合ほどしか酒の進まないヨシミチに、このように言い訳をした。
ナオミがヨシミチに言った。
「ところで、リオンさんの、例のマリモの絵のことですけれど、やっぱりどういう意味なのか分からなくって・・・」
「ああ、覚えておられたのですね。」
「私は余程気にしているのか、夢にマリモが出てきました。」
「どんな夢でしたか?」
「水の底に、マリモがいくつかあって、その先に立派な建物がある、それだけでした。」
「水底の建物は、龍宮城みたいなものですか?」
「そうですね。その建物は、龍宮と呼べないこともないでしょう。」
「リオンは、独りで龍宮の主をしているような心の状態なのでしょうか?」
「そういうことなのかもしれないですね。リオンさんがこの世の主催者だと思っているというのは、龍宮の主ということなのかもしれませんね。最近は拒食症の方も多少良くなったので、よかったですね。」
「先生のおかげで、ありがとうございます。」
「あら、先生とは呼ばない約束でしょう?」
「そうですね。失礼しました。」
ヨシミチはそう答えながら、ナオミの夢を絵にするとどういうものになるか、想像していた。
「ナオミさんの夢を絵にするのは、難しいなあ。自分は具象から入って行くやり方なので、初めから見たことのないものを描くのは、やったことがないんです。」
「そうだ、絵と言えば、オリガをモデルにした絵を描いておられるのでしょう?一度見てみたいわ。」
「なかなか完成しないんです。もう何年も描き続けているのですが、オリガさんのコンサートに行くたびに、新しい印象が付け加えられるものですから。」
「オリガは言うことがころころ変わるから。本人は自分の気持ちに正直なんですが、周りはよく振り回されます。きのうも突然、バッハを極めたいって言い出して、長い間放っておいていたチェロ組曲の楽譜を引っ張り出して、朝から夜中までずっと弾いていたんです。彼女にはマネジャーがいるんですが、もう決まっているコンサートの曲目を急に変更されるんじゃないかって、気を揉んで見ていました。」
「そうですか。また自分の絵を直さないといけなくなりそうですね。」
時計が十時を回ったところで、二人は勘定を割り勘で済ませて、店から出た。
ヨシミチは、地下鉄の駅までナオミを送った。彼は尋ねた。
「ナオミさん、患者の親族と、プライベートで仲良くなったりするのは、まずいとか、あるんですか?」
「病院の建前はどうなんでしょうかね?私は気にならないんだけど。割り勘だから問題ないでしょう。サエキさん、またお酒に付き合っていただけますか?」
「喜んで。」
「じゃ、来週の火曜日の夜はどうかしら?」
「空いていると思います。」
二人は再会を約束すると、ナオミは地下鉄の駅の階段を下りて行き、ヨシミチはその姿を見送ってから夜道を歩いて自宅に戻った。
ヨシミチが帰宅すると、リオはまだ寝ないで彼の帰りを待っていた。
「お兄ちゃん、私の言う通りにしたみたいね。」
「うん。また会おうということになった。」
「それでいいのよ。」
リオンはぶっきらぼうにそう言うと、自分の寝室代わりにしている押し入れの下段に入って襖をぴしゃりと閉めた。
第七章
ナオミは、オリガと朝食を摂りながら、前の晩にヨシミチと飲んだことをオリガに話した。
ナオミはオリガにこう言った。
「サエキさん、よくオリガのコンサートで花束を持って来ていたらしいわ。インスタグラムとか、よく書き込みをしているって言ってた。オリガ、どんな人か知ってた?」
「そういう人がいるっていう程度。いつも文章の書き込みをして来る人で、私は誰の書き込みもだいたい読み飛ばしてるから、何を書いて来ているのか、覚えてないわ。」
「オリガの好みのタイプじゃないわね。草食系の美少年が、三十代に入って、程よく熟れたっていう感じの人よ。目が子供みたいにきらきらしているのよ。背はそんなに高くないけれど。身なりはあまり構わないタイプね。」
オリガの目が急に険しくなった。オリガはそれまでと違う低い声で、ナオミに言った。
「姉さん、私のファンを自分のものにするつもり?」
ナオミはオリガの反応に驚いて、口に運びかけたコーヒーカップを宙で止めた。
「だって、オリガにとって、『そういう人がいる』っていう程度の人じゃないの?」
「私が、そういう人がいるって意識しているファンは、五人ぐらいしかいないのよ。姉さん、また私のものを取って行こうとしてるわね。」
ナオミは、その言葉でオリガが幼少の頃のことを思い出した。もともとオリガがさして大事にしていなかった人形でナオミが遊んでいると、オリガはむきになって、
「お姉ちゃん、私のものを取ってゆかないで!」
と言って取り返しに来たものだった。
オリガが続けた。
「そう言えば、きのうはその人、私に花束を持って来なかったわ。」
「それはオリガのソロじゃなくて、カルテットの一員だから、控えたんだと思うよ。」
「そうじゃないわ。病院で姉さんに会った時から、姉さんに気があったのよ。」
ナオミは、オリガがこのような決めつける言い方を始めると、機嫌が直るのに結構手こずることを経験で知っていた。
ナオミはオリガの気を鎮めなければと言葉を探して、言った。
「サエキさんは、オリガをモデルにした絵を、ずっとライフワークみたいに直し続けているのよ。私はサエキさんを取り上げたりしないから、きっとこのままあなたのファンを続けるわ。」
ナオミは内心で、オリガがファンを普段大切にしないでおいて、こういう時には自分の所有物のように権利を主張する資格はないと思ったが、内心に押し込めて、口には出さなかった。
オリガが呟いた。
「その絵、どんな絵なのかしら?見てみたいわ。」
ナオミが言った。
「ファンのことが気になるなんて、珍しいわね。サエキさんに会ったら頼んでおいてもいいわ。」
オリガはナオミに頼むとも何とも返事をしなかった。
オリガは自室に戻ると、過去のインスタグラムなどへのサエキ・ヨシミチの書き込みを、一つずつ掘り起こして行った。
それは彼女にとって、ここ数年の自分の辿った月日を遡ることでもあった。
彼女は、過去には一切縛られないで、その時その時に自分がしたいことをするという生き方をして来たので、過去を振り返ることは今までやったことがなかった。
彼女は、ヨシミチの書き込んだ言葉を確認した。彼女はそのうえで、自分がその時その時の気分で行って来たことに、ヨシミチがすべて賛意を示していることから、彼は自分の考えのない、お追従ものではないか、という気がした。しかしながら、自分への批判がいささかも含まれることのない彼の言葉を続けて読むことは、自分のプライドの部分で心地よいことは否めなかった。彼女は、もしも彼がお追従ものではないとすれば、本気で自分のことを愛しているのかもしれない、とさえ思った。
彼女は、その性分として、そのような考えに至った以上、行動によって確かめたいという結論を導き出した。
彼女は、ダイニングルームに戻って、休日でパジャマのままで雑誌を繰っていたナオミに言った。
「姉さん、そのサエキさんの絵を見てみたい。一度会えるようにしてくれない?」
ナオミは雑誌から顔を上げてオリガを見た。オリガの表情には、相手に有無を言わさない意志が表れていた。
ナオミは答えた。
「わかったわ。今度会った時に聞いてみるから。」
オリガは自分の依頼への手ごたえを感じたので、そのままくるりと後ろを向いて、自室に戻って行った。
ナオミは、次の週の火曜日の晩、約束の通り、ヨシミチと居酒屋で待ち合わせた。
ナオミがヨシミチに尋ねた。
「リオンさん、お兄さんをまた夜に連れ出して、何か言っていませんでしたか?」
「いいえ。リオンも来るかと尋ねたら、断られましたが。」
「そうね。リオンさんも成人なんだから、お酒を飲んでもいいわよね。」
「リオンは酒は嫌いみたいです。東京に知り合いがいないから、買い物の他はずっと家に籠っているのがちょっと心配ですが・・・」
「リオンさんの症状も多少改善しましたので、そろそろ、お話ができる人の輪に入るようにした方がいいと思っています。方法を考えます。」
「ありがとうございます。」
「ここは病院ではないから、リオンさんの病気のことはこのぐらいにしておきましょう。」
ナオミは、オリガの依頼を自然な形でもちかけるため、ヨシミチにまずは自分の家族の話を始め、それからオリガの普段の様子を話して聞かせた。
「・・・それで、マネジャーのジョウさんは、オリガの気まぐれの変更に対応するのがたいへんなのよ。」
「オリガさんらしいですね。いつも自信にあふれていて、いつも新しいことを発案する。芸術家肌なんですね。」
「サエキさんだって、芸術家肌に見えますよ。」
「えっ、どのあたりが、ですか?」
「だって、学校の先生のお仲間にも入っていないみたいだし、あまりお友達は多くないみたいだし。」
「そう言われればそうですね。昼休みに同僚と弁当を食べるぐらいですね。仲良くしている同僚も一人二人いるにはいるんですが、あまり飲みに行くわけでもないですし。でも、それは自分が変わっているということで、別に芸術家肌とかじゃないですよ。」
「あなたが人と群れないのは、人を観察していたいから、見る人でありたいからでしょう?」
ヨシミチは盃を持った手を止めた。
「さすがよくわかりましたね。見る人、まさにそうですね。自分の絵は、見ることの積み重ねの後の、エッセンスのアウトプットだと思っています。」
「そういえば、私はあなたの絵を見たことがないわ。」
「インスタグラムに絵を写真に撮って投稿したこともありますが、誰も見ている様子がないので、消しました。それに、絵には大きさや、絵具の凹凸にも思い入れがあるので、写真では自分としてはどうも満足できません。」
「それじゃあ、現物を見るしか方法はないってことかしら。」
「現物は、大きいものは学校の美術室に置いています。小さいものはうちの押し入れにあります。押し入れの下の段がリオンの寝室です。」
「おたくまで押し掛けるのはまずいし・・・」
「それならば、うちの学校の学園祭が来月ありますから、その時ならば外部の方も学校に入れます。大きな作品はそこでお見せできます。」
「オリガをモデルにした絵も、学校にあるんですか?」
「そうですが、未完成です。」
「実はね、オリガにあなたの話をしたら、自分をモデルにした絵をぜひ見たいと言い出したんだけれど、連れて行ってもいいかしら?」
「ああ、そうなんですね。自分は構いません。でも未完成ですし、相当に抽象化されていますので、オリガさんの気に入らないかもしれませんよ。本当に見に来られるんですか?」
「あの子の性分で、言い出したら聞きませんから、本当に見に行きます。」
「そうなると、うちの学校はがさつな男子校ですが、みんな頭はよく回るので、オリガさんのような有名な方が来られると、すぐに気付いて騒ぐでしょうから、目立たない恰好で来ていただいた方がいいです。」
ナオミはヨシミチから学園祭の日時を聞いた。
ヨシミチは、オリガの来訪の希望を、自分でも驚くほど冷静に受け止めた。
有名人のファンであれば、本人の来訪は光栄の至りで、舞い上がるほど喜んでもよいはずであったが、彼は自分の気持ちにはそういう興奮は見出せなかった。
彼の胸中には、絵のモデルを舞台の上でない場所で観察することへの、期待と不安とが交錯した。期待と不安とのどちらが大きいかというと、不安の方が大きかった。それは、彼がこれまで三年間推敲を重ねて来たモデルのイメージを覆さなければならなくなるかもしれないからであった。
彼は妹のリオンに、オリガがナオミと自分を訪ねて来ることを話した。
リオンは言った。
「お兄ちゃんの中で、オリガがどういう存在なのか、自分でよくわかったでしょう。ファンだということは、その人と自分との間に距離を置いていることとは、矛盾しないのよ。お兄ちゃんは、高嶺の花を欲しがる苦労性なのよ。それは自分を満足させるのが、本当は嫌だからなのよ。すぐ手に入るものならば、満足が現実になってしまうから。」
彼には妹の言うことがすぐには理解できなかったが、後で心中で反芻するうちに、妹がヨシミチのことをヨシミチ自身よりもよくわかっていることに気が付いた。彼は、オリガはあくまで自分の絵のモデルであって、男女の関係をもつようなことは期待していなかったが、オリガを女性として美しいと思っていたことは間違いがなかった。彼はオリガのコンサートに通い続けたのには、高嶺の花を求める心、もっと言うと、そういうストイックな自己像を愛する心、そういう心がなかったかというと、それは嘘になると思った。そしてその気持ちは、オリガを女性として愛しているということとは、紙一重で異なることに気が付いた。
五月末の学園祭の当日、ナオミがヨシミチと予め打ち合わせた時刻に、オリガのマネジャーのジョウの運転するスポーツカーが正門を少し行き過ぎた場所に停まった。車からナオミとオリガが降りて、二人は学校の玄関の案内図を確かめると、ヨシミチの待つ美術室を訪ねた。
オリガは、人目に立たないようにしているつもりで、迷彩柄のパンツに同じ柄のキャップを被って、サングラスをかけていたが、ナオミは彼女の派手な服装に内心ひやひやして連れて来たのであった。
学園祭の最中とあって、体育館で生徒のバンドが演奏しているベースギターの音が、美術室のガラスをじんじんと鳴らしていた。
「サエキさん、こんにちは」
「ああ、どうも。ようこそこんなところまでお越しくださいました。」
「こちらが妹のオリガです。」
オリガが挨拶した。
「初めまして。オリガです。」
「サエキです。いつもお姉さまにはお世話になっています。オリガさんのコンサートも何度かうかがっています。」
「存じています。いつも花束をいただいて、ありがとうございます。」
ナオミは、ヨシミチがオリガのファンなのに、嬉しそうな表情でもなく、握手を求めたりすることもなく、以前からの知人を迎えるような淡々とした様子であることを不思議に思った。
ヨシミチはナオミとオリガに、いつも司書たちに振舞っているのと同じお茶を出した。
ナオミは、サエキがにこやかな様子でお茶を給仕しながらも、彼がオリガの様子を目だけは笑わないでじっと観察していることに気が付いた。
オリガが言った。
「いつもインスタグラムにお書きいただくコメント、読んでました。いつも励ましていただいて感謝します。返信はどなたにもしないもので、ごめんなさいね。」
「いえ、いえ。ファンの独り言ですから。スルーしていただいていいんです。むしろ、あんなことを書いてご気分を悪くしていれば、申し訳ありません。どうも人様とのほどよい距離感をつかむのが苦手で、馴れ馴れしく見えているのではと思っています。書き込みをする人には相当変わった方もいるらしいですから、有名な人はレスポンスをされない人も多いでしょう。」
ナオミは、サエキ・ヨシミチが今までファンとしてオリガに憧れていたはずなのに、オリガを前にして感激している様子の見えないことが意外に思えた。彼は、日ごろ通信を交わすだけで長く会ったことのない知人に接するような、淡々とした表情を崩さなかった。ナオミは、ソーシャルネットワークを通じた知り合いは、スマホの画面という、枕元に置かれることのあるプライベートなデバイスを通したもので、しかも頻度の高いやりとりをしていればなおさら、なまじ直接面識のある人よりも、距離感が少ないのかもしれないと思った。彼女は、公開されたプロフィールには、名刺以上にその人を物語る情報が掲載されているので、たとえば何年も一緒の職場にいる人についてよりも、背景や性格などの知識を得やすいのかもしれない、とも思った。そして、彼女は、そうであれば、オリガとヨシミチとの距離は、自分と彼との距離よりも、もしかすると近いのかもしれない、とさえ思った。
オリガが言った。
「姉から、私のことをいろいろお聞きになっているんでしょう?わがままで、言うことがころころ変わるとか、言ってませんでしたか?」
「お姉さまは音楽家としてのオリガさんのことをよくわかっておられて、自分には参考になります。」
「私は、わがままには違いないんでしょうけれど、言葉に囚われた生き方をしたくないんです。だから音楽家をやっているようなものです。音楽は言葉のように意味の力で人を拘束しませんから。」
「なるほど、オリガさんは自分の想像していた通りの音楽家です。自分の場合は、意味というものに拘った方法をとっています。目の前の現実をよく観察して、その意味を捉えて画面に定着させるやり方です。自分にとって、意味は拘束するものではありますが、同時に解放するものでもあります。人が知らず知らずのうちに受け入れている拘束を、自分の描いた意味によって解放するのです。まあ、口ではこのように言えますが、解放に成功しているかどうかは自分ではよくわかりませんが・・・」
「サエキさんも、私が想像していた通りの方ね。まじめですね。」
「いえ、融通が利かないのです。夢で見たような、現実ではない世界をそのままカンバスに移して見せるようなことは、自分にはできないのです。」
ヨシミチが言った。
「お忙しいなか来られたのですから、早速絵をご覧になりますか?」
ヨシミチはそう言って、机のすぐ横にある、絵具で汚れたシーツのような布を外すと、ヨシミチの肩ほどまでの大きさのあるカンバスが表れた。
カンバスに描かれたのは、人物像というよりは、塔のようなものが何重にもねじれたような印象を与える、たくさんの鮮やかな色彩の塊であった。
「初めは黒で、チェロを演奏する人物の輪郭のような感じで描き始めたのですが、三年ぐらい少しずつ直すうちに、このようになりました。これはまだ完成品ではありません。」
オリガはしばらく黙ってその絵を見ていたが、やがてヨシミチに言った。
「ドラゴン・・・龍みたい。」
ヨシミチは言った。
「ドラゴン、ですか。そうですね、絶えず変わりながらも、同じ主体が貫かれている、そういうイメージですね。もっとも、そういうことを考えて描いているのではなくて、後付けの解説です。」
ナオミが尋ねた。
「ドラゴンの足元に、マリモのようなものがいくつも描いてありますね。」
ヨシミチが答えた。
「なぜこういうものが表れたのかわからないのです。妹の絵に影響されたのかもしれませんが、なぜという答えはありません。」
ナオミが付け加えた。
「サエキさんの妹さん、マリモみたいなものをたくさん描いていたんです。」
オリガが言った。
「ドラゴンが脱ぎ捨てた皮が、あちらこちらにマリモになって固まっているのかしら?」
ナオミがオリガに言った。
「次々に新しい服に着替える、あなたみたいね。脱ぎ捨てた服を丸めて、ちゃんと畳まないところも。」
オリガはナオミの言葉に笑った。
ヨシミチは、ナオミの「脱ぎ捨てた皮」という言葉を脳裏で繰り返した。そして、妹の描くマリモも、心の中で脱ぎ捨てているものの象徴かもしれない、と思った。
ふと、ヨシミチは、オリガを近くで観察できてよかった、この絵はあと一息で完成だ、と思った。
「見ていただいてありがとうございます。どこに筆を入れるといいか、ヒントがつかめました。」
ナオミが尋ねた。
「どこに筆を入れるの?」
ヨシミチが答えた。
「それはやってみないとうまくゆくかはわかりません。」
オリガが言った。
「私をカンバスに閉じ込めるような絵ではないことがわかって、安心しました。」
ナオミはオリガに聞き返した。
「オリガ、それが確かめたかったっていうこと?」
「そうよ。もっと言えば、サエキ・ヨシミチさんが、私をカンバスに閉じ込めるような人ではないことを見たかった、っていうのが正確ね。」
ナオミは、オリガが結局は自分の絵ではなくて、それを描いているサエキ・ヨシミチがどういう男であるか、見たかったのだろうと思った。
オリガが言った。
「絵が完成したら、また見に来ていいかしら?」
「もちろん。どうぞお越しください。」
「ナオミと時々食事されているんでしょう。私もご一緒していいかしら?」
ナオミはその言葉を聞いて、オリガはやっぱりそれを言い出したな、と思った。
ナオミは言った。
「食事と言ってもいつも居酒屋よ。私やサエキさんみたいな、勤め人の行く店だから、あなたみたいなセレブのお気に召すようなところじゃないわよ。」
ヨシミチは、ナオミとオリガとの間に流れた微妙な空気を感じた。
彼は一応礼儀として答える必要を感じて、言った。
「機会があれば三人で飲みましょう。いいお店、調べておきます。」
オリガは次のスケジュールが入っていたので、話はそこで打ち切りとなり、ナオミと連れ立って帰って行った。
ヨシミチは、二人を正門まで送ると、美術室のカンバスの前に戻った。そして半時間ほど思案してから、絵筆をとって、マリモのような黒い塊を一つずつ丁寧に金色に塗り替えて行った。
オリガは、ジョウの運転するスポーツカーのオフホワイトの革張りの助手席で、後部座席のナオミに話し掛けた。
「姉さん、久しぶりに面白い思いをしたわ。ファンなのに、私に握手もサインも求めないうえに、自分はやり方が違うってはっきり言うなんて、珍しい人だったわ。」
「芸術家でもオリガとは全く違うタイプね。」
「姉さん、あの人のそういう地に足の着いたところがいい、そういうことね。」
ナオミはどう答えてよいものか当惑した。運転席では、ジョウが姉妹の会話を聞いているはずであるが、ジョウはいつものとおり、オリガたちの会話がまるで聞こえていないかのように運転を続けていた。
ナオミは、何も言わないのはかえってオリガの邪推を促しかねないと思ったので、つぎのように言った。
「サエキさんは、私の患者さんのお兄さん。面白い人だけれど、今のところお友達。でも、いい人だと思う。それは隠すつもりはないわ。」
「そう。それならば、姉さんのものではないわね。」
ナオミは、人間はどんな人でも誰かのものと決まってはいないのに、と思ったが、言い合いになりかねないので、口には出さなかった。
第八章
ヨシミチが比較的親しくしていた学校の同僚に、数学の教師のイイダという男がいた。
イイダは、ヨシミチと同い年で、本人の語るところによると、十代の時には数学の天才少年と言われていたが、大学での成績が振るわず、大学に残らないで教師になったという人物であった。ヨシミチは、彼の経歴が自分のそれとやや似通っているので、この学校に奉職した時からイイダに親しみを覚えていた。
イイダは、あまり同僚と付き合わないヨシミチを、二か月に一度ほど、飲みに誘うのであった。
学園祭が終わって、学校に日常が戻ったある晩、イイダはヨシミチを上野駅の近くのホルモン焼屋に誘った。六月の初めで、梅雨には少し早い時期なのに、冷たい雨の降る夜であった。
店外の肌寒さとはうって変わって、動物の肉を焼く煙の充満した生暖かい店内で、イイダは熱燗の盃を口に運びながら言った。
「そうだ、学園祭の時に、外人の女性が二人、美術室に入って行ったらしいじゃないか。」
「ああ、そのことか。気が付いた奴がいるんだな。来たのは外人じゃないんだ。二人は姉妹で、姉は医者、妹は音楽家で、俺の絵を見にわざわざ来てくれたんだ。」
「ふうん、わざわざというのは、おまえの絵が何百万円の値段で売れるとか、そういう話かい?」
「そういう話じゃないんだ。医者の方は俺の妹の主治医で、俺が付き添っているうちに知り合いになったんだ。それで、妹の方が、姉さんから絵の話を聞いたらしくて、ぜひ見たいと言い出したらしいんだ。」
「その絵は、おまえが授業のないときにいつも筆を入れている、あの大きな絵のことか?」
「よく知っているな。そうなんだ。」
「それで、どんな感想だったんだ?」
「ドラゴンの絵だろうとか言ってた。」
「絵にタイトルもないのに?」
「そうだ。」
「まあ、見る人によってはいろいろな意味を読み取りたいんだろうな。」
「また、意味の話か?意味ってものはないっていう話だろう?」
「俺の持論さ。意味っていうものは、およそ表現されたものにはないんだ。あると思うのは、それは表現されたものを見て、別の表現を新たにしているだけのことだ。」
「例の、表現されたものだけが、全てだ、という持論だな。」
「そうさ。だって、同じ絵を見たって、ドラゴンだという人もいれば、虹色の人物だという人もいるだろう。絵には意味はない。あるのは絵だけ。その意味はこうこうだ、と言うのは、その人が新たに絵をきっかけに表現をしているのさ。数学で、数式だけがあるのと同じだ。数式の論理的な正しさというものはある。しかし、その裏に隠れている意味なんてものはない。」
「俺、前におまえからその話を聞いて考えたんだけれど、どんな嘘でも、話の辻褄が合っていれば本当だ、ということになるのか?」
「嘘とか本当とかいうことがない。ただあるのは、言葉、絵、表現。以上だ。」
「原因と結果との科学的な法則はどうなんだ?」
「数式で書き表されれば、ある。そうでなければ、ない。」
「数式の論理的正しさが前提なんだな。」
「誰でも同じ結果を再現できるということが、正しいということだ。」
「じゃあ、表現をしたいという意思はどうなんだ?」
「ない。表現されれば、表現だけがあることになる。意思も無意識も、表現を離れては存在しない。」
「人と人との会話はどうなんだ?」
「一人が話し、また一人が話す。その論理的正しさをお互いに確認することが、会話が通じるということだ。」
「おまえはそう言い切るが、俺はそうは思わないんだ。人間には、無意識がある。無意識は全てを意識できていないということで、表現というのは、相手としては意識できていないことに気が付く、その契機になるものだ。人の言葉は必ず文法を伴う。文法は目に見えないけれど、みんなが共通して持っているではないか?」
「文法は、文法書として書かれることで初めて存在するんだ。」
「嘘も本当もないのならば、善も悪もないことにならないか?」
「ないんだからしかたない。現実に成ったことが全てさ。論理的に間違ったことは、人間は誰でも嫌いだから、それは力で排斥するだろう。それで世の中は保たれるんだよ。正義はない。論理整合性のある表現を、そのとおり力が実現する、それが全てだ。」
「自分というものもないのか?」
「ない。あるのは俺の話す言葉、俺の表現だけだ。」
「力ってなんだ?論理整合性とは別にあるものかい?」
「力の意味?意味ってものはないと言ったじゃないか。成ったものは、力があったということなんだ。そういう説明で十分だろう。」
「いつもこういう話になるんだけれど、なんか怖いんだよな。現に、文法というものもあれば、美しい美しくないということもある。悪いことは悪いと思う感情もある。人間は自分のやった悪事に耐えられるほど強い心を持って生まれていない、とロシアの誰か文豪が言っていたな。」
「俺もヒューマニズムは好きだよ。数学のできのよくない生徒が、少しずつできるようになると、俺はとても嬉しい。そこに教師として生き甲斐を感じる。でもそれは好みであって、正しい、正しくないという話ではない。」
「すると、おまえの御心次第ということにならないか?」
「御心なんて、ない。」
イイダはそう言いながら、空になったヨシミチの盃に熱燗を注いだ。
ヨシミチは、注がれた盃を口に運ぼうとして、手を止めて言った。
「どうもおまえの説は、論理を言っているようで力に頼っているように思える。結局現実に成らなかったことに対して、努力した人は、浮かばれないんじゃないか?」
ヨシミチはそう言って、盃を目に見えないものに捧げるようにちょっと上に持ち上げてから、自分の口に運んだ。
イイダは、目玉を天井の方に向けて言った。
「それは、そう成ったのだから仕方ないじゃないか。」
「ならば、おまえが毎晩飲まないと気が済まないというのは、どう説明するんだ?」
「説明は要らないんだよ。」
「でも、抑えることはできないんだろう?」
「成り行きだからしようがない。」
「成り行きに初めから負けているんじゃないかね?」
「ははは、いつもそうやっておれをやり込めようとするんだね。」
「おまえをやり込めることが目的じゃないんだ。」
「でも、おまえだって、おまえの言葉に俺をひれ伏させようとしているんじゃないかね?」
「ひれ伏してくれなくてもいいんだ。自分自身が納得できないから言っているんだ。」
「そうか。それならば独り言だな。」
「おまえの説だとそういうことになるのか。」
「そういうことだ。俺は、人の説に屈するのも、後悔するのも、反省するのも、いやなんだ。」
「そのように正直に言ってくれれば、その気持ちはわかる。おまえの説は賛成しないが、なぜそう言いたいのかはわかる。」
ヨシミチのその言葉を聞いて、イイダはにやっと笑って答えた。
「そうか。俺は、わかってもらえなくてもいいんだよ。コミュニケーションは、結局、独り言と独り言との闘い、そこで勝つか負けるかだけだ。それでもおれはヒューマニズムは好きだ。」
「おまえは現代人なんだな。目に見えるものが全て、計算できるものが全て。」
「俺の仕事は生徒の偏差値と進学率が全てさ。」
「だから遣り手の教師として評判が高いんだな。」
イイダはそこで顔つきが急に曇った。彼は少し間を置いてから、つぎのように言った。
「実は予備校から高給で誘われていて、どうしようかと思ってるところだ。」
「そうなのか。おまえでも迷うことがあるんだ。」
イイダは盃を卓に置くと、それをじっと見つめて言った。
「いや、計算がまだ立っていないだけさ。予備校の講師は、人気がなくなったらばそこでクビだから。」
「おまえの説だと、そういう計算をしなければ、そういう心配なんてないんじゃないか?」
「サエキ、そんな意地悪を言うなよ。本当に悩んでるんだから。」
「その一言で、安心したよ。おまえも人間だって思える。」
イイダはヨシミチの目を見て言った。
「俺、おまえとの議論に負けちゃったのかな?」
「勝ち負けじゃないよ。おれ、別に勝たなくてもいいんだ。おまえが予備校に行っちゃうと、学校でこうやって話せる相手がいなくなるのが心配なだけさ。」
イイダは、お銚子のお代わりを注文して、ひとつため息をついてから、言った。
「俺自身の話はそのぐらいにしよう。それで、その美人姉妹とおまえとの関係を聞こうじゃないか。おまえが目を付けているのは、姉か?妹か?」
「目を付けているわけじゃないが、初めに存在を知ったのは妹の方だ。オリガっていう、音楽家なんだが、聞いたことはあるか?」
「いいや。俺は音楽には疎いから。」
「でも会ったのは学園祭の時が初めてだ。姉の方は俺の妹の主治医で、ナオミさんというんだ。何度か会ったことがある。ナオミさんとオリガさんの二人が姉妹だっていうことは、ナオミさんから聞くまで、知らなかったんだ。」
「ふうん、ナオミさんに、オリガさん。か。姉妹で一人の男性を取り合うの図、ということだな。」
「いいや、二人ともそれほど俺なんかに興味はないだろう。俺の絵が見たかっただけらしい。」
「絵が見たいだけで、わざわざ出かけて来るもんか。それとも、おまえ、本当にそう思っていたのか?男女関係に慣れてなさそうだから、あり得る話だな。」
「イイダ、おまえ、本当にそう思うか?」
「おまえにとって、女性は対等な友達付き合いの相手ではあっても、男女関係の相手ではないんだろう。毎日事務員のマイカや司書のマチコと昼飯を食ってても、何も起こらないんだもんな。ヨッシーとか呼ばれちゃってな。」
「かりに、おまえが想像するようなことだったとして、俺はどうすればよいのだろう?」
「まず、おまえは姉妹のどちらとならば付き合いたいと思っているかだ。」
「いきなり、答えにくいところを突いてきたな。友達付き合いならば、どちらともできそうなんだけれど。」
「付き合った後でおまえとぶつかりそうなのは、どっちだ?」
「オリガさんかな。」
「ならば、ナオミさんを選ぶのが穏当なところだろう。」
「なるほど、数学者はそうやってデジタルに決めて行くんだな。オリガさんは俺にとっては初めから高嶺の花で、男女関係なんて意識したことはないから、可能性だけを言えば、ナオミさんの方なのは、まちがいない。おまえの言うとおりだ。でも、ナオミさんも男性の友達は多いらしいから、そっちの目もないと思う。」
「例によって諦めが早いな。」
「おまえが、諦めが遅いんだよ。」
「諦めが遅いって、おまえ、俺がリオンさんのことを諦めていないことを言っているのか?」
「リオンはね、難しいよ。」
イイダは、ヨシミチの妹のリオンを学校の運動会の時に見かけて以来、ヨシミチに紹介してくれと執拗に頼んでいた。ヨシミチは、リオンが病気療養中であること、激高の傾向があることから、紹介を拒んでいた。ただし、彼はイイダには、妹の病気や激高の話はしないで、ただ勉学中で男性には興味がないから、放っておいてほしいと説明していた。
「おまえが難しいと言えば言うほど、俺は気になってしようがないんだ。リオンさんも未成年ではないんだから、一度三人で飲むような機会は作ってもらえないもんかね。」
「俺がおまえみたいに図々しければ、俺にももっと違う人生が開けていたかもな。」
「今からでも遅くはないぜ。なあ、考え直して、リオンさんと会わせてくれないか?」
「本人に一応聞いてはみるよ。色よい返事は期待できないけれど。本人が嫌がるものを引き合わせるわけには、いくら兄だからといってもできないから、それは予め言っておく。」
ヨシミチはそう言いながらも、リオンに聞くべきかどうか迷った。彼は、イイダが今後執拗に間を取り持つよう頼んで来た時には、リオンの病気のことや激高のことも話さざるをえないだろうと思った。
第九章
ナオミは、オリガとヨシミチとの三人での会食には気が進まなかったので、学園祭で絵を見た翌週にヨシミチと飲んだ時に、ヨシミチには、店を探したりしなくてもよいと伝えた。
「ヨシミチさん、オリガは、きっと自分では本当には好きでなくても、姉にとられたと思ったものは取り返したい性分だから。」
ナオミは、ヨシミチのことを、サエキさんとではなく、ヨシミチさんと呼ぶようになっていた。
ヨシミチが答えた。
「でも、ナオミさんと自分とは、飲み友達で、オリガさんが思うような関係じゃありません。」
「そうね。飲み友達以上の関係には、なかなか進まないわね。ヨシミチさん、そういう関係になるの、嫌だったりするの?」
「別に嫌ではないんですが、自分は女の人とは友達付き合い以上の関係になったことがないんです。」
「それはヨシミチさんが自分から持って行かないからじゃない?」
「そういう方法がわからないんです。」
「それはヨシミチさんがいつも女の子が向いているのと同じ向きになっているからよ。あなたの言っている方法って、女とは違う向きになって、向かい合ってみるってことなんだけど。」
「・・・たとえば、こうやって、ですか?」
ヨシミチはカウンターで隣り合って座っているナオミの方に半身向き直って、ナオミの目を覗き込んだ。
ナオミが言った。
「ヨシミチさん、私の目を初めて見てくれた。」
ヨシミチは、顔を幾分紅潮させてナオミの目を見ながら言った。
「こういうふうにすればいいんでしょうか?」
ナオミは微笑を浮かべて静かにヨシミチに答えた。
「まずはそれでいいわ。やってみれば簡単なことでしょう?」
「でも、ここから先は急ぎたくありません。」
「いいわよ。私も急がないから。」
一方、オリガは、ヨシミチから会食の誘いが一向に来ないことに業を煮やしていた。
その夜、ナオミが日本酒の匂いを漂わせて帰ってきたので、オリガは、きっと姉さんはヨシミチに会ったに違いないと推測した。
「姉さん、サエキさんに会ったでしょう。」
「会ったわよ。」
「そうだと思ったわ。ずいぶん楽しそうに帰ってきたから、すぐわかったわ。」
「オリガ、あなたは姉さんのものがほしいだけで、ヨシミチさんのことを好きなわけじゃあないんでしょう。あなたには、歌舞伎役者とか、ボクサーとか、周りに沢山男の人がいるじゃあないの。」
「そんなの、退屈なだけよ。たいていの男は、抱ける女ならば、誰でもいいんだから。私の音楽、碌に聞いてくれていないし。私には、本当の彼氏なんていたことは一度もないわ。」
「どんな世界だって、まともな男の人はいるはずよ。多分あなたは、恵まれすぎて、まわりの男の人たちに飽きているだけなのよ。」
「姉さんこそ、彼氏ができて、恵まれてるんじゃない?ヨシミチさん、なんて呼んじゃって。」
「私、この度は、あなたに遠慮しないわ。あなたをヨシミチさんに会わせるわけにはゆかないのよ。」
「そう。それならば、私独りでサエキさんに会いに行くわ。」
「オリガ、およしなさい。ヨシミチさんにご迷惑よ。マスコミが誤解したりすると、あの人の生活をおびやかすことになるわ。」
「私も子供ではないから、そこはうまくやるわ。ずかずか学校に乗り込んで行ったりはしないから。」
オリガとしては、元々自分のファンであったのに、事の成り行きで姉が自分の彼氏にしてしまったらしいことが、悔しかった。彼女は、実際のサエキ・ヨシミチに会ってみて、彼が芸術家として自分とは方法が違うが相当の才能を持っていることを見抜いていた。だから、彼が自分とはかけ離れた世界にいるとは思えなかった。彼女としては、姉の持っているものを自分が欲しがることは自分でもわかっていたが、この度はそういう話ではなく、ヨシミチが自分にとても近い存在であると信じたのであった。
「それから、私、確かに姉さんの持っているものは何でも欲しがる方だけれど、この度はそうじゃない。あの人、芸術家として一流よ。それがわかったの。姉さんは気付いていないでしょう。私の方が、あの人のことをわかっているのよ。」
ナオミは、オリガがそのようなことを言うとは予想していなかった。もとより、彼女はヨシミチのことを男性として見てはいたが、芸術家としてどうかという観点では見たことがなかった。しかし、だからと言って、彼女はオリガに対して一歩も退くつもりはなかった。
オリガは続けた。
「とにかく、芸術家同士で、芸術表現について話をしてみるつもりよ。私は姉さんとはやり方が違うわ。」
「芸術家同士のお話に口を差し挟むつもりはないわ。でも、ヨシミチさんはあなたには絶対渡さない。」
ナオミは、自分が意図していたのよりもずっと強い言葉を口にしたことを、自分でも意外に思った。
深夜の姉妹の会話は、すれ違いのまま終わった。
オリガは自室に戻ると、スマホでヨシミチに次のようなメッセージを送った。
「先日は絵を見せていただいてありがとうございます。同じ芸術家として、ご意見をうかがいたいことがあります。自分は演奏をする上で、自分の表現したい通りに表現してよいのか、聴衆の期待に応える表現をするべきなのか、よく迷うのです。あなたはこの問題、どう思っておられますか?」
ヨシミチは、ナオミと飲んで帰ってから、目が冴えて、まだ起きていた。
彼はオリガからのこのメッセージを読んで、どう返信したものか、迷った。
その時、たまたま妹のリオンが、お手洗いに起きて来たので、彼は声を掛けた。
「リオン、夜中で悪いけれど、ちょっと相談がある。オリガさんからメッセージが届いて、どうしようかと思ってるんだ。」
リオンは、眠そうに目をこすりながら答えた。
「ナオミ先生に文面を見せて、先生と相談して、どうするか決めるのよ。明日でいいんじゃない。」
「そうだな。返事を急ぐこともないな。明日ナオミさんに相談してみる。」
「お兄ちゃん、迷ったら何でも私に聞けばいいわ。この話、元はといえば、私が言い出したようなもんだから。」
リオンはこう言うと、押し入れの中の寝床に戻って行った。
オリガは、すぐにでもヨシミチから返信があるのではと待っていたが、一時間ほどしても何も返信がないので、諦めて寝床に入った。
翌朝、ヨシミチは出勤の前に、ナオミに次のようなメッセージを送った。
「昨晩、オリガさんから、つぎのようなメッセージが届きました。芸術表現の問題をどう考えるか、と尋ねる内容です。返事をした方がいいですか?」
ナオミからはすぐ返信があった。
「考えて返信しますが、たぶん午後になります。」
ナオミは、出勤の支度をしながら、横目で寝間着のオリガの様子を窺った。オリガは昨夜の言い合いがなかったかのように、平静に振舞っていた。ナオミもそこは調子を合わせて、平静に振舞うことにして、家族四人で朝食を囲むと、勤務先の病院に向けて出発した。
ナオミは、仕事の合間に考え続けていたが、結局、ヨシミチがかりにオリガに返事をするならば、どういう文面にするのか、聞いてみようと思った。彼女はヨシミチにその旨のメッセージを送った。
ヨシミチのナオミへの返信は速かった。
「つぎのような文面を考えました。・・・鑑賞する人は、芸術家がどう生きているのかが見たいのです。人間は人間が見たい、といわれるのは、このような意味においてです。そして鑑賞する人は、それを説明されるのではなくて、自分で見出したいのです。鑑賞者は、芸術家に愛してもらおうなんて思っていません。芸術家のするべきことは、自分が美をどのように見つけ、どのように感動して、どのように生きているかを、表現を通じて示すこと、しかもそれをあからさまに説明するのではなくて、鑑賞する人が自分で見つけられるようにすることです。自分が芸術家として答えるとすれば、以上の通りです。ひとつ、大事なことですので申し添えますが、自分はナオミさんと真剣にお付き合いしています。あなたとの会話は芸術家同士としての会話です。」
ナオミはこの返信を読んで、ヨシミチがオリガにはっきりと、自分がナオミを選んでいることを表明しようとしていることがわかった。彼女は、自分の喜ぶ表情を病院の同僚に見られないようにしながら、ヨシミチに返信した。
「ヨシミチさん、ありがとう。オリガに言うべきことをはっきり言っていただいている内容で、とてもうれしいです。」
ヨシミチはナオミに返信した。
「では、この文面をオリガさんに送ります。」
ヨシミチはナオミに相談した文面を、オリガに送った。
オリガは、自宅でチェロの練習をしながら、ヨシミチの返信を内心いらいらして待っていた。
ヨシミチの返信がオリガに届いたのは、午後一時前であった。
オリガは、返信の文面を読んで、自分が姉のナオミに、まずは負けていることを悟った。
しかし、彼女は、自分がヨシミチと、ナオミでは持つことのできない、芸術家同士の関係を持つことができることを確信していた。
彼女は早速返信を書いた。
「なるほど、人間は、人間の本当の心が見たいわけですね。鑑賞者は、舞台の上に予想通りのものが表れることを期待しているのではなくて、思いもしなかった本物の心の動きを見聞きして感動したい、そういうことでしょうか?私は、聴衆が聞きたがる人気の曲を演奏しないと言われるのですが、自分が演奏したくない曲を演奏すると、かえって聴衆に対して不誠実だと思っていました。私はいつも、真剣な自分の表現を聴衆に感じてもらいたいと思って演奏してきました。だから、あなたの回答で、自分がまちがっていないと確信できました。でも、良いと信じるものを出し続けるとして、それに人々がお金を払ってくれなくても、本当にいいのか、という問題もあります。あなたはこの問題をどのように考えていますか?」
ヨシミチは、この返信を読んで、オリガが諦めることなく自分と何らか連絡を取り合う関係を持ち続けようとしている意思を感じたが、それと共に、彼女が提起した問題に正面からどう答えるべきか、考え始めた。
それは、自分の画家としてのあり方に関わる問題であった。
彼としては、自分がよいと信じるものを描いているつもりであるが、鑑賞者から芳しい評価を得たことはなかった。大学を出たての頃の彼は、自分に画壇へのつてがないから、知名度が得られず、そのため評価も得られないのだと考えていた。その一方で、絵画は家具調度と同様に室内の装飾として成り立つ必要があるのではないかと考えることもあった。彼は商業美術を決して否定はせず、人々の生活の中に美を提供することに理解を持っていたが、それが自分の進みたい方向と思わなかった。結局、彼は画風を変えることをしなかった。それから十年ほど教師として生活している間に、自分の描くものに自信を失った数年間を経て、今は、あたかも独り言を呟くようにして、描きたいものを描くしか自分には道がないと思い始めていた。そして、数は少なくてもよいから、自分の絵の良さをわかってくれる鑑賞者が現れることを望んでいた。
その一方で、彼の内心では、売れないものは、結局は良いものではないのではないか、という考えも頭をもたげるのであった。人々が求めるからこそ、売れるのであり、そして人々は決して愚かではなく、良いものを判別する力はある。苦労して稼いだ大切なお金を費やすのだから、その判断は実は想像するよりもずっと高度なものではないか?でも、ものを描くというのは、見る人に媚びることではない、媚びたようなものは、売り物にはならない、だから自分が良いと信じたものを描くしかない・・・彼の考えはまたもとの地点にいつの間にか戻っているのであった。
彼は、このように自分の中でも考えが堂々巡りしているのに、オリガに考えをまとめて返信することはできないと思った。できないのであれば、できないと返信するまでだ、彼はそう思った。彼は、そういう返信であれば、ナオミへの相談は要らないだろうと思った。
彼はオリガにつぎのように返信した。
「お尋ねの問題、自分でも日頃よく考えるのですが、考えが堂々巡りしていて、答えることができません。いずれ考えがまとまったらば、お知らせしたいですが、何年もかかるかもしれません。」
オリガはこの返信を読んで、ヨシミチが誠実に答えようとしていることは感じたが、その一方で、彼が自分の手のうちからするっと逃げたのだと思った。それは彼女のプライドを傷つけかねないことであり、彼女は、傷つかないように自分を守る必要があった。彼女は急に、「もうこの人のことはいい、よしておこう」と思った。彼女はそう思いながらも、自分だけがぽつんと取り残されたような寂しさを感じた。
彼女は、常々、自分には虚名があるだけで、自分の音楽に正面から向き合って聞いてくれる人には恵まれていないと思っていた。ヨシミチの返信は、彼女のその思いを一層強くした。彼女は、ヨシミチが、ナオミといかなる関係になるとしても、数少ない自分の聴き手の一人であり続けてくれることを願ったが、それで寂しさを払拭することはできなかった。
第十章
ヨシミチは、夏休みに入った七月の下旬のある日の午後、彼は妹のリオンを学校の美術室に連れて行って、完成したばかりの絵を見せた。
リオンは、カンバスの絵をしばらく眺めていたが、やがてつぎのように言った。
「お兄ちゃん、いい絵がかけるようになったわね。これまではお兄ちゃんだけがわかるような、暗い絵が多かったけれど、この絵は、はっきり言って、色彩がきれいよ。それに、この絵には、完成までの長い間のお兄ちゃんの人生が裏付けになっているわ。絵でも音楽でも、そのために犠牲になったものがあって、初めて美しく見えるのよ。費やした犠牲がぎらぎらと見えるようじゃだめなの。犠牲がエキスになってなきゃ。芸術家って、自分の人生のエキスを絞って人に見せる仕事でしょ。」
ヨシミチは、絵や芸術について、リオンと話をしたのは初めてであった。
「リオンはあんまり美術展とか行かないのに、よく絵のことがわかってるね。」
リオンはいつもヨシミチと話を合わせることはなく、自分の思うことを言った。それがたまたまヨシミチの発言とかみ合うこともあるが、ヨシミチの発言とは全く関係のないことを唐突に言うことも多かった。
リオンが続けた。
「才能って、犠牲のエキスを絞ることを言うのよ。才能のある人っていうのは、表現のために自分の人生がみんな食われちゃってる人なのよ。たぶん、自分自身はどこかにぽつんと置き去りになったままになってるわ。お兄ちゃん自身、そうじゃない?」
「俺は自分の好きなように絵を描いているだけだよ。何か犠牲を払っているつもりがないから、才能はないんだろうな。でも、それでいいんだ。絵を描いてさえいれば、自分は満足なんだ。」
「私にはお兄ちゃんの人生は時間が止まっているように見えるの。だからちっとも老けて見えないんだわ。お兄ちゃんって、子供の頃と全然変わっていないと思う。お兄ちゃんが気付かないだけで、お兄ちゃんの人生は絵の犠牲になってるのよ。」
「世の中の立ち回りとか、俺にはできないから、絵を描くしかないんだ。勤め人をしながら、絵を描く、俺の人生はそういう人生なんだ。」
「だから、そういうお兄ちゃんを支える人は、同じ芸術家じゃだめなのよ。」
「リオンはオリガさんのことを言っているのか?」
「そうよ。家の中で、独りぼっちが二人住んでいるようなことになるわ。」
「いい機会だから聞くけれど、ナオミ先生ならばどう?」
「早くしないと、他の男と結婚しちゃうかもしれないわ。」
その時、美術室の引き戸のガラスをノックする音が聞こえた。
「ヨッシー、妹さんと来ているんだろう?」
その声は、ヨシミチと親しい、数学教師のイイダであった。
イイダは、ヨシミチが入ってよいという前に、がらっと扉を開けて、美術室に入った。
イイダは言った。
「リオンさん、こんにちは。覚えているかな、イイダです。」
イイダはリオンに挨拶すると、ヨシミチに向き直って言った。
「さっき、おまえとリオンさんが入って行くのを見ていたんだ。」
「今日はリオンに俺の絵を見せに連れて来たんだ。」
イイダはまたリオンの方に向き直って言った。
「それで、リオンさん、お兄さんの絵はどうでした?」
ヨシミチは、リオンがうまく受け答えして会話が成立するか、心配した。
リオンが答えた。
「イイダ先生、私のことを覚えていたんですね。今日見た絵は、今までよりずっといいわ。」
ヨシミチは、リオンの発言がイイダとかみ合っていたので、ほっとした。
イイダは、リオンの隣に来て、ヨシミチの絵を見た。
「俺には抽象絵画はよくわからないが、螺旋形が色をいろいろ変えながらぐるぐる回っているみたいだな。まわりに楕円形の玉がきらきら光っているのは、何だろう?この絵、きらいじゃないな。」
ヨシミチは答えた。
「そう言ってくれるとうれしい。」
「タイトルは何て言うんだ?」
「まだつけてない。」
リオンが断定するような口調で言った。
「龍宮のマリモ。」
イイダがリオンに尋ねた。
「それがこの絵のタイトル?」
リオンは、相手に有無を言わさない調子で繰り返した。
「龍宮のマリモ。」
「リオンさん、マリモということは、この絵の主役は螺旋形の方でなくて、楕円形の方なのかな?」
「主役も脇役もないんだけど、私はそういう感じがしただけ。」
その会話を聞いて、ヨシミチには気付いたことがあった。
自分が描きたかったのは、螺旋形に化したオリガではなくて、オリガが脱皮を繰り返すなかで、丸めて残された皮の方ではないか?リオンにはそれが感覚的にわかるのだ・・・
彼は、リオンの命名は直感的にぴったりすると思った。彼は言った。
「タイトルは『龍宮のマリモ』ということにしよう。」
リオンは、イイダの方を見て話し掛けた。
「この通り、兄は私に素直なんです。そういう人でないと、私とは暮らせないんです。」
リオンは、イイダが自分と付き合いたがっているらしいことを、初対面の時に感じ取っていた。
彼女は、自分が兄と同居していることが兄にとっては負担になっていると思っていた。彼女は、自分が兄のアパートからは出るとしても、実家はたぶん自分を受け入れないし、自分も帰るのは嫌であった。彼女は兄が出掛けている昼間、独居するために何か働き口がないか、探し始めていたところであった。
彼女は、かりにイイダと結婚すれば、兄のアパートを出ることができると思った。彼女はイイダのことは嫌いではなかったので、兄のために無理に付き合うということではなかった。
彼女は、自分が時に激高することは、自分の思っている世界の枠組みと同じように、自分の力ではどうしようもないことであった。彼女にとって、自分がこの世の主宰者ということは、犠牲者ということであって、この世の枠組み自体は自力ではどうしようもないことなのであった。自分の力ではどうしようもないことであれば、自分はそれと一生付き合ってゆくほかないと考えていた。彼女は、イイダには、自分がこの世の主宰者であることを明かすまいと思った。そして、イイダであれば、もしも自分の激高に耐えられないとしても、たぶん彼女を放っておいて自分の数学の研究に逃げ込むだろうと想像した。
イイダがリオンの言葉に答えた。
「素直、ですか・・・」
ヨシミチが言った。
「イイダは数学の論理が大事なんだろう。おまえの説の最後の支えは論理の整合だったはずだ。論理に合わないことに、素直になれるとは、俺には思えないんだけどな?」
イイダは、ヨシミチの言葉の終わらないうちに、その言葉を打ち消すように、声をやや大きくして答えた。
「その論理、捨てて惜しくない気になったんだ・・・リオンさんと話してみて・・・」
リオンが言った。
「それはイイダ先生にとって、大冒険ね。」
イイダは、まじめな顔つきになり、改まった口調でリオンに言った。
「リオンさん、私とお付き合いしていただけませんか?」
リオンが言った。
「イイダ先生、本当に私と付き合ってみますか?私の方は構わないです。」
ヨシミチは、リオンの体調が回復していて、しかも今日はいつになく機嫌がよいのを見て、彼女がイイダと付き合っても、何とかうまくゆくのではないかという気がした。ヨシミチは言った。
「二人とも、先に行っていいよ。俺は美術室を片付けてから帰る。」
ヨシミチは、イイダとリオンの二人が先に部屋を出て行くのを見送ると、カンバスに布をかけながら考えた。
自分の山梨の実家は、リオンを自分に押し付けるつもりだ。だから、自分は体調のすぐれないリオンと暮らさなければならないので、独身を通すしかないと思っていた。しかし、リオンがもしもイイダと暮らすようになれば、独身に拘る理由はなくなる。リオンはそのことがわかっていて、イイダと付き合ってもよいと言い出したのではなかろうか?イイダはリオンのことを本当に大事にしてくれるだろうか?彼は、リオンの激高が、もう起こらないと決まったわけではないことが心配になったが、物事良い方に考えようと、その心配を打ち消した。
彼は、自席で熱いお茶を入れて、冷房のない室内で汗をかきながらゆっくりと飲んだ。彼は、暑中に熱い茶を飲むと、かえって涼味を覚えることを知っていた。彼は、お茶を飲みながら、今日はリオンにとっても、イイダにとっても、そして自分にとっても、新たな脱皮の始まりだと思った。
第十一章
オリガは、大阪の夏は、東京に比べると、瀬戸内海のもたらす湿度が高いせいか、一段と暑いと感じた。
彼女はコンサートと講習会での指導のために、大阪に来ていた。
彼女は大阪には年に十回程度は出張する機会があった。彼女は高麗橋の古いホテルを定宿にしていて、ビルの建設ラッシュの中で高級ホテルが次々に開業しても、学生の頃から泊まり慣れているこのホテルを愛用していた。
彼女は、仕事の時間が空くと決まって訪ねる場所があった。
そこは、大阪在住の知人のピアニストに数年前に案内してもらったことのある、愛染堂という寺院であった。
その知人は、彼女と散歩しながら、大阪の上町台地には、四天王寺を始めとした古刹が多くあることを彼女に教えた。
そのなかでも、愛染堂の境内には、豊臣秀吉が建てさせたという多宝塔が、戦乱や自然災害や、とりわけ苛烈を極めた太平洋戦争の空襲にも残っていた。
その知人は、赤い門をくぐってその寺院の境内に入ると、金堂や多宝塔を彼女に案内しながら、この愛染堂の夏祭りは大阪で最も歴史の古い祭りであること、自分が若い頃は浴衣を着て愛染むすめとして祭りに参加したことなどを彼女に語った。
彼女は、この寺が長い歴史の中で今も人々の信仰を集め続けている不思議な活気がいかにも大阪らしいと思って、それからは大阪に出張する時はほぼ毎回訪ねるのであった。
彼女は、この日も愛染堂を訪ねて、夏の昼下がりの太陽の下、陽炎の中に聳える多宝塔を仰いだ。
彼女はしばらく塔を眺めながら、ヨシミチの描いた絵を思い出していた。
彼女は、あの絵には塔のようなものが描かれていたが、愛染堂の古色を帯びた塔とは異なり、様々な色彩に彩られていたのを思い出した。
彼女は、自分の芸術に対する在り方が、絶えず変化していることを、その絵によって改めて自分の目で確かめたように思っていた。
その姿と比べて、何百年も変わらない姿で聳える目の前の多宝塔の佇まいは、一時の流行に終わらない確乎とした印象を彼女に与えていた。
彼女は、舞台芸術は、録画や録音という形で残ることはあるものの、基本的には演じられるその時一回限りのものであると思っていた。一回限りであるから、一回ごとに変化して差し支えないのだと思っていた。
しかし、この多宝塔の佇まいは、一回性をもって時間の彼方に消えるものとは異なっていた。
「私の芸術が時代を超えて残ると言うことはあるのかしら?」
彼女の胸中にこのような疑問が湧き起こった。今まで溢れるばかりの自信をもって、演奏活動もタレント活動もこなしてきた彼女にとって、このように自分の芸術のあり方を立ち止まって考えるのは初めてであった。
彼女は、自分が世間にタレントとしてもてはやされていながら、自分の演奏を聴いてくれるファンが実のところ少ないことに、日増しに苛立ちを感じていた。
その苛立ちが、かえって彼女を芸術においては先鋭的にさせて、難解な現代曲ばかり選択させるのであった。
時には、バッハのような古典に戻ってみたいと思うこともあって、つい先日も予定されている演奏会の曲目を現代曲からバッハに差し替えようかとまで考えたこともあったが、それは聴衆に自分が膝を屈したかのように思われると思い直して、差し替えはやめたのであった。
彼女は、多宝塔を仰ぎながら胸中でこのように考え続けているうちに、あたかも自分が言葉のなかに埋もれて、息がつまるような気がして来た。
その時、金堂の方から、不意に一陣の風が吹いて、彼女の被っていたヒョウ柄のキャップを飛ばした。
彼女はキャップを拾おうと体を屈めた時、自分を埋め尽くそうとしていた言葉が、どこかへ雲散霧消するのを感じた。
彼女は、続けていた思考を再開する代わりに、この思考の突然の中断に注意を向けた。
「もう一度初めから考え直してみるか。」
彼女は小声でこのように呟いた。
彼女は愛染堂の赤い門を出て、西の方の坂道を下って行った。
坂道の途中で、小学生の女の子二人とすれ違った。
女の子は、学校の教材のリコーダーで、坂を上りながら、昔の日本の唱歌の「海」のメロディーを吹いていた。
オリガが女の子とすれ違う時には、そのメロディーは終わっていて、女の子の一人がもう一人に話し掛けた。
「うち、妹が生まれたばかりやから、夏休みも海にはいけへんのや。リナちゃんと海の歌を吹くのが、そのかわりや。」
「うちもルナちゃんと笛吹くの楽しいわ。もっと一緒に吹ければええんやけど、これから塾や。また遊ぼうな。」
オリガはその会話を何気なく聞いていたが、それからしばらく歩いて、はっとして立ち止まった。
「遊び、忘れていた!」
彼女は、自分の表現活動の中で、遊びを忘れていたことに気が付いたのであった。
彼女の後ろで、小学生の二人がつぎのように話しているのが彼女に聞こえた。
「今すれ違った人、コマーシャルに出てる人とちゃう?自動車のコマーシャルやったかな?」
「そんな人、こういうところには来いへん、来いへん。ぜったい、ちゃうて。」
彼女は、後ろを振り返って、その二人ににっこり笑って手を振ると、再び坂道を下り始めた。
オリガは歩きながら考えた。
自分はこのところ、新しい表現の追求を続けてきたが、それが必ずしも聴衆の心に響いているという実感がなかった。それは、自分の演奏が遊びではなく、自分が楽しいと思って表現するのではなかったからだ。子供の時は、楽器を自分の思うように鳴らすことが自分の遊びであり、自分の楽しみだった。大きくなると、技巧的に難しい曲を弾けるようになることが、自分の楽しみであった。自分が楽しめていないような表現が、聴衆の心に響くわけはない。こうして考えてみると、最近の自分の演奏は、次々に新しい表現のできる自分を聴衆に承認させようとしていただけなのかもしれない。新しい表現を追求すること自体がいけないのではない。それを行うことが自分の楽しみであるならば、それでよいのだ。
自分の演奏を自分が楽しめるということは、その演奏に愛があるということだ。演劇の世界には「人間は人間を見たいのだ」という言葉があると聞いたことがあるが、それは、他の人間の隠し事を見たいという意味ではなくて、人間の偽りのない心の動き、感動、言い換えれば愛、そういうものを見たいということのはずだ。表現をもって聴衆に愛を伝えるということは、聴衆を直接愛して見せるようなことではなくて、愛のある表現を行うことのはずだ。
自分が今日このように気が付いたからといって、自分の演奏が直ちにがらっと変わってしまうかどうかはわからない。ただ、心の持ち方だけは今から変えてみたい・・・
彼女が坂を下り切って左を見ると、「伶人町」という住居表示が見えた。
伶人とは雅楽の楽士のことで、四天王寺の楽士がこのあたりに住んでいたことに因むらしいという話を、彼女は愛染堂に連れて行ってくれた友人から聞いていた。
彼女は、自分も昔風にいえば伶人だと思った。今日は昔の伶人が自分に大事なことを教えてくれたような気がした。
彼女は、ホテルに戻ると、先ほど撮影した多宝塔の写真をインスタグラムに掲載した。
「今日はここで大切なことに気付きました。自分の芸術が、自分にとって楽しみであること。遊びというか、余裕というか、そういうものが大事なこと。」
彼女はこのようなコメントを添えた。
彼女は、最近ヨシミチが自分のコメントに反応して来なくなったことに気付いていた。
ヨシミチは、今までならば必ず何か一文は返していてくれたのに、先日美術室で彼の作品を見せてもらった頃から、何も返してくれなくなっていた。
彼女は姉のナオミの様子から、ナオミとヨシミチが付き合いを深めていることに気が付いていた。彼女は、このままナオミはヨシミチと結婚するのではないかと予想していた。
その予想は、オリガにとっては快いものではなかった。それは、自分がまた独り取り残されるという思いを彼女にもたらした。
かといって、彼女はヨシミチを自分に振り向かせるために、何かする気にはならなかった。彼女は、ナオミとヨシミチの間にどうやって割り込んでゆくかもわからなかった。彼女は、自分が実のところは音楽のエリートとして、才能を日々磨くこと以外には、人生経験がほとんどないことを知っていた。タレントとしての活動は、すべてマネジャーのジョウがお膳立てをしたとおりにこなしているだけで、彼女が自分で何か経験してつかむということはないのであった。彼女は自分が世間知らずであることに思い至ると、独り取り残されているという孤独感が一層つらいものになった。
オリガに従って大阪について来ているマネジャーのジョウは、オリガに最近元気がないことに気付いていたが、その日の夕方、オリガがホテルの部屋から出て来ると、多少表情が明るくなっていたのに安心した。
ジョウはオリガに言った。
「オリガ先生、さっきインスタグラム見ました。どこかのお寺に行っておられたのですね。何か大事なことを気付かれたようで、よかったです。」
オリガが答えた。
「うん、音楽のうえで、とても大事なことに気が付いたわ。それでね、相談があるんだけど・・・」
ジョウは、オリガがこのように切り出す時は、彼女が新しい思い付きをして、それに合わせて演奏会のプログラムを変えたり、共演者を探したりといった仕事が始まることを知っていた。
「今まで子供向けの演奏は断っていたけど、やってみてもいいと思ったの。」
「そうですか。それならば、以前打診のあった学校があったはずですから、連絡をとってみましょう。今からの手配ですと、早くても今年の冬ぐらいになると思います。試しということで、一回だけ企画してみます。」
「曲目は、わりと知られているものにするわ。サン・サーンスの白鳥は、必ず入れましょう。チェロのよさが誰にでもわかると思うわ。」
「そうですか。そういう曲目ならば、たぶん子供のお客様は喜ぶと思います。」
オリガは、つぎの日も愛染堂を訪ねて、本尊に感謝して頭を下げると、タクシーに乗って伊丹空港に向かった。
完
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
