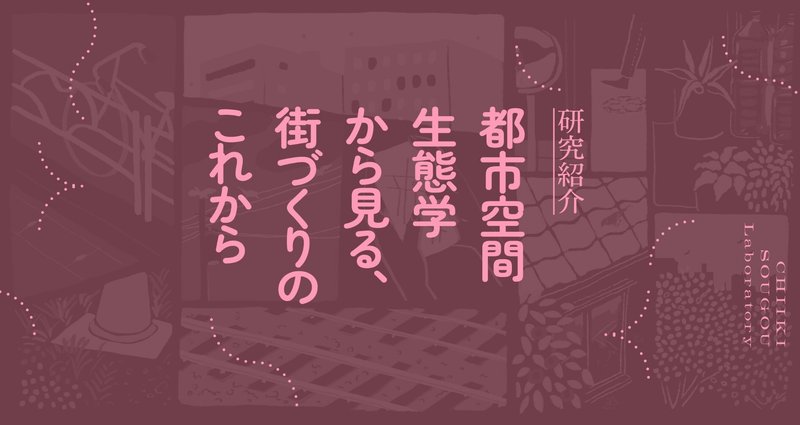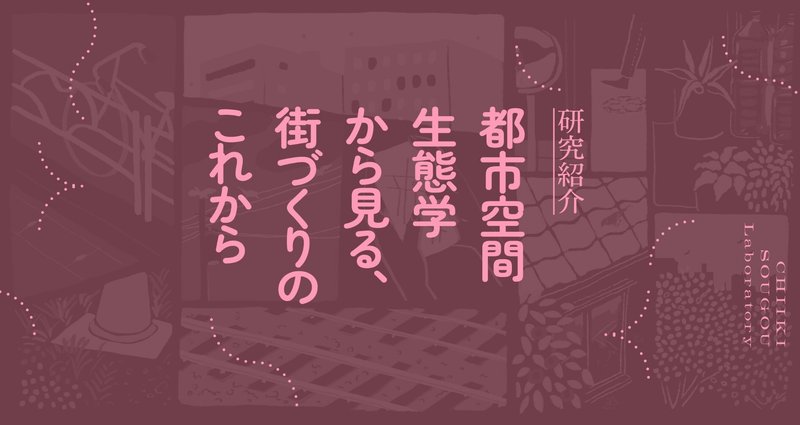当たり前に向き合ってまちをつくる|「都市空間生態学から見る、街づくりのこれから」vol.12
都市空間の生態という「意地悪な問題」にどうアプローチするか
──この連載では都市空間生態学から抽出したエッセンスをいまの社会にどう生かすかという視点から、「まちの主体は誰か」「温度あるデータ」「ブラブラの価値」といったトピックについてこれまでお書きいただきました。今回は、まず都市空間生態学のそもそもの出発点からお聞きしたいと思います。
2015年の研究発足当初は、「データや情報技術を用いたデジタルなデザインの使い所として、都市は面白いんじゃないか」というところから僕の関心は