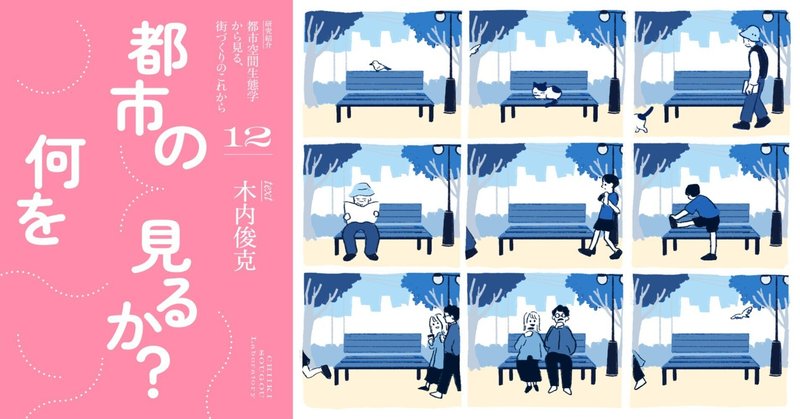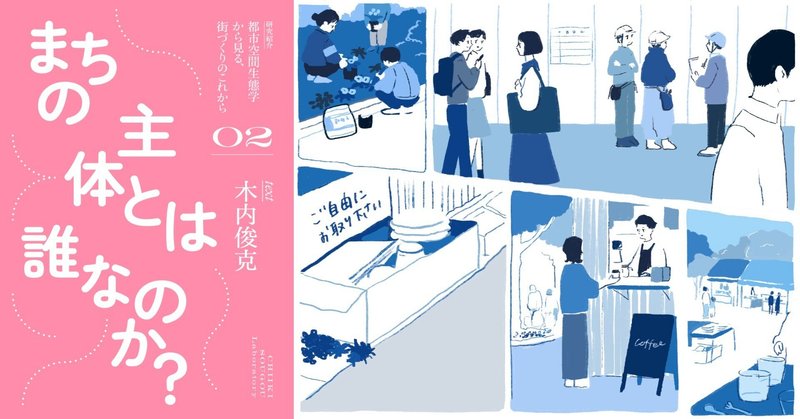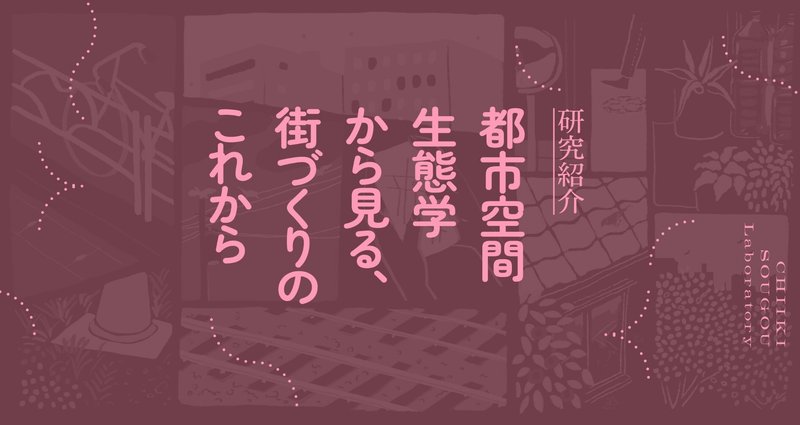
2015〜2020年にかけてNTT都市開発・東京大学Design Think Tank(DTT)・新建築社の3者で行われた共同研究「都市空間生態学」の紹介と、それに紐づく「いま考…
- 運営しているクリエイター
#まちづくり
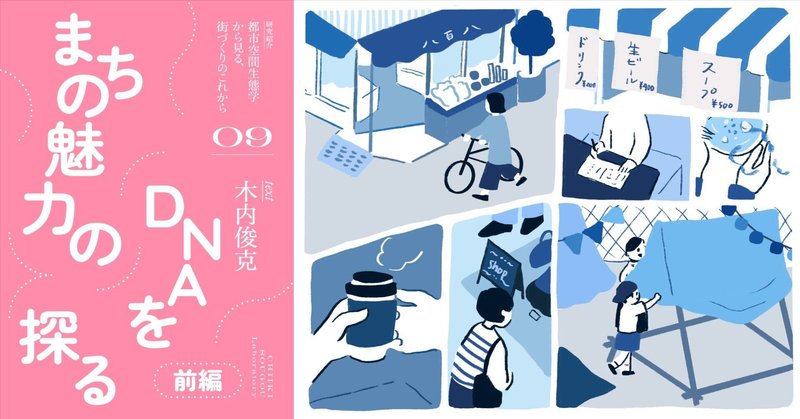
〈ブラブラ〉が育まれるまち_東池袋エリアから考える(前編:住み暮らすことが育むまち)|「都市空間生態学から見る、街づくりのこれから」vol.9
文:木内俊克 〈ブラブラ〉が育まれるまち。それは自転車や歩きでめぐりたくなるきっかけがそこかしこにあって、偶然見かけてついつい寄り道したくなるような場所が、宝探しのように点在しているまち。前回、前々回の記事では、そんなまちの魅力を具体的に捉えるため、都市空間生態学研究で2016~2017年に研究対象とした台東区の三筋・小島・鳥越(以下、三小鳥)を紹介した。この三小鳥、用途地域は「商業地域」で、かつては江戸随一の遊興地・浅草に隣接し、昭和期には町工場とその労働者の空腹を満たす